「櫂」
(かい)
1985年1月15日公開。
宮尾登美子三部作のひとつ。
興行収入:7.5億円
脚本:高田宏治
監督:五社英雄
キャスト:
- 富田岩伍 - 緒形拳
- 女衒で芸妓娼妓紹介業を営む。かつては青年相撲の力士で、力士だった岩伍を喜和が見初める。女衒の仕事に対し「貧乏が人を腐らせてるから、人を買って人助けしてる」と誇りを持っている。森山大蔵という大きな後ろ盾を得て、後に高知市立城北診療所の建設資金を半分寄付するまでに大成する。巴吉に自分の子を孕ませて別れた後、綾子の一切の世話を喜和に押し付け、照と関係を持つ。親は床屋を営んでいたが酒と博打で自殺し、母親は岩伍が5歳の頃に家を捨て、若い男と逃げた過去がある。
- 富田喜和 - 十朱幸代
- 岩伍の妻。岩伍の行動に振り回されながらも耐えて来たが、徐々に本音をぶつけるようになる。岩伍が女衒の仕事をしていることを良く思っておらず、本心では別の仕事をしてほしいと思っている。岩伍からは陰で「青竹が着物を着た融通の利かない一本木」と評されている。辛抱強いが裏を返せば頑固な性格。子宮筋腫を患い手術に成功するが、毛髪を次第に失ってゆく。岩伍の不始末を押し付けられ全てを背負おうが、岩伍と離縁する。
富田家で育つ子供たち(実子以外を含む)
- 菊 - 石原真理子
- 幼い頃、中国に売られて六神丸の材料になるところを、神戸で岩伍に10円で買われ、来ていた着物の模様から岩伍が菊と名付ける。子供の頃、ご飯の食べ方すらまともに親に教えてもらえなかったため周りの手を焼かせたが、喜和に一から教えられて気立ての良い娘に育つ。後に竹市とともに岩伍の朝倉町の店に来る。
- 竜太郎 - 井上純一
- 富田家の長男。生まれつき病弱で肺病を患ったせいで旧制中学校に上がれず弟に劣等感を持つ。菊を実の妹のように可愛がる。多仁川組の取り仕切る賭博場でトラブルになった健太郎をかばい、喀血して死亡。
- 健太郎 - 田中隆三
- 富田家の次男。兄弟である竜太郎とは仲が悪い。高知一中(旧制中学)に進学するが、学校をさぼり放蕩をしている。多仁川組の取り仕切る賭博場で殺傷事件を起こして拘留される。後に出所して喜和と離縁し、岩伍の稼業を手伝う。
- 綾子 - 高橋かおり(子役)
- 岩伍と巴吉の間に生まれた娘だが、生まれた直後に大貞と岩伍によって強引に富田家に引き取られ喜和に育てられる。その後天真爛漫な少女に育ち、喜和を実の母のように慕う。最後は岩伍に引き取られる。
岩伍と関わる女たち
- 大貞(だいさだ) - 草笛光子
- 岩伍と同業で『大貞楼』の女将。岩伍とは大阪にいた頃からの仲で、喜和に対して「男が妾を持つのは当然で、(喜和と)一緒にいるせいで岩伍が肩身のせまい思いをしている」と言い、岩伍の不始末を喜和に押し付けている。なお原作では、大貞の抱えの芸妓が妊娠しても臨月まで客をとらせ、流産しても商売をやめさせないくらいの鬼のような人物。
- 染勇(そめゆう) - 名取裕子
- 裏長屋の生まれで、『大貞楼』に預けられる。後に高知一の芸妓になり、豊美から染勇になる。男を手玉に取るのが上手く、男を次々と乗り換えていると地元では噂されている。子供時代に富田家に来た当初は、家族思いの健気な性格だったが成長後は負けん気の強い性格になる。
- 豊竹巴吉(ともきち) - 真行寺君枝
- 女義太夫で『巴吉太夫』と慕われ、岩伍の興行で人気となる。女義太夫としての喉の良さには定評があり人気の女義太夫だった“ろしょう”の再来と言われている。後日岩伍の妾となり綾子を身ごもる。
- 松井照(てる) - 白都真理
- 元人妻。以前夫は俥の車夫をしており岩伍を乗せていた所、多仁川組の組員に刺殺される。直後に線香を上げに来た岩伍と知り合い、ほどなくして男女の仲となる。
喜和の実家
- 小笠原楠喜 - ハナ肇
- 喜和の兄。古道具・古本「楠木堂」を経営。夫婦間でゴタゴタした時に喜和を数日間住まわせたり、助言したりしている。
- 里江(さとえ) - 園佳也子
- 喜和の姉。富田の家にもらわれたばかりの菊に幼い娘用の古着をあげたり、その後も喜和のことを気にかける。
富田家で働く人々
- 庄 - 左とん平
- 岩伍の店の番頭。岩伍の右腕となり外に仕事に出たり、米たちに色々と指示を出す。
- 米 - 桜金造
- 岩伍の店の若い衆。
- 女中 - 藤山直美
- 富田家の女中。家事をこなしながら喜和の子育てを手伝ったり忙しくしている。
その他
- 森山大蔵 - 島田正吾
- 四国造船の会長で地元で影響力がある人物。元々女義太夫で人気を博した“ろしょう”のファンで、“ろしょう”に似た巴吉のそのスター性を評価する。岩伍の興行の後ろ盾となる。
- 谷川文造 - 成田三樹夫
- ヤクザ、多仁川組の組長。染勇と親しい間柄。岩伍と興行で対立してたが、後に賭博場での一件で失脚する。さらに手下に体を支えられないと一人で歩けない状態となる。
- 木元武造 - 片桐竜次
- ヤクザ、多仁川組の組員。健太郎に刺殺される。
- 松崎 - 成瀬正
- 市場の魚屋で働く。
- 竹市 - 島田紳助
- 市場の魚屋で働く。客の菊とは顔なじみで冗談で「一晩付き合って」などと言っているが、岩伍が怖くて実際には手出しができないでいる。後に菊とともに岩伍の朝倉町の店に来る。
あらすじ:
大正3年、初夏の土佐の高知。
縁町界隈で芸妓・娼妓紹介業を商う富田岩伍(緒形拳)は、商用で大阪・神戸をまわって、旅の途中で拾った少女・菊を連れて帰ってきた。
富田の家には岩伍と喜和(十朱幸代)の間に病弱な長男・竜太郎、きかん坊の次男・健太郎の息子があり、それに番頭格の庄(左とん平)、女中の鶴、若い衆の米と亀がいる。
金使いの荒い岩伍のせいで、人知れず貧乏所帯をきりまわす喜和に、またひとつ菊の養育という苦労が重なった。
ある日、喜和は岩伍に命じられるまま、赤貧にあえぐ裏長屋の巻に米を届けた。
折悪しくそこは赤痢騒ぎ、しかも巻の無残な死骸を見た喜和は不覚にも気を失って倒れた。
死んだ巻の娘・豊美を芸事修業のため、岩伍が大貞楼にあずけたのは、それから間もなくのことだった。
大正15年5月。
菊(石原真理子)は19歳の美しい娘に成長していた。
大貞楼にあずけられた豊美は名も染勇(名取裕子)と改め、高知一の芸者になっていた。
健太郎、竜太郎も19歳、17歳とそれぞれ成長していたが、喜和の心痛は竜太郎の病弱、健太郎の放蕩だった。
この頃、岩伍は40歳中ばの男ざかり、豊栄座に招いた娘義太夫の巴吉(真行寺君枝)と肉体関係をもっていた。
かねてより女衒(ぜげん)という恥かき稼業を嫌っていた喜和はそのことが原因で実家である小笠原家に戻っていたが、そこに大貞楼の女将、大貞(草笛光子)が訪れ、とりなしを計った。
巴吉と岩伍は別れさせるが二人の間にできた子供は喜和が育てるべきだと。
喜和はあまりの理不尽さに身体がふるえた。
喜和が緑町の家に帰ってから間もなく、岩伍と対立する谷川一家の賭場で刃傷沙汰を起こし、弟をかばった竜太郎が多量の血を吐いて息を引き取った。
そして一方、岩伍の子を産み落とした巴吉は高知を去り、綾子と名付けられた赤ん坊の育事は喜和の仕事となった。
昭和11年5月。
綾子は11歳の愛くるしい少女に成長したが、喜和は病いに倒れた。
手術の末、奇跡的に命はとりとめたものの、髪を次第に失っていく悲運に見まわれた。
岩伍は今では大成し、朝倉町に移っていたがそこに照という女を住まわせていた。
ある日、今は父親の仕事を手伝っている健太郎は岩伍の意向で喜和に隠居を命じた。
喜和は綾子を連れて実家に身を寄せたが、追い打つように岩伍からの離縁話、そして綾子を返せという達し。
今では綾子だけが生きがいとなっている喜和はこれを拒否し、岩伍の殴打が容赦なく飛ぶ。
そのとき綾子が出刃包丁で岩伍に斬りかかった。
こんな骨肉の争いがあって間もなく、喜和は大貞の意見を入れ、身を切られるような気持ちで綾子を岩伍のもとに返す決心をした。
別れの日、橋のたもとで喜和は綾子が岩伍の家に入るまで見送った。
喜和はひとり、岩伍の家に背を向けた。
コメント:
原作は、宮尾登美子の同名長編小説。
1972年8月に第一部を自費出版し、1973年の第9回太宰治賞を受賞。
同年12月および1974年3月に筑摩書房より上下巻にて刊行された。
自らの父母をモデルに、大正から昭和初期の高知の花街を舞台に15歳で渡世人に嫁いだ薄幸の女のひたむきな生涯を描く。
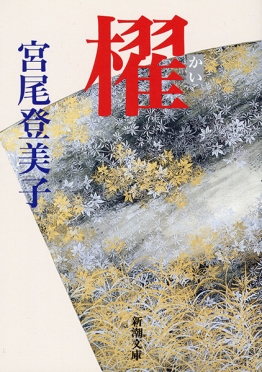
大正初期、女衒(ぜげん)の岩伍(緒形拳)と女房の喜和(十朱幸代)の不条理な愛を描く。
日本の一世紀前は、男尊女卑があからさまだった。
女衒(ぜげん)というのは、山椒大夫に代表される人買いを職業とする人間をいう。
極貧の家庭が借金に困り、自分の娘を芸妓や遊女に出す際に、料亭や遊郭への仲介を行う仲買人である。
現在の人材紹介業者である。
やくざとは異なる。
宮尾登美子の自伝的な話である。
映画では、女性専門の人材紹介をする女衒とはいえ、岩伍(緒形拳)が人でなしのように描かれている。
原作を読むと、岩伍という人物は、近くの貧民窟の長屋に住んでいる最下層の人々を救おうと奮闘する人情豊かな頼れる男という側面も詳しく綴っていて、決して極悪人ではなかったようだ。
だが、問題は、妻の喜和(十朱幸代)の目を盗んで、娘義太夫の巴吉(真行寺君枝)と深い仲になり、ついに巴吉を妊娠させてしまったことだ。
それを知った喜和が実家に帰ってしまう。
その後、岩伍は巴吉と別れる決意をする。
だが、条件として、巴吉のお腹の子は岩伍が引き取り、喜和が育てるということになった。
つまり、岩伍の実の子として、正妻である喜和が育て上げねばならないという不条理な解決策なのだ。
浮気相手が産んだ子を育てさせられるという正妻にとってこれ以上の屈辱はない、
さらに、生みの親である巴吉は、出産次第住む家を追われ、生涯親子の名乗りをしないことを強要された。
つまりは、男尊女卑の社会にあっては、男の思うがままだったのだ。
令和の時代には絶対にあり得ない話だが、妾の子を正妻が育てることは戦前の日本では当たり前だったようだ。
五社英雄監督らしく、十朱幸代をはじめ真行寺君枝、白都真理を脱がせている。
島田正吾は、森山大蔵という人物に扮している。森山は、四国造船の会長で地元で影響力がある人物。
- 元々女義太夫で人気を博した“ろしょう”のファンで、“ろしょう”に似た巴吉のそのスター性を評価する。
- 緒形拳扮する岩伍の後ろ盾となっている。
- 「ろしょう」というのは、豊竹 呂昇(とよたけ ろしょう)という女義太夫師のこと。
- 明治から大正にかけて女義太夫の頂点にいたという。
本作は、『鬼龍院花子の生涯』・『陽暉楼』と合わせ、宮尾登美子原作、五社英雄監督のコンビ作品で「高知三部作」とも呼ばれる。
宮尾登美子の原作の刊行順で言うと「鬼龍院」や「陽暉楼」よりも先で、作家の初期にあたる作品。
「櫂は三年、櫓は三月、浮かしておけば流される」というこのことわざが映画の冒頭に流れる。
原作の小説の中で、この言葉を見つけるのは大変だ。
たった一か所にしか出てこないのだ。
このタイトルが何を意味するのか。
原作をしっかりと2度読んで、ようやく発見できた。
原作の第一部の最後の部分にこういう文章が出てくる:
「岩伍も喜和も、舟で云えば、漕ぎ抜けて来たあとの櫂を、今はじっと休めている時期なのだとも思われる。
舟に委しい誰ぞの言葉のように、櫂は三年櫓は三月、繰りかたをやっと覚えた櫂も、浮かしておけば流される、と云うなら、漕ぎ休めている今の時期こそ、岩伍にも喜和にも大切な月日なのであった。」
「櫂」は見慣れない漢字だし、令和の若い世代の人たちは、それがどんなものなのか知らないのではないだろうか。
これは、ボートの「オール」と同じ意味なのだ。
「櫂は三年、櫓は三月」というのは、船をこぐ道具では「櫂」と「櫓」では難しさに違うという。
「櫂」というのは、水をかいて舟を進める道具。棒の一端を幅広く平らに削ったもの。オール。
「櫂」も「櫓」も舟をこぐ道具。
「櫂」の方が難しい。
己が生きる為に漕ぎ続けなければ流され、手を離せば死が待つ。
理不尽にも、亭主の犠牲になり、他人の為に、己が為の如く櫂を漕ぐ喜和の生き様を「櫂」に例えているのだろう。
ヤクザ社会と花柳界という古いしきたりの中で喘ぐ女たちの姿が、より凝縮された形で描かれている。
喜和の夫である女衒(ぜげん)の岩伍(緒形拳)という存在は、「鬼龍院花子の生涯」での鬼政に当たる。
気に入った女を次々に手篭めにする岩伍。
その度に嫉妬と悲しみにくれる喜和。
男尊女卑がまかり通った前時代の女の悲しみはこのヒロインの姿に凝縮されている。
周囲を彩る女優陣も多彩。
岩伍に拾われてきた菊役の石原真理子や、のちに売れっ子芸者・豊美となる名取裕子、女義太夫役の真行寺君枝、岩伍と懇ろになる白都真理などの美人女優達。

(十朱幸代)

(真行寺君枝)

(白都真理)
この映画は、Amazon Primeで動画配信可能:





