ジョージ・オーウェル 1984年 ①
一九八四年[新訳版] (ハヤカワepi文庫)/ジョージ・オーウェル

さて、純文学とは何ぞや?通俗小説ではない小説。優等生はそう答えるでしょうな。小林秀雄曰く、日本の純文学は私小説のことである。文学青年ならそう答える。そしてどちらの答えも受け売りである。受け売りは良い。もっともらしいからね。でも受け売りはいつもツマラナイ。中身のない自分をさらけ出すのと変わらないのだ。
ならば純文学とは?僕なら“異端の”小説であると答える。言い換えれば異常者の書いた小説だ。通俗小説が哀しみを、恋愛を、感情の昂りを恥ずかしげもなく書く一方で、純文学は歪んだ目線でそれらを書く。太宰治や川端康成のように日常生活の汚さを通して書くかもしれない。村上春樹のように無駄に洗練されたシュールな世界を通して描くかもしれない。
彼らに共通するのは社会や世間に適応出来ていない、そんな自分を書くことにためらいがないことなんだろうな。純文学を読む楽しみというのは、そんな(たぶん誰しもが持つ)疎外感、世界を占めている多数派への抵抗意識を共有する密かな歓びだろう。
物語を楽しみたいなら通俗小説を読みなさい。興奮したいなら娯楽小説を読みなさい。泣きたいのなら恋愛小説を、カタルシスを味わいたいなら歴史小説を読めばいい。純文学の歓びは小説自体の面白さにあるのではなく、反社会的・反教訓的物語を書いた作者本人との対話にあるんだと思うんだな。
(だからこそメタファーだけを抜き出す、一部のハルキストの姿勢には共感できない)
1984年を読んでいる。中断しながら読んでるのでまだ半分くらいだが、純文学の楽しみを充分に伝えてくれている。この新訳も良い。翻訳小説は訳の不自然さが嫌になって投げ出すことが多いのだけれど、抵抗感なく読めます。
(翻訳文学の好悪は翻訳者が直接的に握っている。文学的な素養もないただの研究者が訳出した本が多いから、翻訳本は売れないんだろうと思う。小説家が訳すのも良いし、上手な翻訳者が出てくることも喜ばしいことだ。最近だとゲバラの「モータサイクル・ダイアリーズ」なんかも違和感がなくて素晴らしかった。 あと日本の純文学は文体に偏り過ぎてる。村上春樹を純文学と認めない一部の風潮が象徴しているように。文学雑誌を買って読んでみたんだが、作者たちの文学青年ぶりが鼻についてとても読めたもんじゃなかった。)
小説が面白いかどうかは微妙なところだ。正直。それでも読み続けたい、と思わせるのはオーウェル本人のことをもっと知りたいと思うからなんじゃないだろうか。それなら演劇でも映画でもオペラでもミュージカルでも美術なんかでも良いんだけれど、僕は紙とインクと言葉だけで成り立ってるこの小説の、とってもシンプルで洗練された在り方に、他のどの芸術よりも愛着と共感を覚えます。
結局作品についてなんも書いてないや。読み終わったらなんか書くかも知れませんね。じゃ。
モーターサイクル・ダイアリーズ (角川文庫)/エルネスト・チェ ゲバラ
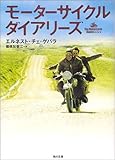
コレ
↓最近観た映画たち。どれも面白いっすよ。あともう二本くらい観たんだが忘れた。
エターナルサンシャイン DTSスペシャル・エディション [DVD]/ジム・キャリー,ケイト・ウィンスレット,キルステン・ダンスト
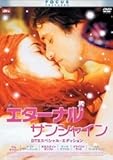
恋人との大切な思い出を失ってしまったらどうしますか?泣けるかも
デッドマン・ウォーキング [DVD]/スーザン・サランドン,ショーン・ペン,ロバート・プロスキー
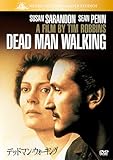
廃止/肯定は別にして、死刑に興味ある人は観るべき。むしろこれを観ずに死刑を語るなと言いたい
ジョー・ブラックをよろしく 【プレミアム・ベスト・コレクション¥1800】 [DVD]/アンソニー・ホプキンス,ジェイク・ウェバー,ジェフリー・タンバー

テンポ感悪し。ストーリーは面白い。ブラピの死神は格好良いよ
ビューティフル・マインド [DVD]/エド・ハリス,クリストファー・プラマー,ラッセル・クロウ
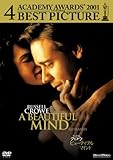
少しコワい映画。天才数学者の実話をもとにしたサスペンス(?)
ケンタッキー・フライド・ムービー [DVD]/ドナルド・サザーランド,ジョージ・レーゼンビー

稀に見るバカムービー。外人のギャグセンスで笑えたのは初めてかもしれん
JUNO/ジュノ<特別編> [DVD]/エレン・ペイジ,マイケル・セラ,ジェニファー・ガーナー
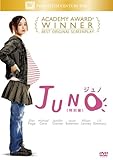
奔放な女子高生が性的に色々ヤッちゃう話

さて、純文学とは何ぞや?通俗小説ではない小説。優等生はそう答えるでしょうな。小林秀雄曰く、日本の純文学は私小説のことである。文学青年ならそう答える。そしてどちらの答えも受け売りである。受け売りは良い。もっともらしいからね。でも受け売りはいつもツマラナイ。中身のない自分をさらけ出すのと変わらないのだ。
ならば純文学とは?僕なら“異端の”小説であると答える。言い換えれば異常者の書いた小説だ。通俗小説が哀しみを、恋愛を、感情の昂りを恥ずかしげもなく書く一方で、純文学は歪んだ目線でそれらを書く。太宰治や川端康成のように日常生活の汚さを通して書くかもしれない。村上春樹のように無駄に洗練されたシュールな世界を通して描くかもしれない。
彼らに共通するのは社会や世間に適応出来ていない、そんな自分を書くことにためらいがないことなんだろうな。純文学を読む楽しみというのは、そんな(たぶん誰しもが持つ)疎外感、世界を占めている多数派への抵抗意識を共有する密かな歓びだろう。
物語を楽しみたいなら通俗小説を読みなさい。興奮したいなら娯楽小説を読みなさい。泣きたいのなら恋愛小説を、カタルシスを味わいたいなら歴史小説を読めばいい。純文学の歓びは小説自体の面白さにあるのではなく、反社会的・反教訓的物語を書いた作者本人との対話にあるんだと思うんだな。
(だからこそメタファーだけを抜き出す、一部のハルキストの姿勢には共感できない)
1984年を読んでいる。中断しながら読んでるのでまだ半分くらいだが、純文学の楽しみを充分に伝えてくれている。この新訳も良い。翻訳小説は訳の不自然さが嫌になって投げ出すことが多いのだけれど、抵抗感なく読めます。
(翻訳文学の好悪は翻訳者が直接的に握っている。文学的な素養もないただの研究者が訳出した本が多いから、翻訳本は売れないんだろうと思う。小説家が訳すのも良いし、上手な翻訳者が出てくることも喜ばしいことだ。最近だとゲバラの「モータサイクル・ダイアリーズ」なんかも違和感がなくて素晴らしかった。 あと日本の純文学は文体に偏り過ぎてる。村上春樹を純文学と認めない一部の風潮が象徴しているように。文学雑誌を買って読んでみたんだが、作者たちの文学青年ぶりが鼻についてとても読めたもんじゃなかった。)
小説が面白いかどうかは微妙なところだ。正直。それでも読み続けたい、と思わせるのはオーウェル本人のことをもっと知りたいと思うからなんじゃないだろうか。それなら演劇でも映画でもオペラでもミュージカルでも美術なんかでも良いんだけれど、僕は紙とインクと言葉だけで成り立ってるこの小説の、とってもシンプルで洗練された在り方に、他のどの芸術よりも愛着と共感を覚えます。
結局作品についてなんも書いてないや。読み終わったらなんか書くかも知れませんね。じゃ。
モーターサイクル・ダイアリーズ (角川文庫)/エルネスト・チェ ゲバラ
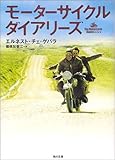
コレ
↓最近観た映画たち。どれも面白いっすよ。あともう二本くらい観たんだが忘れた。
エターナルサンシャイン DTSスペシャル・エディション [DVD]/ジム・キャリー,ケイト・ウィンスレット,キルステン・ダンスト
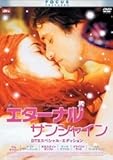
恋人との大切な思い出を失ってしまったらどうしますか?泣けるかも
デッドマン・ウォーキング [DVD]/スーザン・サランドン,ショーン・ペン,ロバート・プロスキー
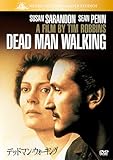
廃止/肯定は別にして、死刑に興味ある人は観るべき。むしろこれを観ずに死刑を語るなと言いたい
ジョー・ブラックをよろしく 【プレミアム・ベスト・コレクション¥1800】 [DVD]/アンソニー・ホプキンス,ジェイク・ウェバー,ジェフリー・タンバー

テンポ感悪し。ストーリーは面白い。ブラピの死神は格好良いよ
ビューティフル・マインド [DVD]/エド・ハリス,クリストファー・プラマー,ラッセル・クロウ
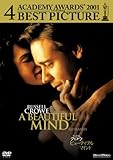
少しコワい映画。天才数学者の実話をもとにしたサスペンス(?)
ケンタッキー・フライド・ムービー [DVD]/ドナルド・サザーランド,ジョージ・レーゼンビー

稀に見るバカムービー。外人のギャグセンスで笑えたのは初めてかもしれん
JUNO/ジュノ<特別編> [DVD]/エレン・ペイジ,マイケル・セラ,ジェニファー・ガーナー
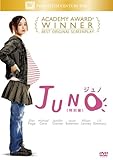
奔放な女子高生が性的に色々ヤッちゃう話
海辺のカフカ後編
やっと読み終わった。「海辺のカフカ」を読んで再確認したことがある。それは村上春樹という作家には、評論や批評、分析が必要ないということ。作品が、登場人物がそれらを求めていない。では私達読者は何をすれば良いのだろう。一つの作品を読み終えた満足感を一人で味わうのは、味気ないものだ。
説明か。説明であれば確かに角はたたない。でも小説を前にすると、説明はナンセンスだ。それは文学であろうと美術であろうと必要のない余剰物だ。僕が思うに、感想だろう思う。玄人ぶった解説や評論ではなく、素直な一個人としての感想だけが村上春樹を語り得るように思う。
例えば下巻の最後の辺りに、トラック運転手の青年が白いぬめった物体と戦うシーンがある。前にも後にも説明がないもんだから、よく意味がわからない。しかも物語としては、重要な情景である気がする。それを文学史に照らして「あれはポスト・モダンの産んだ“恐れ”を表象している」とか「村上春樹の生い立ちに鑑みて、筆者の無理解な他者大多数に対する距離感を映像的に表した」とか、その類の知ったかぶった評論は筆者にも読者にも届かない空虚な言葉の羅列なんだろうなぁと思う。
「よく分かんなかったけど、面白かったね」とか「あのシーンがとても印象に残ったんだよね」とか、「読みやすいけどよく分かんね。こんなの作者のオナニーだよ」とかそういうシンプルな感想の方が素直に作品を表せてる気がする。
とまぁ前置きは置いといて。僕個人として「カフカ」はまぁまぁ面白く読ませてもらった。上巻の面白さにくらべると下巻は冗長で、読むのに苦労した。分量的には3/4くらいで良いかも。最後の辺りは面白かった。
暗喩だの隠喩だのメタファーとは別に、作品を流れる「孤独な人間としての僕」という感覚にはとても共感した。村上春樹という人は、よくも悪くも童心というか青年の心を持ち続けてるんだと思う。しかもなんだか寂しい青年時代を過ごした記憶、感覚。
家庭は彼を理解しようとしなかったし、周りの人もそうだった。でもごく一部の人たちだけが、それは図書館職員の性同一障害でゲイの女性だったり、ゆきずりの女性だったかもしれないけれど、彼の事を分かってくれた。
主人公の「田村カフカ」は父親を殺して、母親や姉とセックスする。幸せな家庭に生まれていればこんな設定にしないんじゃないかな。そう思います。人間同士の関係が希薄になっている現代に、村上春樹の小説が当たるのはなんとなく分かる気がする。良い意味で時代を象徴してるのかな。
村上ハルキ作品は「色付された無気力」だと思う。物語として面白いから読んでる時は良いんだけど、読み終わった後になにも残らない。鮮明なイメージが交錯してドキドキするし、なんだか“オシャレな”小道具が配置されているから錯覚も起こす。そして“メタファー”だ。村上作品の芸術的価値というのは、文学のものではなく、そのイメージによる色使いの面白さ、それは例えば絵画的な面白さだと思うんだ。
良い、悪い、は別にしてやっぱり村上春樹の作品は純文学だと思う。そしてごく個人的な感想として、僕は彼のことを余り好きになれそうにない。小説は面白いからこれからも読み続けるし、その過程で僕自身変わることもあるかもしれないが、暫定的にそう感じた。
さて、次は1Q84だ。まずはオーウェルの1984年を新訳で読もうかと思う。それでは。
一九八四年[新訳版] (ハヤカワepi文庫)/ジョージ・オーウェル

¥903
Amazon.co.jp
もう買いました
説明か。説明であれば確かに角はたたない。でも小説を前にすると、説明はナンセンスだ。それは文学であろうと美術であろうと必要のない余剰物だ。僕が思うに、感想だろう思う。玄人ぶった解説や評論ではなく、素直な一個人としての感想だけが村上春樹を語り得るように思う。
例えば下巻の最後の辺りに、トラック運転手の青年が白いぬめった物体と戦うシーンがある。前にも後にも説明がないもんだから、よく意味がわからない。しかも物語としては、重要な情景である気がする。それを文学史に照らして「あれはポスト・モダンの産んだ“恐れ”を表象している」とか「村上春樹の生い立ちに鑑みて、筆者の無理解な他者大多数に対する距離感を映像的に表した」とか、その類の知ったかぶった評論は筆者にも読者にも届かない空虚な言葉の羅列なんだろうなぁと思う。
「よく分かんなかったけど、面白かったね」とか「あのシーンがとても印象に残ったんだよね」とか、「読みやすいけどよく分かんね。こんなの作者のオナニーだよ」とかそういうシンプルな感想の方が素直に作品を表せてる気がする。
とまぁ前置きは置いといて。僕個人として「カフカ」はまぁまぁ面白く読ませてもらった。上巻の面白さにくらべると下巻は冗長で、読むのに苦労した。分量的には3/4くらいで良いかも。最後の辺りは面白かった。
暗喩だの隠喩だのメタファーとは別に、作品を流れる「孤独な人間としての僕」という感覚にはとても共感した。村上春樹という人は、よくも悪くも童心というか青年の心を持ち続けてるんだと思う。しかもなんだか寂しい青年時代を過ごした記憶、感覚。
家庭は彼を理解しようとしなかったし、周りの人もそうだった。でもごく一部の人たちだけが、それは図書館職員の性同一障害でゲイの女性だったり、ゆきずりの女性だったかもしれないけれど、彼の事を分かってくれた。
主人公の「田村カフカ」は父親を殺して、母親や姉とセックスする。幸せな家庭に生まれていればこんな設定にしないんじゃないかな。そう思います。人間同士の関係が希薄になっている現代に、村上春樹の小説が当たるのはなんとなく分かる気がする。良い意味で時代を象徴してるのかな。
村上ハルキ作品は「色付された無気力」だと思う。物語として面白いから読んでる時は良いんだけど、読み終わった後になにも残らない。鮮明なイメージが交錯してドキドキするし、なんだか“オシャレな”小道具が配置されているから錯覚も起こす。そして“メタファー”だ。村上作品の芸術的価値というのは、文学のものではなく、そのイメージによる色使いの面白さ、それは例えば絵画的な面白さだと思うんだ。
良い、悪い、は別にしてやっぱり村上春樹の作品は純文学だと思う。そしてごく個人的な感想として、僕は彼のことを余り好きになれそうにない。小説は面白いからこれからも読み続けるし、その過程で僕自身変わることもあるかもしれないが、暫定的にそう感じた。
さて、次は1Q84だ。まずはオーウェルの1984年を新訳で読もうかと思う。それでは。
一九八四年[新訳版] (ハヤカワepi文庫)/ジョージ・オーウェル

¥903
Amazon.co.jp
もう買いました
最高の人生の見つけ方 ラブ・アクチュアリー
~暇人を装うのは簡単だ。僕はそうして詩人になった。 byヴィヨン~
現実から目を背けると目に入るのはフィクションばかりです。逃げた先の洞穴には、誰の目にも明らかな落とし穴がある訳ですが。見え透いた罠にこそハマる、甘美なもんです。…えぇ映画を観たんです。しかも二本。馬鹿ですね。
「最高の人生の見つけ方」
例えばあなたは映画に何を求めますか?ストーリー、アクション、カメラワーク、配役、音楽、感動、希望、愛、暴力、リアルな現実、夢。なんだかこの映画観るとそんな些細な事がどうでも良くなった。ストーリー、月並。笑いも大したことない。音楽なんかほとんど流れないし、配役もベタと言える。映画としては失敗の部類に入れても良いと思う。個人的には。期待は裏切られます。
でも観てる途中でびっくりした。すごくドキドキしたんだ。この映画はモーガン・フリーマンとジャック・ニコルソン、二人の演技を見せるためだけの作品だ。ストーリーも、セットもCGも監督も、彼らには必要ない。映画でなくて良いんだよ。舞台でも良い。テレビでも良い。この二人がいるだけで物語になってしまう。
映画の全てを二人が各々食ってしまった。そこに浮かび上がるのはフィクションの快さを排除した、名優の裸の生き様だ。一回観ただけでインスタントな感動が味わえる安っぽい映画ではなく、何度観てもいい実に“味のある”映画だった…という感想です。余りにも自分中心の感覚だったので、他人には勧めません。ジャック&モーガン好きな人が観れば良いと思います。
最高の人生の見つけ方 [DVD]/ジャック・ニコルソン,モーガン・フリーマン,ショーン・ヘイズ
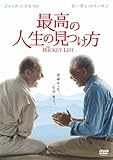
「ラブ・アクチュアリー」
9組くらいのカップルの栄枯盛衰が立体的に交差して、ハッピーエンドに向かっていく素敵なロマンティック・コメディー。観たあとは幸せな気分になります。…前から思ってたけど、クリスマスを題材にした映画はどこかにそう表示して欲しいよな。クリスマス以外に観ると妙な違和感に襲われるよ。別にいいけどさ。
当たり前ですがカップル覚えるのが大変です。最初から集中してストーリー追ってないと、誰が誰やら分かんなくなります。男優は特に。笑。それでも楽しめますが。人数が多い分飽きずに観る事ができる。ちょいちょい良いシーンがあちこちに散らばってます。首相のシーンとか鳩山さんに見習わせたいです。
軽くて観やすくて、そんなに安っぽくもないいい感じの映画。Mr.ビーンの人は出番が少ないながら美味しい役どころですね。
ラブ・アクチュアリー 【プレミアム・ベスト・コレクション¥1800】 [DVD]/エマ・トンプソン,ローラ・リニー,ローワン・アトキンソン
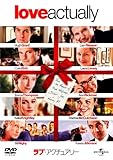
現実から目を背けると目に入るのはフィクションばかりです。逃げた先の洞穴には、誰の目にも明らかな落とし穴がある訳ですが。見え透いた罠にこそハマる、甘美なもんです。…えぇ映画を観たんです。しかも二本。馬鹿ですね。
「最高の人生の見つけ方」
例えばあなたは映画に何を求めますか?ストーリー、アクション、カメラワーク、配役、音楽、感動、希望、愛、暴力、リアルな現実、夢。なんだかこの映画観るとそんな些細な事がどうでも良くなった。ストーリー、月並。笑いも大したことない。音楽なんかほとんど流れないし、配役もベタと言える。映画としては失敗の部類に入れても良いと思う。個人的には。期待は裏切られます。
でも観てる途中でびっくりした。すごくドキドキしたんだ。この映画はモーガン・フリーマンとジャック・ニコルソン、二人の演技を見せるためだけの作品だ。ストーリーも、セットもCGも監督も、彼らには必要ない。映画でなくて良いんだよ。舞台でも良い。テレビでも良い。この二人がいるだけで物語になってしまう。
映画の全てを二人が各々食ってしまった。そこに浮かび上がるのはフィクションの快さを排除した、名優の裸の生き様だ。一回観ただけでインスタントな感動が味わえる安っぽい映画ではなく、何度観てもいい実に“味のある”映画だった…という感想です。余りにも自分中心の感覚だったので、他人には勧めません。ジャック&モーガン好きな人が観れば良いと思います。
最高の人生の見つけ方 [DVD]/ジャック・ニコルソン,モーガン・フリーマン,ショーン・ヘイズ
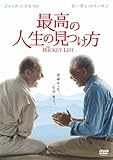
「ラブ・アクチュアリー」
9組くらいのカップルの栄枯盛衰が立体的に交差して、ハッピーエンドに向かっていく素敵なロマンティック・コメディー。観たあとは幸せな気分になります。…前から思ってたけど、クリスマスを題材にした映画はどこかにそう表示して欲しいよな。クリスマス以外に観ると妙な違和感に襲われるよ。別にいいけどさ。
当たり前ですがカップル覚えるのが大変です。最初から集中してストーリー追ってないと、誰が誰やら分かんなくなります。男優は特に。笑。それでも楽しめますが。人数が多い分飽きずに観る事ができる。ちょいちょい良いシーンがあちこちに散らばってます。首相のシーンとか鳩山さんに見習わせたいです。
軽くて観やすくて、そんなに安っぽくもないいい感じの映画。Mr.ビーンの人は出番が少ないながら美味しい役どころですね。
ラブ・アクチュアリー 【プレミアム・ベスト・コレクション¥1800】 [DVD]/エマ・トンプソン,ローラ・リニー,ローワン・アトキンソン
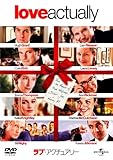
今敢えて海辺のカフカを読んでる。
今朝方上巻を読み終わりました。メモ程度に徒然に記します。備考録的に。まとまってないんで興味ない人は読まなくてよし。
作品が作者を映す鏡である、とどこかで聞いた気がする。なら村上春樹の小説が村上春樹自身を表している、と言っても語弊はないはずだ。彼は解釈を、分析を、理解を、主観の立ち入る一分の隙間を認めない。ただムラカミ・ハルキというあるがままの存在を受け入れることだけを願っている、そんな印象を「海辺のカフカ」から受けた。
泉鏡花は作品中に出てくる女性を通して、“母”への憧れを、少年のような純粋さで書いたらしい。村上春樹も作品を通して女性の理想像を追っているように感じるが、少年というよりは青年の、しかもどうやら母親というフィルターを通していないように思う。
では村上春樹の描く異性への憧れは、誰に対して向けられるものであるのか。恋人、姉、行きずりの、少女に対する?結論から言えば小説を2,3かじった程度ではどうも分からん。彼自身にも分からないままに探している印象をうけるが。泉鏡花が女性に包容されているのに対して、村上春樹は女性と一定の距離を保っている(セックスはするけど)。
そういえば彼の小説には“家庭”が希薄だ。「海辺のカフカ」の中でも母親は黙示録的に描かれていて、タブー視されている。この人間関係をどう読みとけば良いのやら。
「カフカ」の中で年上の女性ふたりを主人公田村カフカの姉と母親になぞらえてる箇所がある。こんなことを自分で書くから評論家から嫌われるのだと思うが、僕はなんだか引っ掛かりを感じる。素直に行きずりの年上女性から受ける好意をそのまま書いただけなのかなぁ?
敢えて分からないようにしているのなら妻に対して、本人も気付いてないのならまだ見ぬ娘に対しての憧れなんだろうか。それとも60年代を生きたヒッピー的な普遍世界でも体現してるんだろうか。彼の小説を誠実に読めば答えは出るのだろう。まだ分からないということは僕はまだ充分な労力を彼の著作に振り分けてないってことなんだろうけど。僕にとって村上春樹の内面世界はカオスだ。
あと「カフカ」は「ノルウェイの森」に較べてさらに主人公の感情の起伏が少ないように感じた。1Q84ではどうなっちゃうんだろう。楽しみだ。
ナカタという文字の読めない老人が新宿で迷っている時に、若い女性の二人組が手助けする描写がある。そのうち一人は茶髪なんだが、それになんだか救われたような気持ちになったのは僕だけ?現代の若者は誤解されがちだと思う。文学の中で茶髪の若者をポジティブに描いた作品を僕は他に知らない。素直に嬉しかった。
人間にとって最大の哀しみは他人からの無理解だと思う。村上春樹の小説では理解者/無理解な多数者の線引きがはっきりしている。僕の経験を踏まえて言えば、この種の区別をする契機は両親からの無理解であることが多い。村上春樹も多感な時期を親の無理解の中で育ったんだろうと憶測している。彼の現在の排他的な人間関係からも香ってくることでもあるが。
最後に自称“ハルキスト”について書きたい。昨日Mr.サンデーとかいう新番組で1Q84ブームをかなり懐疑的な目線で分析していた(リンク先で2ちゃん実況板の空気感をお楽しみください)。Book3の発売日の晩に集会を開くハルキストがいたそうだ。なんか「メタな視線が…」とか「ハルキはコミットメントを分かってる」とかマジで笑わせる発言を繰り広げてて一人でニヤニヤしてた。あとヒップホップ聞きながら読むヤツとか、「自分を描いた小説みたい」とか平気で抜かしてるヤツもいた。
1Q84はBook12合わせて200万部以上売り上げてるらしい。僕にはどうも日本人一億人中、(例えば)田村カフカと多く共通点を持つ(≒共感する、感情移入する)人間が100万人もいるとは思えない。あの番組を観て、むしろ可能性として高いのは、田村カフカと共通点を持ち“たがる”人数がそれと合致することだろうなと思う。
多くの日本人が社会の一員として機能する事になんら違和感をもっていないと思う。村上春樹の書く主人公がもし存在するとすれば、何らかの形で社会からドロップアウトしてるに違いない。
だとすれば村上春樹の購買層ってのはハルキ的な人ではなく、ハルキ的な生き方にただ単に憧れてる人じゃないかな。もっと言えば内容を理解してるのか、そもそも読んでいるかも怪しいと思う。不十分な理解での横文字の使用が作品の中でバカにされてるのに、得意げに使ういわゆるハルキスト(この語感にも吐き気を感じるが)の鈍い感性をなんとかして欲しいと思う。
本当に村上春樹を愛好する人は愚かしいブームが落ち着いた時に本屋に行くだろう。村上春樹ファンを公言する恥ずかしさを知っているからこそ、一人で単行本にカバーでも掛けて読むことだろう。もし本当に村上春樹を愛好するのであれば、純文学にも多少のウンチクはあるだろうし、当然同時期に発売された大江健三郎の「水死」も読んでいることだろう。大江健三郎が読みにくいとか笑かしてくれるよ、マジで。村上春樹は読みやすいけど純文学なんだぜ?大江文学を読むことすらできない人間に村上春樹を理解することができるとは思えないね。「水死」がベストセラーやミリオンセラー、それどころか増刷になったニュースもヒットしません。近年稀に見る純文学らしい純文学なのに。
村上春樹本人は 『遠い太鼓』の中で、作品が売れ始めた頃は嬉しかったが、それが自分には想像不可能な人の数になるにつれて、むしろ自分は憎まれているような孤独を感じたと綴っている。えぇ分かる気がします。
あぁ別に僕自身は村上春樹を愛好してるわけではないです、念のため。尊敬はするけど好きでもキライでもないです。一般論として読んでください。
海辺のカフカ (上) (新潮文庫)/村上 春樹

海辺のカフカ (下) (新潮文庫)/村上 春樹

¥780
Amazon.co.jp
読み終わって発見があれば書きます
1Q84 BOOK 3/村上春樹

¥1,995
Amazon.co.jp
全国的に売り切れが続出している中、某書店ではバベルの塔の様に積み上げられてるのを目撃。100冊はあったな…。出版流通の問題をまざまざと見させてもらった
水死 (100周年書き下ろし)/大江 健三郎

読んであげてください
作品が作者を映す鏡である、とどこかで聞いた気がする。なら村上春樹の小説が村上春樹自身を表している、と言っても語弊はないはずだ。彼は解釈を、分析を、理解を、主観の立ち入る一分の隙間を認めない。ただムラカミ・ハルキというあるがままの存在を受け入れることだけを願っている、そんな印象を「海辺のカフカ」から受けた。
泉鏡花は作品中に出てくる女性を通して、“母”への憧れを、少年のような純粋さで書いたらしい。村上春樹も作品を通して女性の理想像を追っているように感じるが、少年というよりは青年の、しかもどうやら母親というフィルターを通していないように思う。
では村上春樹の描く異性への憧れは、誰に対して向けられるものであるのか。恋人、姉、行きずりの、少女に対する?結論から言えば小説を2,3かじった程度ではどうも分からん。彼自身にも分からないままに探している印象をうけるが。泉鏡花が女性に包容されているのに対して、村上春樹は女性と一定の距離を保っている(セックスはするけど)。
そういえば彼の小説には“家庭”が希薄だ。「海辺のカフカ」の中でも母親は黙示録的に描かれていて、タブー視されている。この人間関係をどう読みとけば良いのやら。
「カフカ」の中で年上の女性ふたりを主人公田村カフカの姉と母親になぞらえてる箇所がある。こんなことを自分で書くから評論家から嫌われるのだと思うが、僕はなんだか引っ掛かりを感じる。素直に行きずりの年上女性から受ける好意をそのまま書いただけなのかなぁ?
敢えて分からないようにしているのなら妻に対して、本人も気付いてないのならまだ見ぬ娘に対しての憧れなんだろうか。それとも60年代を生きたヒッピー的な普遍世界でも体現してるんだろうか。彼の小説を誠実に読めば答えは出るのだろう。まだ分からないということは僕はまだ充分な労力を彼の著作に振り分けてないってことなんだろうけど。僕にとって村上春樹の内面世界はカオスだ。
あと「カフカ」は「ノルウェイの森」に較べてさらに主人公の感情の起伏が少ないように感じた。1Q84ではどうなっちゃうんだろう。楽しみだ。
ナカタという文字の読めない老人が新宿で迷っている時に、若い女性の二人組が手助けする描写がある。そのうち一人は茶髪なんだが、それになんだか救われたような気持ちになったのは僕だけ?現代の若者は誤解されがちだと思う。文学の中で茶髪の若者をポジティブに描いた作品を僕は他に知らない。素直に嬉しかった。
人間にとって最大の哀しみは他人からの無理解だと思う。村上春樹の小説では理解者/無理解な多数者の線引きがはっきりしている。僕の経験を踏まえて言えば、この種の区別をする契機は両親からの無理解であることが多い。村上春樹も多感な時期を親の無理解の中で育ったんだろうと憶測している。彼の現在の排他的な人間関係からも香ってくることでもあるが。
最後に自称“ハルキスト”について書きたい。昨日Mr.サンデーとかいう新番組で1Q84ブームをかなり懐疑的な目線で分析していた(リンク先で2ちゃん実況板の空気感をお楽しみください)。Book3の発売日の晩に集会を開くハルキストがいたそうだ。なんか「メタな視線が…」とか「ハルキはコミットメントを分かってる」とかマジで笑わせる発言を繰り広げてて一人でニヤニヤしてた。あとヒップホップ聞きながら読むヤツとか、「自分を描いた小説みたい」とか平気で抜かしてるヤツもいた。
1Q84はBook12合わせて200万部以上売り上げてるらしい。僕にはどうも日本人一億人中、(例えば)田村カフカと多く共通点を持つ(≒共感する、感情移入する)人間が100万人もいるとは思えない。あの番組を観て、むしろ可能性として高いのは、田村カフカと共通点を持ち“たがる”人数がそれと合致することだろうなと思う。
多くの日本人が社会の一員として機能する事になんら違和感をもっていないと思う。村上春樹の書く主人公がもし存在するとすれば、何らかの形で社会からドロップアウトしてるに違いない。
だとすれば村上春樹の購買層ってのはハルキ的な人ではなく、ハルキ的な生き方にただ単に憧れてる人じゃないかな。もっと言えば内容を理解してるのか、そもそも読んでいるかも怪しいと思う。不十分な理解での横文字の使用が作品の中でバカにされてるのに、得意げに使ういわゆるハルキスト(この語感にも吐き気を感じるが)の鈍い感性をなんとかして欲しいと思う。
本当に村上春樹を愛好する人は愚かしいブームが落ち着いた時に本屋に行くだろう。村上春樹ファンを公言する恥ずかしさを知っているからこそ、一人で単行本にカバーでも掛けて読むことだろう。もし本当に村上春樹を愛好するのであれば、純文学にも多少のウンチクはあるだろうし、当然同時期に発売された大江健三郎の「水死」も読んでいることだろう。大江健三郎が読みにくいとか笑かしてくれるよ、マジで。村上春樹は読みやすいけど純文学なんだぜ?大江文学を読むことすらできない人間に村上春樹を理解することができるとは思えないね。「水死」がベストセラーやミリオンセラー、それどころか増刷になったニュースもヒットしません。近年稀に見る純文学らしい純文学なのに。
村上春樹本人は 『遠い太鼓』の中で、作品が売れ始めた頃は嬉しかったが、それが自分には想像不可能な人の数になるにつれて、むしろ自分は憎まれているような孤独を感じたと綴っている。えぇ分かる気がします。
あぁ別に僕自身は村上春樹を愛好してるわけではないです、念のため。尊敬はするけど好きでもキライでもないです。一般論として読んでください。
海辺のカフカ (上) (新潮文庫)/村上 春樹

海辺のカフカ (下) (新潮文庫)/村上 春樹

¥780
Amazon.co.jp
読み終わって発見があれば書きます
1Q84 BOOK 3/村上春樹

¥1,995
Amazon.co.jp
全国的に売り切れが続出している中、某書店ではバベルの塔の様に積み上げられてるのを目撃。100冊はあったな…。出版流通の問題をまざまざと見させてもらった
水死 (100周年書き下ろし)/大江 健三郎

読んであげてください
ニューズウィーク 3・24
ついにきましたね。ニューズウィークの日本批判。「トヨタが告げる日本の終わり」
Newsweek ( ニューズウィーク日本版 ) 2010年 3/24号 [雑誌]/著者不明

「00年代前半、『セレブ首相』の小泉純一郎の下で日本は『ナノ』や『バイオ』など最先端技術に活路を見出そうとしたが、どれも長続きしなかった。いまだに和製グーグルは生まれていない。」
「子育てと仕事で忙しい30~40代はどんな小さいリスクも嫌う。外食も旅行もしない巣ごもり族は、家でテレビやパソコンにかじりついている。草食系男子は遊びにも仕事にも消極的だ。」
「日本は国力の衰えを少子高齢社会の到来や国際政治における勢力図のせいにし、諦めの境地で競争力を失っていくのかもしれない。『しょうがない』とつぶやきながら。日本の衰退ペースが一気に加速することはないだろう。だが衰退を止めるブレーキはどこにもないという諦めムードが今の日本に漂っていることも確かだ。」
ええ、仰る通りです。叩かれると嬉しいんでもっと叩いてください。これまではなぜか日本に矛先が向かなかったニューズウィーク(トヨタの時も割とオブラートに包んでた気がする)ですが、いきなり核心ついてきましたね。まだ本気出してないみたいだけど。
僕は一日本人として、この論説に対して一言の反論もできない。アメリカからはるばる突きつけられるから驚きもするのだけれど、書いてある事は正に身の回りに転がってるものばかり。「お前に何が分かるんだ!」と言ってやりたいのは山々なんですけどね…。
日本の国力が衰えてるのは優れた指導者が出ていないから。それは政治家になる為の、なってからの維持にかかる費用が掛かり過ぎる結果、間口が狭まったから。それは政治家達が現状に甘んじて、保身も含めた意味での仕組作りをしてこなかったから。その政治家は私たち国民が選んできたのだから。
中堅社員が守りに入っているのは、いくら仕事をしてもそれに見合った報酬と地位を与えられないことが分かっているから。彼ら若手の意見を取り入れるには、日本の企業組織は閉鎖的過ぎるから。起業精神が育たないのは、政府が既存の企業の権益を守るために、補助を与えてこなかったから。
和製グーグルは生まれる可能性があった。いや、既に生まれていたと言って良い。その芽を摘んでしまったのは、他でもない日本の検察であり、影響力を持ち得た日本の政治家であり、それを煽ったマスコミであり、それを信じて疑わなかった日本の国民だ。
そう、日本の凋落はすべて私たち国民一人一人の怠慢によって起こされてきた。今でも日本経済大国神話を信じている国民が殆んどだろう。40代以上はバブルを懐かしむばかりだ。30代以下はもはや諦めて自分の幸せを追いかけている。(ホリエモン逮捕はその流れを間違いなく加速させた)
僕たち20代のうち優秀な人間は当たり前のように外資に就職してゆく。オリンピックでも振るわず、教師は国歌の斉唱を拒否して訴訟を起こす。政治家は政治を弄び、保身に走り、政局に対する興味しか持てない。若者は政治を語らず、文学を読まず、未来を祝わず、希望を忘れ、俯くばかりで、社会の中で可能性を磨り減らしてゆく。子供は笑わず、少女は歌わず、青年は妥協し、大人は徒に怒り、母は子供に当たり、老人は虐げられる。そんな日本。2010年の日本。
残念ながら日本は貧しい時は艱難を厭わないのに、裕福になると尊大になり享楽に走る、貧乏性の国民性を持ってるみたいだ。そして僕たち20代はそんな最悪な時代に、くだらない大人からのロクでもない教育で多感な時期を空費した挙句に、企業のエゴイズムに塗れた就職活動を経て、出世・昇給の見込みのない社会に放り出され、バブルで遊び呆けた老人の下の処理までしないといけないらしい。「クソッタレ!」
さて、アナタが30年後住む国は次のうちどれ?
①アメリカ
②中国
③インド
④極東のしがない島々(日本州?日本省?人住んでないかも)
僕は④だ。それでも僕はこの国を愛し、守っていく。俺にはすべき事がまだある。
Newsweek ( ニューズウィーク日本版 ) 2010年 3/24号 [雑誌]/著者不明

「00年代前半、『セレブ首相』の小泉純一郎の下で日本は『ナノ』や『バイオ』など最先端技術に活路を見出そうとしたが、どれも長続きしなかった。いまだに和製グーグルは生まれていない。」
「子育てと仕事で忙しい30~40代はどんな小さいリスクも嫌う。外食も旅行もしない巣ごもり族は、家でテレビやパソコンにかじりついている。草食系男子は遊びにも仕事にも消極的だ。」
「日本は国力の衰えを少子高齢社会の到来や国際政治における勢力図のせいにし、諦めの境地で競争力を失っていくのかもしれない。『しょうがない』とつぶやきながら。日本の衰退ペースが一気に加速することはないだろう。だが衰退を止めるブレーキはどこにもないという諦めムードが今の日本に漂っていることも確かだ。」
ええ、仰る通りです。叩かれると嬉しいんでもっと叩いてください。これまではなぜか日本に矛先が向かなかったニューズウィーク(トヨタの時も割とオブラートに包んでた気がする)ですが、いきなり核心ついてきましたね。まだ本気出してないみたいだけど。
僕は一日本人として、この論説に対して一言の反論もできない。アメリカからはるばる突きつけられるから驚きもするのだけれど、書いてある事は正に身の回りに転がってるものばかり。「お前に何が分かるんだ!」と言ってやりたいのは山々なんですけどね…。
日本の国力が衰えてるのは優れた指導者が出ていないから。それは政治家になる為の、なってからの維持にかかる費用が掛かり過ぎる結果、間口が狭まったから。それは政治家達が現状に甘んじて、保身も含めた意味での仕組作りをしてこなかったから。その政治家は私たち国民が選んできたのだから。
中堅社員が守りに入っているのは、いくら仕事をしてもそれに見合った報酬と地位を与えられないことが分かっているから。彼ら若手の意見を取り入れるには、日本の企業組織は閉鎖的過ぎるから。起業精神が育たないのは、政府が既存の企業の権益を守るために、補助を与えてこなかったから。
和製グーグルは生まれる可能性があった。いや、既に生まれていたと言って良い。その芽を摘んでしまったのは、他でもない日本の検察であり、影響力を持ち得た日本の政治家であり、それを煽ったマスコミであり、それを信じて疑わなかった日本の国民だ。
そう、日本の凋落はすべて私たち国民一人一人の怠慢によって起こされてきた。今でも日本経済大国神話を信じている国民が殆んどだろう。40代以上はバブルを懐かしむばかりだ。30代以下はもはや諦めて自分の幸せを追いかけている。(ホリエモン逮捕はその流れを間違いなく加速させた)
僕たち20代のうち優秀な人間は当たり前のように外資に就職してゆく。オリンピックでも振るわず、教師は国歌の斉唱を拒否して訴訟を起こす。政治家は政治を弄び、保身に走り、政局に対する興味しか持てない。若者は政治を語らず、文学を読まず、未来を祝わず、希望を忘れ、俯くばかりで、社会の中で可能性を磨り減らしてゆく。子供は笑わず、少女は歌わず、青年は妥協し、大人は徒に怒り、母は子供に当たり、老人は虐げられる。そんな日本。2010年の日本。
残念ながら日本は貧しい時は艱難を厭わないのに、裕福になると尊大になり享楽に走る、貧乏性の国民性を持ってるみたいだ。そして僕たち20代はそんな最悪な時代に、くだらない大人からのロクでもない教育で多感な時期を空費した挙句に、企業のエゴイズムに塗れた就職活動を経て、出世・昇給の見込みのない社会に放り出され、バブルで遊び呆けた老人の下の処理までしないといけないらしい。「クソッタレ!」
さて、アナタが30年後住む国は次のうちどれ?
①アメリカ
②中国
③インド
④極東のしがない島々(日本州?日本省?人住んでないかも)
僕は④だ。それでも僕はこの国を愛し、守っていく。俺にはすべき事がまだある。