市民文学としてのクチコミ、サクラ騒動
ちょっと色々お店を食べログで調べていたんだけど、本当に色んなレビューがあって驚く。八割方のクチコミで「リピはなしです」「あぁ食べログ読むんだった」と酷評されてる中で、かなり始めの方に嘘臭いテンションで「味・接客・雰囲気三拍子揃ったお店!☆5つ!」とか書いてて、しかもレビューはそれ一件だけという、えぇもう完全にお店の人でしかないです。お疲れ様です、本当に。大変だね飲食店はとか色々考えさせられた。

そういえば食べログのサクラ騒動が新聞を賑わしていたらしいですね。店からお金を貰ってレビューを書く業者がいたとか。まぁ多少なりともネットになれた人ならレビューの温度差を感じられるだろうから、そんなに騒ぐほとのことかね、とも思う。で。クチコミ見てるとなかなか面白い文章書く人いっぱいいますね。正直なところ、たかが食い物のために30行も40行も文章書く人の気が知れないとは思うんですが、時折キラリと輝くというか、引きこまれて読んでしまうようなレビュアーの方も結構いて、侮れないなと今さっき思いました。
勝手に引用しちゃおう。例えばこんな方。食べログレビュアーの火胃俗皇・Kさん。
・もう逃れられない、夜のワールド。
・新たなカレーよ、こんにちは。
・この店(店主)、サービス過剰につき。
・あら煮でトランス状態に(笑)
・肉よ、肉よ。
僕はもうこのタイトルのネーミングセンスに脱帽です。どんな内容だよ!って読みたくなりません?笑。もう半分吹き出しながら読んでたんですが、これがまた面白い。
地下鉄「本郷三丁目」より徒歩5分圏内に立地。出逢いは、ある夜に突然訪れたのだった。そろそろと静かに何気なく。けれど今となっては、超一流店特有の圧倒的なインパクト、爪痕が私の中に深く刻まれて消しようもない。消したくもないが。とにかく、また再訪しなくてはいけない。近日中にだ。(『この店(店主)、サービス過剰につき。』より)
再び訪れたこの店。原則的にどれを食べても「美味い」のが基本線(苦笑)。かなり美味い、凄く美味い、とんでもなく美味いで終始した。恐るべき1時間半。ややオーバーに言うなら、自らの人生においてある意味で有史的な時間を過ごした。ここまで客に悟らせるとは。これぞ超一流の証である。今回は裏メニューとして名高い「焼ユッケ」「握り寿司」などを注文。どちらも独創性豊かで味はもう何も言うまい。ただし、もっと美味く個人的に既存の価値観が嬉しく弾けまくったのは、「煮込み」であった。こんなの出しちゃ他店は己との差におののき、皆泣くだろう。私はもう他店では満足できないのではないか。(『「超一流の肉」に、追いつけない(笑)』より)
決して辛くはないのだが、色々なスパイスをどうしても感じてしまうのだ。間違いなく、この店でしか食べられない味である。要するに凄く、新しい。初めての感じだ。カレーなのに、「ここまで、違うのか」という思いと共に、今まで食べてきたカレーに対するイメージがガラガラと崩れ去ったのだった。(『新たなカレーよ、こんにちは。』より)
やはり間違いのない美味しさである。そう魚の目利きと調理方法が正確であるため必ず美味いのだ。ほぐれた魚の身とやや濃い目の甘辛の煮汁があいまってご飯と一緒に食べる時のこの幸福感はなんだ(苦笑)。今、振り返ると私は4口目位から先の記憶が無い。気づいたらもう骨しか残っていなかった・・・。というのは嘘だが、それに近いトランス状態を魚を使い何食わぬ顔して提供するとは、さすがの高格付店である。(『あら煮でトランス状態に(笑)』より)
などなど。これがレビューとしてどの程度機能してるか知らないけど、食べ物の驚きとか喜びなんかを真面目なんだか不真面目なんだか不思議なくらい情熱を傾けて書いていて、文章がうまいぶん余計におかしみがあってすごく楽しい。友人になったら面白い人なんだろうな、恥ずかしげのない感情表現がスカッとして気持ちいいです。
金銭目的でなく、また読者のためとかいうおためごかしでもない、ただ人が好きで書いてる文章の良さってものを考えさせられました。サクラ騒動は国まで絡んで面倒なことになりそうですが、もともと人が集まる仮想コミュニティーなのだから、問題が起きるのは当然で、また相手の話を信じるかどうか、虚実ないまぜになってるネット上での判断力というのはサクラがあろうがなかろうかどのみち必要とされている。
いつ頃からか言われだした「自己責任」の時代を生きている僕らは、その代わりに、広大な情報の海の中から優れた友人を見つけ出し情報を共有することで、いままで考えられなかったくらい利便や繋がる喜びを享受しているんだな。火胃俗皇さんにしても、こんな文章を読めるのはレビューサイトだけだろうし、同じ時間を生きる他人が何を考えてるのかを肌感覚で知れる楽しみがある。
そうした意味で食べログにしろアマゾンにしろ、レビューというのは文章が生きていて、ある意味「市民文学」のような存在になり得るのかなと思う。勿論火胃俗皇さんの文章は、他のレビュアーのそれと較べて異色なものなのだけれど、たかが食べ物や商品レビューとはいえ、そこに籠った思いは本物で、間違いなく人へ伝わるなにかがあるんだと思うし、そうした可能性をレビューサイトは秘めている。
食べログやアマゾンで自分の好きなお店、好きな映画や小説を検索してみて、自分の価値観が一致するレビュアーの他のレビューに触れることの楽しさ。自分の嗜好にあった情報を容易に得られる便利さというものを、このサクラ騒動でみんな噛み締めるべきなんじゃないかと僕はおもいますね。つまりはサクラ騒動がどうあれレビュー文化はこれからも必要とされてゆくし、その中でなにがしか面白い価値観が垣間見えるので、僕自身もそれを支持します。
まとまった、かな?まぁちょっと意味分かんないですけど、ふと思ったことを文章にしてみた。最近読んだ本について書いたり、関西人について書いてみたいのでそのうちアップするかもしれません。あと2011年の置き土産はまだ大量に残ってるのでそれも処分せんと。まぁそんな感じです。それでは、ごきげんよう。
「自己責任」とは何か (講談社現代新書)/桜井 哲夫

¥735
Amazon.co.jp

そういえば食べログのサクラ騒動が新聞を賑わしていたらしいですね。店からお金を貰ってレビューを書く業者がいたとか。まぁ多少なりともネットになれた人ならレビューの温度差を感じられるだろうから、そんなに騒ぐほとのことかね、とも思う。で。クチコミ見てるとなかなか面白い文章書く人いっぱいいますね。正直なところ、たかが食い物のために30行も40行も文章書く人の気が知れないとは思うんですが、時折キラリと輝くというか、引きこまれて読んでしまうようなレビュアーの方も結構いて、侮れないなと今さっき思いました。
勝手に引用しちゃおう。例えばこんな方。食べログレビュアーの火胃俗皇・Kさん。
・もう逃れられない、夜のワールド。
・新たなカレーよ、こんにちは。
・この店(店主)、サービス過剰につき。
・あら煮でトランス状態に(笑)
・肉よ、肉よ。
僕はもうこのタイトルのネーミングセンスに脱帽です。どんな内容だよ!って読みたくなりません?笑。もう半分吹き出しながら読んでたんですが、これがまた面白い。
地下鉄「本郷三丁目」より徒歩5分圏内に立地。出逢いは、ある夜に突然訪れたのだった。そろそろと静かに何気なく。けれど今となっては、超一流店特有の圧倒的なインパクト、爪痕が私の中に深く刻まれて消しようもない。消したくもないが。とにかく、また再訪しなくてはいけない。近日中にだ。(『この店(店主)、サービス過剰につき。』より)
再び訪れたこの店。原則的にどれを食べても「美味い」のが基本線(苦笑)。かなり美味い、凄く美味い、とんでもなく美味いで終始した。恐るべき1時間半。ややオーバーに言うなら、自らの人生においてある意味で有史的な時間を過ごした。ここまで客に悟らせるとは。これぞ超一流の証である。今回は裏メニューとして名高い「焼ユッケ」「握り寿司」などを注文。どちらも独創性豊かで味はもう何も言うまい。ただし、もっと美味く個人的に既存の価値観が嬉しく弾けまくったのは、「煮込み」であった。こんなの出しちゃ他店は己との差におののき、皆泣くだろう。私はもう他店では満足できないのではないか。(『「超一流の肉」に、追いつけない(笑)』より)
決して辛くはないのだが、色々なスパイスをどうしても感じてしまうのだ。間違いなく、この店でしか食べられない味である。要するに凄く、新しい。初めての感じだ。カレーなのに、「ここまで、違うのか」という思いと共に、今まで食べてきたカレーに対するイメージがガラガラと崩れ去ったのだった。(『新たなカレーよ、こんにちは。』より)
やはり間違いのない美味しさである。そう魚の目利きと調理方法が正確であるため必ず美味いのだ。ほぐれた魚の身とやや濃い目の甘辛の煮汁があいまってご飯と一緒に食べる時のこの幸福感はなんだ(苦笑)。今、振り返ると私は4口目位から先の記憶が無い。気づいたらもう骨しか残っていなかった・・・。というのは嘘だが、それに近いトランス状態を魚を使い何食わぬ顔して提供するとは、さすがの高格付店である。(『あら煮でトランス状態に(笑)』より)
などなど。これがレビューとしてどの程度機能してるか知らないけど、食べ物の驚きとか喜びなんかを真面目なんだか不真面目なんだか不思議なくらい情熱を傾けて書いていて、文章がうまいぶん余計におかしみがあってすごく楽しい。友人になったら面白い人なんだろうな、恥ずかしげのない感情表現がスカッとして気持ちいいです。
金銭目的でなく、また読者のためとかいうおためごかしでもない、ただ人が好きで書いてる文章の良さってものを考えさせられました。サクラ騒動は国まで絡んで面倒なことになりそうですが、もともと人が集まる仮想コミュニティーなのだから、問題が起きるのは当然で、また相手の話を信じるかどうか、虚実ないまぜになってるネット上での判断力というのはサクラがあろうがなかろうかどのみち必要とされている。
いつ頃からか言われだした「自己責任」の時代を生きている僕らは、その代わりに、広大な情報の海の中から優れた友人を見つけ出し情報を共有することで、いままで考えられなかったくらい利便や繋がる喜びを享受しているんだな。火胃俗皇さんにしても、こんな文章を読めるのはレビューサイトだけだろうし、同じ時間を生きる他人が何を考えてるのかを肌感覚で知れる楽しみがある。
そうした意味で食べログにしろアマゾンにしろ、レビューというのは文章が生きていて、ある意味「市民文学」のような存在になり得るのかなと思う。勿論火胃俗皇さんの文章は、他のレビュアーのそれと較べて異色なものなのだけれど、たかが食べ物や商品レビューとはいえ、そこに籠った思いは本物で、間違いなく人へ伝わるなにかがあるんだと思うし、そうした可能性をレビューサイトは秘めている。
食べログやアマゾンで自分の好きなお店、好きな映画や小説を検索してみて、自分の価値観が一致するレビュアーの他のレビューに触れることの楽しさ。自分の嗜好にあった情報を容易に得られる便利さというものを、このサクラ騒動でみんな噛み締めるべきなんじゃないかと僕はおもいますね。つまりはサクラ騒動がどうあれレビュー文化はこれからも必要とされてゆくし、その中でなにがしか面白い価値観が垣間見えるので、僕自身もそれを支持します。
まとまった、かな?まぁちょっと意味分かんないですけど、ふと思ったことを文章にしてみた。最近読んだ本について書いたり、関西人について書いてみたいのでそのうちアップするかもしれません。あと2011年の置き土産はまだ大量に残ってるのでそれも処分せんと。まぁそんな感じです。それでは、ごきげんよう。
「自己責任」とは何か (講談社現代新書)/桜井 哲夫

¥735
Amazon.co.jp
続・高田渡 高田渡とお店
これも2011年の置き土産。高田渡についてはちょい前に生活の柄を取り上げて、エントリにしてたんですがまぁなんというか余計な理屈をこね過ぎて、高田渡の歌の良さでありその一種静かな佇まいを伝えきれたのか疑問が残ってます。そしてこの高田渡というフォークシンガーは不思議と誰かに教えたくなる人です。どうしてでしょうかね。さて。
今回は高田渡と土地です。歌に地名や店名を入れるということ、それは作詞者の土地への愛着を表すと思います。それはとても素朴な感情で、なんともいえない愁いがあります。古い歌なのですが、味わいのある2曲です。良ければ聴いてみてください。
ブラザー軒という洋食屋は仙台市は青葉区に今もあるそうです。このブログによれば太宰治の「惜別」にブラザー軒の記述があるんだとか。この詩は菅原克己という宮城出身の詩人によって作られたものだそうです。不思議な取り合わせの三人だなぁ。
珈琲不演唱歌(コーヒーブルースと読む)という曲です。三条堺町にあるイノダコーヒに若いころの高田渡はよく行ってたとか。なんてことのない歌詞だからこそ、余計にお店や土地に対する愛情を感じますね。最近では辻香織って歌手がカバーしていたりと、長く歌い継がれているようです。いい曲ですもんね。
固有名詞を歌うことで、同じものを愛する人たちの思いが交錯するのがわかります。地元の人であり、観光客であり、歌手であり、小説家であり。馬鹿馬鹿しく思う人もいるかもしれないですが、歌によって繋がる人の輪、その牧歌的な光景に僕は安心します。何気ないからこそ嘘偽りのない思いですから。
まぁそんな感じです。高田渡についてはもう一回書くかもしれません。最後に少しまじめにフォークについて書きたいですね。期待せずにお待ちください。生活の柄を寝ぼけながら歌う素敵な高田渡さんをおまけにつけときます。それではまた。
関連エントリ: 生活の柄 - 高田渡
ごあいさつ/高田渡
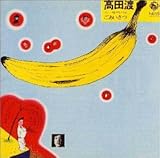
¥1,800
Amazon.co.jp
コーヒーブルース/スタンダード/辻香織

¥840
Amazon.co.jp
今回は高田渡と土地です。歌に地名や店名を入れるということ、それは作詞者の土地への愛着を表すと思います。それはとても素朴な感情で、なんともいえない愁いがあります。古い歌なのですが、味わいのある2曲です。良ければ聴いてみてください。
ブラザー軒という洋食屋は仙台市は青葉区に今もあるそうです。このブログによれば太宰治の「惜別」にブラザー軒の記述があるんだとか。この詩は菅原克己という宮城出身の詩人によって作られたものだそうです。不思議な取り合わせの三人だなぁ。
珈琲不演唱歌(コーヒーブルースと読む)という曲です。三条堺町にあるイノダコーヒに若いころの高田渡はよく行ってたとか。なんてことのない歌詞だからこそ、余計にお店や土地に対する愛情を感じますね。最近では辻香織って歌手がカバーしていたりと、長く歌い継がれているようです。いい曲ですもんね。
固有名詞を歌うことで、同じものを愛する人たちの思いが交錯するのがわかります。地元の人であり、観光客であり、歌手であり、小説家であり。馬鹿馬鹿しく思う人もいるかもしれないですが、歌によって繋がる人の輪、その牧歌的な光景に僕は安心します。何気ないからこそ嘘偽りのない思いですから。
まぁそんな感じです。高田渡についてはもう一回書くかもしれません。最後に少しまじめにフォークについて書きたいですね。期待せずにお待ちください。生活の柄を寝ぼけながら歌う素敵な高田渡さんをおまけにつけときます。それではまた。
関連エントリ: 生活の柄 - 高田渡
ごあいさつ/高田渡
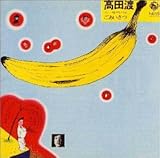
¥1,800
Amazon.co.jp
コーヒーブルース/スタンダード/辻香織

¥840
Amazon.co.jp
葉隠と近代ゴリラ
新年早々三島由紀夫のことを書きたいと思うのだ。別に預言者ぶって2012年に警鐘を鳴らすつもりなんか毛頭なく、ただ純粋に時間を持て余していて、たまたま本棚からまだ読んでない三島由紀夫が転がり落ちてきたというだけに過ぎない。その文学論であったり、修辞法的美学についてはいつかエントリで扱いたいとは思っているものの、今から書きたいのは彼の自衛隊市ヶ谷駐屯地での一種謎に包まれた死について、少し思うところがあるので書きたいと思った。ちなみに右翼的なエッセンスに関しては極力排してゆくので、そういう心づもりでここに辿りついた方は申し訳ないが、ブラウザを閉じて違うブログを読むことを強めにお勧めする。

この話は僕が年末に手に取った三島由紀夫が、『葉隠入門』であったところから始まる。何の気なしに読み進めてゆくと彼の死と葉隠という逆説的な教科書が密接に関係していることに気が付いた。三島由紀夫という男を抜きにしてもこの本は素朴に面白いので、色々と持て余している人は読んでみればいいと思う。
ヨーロッパ近代理念における愛国心も、すべてアガペーに源泉を持っているといってよい。しかし日本では極端にいうと国を愛するということはないのである。女を愛するということはないのである。日本人本来の精神構造の中においては、エロースとアガペーは一直線につながっている。ある女あるいは若衆に対する愛が、純一無垢なものになるときは、それは主君に対する忠となんら変わりはない。このようなエロースとアガペーを峻別しないところの恋愛観念は、幕末には「恋闕の情」という名で呼ばれて、天皇崇拝の感情的基盤をなした。いまや、戦前的天皇制は崩壊したが、日本人の精神構造の中にある恋愛観念は、かならずしも崩壊してるとはいえない。それは、もっとも官能的な誠実さから発したものが、自分の命を捨ててもつくすべき理想に一直線につながるという確信である。
そもそも三島事件とはどういう目的で起こされた事件なのだろう。僕はそんなに無垢な精神をもっていないので、彼が本気で自衛隊を決起させてクーデターを起こす意図を持っていたとは、三島の明晰な頭脳から考えられないと思うし、スピーカーを忘れたりといった杜撰なこともしているので、綿密に準備されたことのようにも思われない。
『豊饒の海』を上梓した三島にとって、彼の文壇それも海外も含めた範囲での評価は絶頂に達したものだと思う。惜しくも師匠筋の川端康成に先を越されたとはいえ、10年もすればノーベル賞を得ることも当然のように思われてただろうし、その結果後世における彼への評価も、その老後も安泰を約束されたと書いて過言ではないだろう。
安らかな後半生、潔白な名誉、文学者としての職業倫理をなげうってまで、成功の見込みのないクーデターを企てた三島由紀夫の意図はどこにあったろうと、恐らく三島事件を知る者は知れば知るほど分からなくなるんじゃないか。テロリストとしてタグ付けするのも、狂人扱いするのも、ただの極右だと判断することも、どこかしら思考に妥協があって、安易な気はしている。
そう言うと肉体への執着を持ち出す者がいる。ボディビルディングによって作りあげた肉体は、精神を再生させタフでマッチョな思考に三島を駆り立てたと共に、その肉体への精神依存、中年を過ぎて衰えゆくことへの恐怖を産みつけた。老残への蔑視が美しく強いままの姿での保存、自死へと導かれたのだとする。その自ら設定した結晶化の舞台が市ヶ谷駐屯地だったのではないかと言う。
また自己犠牲を叫ぶ人がいるかもしれない。始めからクーデターの成功を企図していた訳ではなく、事件を起こすことで戦後を生きる人々と自衛隊員の意識を変革を目指したのではないか。名声高い作家の自死を伴う事件の影響力の強さを吟味した上で、人柱として戦後社会に警鐘を鳴らそうとしたのではないか。そこには楯の会という彼の創作物が舞台装置として機能していて、自らを小説とある種の一体化を図ったのだと言う。
まぁ別に、これら言説はある意味での三島像を明瞭に描いている訳で、そこには一種真実めいた雰囲気もあって三島本人でなければ反論できない心理の問題でもあるのだから、僕らはなんとなく口を噤んで納得した風を装っている。しかしまぁどの説を咀嚼してみたところで、なんというか紙でも食ってるような二次元の味しかしていなくて、生きた人間の血の通った肉の味がそこにはない。
例えば純文学作家として、例えば国粋主義者として、例えばインテリゲンチャとして、僕たちは無意識のうちに三島由紀夫を偶像化していて賛美もしくは侮蔑している。どこかで理解出来ない生き物として彼を扱い、同じ人間としての素朴な共感を忘れている気がしている。本やブログを読んで受けるあくまでも僕の印象だが。それか彼の閉ざされた精神に足を踏み入れる事ができないだけなのか。
どちらにしても“奇矯(偉大)な行いをした小説家”として無意識に扱う僕ら後世の人間というのは、薄情というか冷たいというか。戦後を生きる僕らに命と名誉をかけて何かしらのメッセージを発した、三島という文化人に対する後ろめたさを感じるのは僕だけだろうか。そして今回葉隠入門を手にとってみて、三島由紀夫という孤独で難解な作家を理解する上で、彼と葉隠との関連はひとつの糸口となり得るように思ったのだ。
ここにただ一つ残る本がある。それこそ山本常朝の「葉隠」である。戦争中から読みだして、いつも自分の机の周辺に置き、以後二十数年間、折りにふれて、あるページを読んで感銘を新たにした本といえば、おそらく「葉隠」1冊であろう。わけても「葉隠」は、それが非常に流行し、かつ世間から必読の書のように強制されていた戦争時代が終わったあとで、かえってわたしの中で光を放ちだした。「葉隠」は本来そのような逆説的な本であるかもしれない。戦争中の「葉隠」は、いわば光の中に置かれた発光体であったが、それがほんとうに光を放つのは闇の中だったのである。
美しい日本語というのはタイプしながらでも生理的な快感があるもんだな。これは葉隠入門、「若い時代の心の伴侶としては、友だちと書物とがある。」という一節から始まる、プロローグ「葉隠」とわたし、から抜粋した。この前書きを読むだけで三島由紀夫にとって、葉隠という書物がいかに特別な存在であったか分かるんじゃなかろうか。しかも文字通り座右の書であり、彼の背骨となった書物であることが読み進めるにつれて段々分かってくる。
わたしは「葉隠」に、生の哲学を夙に見いだしていたから、その美しく透明なさわやかな世界は、つねに文学の世界の泥沼を、おびやかし挑発するものと感じられた。その姿をはっきり呈示してくれることにおいて、「葉隠」はわたしにとって意味があるのであり、「葉隠」の影響が、芸術家としてのわたしの生き方を異常にむずかしくしてしまったのと同時に、「葉隠」こそは、わたしの文学の母胎であり、永遠の活力の供給源であるといえるのである。すなわちその容赦ない鞭により、叱咤により、罵倒により、氷のような美しさによって。
そもそも葉隠とは、隠遁生活をしていた元佐賀藩士山本常朝のもとに通い、その語るところを筆記したもので、「鍋島論語」と呼ばれ尊重された武士の哲学書だそう。「武士道といふは、死ぬ事と見付けたり。」という有名な一節に代表されるように、その行動哲学は自発的な死の存在を前提としていかに生きるかについてを考える「侍」のそれである。
三島曰く葉隠には特色があって、死によって生を照らす(行動哲学)、滅私奉公の在り方女性の愛し方(恋愛哲学)、生活の上での具体的な知恵(生活哲学)の三つであるらしい。彼の愛した行動哲学に分類される最重要な一節と、訳を引用してみる。
「武士道は死狂ひなり。一人の殺害を数十人して仕かぬるもの。」と、直茂公仰せられ候。本気にては本業はならず。気違ひになりて死狂ひするまでなり。又武士道に於て分別出来れば、はや後るるなり。忠も孝も入らず、武士道に於ては死狂ひなり。この内に忠孝はおのづから籠るべし。
(訳)「武士道とは死に狂いである。そうした一人を倒すのに、数十人がかりでもできかねる場合がある。」と直茂公がおっしゃった。正気でいては、大仕事を達成することはできない。気ちがいになって、死に狂いするまでである。 また武士道では、思慮がうまれでると、すでにおくれをとったようなものである。武士道にとっては忠孝なども論外なので、ただ死に狂いがあるばかりである。そのなかに、忠孝は自然と宿るものだ。
三島の解説も引用する。ここに籠められた三島の思いというものは、三島事件に期待したであろうそれとかなりの部分で重複するように僕は思う。
前項の思想による欺瞞をもっともまぬがれた極致にあるものは、忠も孝も、あらゆる理念もいらない純粋行動の爆発の姿である。常朝はたんにファナチズムを容認するのではない。しかし行動が純粋形態をとったときに、おのずから忠と孝とをこもらせることになるかどうかは、予測のつくことではない。しかし、人間の行動は予測のつくことに向かってばかり発揮されるものではない。(中略)(別文引用)もし人間が行動を誤るとすれば、死ぬべきときに死なないことだと常朝は考えた。しかし、人間の死ぬときはいつもくるのではない。死ぬか生きるかの決断は、一生のうちについにこないかもしれない。常朝自身がそうであったように、彼が六十一歳で畳の上で死んだときに、あれほど日々心に当てた死が、ついにはこのような形で自分をおそってくることになるのを、どのような気持ちで迎えたであろうか。
1970年11月25日ないしその前夜、彼の心の伴侶として葉隠がまだ存在していたのであれば、書きぶりからから分かるように、彼は自死を含む自らの行動が狂気の沙汰(ファナティック)であることはまず理解していたことになる。そのうえで、仮に狂人扱いされたとしても、反理性行動に自ずから籠るであろう忠孝への共感を期待したのではないかと思う。
ではこの場合の忠孝とは何かと考えてみれば、晩年の三島が固執していた天皇制に向けられたものかもしれないが、『檄』ないし演説を読む限り彼の思いは天皇制だけに向けられたものではなく、その突き詰めた先にある“国家愛”へと強烈に向けられている。冒頭に引用したように日本人の国家への愛着は、伝統的に恋愛観念の形をとり、時に擬人化される。演説最後の万歳三唱は彼の“恋闕の情”であり、すなわち三島事件とは、虚弱な体躯で戦争時代を生きてしまった三島由紀夫という文化人の、国家への愛情の吐露に他ならない。身命を賭した告白だったのだ。
彼は悩んだだろう。栄達の約束された後半生、また築きあげてきた作家としての名声を、なげうち泥を塗ることになることが容易に考えられるからだ。後世からは畸形人として扱われ、その作品群は石もて打たれることになるかしれない。彼ほど明晰な頭脳を持った者が、生か死なら死を選べとする葉隠に、死によって名誉を得た人間の記載がないことにも気付いていたろう。なにより常朝自身が床の上で死ぬのである。自身で解釈しているように、葉隠はあくまで平和の世に生を見つめる書であるから、心得として死を想定していても、戦中なら知らず、実際に死の決断が迫られる時に敢えて死を選ぶことを必ずしも肯定していないのだ。
しかし彼は打算や勘定を侮蔑する常朝の言葉に共感する男だった。葉隠の定義する、ごく限定された武士像への憧憬を、少年の心で追い続ける知識人であった。同時に葉隠からの叱責に怯える芸能の従事者であった。三島の心の天秤は死へと傾く。武士に憧れ続けた男は、そうすることでしか武士になれなかった。奇人となり、狂人となり、犯罪者となり、作家であることを捨て、著作すべてに呪いをかけ、安らかな後半生を切り落として。
その動機を言葉にしたとき、戦後社会への失望にあったかもしれないし、肉体の衰退を恐れたと捉えることもできる。何らかの肉体・精神の不調を抱えていたかも知れない。老残への侮りであったかもしれないし、それはもしかすると三島の幼児性であったかもしれない。何が彼をそこへ駆り立てたのかなんて、他者としてのみ存在を許される僕らには結局のところ分かりっこない。三島研究者でもない僕がそれを語る資格もないように思う。
僕は三島事件を肯定しようとは思わない。どこかしら無理のある論理がそこには潜んでるように思う。僕は三島由紀夫の文章が好きだ。その分量を減らした事件を僕は憎んでいると言って良い。でも、命を賭けてこの国を愛した男がいたことを、馬鹿馬鹿しいほど大きな犠牲を払ってこの国に告白した男がいたことを、文化人のくせに行動の美徳に殉じた男がいたことを、僕は次世代へと伝えてゆくだろう。男らしさへの、古臭いものへの、理屈でわり切れないものへの憧れを。力強く放り投げた男がいたことを。
三島由紀夫vs東大全共闘(長尺版)
葉隠入門 (新潮文庫)/三島 由紀夫

¥452
Amazon.co.jp
三島由紀夫 (新文芸読本)/著者不明
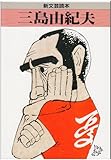
¥1,223
Amazon.co.jp

この話は僕が年末に手に取った三島由紀夫が、『葉隠入門』であったところから始まる。何の気なしに読み進めてゆくと彼の死と葉隠という逆説的な教科書が密接に関係していることに気が付いた。三島由紀夫という男を抜きにしてもこの本は素朴に面白いので、色々と持て余している人は読んでみればいいと思う。
ヨーロッパ近代理念における愛国心も、すべてアガペーに源泉を持っているといってよい。しかし日本では極端にいうと国を愛するということはないのである。女を愛するということはないのである。日本人本来の精神構造の中においては、エロースとアガペーは一直線につながっている。ある女あるいは若衆に対する愛が、純一無垢なものになるときは、それは主君に対する忠となんら変わりはない。このようなエロースとアガペーを峻別しないところの恋愛観念は、幕末には「恋闕の情」という名で呼ばれて、天皇崇拝の感情的基盤をなした。いまや、戦前的天皇制は崩壊したが、日本人の精神構造の中にある恋愛観念は、かならずしも崩壊してるとはいえない。それは、もっとも官能的な誠実さから発したものが、自分の命を捨ててもつくすべき理想に一直線につながるという確信である。
そもそも三島事件とはどういう目的で起こされた事件なのだろう。僕はそんなに無垢な精神をもっていないので、彼が本気で自衛隊を決起させてクーデターを起こす意図を持っていたとは、三島の明晰な頭脳から考えられないと思うし、スピーカーを忘れたりといった杜撰なこともしているので、綿密に準備されたことのようにも思われない。
『豊饒の海』を上梓した三島にとって、彼の文壇それも海外も含めた範囲での評価は絶頂に達したものだと思う。惜しくも師匠筋の川端康成に先を越されたとはいえ、10年もすればノーベル賞を得ることも当然のように思われてただろうし、その結果後世における彼への評価も、その老後も安泰を約束されたと書いて過言ではないだろう。
安らかな後半生、潔白な名誉、文学者としての職業倫理をなげうってまで、成功の見込みのないクーデターを企てた三島由紀夫の意図はどこにあったろうと、恐らく三島事件を知る者は知れば知るほど分からなくなるんじゃないか。テロリストとしてタグ付けするのも、狂人扱いするのも、ただの極右だと判断することも、どこかしら思考に妥協があって、安易な気はしている。
そう言うと肉体への執着を持ち出す者がいる。ボディビルディングによって作りあげた肉体は、精神を再生させタフでマッチョな思考に三島を駆り立てたと共に、その肉体への精神依存、中年を過ぎて衰えゆくことへの恐怖を産みつけた。老残への蔑視が美しく強いままの姿での保存、自死へと導かれたのだとする。その自ら設定した結晶化の舞台が市ヶ谷駐屯地だったのではないかと言う。
また自己犠牲を叫ぶ人がいるかもしれない。始めからクーデターの成功を企図していた訳ではなく、事件を起こすことで戦後を生きる人々と自衛隊員の意識を変革を目指したのではないか。名声高い作家の自死を伴う事件の影響力の強さを吟味した上で、人柱として戦後社会に警鐘を鳴らそうとしたのではないか。そこには楯の会という彼の創作物が舞台装置として機能していて、自らを小説とある種の一体化を図ったのだと言う。
まぁ別に、これら言説はある意味での三島像を明瞭に描いている訳で、そこには一種真実めいた雰囲気もあって三島本人でなければ反論できない心理の問題でもあるのだから、僕らはなんとなく口を噤んで納得した風を装っている。しかしまぁどの説を咀嚼してみたところで、なんというか紙でも食ってるような二次元の味しかしていなくて、生きた人間の血の通った肉の味がそこにはない。
例えば純文学作家として、例えば国粋主義者として、例えばインテリゲンチャとして、僕たちは無意識のうちに三島由紀夫を偶像化していて賛美もしくは侮蔑している。どこかで理解出来ない生き物として彼を扱い、同じ人間としての素朴な共感を忘れている気がしている。本やブログを読んで受けるあくまでも僕の印象だが。それか彼の閉ざされた精神に足を踏み入れる事ができないだけなのか。
どちらにしても“奇矯(偉大)な行いをした小説家”として無意識に扱う僕ら後世の人間というのは、薄情というか冷たいというか。戦後を生きる僕らに命と名誉をかけて何かしらのメッセージを発した、三島という文化人に対する後ろめたさを感じるのは僕だけだろうか。そして今回葉隠入門を手にとってみて、三島由紀夫という孤独で難解な作家を理解する上で、彼と葉隠との関連はひとつの糸口となり得るように思ったのだ。
ここにただ一つ残る本がある。それこそ山本常朝の「葉隠」である。戦争中から読みだして、いつも自分の机の周辺に置き、以後二十数年間、折りにふれて、あるページを読んで感銘を新たにした本といえば、おそらく「葉隠」1冊であろう。わけても「葉隠」は、それが非常に流行し、かつ世間から必読の書のように強制されていた戦争時代が終わったあとで、かえってわたしの中で光を放ちだした。「葉隠」は本来そのような逆説的な本であるかもしれない。戦争中の「葉隠」は、いわば光の中に置かれた発光体であったが、それがほんとうに光を放つのは闇の中だったのである。
美しい日本語というのはタイプしながらでも生理的な快感があるもんだな。これは葉隠入門、「若い時代の心の伴侶としては、友だちと書物とがある。」という一節から始まる、プロローグ「葉隠」とわたし、から抜粋した。この前書きを読むだけで三島由紀夫にとって、葉隠という書物がいかに特別な存在であったか分かるんじゃなかろうか。しかも文字通り座右の書であり、彼の背骨となった書物であることが読み進めるにつれて段々分かってくる。
わたしは「葉隠」に、生の哲学を夙に見いだしていたから、その美しく透明なさわやかな世界は、つねに文学の世界の泥沼を、おびやかし挑発するものと感じられた。その姿をはっきり呈示してくれることにおいて、「葉隠」はわたしにとって意味があるのであり、「葉隠」の影響が、芸術家としてのわたしの生き方を異常にむずかしくしてしまったのと同時に、「葉隠」こそは、わたしの文学の母胎であり、永遠の活力の供給源であるといえるのである。すなわちその容赦ない鞭により、叱咤により、罵倒により、氷のような美しさによって。
そもそも葉隠とは、隠遁生活をしていた元佐賀藩士山本常朝のもとに通い、その語るところを筆記したもので、「鍋島論語」と呼ばれ尊重された武士の哲学書だそう。「武士道といふは、死ぬ事と見付けたり。」という有名な一節に代表されるように、その行動哲学は自発的な死の存在を前提としていかに生きるかについてを考える「侍」のそれである。
三島曰く葉隠には特色があって、死によって生を照らす(行動哲学)、滅私奉公の在り方女性の愛し方(恋愛哲学)、生活の上での具体的な知恵(生活哲学)の三つであるらしい。彼の愛した行動哲学に分類される最重要な一節と、訳を引用してみる。
「武士道は死狂ひなり。一人の殺害を数十人して仕かぬるもの。」と、直茂公仰せられ候。本気にては本業はならず。気違ひになりて死狂ひするまでなり。又武士道に於て分別出来れば、はや後るるなり。忠も孝も入らず、武士道に於ては死狂ひなり。この内に忠孝はおのづから籠るべし。
(訳)「武士道とは死に狂いである。そうした一人を倒すのに、数十人がかりでもできかねる場合がある。」と直茂公がおっしゃった。正気でいては、大仕事を達成することはできない。気ちがいになって、死に狂いするまでである。 また武士道では、思慮がうまれでると、すでにおくれをとったようなものである。武士道にとっては忠孝なども論外なので、ただ死に狂いがあるばかりである。そのなかに、忠孝は自然と宿るものだ。
三島の解説も引用する。ここに籠められた三島の思いというものは、三島事件に期待したであろうそれとかなりの部分で重複するように僕は思う。
前項の思想による欺瞞をもっともまぬがれた極致にあるものは、忠も孝も、あらゆる理念もいらない純粋行動の爆発の姿である。常朝はたんにファナチズムを容認するのではない。しかし行動が純粋形態をとったときに、おのずから忠と孝とをこもらせることになるかどうかは、予測のつくことではない。しかし、人間の行動は予測のつくことに向かってばかり発揮されるものではない。(中略)(別文引用)もし人間が行動を誤るとすれば、死ぬべきときに死なないことだと常朝は考えた。しかし、人間の死ぬときはいつもくるのではない。死ぬか生きるかの決断は、一生のうちについにこないかもしれない。常朝自身がそうであったように、彼が六十一歳で畳の上で死んだときに、あれほど日々心に当てた死が、ついにはこのような形で自分をおそってくることになるのを、どのような気持ちで迎えたであろうか。
1970年11月25日ないしその前夜、彼の心の伴侶として葉隠がまだ存在していたのであれば、書きぶりからから分かるように、彼は自死を含む自らの行動が狂気の沙汰(ファナティック)であることはまず理解していたことになる。そのうえで、仮に狂人扱いされたとしても、反理性行動に自ずから籠るであろう忠孝への共感を期待したのではないかと思う。
ではこの場合の忠孝とは何かと考えてみれば、晩年の三島が固執していた天皇制に向けられたものかもしれないが、『檄』ないし演説を読む限り彼の思いは天皇制だけに向けられたものではなく、その突き詰めた先にある“国家愛”へと強烈に向けられている。冒頭に引用したように日本人の国家への愛着は、伝統的に恋愛観念の形をとり、時に擬人化される。演説最後の万歳三唱は彼の“恋闕の情”であり、すなわち三島事件とは、虚弱な体躯で戦争時代を生きてしまった三島由紀夫という文化人の、国家への愛情の吐露に他ならない。身命を賭した告白だったのだ。
彼は悩んだだろう。栄達の約束された後半生、また築きあげてきた作家としての名声を、なげうち泥を塗ることになることが容易に考えられるからだ。後世からは畸形人として扱われ、その作品群は石もて打たれることになるかしれない。彼ほど明晰な頭脳を持った者が、生か死なら死を選べとする葉隠に、死によって名誉を得た人間の記載がないことにも気付いていたろう。なにより常朝自身が床の上で死ぬのである。自身で解釈しているように、葉隠はあくまで平和の世に生を見つめる書であるから、心得として死を想定していても、戦中なら知らず、実際に死の決断が迫られる時に敢えて死を選ぶことを必ずしも肯定していないのだ。
しかし彼は打算や勘定を侮蔑する常朝の言葉に共感する男だった。葉隠の定義する、ごく限定された武士像への憧憬を、少年の心で追い続ける知識人であった。同時に葉隠からの叱責に怯える芸能の従事者であった。三島の心の天秤は死へと傾く。武士に憧れ続けた男は、そうすることでしか武士になれなかった。奇人となり、狂人となり、犯罪者となり、作家であることを捨て、著作すべてに呪いをかけ、安らかな後半生を切り落として。
その動機を言葉にしたとき、戦後社会への失望にあったかもしれないし、肉体の衰退を恐れたと捉えることもできる。何らかの肉体・精神の不調を抱えていたかも知れない。老残への侮りであったかもしれないし、それはもしかすると三島の幼児性であったかもしれない。何が彼をそこへ駆り立てたのかなんて、他者としてのみ存在を許される僕らには結局のところ分かりっこない。三島研究者でもない僕がそれを語る資格もないように思う。
僕は三島事件を肯定しようとは思わない。どこかしら無理のある論理がそこには潜んでるように思う。僕は三島由紀夫の文章が好きだ。その分量を減らした事件を僕は憎んでいると言って良い。でも、命を賭けてこの国を愛した男がいたことを、馬鹿馬鹿しいほど大きな犠牲を払ってこの国に告白した男がいたことを、文化人のくせに行動の美徳に殉じた男がいたことを、僕は次世代へと伝えてゆくだろう。男らしさへの、古臭いものへの、理屈でわり切れないものへの憧れを。力強く放り投げた男がいたことを。
三島由紀夫vs東大全共闘(長尺版)
葉隠入門 (新潮文庫)/三島 由紀夫

¥452
Amazon.co.jp
三島由紀夫 (新文芸読本)/著者不明
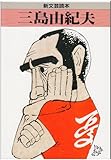
¥1,223
Amazon.co.jp
2Q11
まぁ今更感は漂っている訳なのだが、2011年という節目の年をまとめないことにはこのブログの2012年は始まらないと思うんだな。それだけ色んなことが起きた年であり、その中には歴史に残る出来事も多くあった。未来の僕らが振り返るような事件もきっとあるだろう。データを集積しながら様々な思いが過ぎ去っていった。そして曖昧な肌感覚はなぜか雄弁に、2011年を特殊な一年に位置づけようとしている。2012年になった今だからこそ、僕は『2011』という語感と視覚イメージに強く懐かしみを感じている。
去年は年が明けた瞬間に、何か戦慄のようなものも感じていたしな。少なくとも僕の中で、自分の節目であったことも含めて、特別な一年だった。去りゆく年、そして迎えた2012年。まぁ振り返ろうじゃないか。
天災
1月
ラニーニャ現象、オーストラリアで多雨、ブラジルなど世界各地で大規模な水害
デリーで40年ぶりの寒波
ブラジルで鉄砲水、大雨で500人以上が死亡
スリランカで洪水、23人が死亡
オーストラリア北東部で洪水、被害額は同国史上最悪規模、20万人以上が被災
南アフリカで洪水、100人以上が死亡
霧島山・新燃岳が、189年ぶりにマグマ噴火
2月
超大型サイクロンがオーストラリア北東部を襲う
ニュージーランドクライストチャーチでマグニチュード6.3の地震、181人が死亡
3月
東北地方太平洋沖地震(マグニチュード9.0)、死者15,843人、重軽傷者5,890人、行方不明者3,469人
4月
5月
アメリカミズーリ州に竜巻、122人が死亡
6月
東アフリカで過去60年で最悪の旱魃、1000万人に影響
チリ南部のプジェウエ火山が噴火、3000人以上が避難
7月
8月
9月
10月
タイで過去最悪規模の水害、国土の3分の1が水没
トルコ東部ワン地震(マグニチュード7.1)発生、600人以上が死亡
11月
12月
皆既月食観測される
勿論2011年を語る時に東日本大震災を外す訳にはいかない。夏頃まではどこで被災したかっていうのが定番の話題になってたな。知識人も頻繁に口にするようになった“3.11”、あの日以降僕たち日本人の意識も微妙に変わりつつある気がしている。政治不信に加えてマスコミ不信、東電を始めとした大企業に対する不信感。“きっと誰かがなんとかしてくれる”時代は終わり、“自分こそが物事を変えてゆく”時代が訪れたんだと思ってます。僕らは何者にも頼らず、自分の意志で進まないといけないんだろう。
また日本だけでなく歴史的な天災が世界中で起きた。地球の怒りが噴出して、人間の思い上がりを打ち砕くかのように。世界中の人々が無力感を噛み締めていただろう。そして同時に、だからこそ、人間の尊厳というか露わな本質に光が当たった。海外の音楽家が日本公演を次々とキャンセルする一方で、レディーガガはチャリティーを呼びかけ、収益全額及び同額の個人資産を寄付、三度の来日で日本の海外イメージを守ってくれた。
日本が国家として認めていない台湾が最大額の義援金を集めてくれたことも忘れちゃいけないし、台湾の厚意に応えた一民間人がいたことも記憶に新しい。米軍の協力。自衛隊の尽力。その一方で僕らは節電だとか脱原発だとか安い言葉を口にするだけで何もできなかった。政府政権への批判はそのままに、僕ら自身に跳ね返ったことに多くの人が気付いた年。なんだ結局東日本大震災のことしか書いてないけど、まぁ良いか。
世界

1月
チュニジアでジャスミン革命、23年間の独裁政権が崩壊
エジプトで数万人規模の反体制デモ
イエメンで数千人規模の反体制デモ
2月
ヨルダンで内閣退陣
イエメンで2万人規模のデモ
エジプトで追放の金曜日デモ推定20万人
リビアで内戦
3月
4月
キューバのカストロが退任
5月
ウサマ・ビンラディンが銃撃戦で死亡
6月
7月
南スーダン共和国が独立
8月
アメリカ国債、債務不履行危機
イギリスで暴動
リビア、カダフィ政権の崩壊、内戦の終結
9月
アメリカでウォール街占拠デモ
10月
カダフィ死亡
11月
ギリシャ政権崩壊
イタリア、ベルルスコーニが退任
12月
アメリカ軍イラク撤退完了
金正日死亡
まぁアラブの春も含め、昨年は主に途上国で、指導者が失脚ないし死亡することの多い年だった。2011年のタイム誌「パーソン・オブ・ザ・イヤー」は「プロテスター(抗議者)」らしいが、その助けとなったSNS、ネットの普及は群衆の力を縒り集め、なんだかんだ世界を変えてゆく気配を見せている。SNSの容易さはリビアのように内戦で荒廃した国、シリアのように未だに内戦を続ける国を見るかぎり必ずしも素晴らしいものとは言えないから、その国主権者たる国民の政治的成熟度がこれから問われてゆくのだろう。
EU経済のアキレス腱であるPIGSの状况を聞く限り、また米国債のデフォルト危機、日本の円高デフレの様子にしても、リーマンショックの傷から世界は未だ立ち直れず、EUに関してはむしろ傷口が広がっているようにさえ見える。主要8か国は明るい話題に欠いたが、米中露仏韓台の首脳が交代する再編の2012年へ向けて世界はどう変わってゆくのだろう。正恩体制に移行した北朝鮮がどうなるのかも興味があるな。
日本
1月
タイガーマスク運動
菅第2次改造内閣が発足
芥川賞を朝吹真理子・西村賢太がダブル受賞
阿久根市の出直し市長選挙
一票の格差を高松高裁が違憲判決
トヨタ自動車が国内外で約170万台のリコール
小沢一郎強制起訴
2月
大相撲八百長問題
3月
東日本大震災
4月
5月
6月
内閣不信任決議案顛末
2万人規模の脱原発デモ
ホリエモン収監
7月
地デジ完全移行
8月
紳助引退
野田内閣成立
フジテレビ抗議デモ、8000人以上
9月
10月
オリンパス損失隠し事件
11月
就活ぶっこわせデモ、参加者100人以上
大阪維新の会が市長知事選で圧勝
12月
寒ぶりを愛する男、児童養護施設に
NHK抗議デモ
東日本大震災については大体書いた。二点。脱原発・フジテレビ・就活・NHKとデモの絶えない年だった。思ったことをそのまま行動に移すということ、デモとして社会の反応と影響を試すという行為自体は健全な民主主義の在り方として必要不可欠なものだから、まぁ日本にとって良い兆候だと思う。ただ現実に参加している人たちの主張にはまるで共感できないし、そこはかとなく漂う幼児性、異論を許さぬヒステリックな雰囲気もしくは悪ふざけのような雰囲気は、申し訳ないが不快でしかない。
唯一就活デモだけは明確な対立構造があり、彼らがマイノリティーであること、参加者の切実さも手伝ってひそかに共感していた。ホリエモン収監にしても、ライブドアに較べて悪質な違反をしていたオリンパスが課徴金程度の処分に留まりそうなことを考えると、ホリエモンが可哀想というか、なんだか日本の構造的な問題を突き付けられて不安になる。気付いてないのか、蓋をしているのか、多くの人が口を噤んでいるのも納得できない。んー、なんだかなぁ。
まぁその辺のとこもエントリにしたかったんだが、結局果たせなかった悔しさを噛み締めつつ(世間のマジョリティーに噛み付くエントリは愚痴か暴言になりがちだから難しいんだ)、純文学に吹いた一陣の腥風こと西村賢太の登場を祝ぎ、今年の芥川賞への期待に胸を膨らまそう。
訃報

1月
喜味こいし(83 肺癌 漫才師 いとしこいし)
2月
3月
谷沢永一(81 心不全 文芸評論家)
坂上二郎(76 脳梗塞 コメディアン コント55号)
4月
出崎統(67 肺癌 アニメ監督 エースをねらえ!)
サイババ(84 心臓・呼吸器不全 霊的指導者・社会慈善家)
田中好子(55 乳癌 歌手 キャンディーズ)
5月
団鬼六(80 食道癌 官能小説家)
上原美優(24 自死 グラビアアイドル)
児玉清(77 胃癌 司会者)
長門裕之(77 肺炎・動脈硬化の合併症 映画俳優)
6月
7月
小松左京(80 肺炎 SF作家 日本沈没)
伊良部秀輝(42 自死 元プロ野球選手)
8月
9月
クルト・ザンデルリンク(98 老衰 ドイツの指揮者)
10月
スティーブ・ジョブズ(56 膵臓癌 経営者)
北杜夫(84 腸閉塞 作家 楡家の人びと)
11月
立川談志(75 喉頭癌 落語家)
12月
市川森一(70 肺癌 脚本家 ウルトラセブン)
上田馬之助(71 窒息 プロレスラー)
柳宗理(96 肺炎 工業デザイナー)
そしてまた2011年は有名人が多く死んだ年でもあった。不思議な巡りあわせだが、谷沢永一は『僕のうつ人生』、団鬼六は『悦楽王』、長門裕之は『その壁を砕け』、立川談志は『談志最後の落語論』を昨年か一昨年くらい生前のうちに読んだり観たりしていて、他の作品にも手を広げようかと考えてる間に訃報を聞いた。09年の海老沢泰久の訃報の時にも同じことがあって、なんというか運命的なものというか、第六感的なものというか、不思議な気分がする。しかも悪い気持ちでない。
それにしても訃報というものは一見哀しみを帯びているが、その癖颯爽としていやがる。長門裕之にしろ談志にしろ、彼らのように生ききった者たちの死は一種の優しさで包まれてる感じがする。ほのかに笑顔になってしまうような。無論不意打ちのように訪れる若い訃報には哀しみや虚しさだけを瞬間的に浮き彫るものだが、死という静かで均一的な概念は人々をまるで2次元に落としこむように、感情の襞を取り除き最も快い記憶だけを僕らに残す作用があるように思う。
同時に生に退屈しがちな僕らは、他者の死によって自らの生を照らし躍動させることができる。そうした意味でも今年は訃報が多かった分だけ僕らの生が輝いた一年であったと書いてよいかもしれない。死者一人ひとりに思いを馳せるのも良いだろう。だがどうも僕は過去を懐かしむにはまだ若すぎて、限りある死人の記憶を窯で焼べて前へと進む原動力にしたいと思うのだ。うむ。
とまぁこんな感じでまとまったんだかなんだか曖昧な雰囲気はありますけれど、体裁としては一応出来上がった訳で、自分としては謙虚に書いてもほどほどに頑張ったくらいの自負はあるんだからまぁこんなもんかなと。まとめていながらやっぱり、2011は節目の年であったのだなと思います。人間のどんな営みにおいてもなにがしかの変化が起きた一年だった。
破壊の年でありながら、再編への希望を繋いだ年。人としての尊厳と品格が露われた年。名も無き多くの人が亡くなった年。新しい人材を、次世代への種苗を確かに受け継いだ年。人としてほんの少しばかりでも成長できたと確信した年。
2011年、マグニチュード9.0で文字通り揺れ動いた年。僕はこの一年を決して忘れないだろう。
なんだかんだ今年を象徴してしまった曲。良くも悪くもAKBって凄いね。まぁどうでも良いけれど。そういえばサブカル面というかアニメではまどマギありピングドラムありと豊作の年でしたね。今年も4月からエウレカの二期が始まるわで目が離せそうにないです
去年は年が明けた瞬間に、何か戦慄のようなものも感じていたしな。少なくとも僕の中で、自分の節目であったことも含めて、特別な一年だった。去りゆく年、そして迎えた2012年。まぁ振り返ろうじゃないか。
天災
1月
ラニーニャ現象、オーストラリアで多雨、ブラジルなど世界各地で大規模な水害
デリーで40年ぶりの寒波
ブラジルで鉄砲水、大雨で500人以上が死亡
スリランカで洪水、23人が死亡
オーストラリア北東部で洪水、被害額は同国史上最悪規模、20万人以上が被災
南アフリカで洪水、100人以上が死亡
霧島山・新燃岳が、189年ぶりにマグマ噴火
2月
超大型サイクロンがオーストラリア北東部を襲う
ニュージーランドクライストチャーチでマグニチュード6.3の地震、181人が死亡
3月
東北地方太平洋沖地震(マグニチュード9.0)、死者15,843人、重軽傷者5,890人、行方不明者3,469人
4月
5月
アメリカミズーリ州に竜巻、122人が死亡
6月
東アフリカで過去60年で最悪の旱魃、1000万人に影響
チリ南部のプジェウエ火山が噴火、3000人以上が避難
7月
8月
9月
10月
タイで過去最悪規模の水害、国土の3分の1が水没
トルコ東部ワン地震(マグニチュード7.1)発生、600人以上が死亡
11月
12月
皆既月食観測される
勿論2011年を語る時に東日本大震災を外す訳にはいかない。夏頃まではどこで被災したかっていうのが定番の話題になってたな。知識人も頻繁に口にするようになった“3.11”、あの日以降僕たち日本人の意識も微妙に変わりつつある気がしている。政治不信に加えてマスコミ不信、東電を始めとした大企業に対する不信感。“きっと誰かがなんとかしてくれる”時代は終わり、“自分こそが物事を変えてゆく”時代が訪れたんだと思ってます。僕らは何者にも頼らず、自分の意志で進まないといけないんだろう。
また日本だけでなく歴史的な天災が世界中で起きた。地球の怒りが噴出して、人間の思い上がりを打ち砕くかのように。世界中の人々が無力感を噛み締めていただろう。そして同時に、だからこそ、人間の尊厳というか露わな本質に光が当たった。海外の音楽家が日本公演を次々とキャンセルする一方で、レディーガガはチャリティーを呼びかけ、収益全額及び同額の個人資産を寄付、三度の来日で日本の海外イメージを守ってくれた。
日本が国家として認めていない台湾が最大額の義援金を集めてくれたことも忘れちゃいけないし、台湾の厚意に応えた一民間人がいたことも記憶に新しい。米軍の協力。自衛隊の尽力。その一方で僕らは節電だとか脱原発だとか安い言葉を口にするだけで何もできなかった。政府政権への批判はそのままに、僕ら自身に跳ね返ったことに多くの人が気付いた年。なんだ結局東日本大震災のことしか書いてないけど、まぁ良いか。
世界

1月
チュニジアでジャスミン革命、23年間の独裁政権が崩壊
エジプトで数万人規模の反体制デモ
イエメンで数千人規模の反体制デモ
2月
ヨルダンで内閣退陣
イエメンで2万人規模のデモ
エジプトで追放の金曜日デモ推定20万人
リビアで内戦
3月
4月
キューバのカストロが退任
5月
ウサマ・ビンラディンが銃撃戦で死亡
6月
7月
南スーダン共和国が独立
8月
アメリカ国債、債務不履行危機
イギリスで暴動
リビア、カダフィ政権の崩壊、内戦の終結
9月
アメリカでウォール街占拠デモ
10月
カダフィ死亡
11月
ギリシャ政権崩壊
イタリア、ベルルスコーニが退任
12月
アメリカ軍イラク撤退完了
金正日死亡
まぁアラブの春も含め、昨年は主に途上国で、指導者が失脚ないし死亡することの多い年だった。2011年のタイム誌「パーソン・オブ・ザ・イヤー」は「プロテスター(抗議者)」らしいが、その助けとなったSNS、ネットの普及は群衆の力を縒り集め、なんだかんだ世界を変えてゆく気配を見せている。SNSの容易さはリビアのように内戦で荒廃した国、シリアのように未だに内戦を続ける国を見るかぎり必ずしも素晴らしいものとは言えないから、その国主権者たる国民の政治的成熟度がこれから問われてゆくのだろう。
EU経済のアキレス腱であるPIGSの状况を聞く限り、また米国債のデフォルト危機、日本の円高デフレの様子にしても、リーマンショックの傷から世界は未だ立ち直れず、EUに関してはむしろ傷口が広がっているようにさえ見える。主要8か国は明るい話題に欠いたが、米中露仏韓台の首脳が交代する再編の2012年へ向けて世界はどう変わってゆくのだろう。正恩体制に移行した北朝鮮がどうなるのかも興味があるな。
日本
1月
タイガーマスク運動
菅第2次改造内閣が発足
芥川賞を朝吹真理子・西村賢太がダブル受賞
阿久根市の出直し市長選挙
一票の格差を高松高裁が違憲判決
トヨタ自動車が国内外で約170万台のリコール
小沢一郎強制起訴
2月
大相撲八百長問題
3月
東日本大震災
4月
5月
6月
内閣不信任決議案顛末
2万人規模の脱原発デモ
ホリエモン収監
7月
地デジ完全移行
8月
紳助引退
野田内閣成立
フジテレビ抗議デモ、8000人以上
9月
10月
オリンパス損失隠し事件
11月
就活ぶっこわせデモ、参加者100人以上
大阪維新の会が市長知事選で圧勝
12月
寒ぶりを愛する男、児童養護施設に
NHK抗議デモ
東日本大震災については大体書いた。二点。脱原発・フジテレビ・就活・NHKとデモの絶えない年だった。思ったことをそのまま行動に移すということ、デモとして社会の反応と影響を試すという行為自体は健全な民主主義の在り方として必要不可欠なものだから、まぁ日本にとって良い兆候だと思う。ただ現実に参加している人たちの主張にはまるで共感できないし、そこはかとなく漂う幼児性、異論を許さぬヒステリックな雰囲気もしくは悪ふざけのような雰囲気は、申し訳ないが不快でしかない。
唯一就活デモだけは明確な対立構造があり、彼らがマイノリティーであること、参加者の切実さも手伝ってひそかに共感していた。ホリエモン収監にしても、ライブドアに較べて悪質な違反をしていたオリンパスが課徴金程度の処分に留まりそうなことを考えると、ホリエモンが可哀想というか、なんだか日本の構造的な問題を突き付けられて不安になる。気付いてないのか、蓋をしているのか、多くの人が口を噤んでいるのも納得できない。んー、なんだかなぁ。
まぁその辺のとこもエントリにしたかったんだが、結局果たせなかった悔しさを噛み締めつつ(世間のマジョリティーに噛み付くエントリは愚痴か暴言になりがちだから難しいんだ)、純文学に吹いた一陣の腥風こと西村賢太の登場を祝ぎ、今年の芥川賞への期待に胸を膨らまそう。
訃報

1月
喜味こいし(83 肺癌 漫才師 いとしこいし)
2月
3月
谷沢永一(81 心不全 文芸評論家)
坂上二郎(76 脳梗塞 コメディアン コント55号)
4月
出崎統(67 肺癌 アニメ監督 エースをねらえ!)
サイババ(84 心臓・呼吸器不全 霊的指導者・社会慈善家)
田中好子(55 乳癌 歌手 キャンディーズ)
5月
団鬼六(80 食道癌 官能小説家)
上原美優(24 自死 グラビアアイドル)
児玉清(77 胃癌 司会者)
長門裕之(77 肺炎・動脈硬化の合併症 映画俳優)
6月
7月
小松左京(80 肺炎 SF作家 日本沈没)
伊良部秀輝(42 自死 元プロ野球選手)
8月
9月
クルト・ザンデルリンク(98 老衰 ドイツの指揮者)
10月
スティーブ・ジョブズ(56 膵臓癌 経営者)
北杜夫(84 腸閉塞 作家 楡家の人びと)
11月
立川談志(75 喉頭癌 落語家)
12月
市川森一(70 肺癌 脚本家 ウルトラセブン)
上田馬之助(71 窒息 プロレスラー)
柳宗理(96 肺炎 工業デザイナー)
そしてまた2011年は有名人が多く死んだ年でもあった。不思議な巡りあわせだが、谷沢永一は『僕のうつ人生』、団鬼六は『悦楽王』、長門裕之は『その壁を砕け』、立川談志は『談志最後の落語論』を昨年か一昨年くらい生前のうちに読んだり観たりしていて、他の作品にも手を広げようかと考えてる間に訃報を聞いた。09年の海老沢泰久の訃報の時にも同じことがあって、なんというか運命的なものというか、第六感的なものというか、不思議な気分がする。しかも悪い気持ちでない。
それにしても訃報というものは一見哀しみを帯びているが、その癖颯爽としていやがる。長門裕之にしろ談志にしろ、彼らのように生ききった者たちの死は一種の優しさで包まれてる感じがする。ほのかに笑顔になってしまうような。無論不意打ちのように訪れる若い訃報には哀しみや虚しさだけを瞬間的に浮き彫るものだが、死という静かで均一的な概念は人々をまるで2次元に落としこむように、感情の襞を取り除き最も快い記憶だけを僕らに残す作用があるように思う。
同時に生に退屈しがちな僕らは、他者の死によって自らの生を照らし躍動させることができる。そうした意味でも今年は訃報が多かった分だけ僕らの生が輝いた一年であったと書いてよいかもしれない。死者一人ひとりに思いを馳せるのも良いだろう。だがどうも僕は過去を懐かしむにはまだ若すぎて、限りある死人の記憶を窯で焼べて前へと進む原動力にしたいと思うのだ。うむ。
とまぁこんな感じでまとまったんだかなんだか曖昧な雰囲気はありますけれど、体裁としては一応出来上がった訳で、自分としては謙虚に書いてもほどほどに頑張ったくらいの自負はあるんだからまぁこんなもんかなと。まとめていながらやっぱり、2011は節目の年であったのだなと思います。人間のどんな営みにおいてもなにがしかの変化が起きた一年だった。
破壊の年でありながら、再編への希望を繋いだ年。人としての尊厳と品格が露われた年。名も無き多くの人が亡くなった年。新しい人材を、次世代への種苗を確かに受け継いだ年。人としてほんの少しばかりでも成長できたと確信した年。
2011年、マグニチュード9.0で文字通り揺れ動いた年。僕はこの一年を決して忘れないだろう。
なんだかんだ今年を象徴してしまった曲。良くも悪くもAKBって凄いね。まぁどうでも良いけれど。そういえばサブカル面というかアニメではまどマギありピングドラムありと豊作の年でしたね。今年も4月からエウレカの二期が始まるわで目が離せそうにないです
時と場合によるが
手抜きが許されることがある。確か本田技研の社是だか本田宗一郎の言葉で、スピードこそ全て、みたいなのがあった気がする。別に時速の話ではなく、例えば吟味に吟味を重ね綿密に作り込んだ製品よりも、適切なタイミングに合わせ迅速に商品化されたそこそこの性能の製品が成功を勝ち取る、という語感だった。
日系電機メーカーに先んじたアップルであったり、グレイに先んじたベルであったり。性能よりもスピードが求められる局面は確かに存在していて、それは現代にも通用する、なんとなく真理っぽい風格がある。郭嘉も神速がどうとか言ってたしな。
ある瞬間に自分が何をするか明確に分かっている場合、最善を提供せずともスピードと情熱のみで行動に移す美徳を謳っているのだと思う。頭でっかちに考えすぎて前どころか後ろにも進めなくなり、文字通り進退窮する僕らグズ型人間にとって、まぁ肝に銘ずるべき言葉なんだろうな。
本来は11年中に去年のまとめエントリを書きたかったが諸事情で書けなかったもんだから、新年こそは2012年について抱負やら激動の世界情勢を睨んでまぁ、色々書きたいこともある訳なのだけれども、書き始めると三が日中にまとまらない可能性もあるのだからどうしたもんか取り敢えず取り掛かるべきなのかお屠蘇でも飲んから考えるかとか云々してるうちに日はまた暮れていくのです。その逡巡が無駄なんです、と。まぁだらだら書いてきましたが何を言いたいのかと言いますと。
2012年明けまして、おめでとうございます。
まぁ案外世の中というか、ブログなんて奇ッ怪なものとの付き合いというのも質より頻度で勝負すべきなのかもしれないな、とは去年の中頃くらいには気付いてた。優柔不断なのかな。なかなかどうも割り切れなくてグズってしまう自分もそう嫌いでなくなってきた2012元旦であります。
取り敢えずこのタイミングでこの程度のエントリをアップしておいて、三が日中には書きたいものをぼちぼちアップしていこうかなと皮算用しています。はぁ、書き始めるとキリがないので、ここらで一息。本年が皆様にとって幸多き年となりますように。
謹賀新年。元旦。南海道。
ちなみにご存知春の海、作曲されたのは昭和であります。作曲者の宮城道雄は西洋音楽も学んだ盲の箏奏者で、作曲者自らがフランスのヴィオラ奏者と共演したりしてます。詳しくは川端康成「純粋の聲」をどうぞ。ハーフに美しい人が多いのと同様に、音楽においても雑種は普遍的な価値を得ることが多いようです。なんだか不思議な気もしますね
日系電機メーカーに先んじたアップルであったり、グレイに先んじたベルであったり。性能よりもスピードが求められる局面は確かに存在していて、それは現代にも通用する、なんとなく真理っぽい風格がある。郭嘉も神速がどうとか言ってたしな。
ある瞬間に自分が何をするか明確に分かっている場合、最善を提供せずともスピードと情熱のみで行動に移す美徳を謳っているのだと思う。頭でっかちに考えすぎて前どころか後ろにも進めなくなり、文字通り進退窮する僕らグズ型人間にとって、まぁ肝に銘ずるべき言葉なんだろうな。
本来は11年中に去年のまとめエントリを書きたかったが諸事情で書けなかったもんだから、新年こそは2012年について抱負やら激動の世界情勢を睨んでまぁ、色々書きたいこともある訳なのだけれども、書き始めると三が日中にまとまらない可能性もあるのだからどうしたもんか取り敢えず取り掛かるべきなのかお屠蘇でも飲んから考えるかとか云々してるうちに日はまた暮れていくのです。その逡巡が無駄なんです、と。まぁだらだら書いてきましたが何を言いたいのかと言いますと。
2012年明けまして、おめでとうございます。
まぁ案外世の中というか、ブログなんて奇ッ怪なものとの付き合いというのも質より頻度で勝負すべきなのかもしれないな、とは去年の中頃くらいには気付いてた。優柔不断なのかな。なかなかどうも割り切れなくてグズってしまう自分もそう嫌いでなくなってきた2012元旦であります。
取り敢えずこのタイミングでこの程度のエントリをアップしておいて、三が日中には書きたいものをぼちぼちアップしていこうかなと皮算用しています。はぁ、書き始めるとキリがないので、ここらで一息。本年が皆様にとって幸多き年となりますように。
謹賀新年。元旦。南海道。
ちなみにご存知春の海、作曲されたのは昭和であります。作曲者の宮城道雄は西洋音楽も学んだ盲の箏奏者で、作曲者自らがフランスのヴィオラ奏者と共演したりしてます。詳しくは川端康成「純粋の聲」をどうぞ。ハーフに美しい人が多いのと同様に、音楽においても雑種は普遍的な価値を得ることが多いようです。なんだか不思議な気もしますね