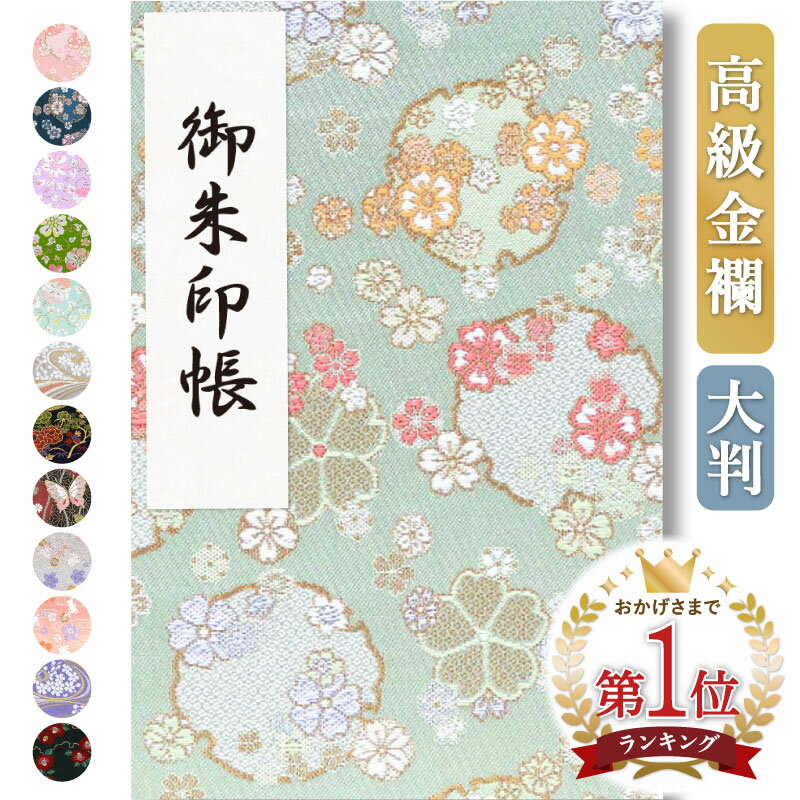琉球八社巡りもついに八社目となりました。
金武町にある金武宮。
まずはベーグル屋さんで腹ごしらえして、
参拝可能な午前9時になるのを待ちました。
今回のブログのタイトルですが、
「金武宮」ではなく「金武観音寺」。
金武宮は創建当初より社殿がなく、
金武観音寺というお寺の境内にある
「日秀洞」という洞窟がお社で、
洞窟内に金武権現として祀られています。
なので他の琉球八社の神社と異なり、
宮司さんもおらず、御朱印もありません。
金武宮 由緒
その創始は詳らかでないが、『沖縄の神社』によれば社殿は創建以来設けられていなかった。
『琉球国由来記 巻11 密門諸寺縁起』の〔金峰山観音寺〕の段にある「金峰山補陀落院観音寺縁起」には観音寺の開基について記してあるが、それによれば補陀落山を求めて渡来した日秀上人が、尚清王の御代の嘉靖年間に琉球王国内を行脚し、この地にあった洞窟を霊跡として宮を建て、自身が彫った三尊を権現正体として崇め奉ったとしている。
『琉球宗教史の研究』では鍾乳洞が当社の御本体となっているところから推測すれば、観音寺を建立した日秀上人が当社を創立したと見るべきであろうと述べているが、そうであるなら『琉球国由来記』の記述から当社創建の時期は尚清王が在位した1527年から1555年の間ということになる。
当社は「官社の制」により琉球八社の一つとされた。『琉球宗教史の研究』によれば、琉球八社へは神職の役俸並びに営繕費が王府から支給されていたが、当社は神職を置かず観音寺の住職が経営していたため王府からの経済的援助は受けていなかった。
参考:Wikipedia
先に金武観音寺の本堂を参拝。
金武観音寺の本堂は昭和17年に再建され、
県内では珍しく戦火を免れた社寺で、
歴史ある立派な木造建築物です。
本堂に向かって右側の端の方に
日秀洞の入口があります。
洞窟には急な階段を下りますが、
入口から既にひんやり冷たい空気。
神聖な雰囲気が漂っていました。
階段を下りると薄暗い場所に
小さな祠があります。

観音寺の御朱印をいただきました。
こちらは書き置きはなく直書きのみ。

仕事用の鞄に付けても
違和感無さそうだったので。
さて、これで琉球八社は全て巡りました。
───────────────
*テーマでまとめています*
───────────────