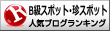今回も当ブログをご覧いただき、ありがとうございます。
前々回、前回と引き続き「鎌倉街道上道」を紹介します。vol.3ですね。今回は仏坂遺跡と毛呂山町歴史民俗資料館に展示されていた堂山下遺跡、崇徳寺跡からの出土品を紹介します。
鎌倉街道上道の指定範囲(2ヶ所の推定ラインを除く)
鎌倉街道A遺跡から南側は開墾などによって鎌倉街道の痕跡は失われてしまっていました。県道114号・川越 越生線からその付近を眺めたのが下の写真です。今回はここからスタートです。
葛川という小さな川が流れていて、下の写真の中央付近でこの小河川を渡っていたとみられています。
県道114号線が葛川を渡る地点より東側に信号のある交差点があります。ここを南に入る細い道が「仏坂遺跡」と呼ばれる鎌倉街道跡です。
道は轍もなく、細長い草地のようになっていて「これこそ遺跡!」といった感じでした。
さらに少し進むと台地の斜面を掘割にした部分が現れ、中世の街道らしい雰囲気になってきました。
ここは歴史民俗資料館から大分離れているので、過去に何度かここ(堂山下遺跡や川角古墳群辺り)を訪ねていた私もその存在を知りませんでした。こんなに状態のいい掘割状遺構が残っていたとは!
ただ、この掘割状遺構の残っている区間は短く、まもなく住宅に突き当たってしまいます。そして舗装整備された町道に出たところで終わります。
これで、鎌倉街道上道の指定範囲は踏破しました。
「え?でもブログはまだ続くって予告していたじゃない?4回目は何を紹介するの?」
と思っていただいた方、隅々まで当ブログをご覧いただいた方ですね。ありがとうございます。
次回は堂山下遺跡を破棄した集落の人々はどこへ行ってしまったのか、その移住先についてお話したいと思っています。また埼玉県内で、遺存状態がいいので追加指定されそうなところ、鎌倉街道上道の遺構が近年になって失われてしまったところなども紹介します。
さて、毛呂山町歴史民俗資料館には堂山下遺跡、崇徳寺跡から出土した遺物が多数展示されています。
堂山遺跡の出土品などは生活感あふれるものばかり、一方で崇徳寺跡はさすが墓地、といいつつ骨壺にするにはもったいないような壺など出土していて、意外と豊かな生活していたことをうかがわせる興味深い展示品をいっぱい見ることができました。
その一部を紹介します。
「中世っぽいなぁ…」という品の写真を3点載せました。
いずれも在地産の製品とみられているもので、生活用品なんです。
調理用の道具ばかりなので、とても生活感が溢れているではありませんか。しかもほとんど復元可能だったわけですから、なおさらです。
一方、こんなものも発見されています。
手のひらサイズの小さな壺で、堂山下遺跡から出土しました。
何の用途だと思いますか?
実は、骨壺らしいのです。分骨壺というものらしいです
故人を偲んで身近に置きたかったのでしょうね。胸に迫るものがあります。
壺の出来も中々のものです。
ほかにも、かわらけが展示されていました。
かわらけといえば使い捨ての容器のことで、安っぽい造りのわりに常にきれいな器として神事にも使用されるという、これが出土すれば意外と裕福な生活をしていた人々を想像してしまう、というアレです。
柳之御所遺跡で大量に出土したことを以前、紹介しました。
堂山下遺跡は街道沿いの一等地に集落があったのですから、意外と裕福な生活をしていたのでしょう。
長く続く不況下に暮らしている我々にはうらやましい限りのはなしです。
続いては崇徳寺跡出土品の紹介です。
特に目が離せなかったのがこちらの板碑。でき立てのような保存状態の良い板碑です。
この板碑は出来てすぐに土中に埋まったのでしょうか、とにかく保存状態がいいんです。
伝世品と違って風化していないので、文字のエッジがしっかりとしているんです。思わず写真を撮ってしまいました。大き過ぎてうまくとれていないのが残念で、申し訳ないです。
拓本で見ていただけば、何が書かれているのかはっきりわかります。
その一方で、逆にこんな小さな板碑も出土しています。こちらは劣化が激しい。
そして、墓地らしく蔵骨器として使用された甕や壺が多く出土しています。
この灰釉瓶子なんかは特に出来がいいです。
最後に、延慶の板碑を昭和37年に移設した際に出土した2点の蔵骨器は埼玉県指定文化財となっています。
出来がいいのに、骨壺…
上の写真の瓶子は梅や唐草の文様を判で押して絵付けしているところが特徴的です。
そして、もともと水注だったものの口を欠いて蔵骨器としたとされる下の写真のものもいい出来のものです。
これらの遺物を見て、皆さんは最初に何を感じましたか?
私は、
「どれも完形に近いまま出土しているのね。」
ということを感じました。
私も遺跡発掘の経験があるのですが、まず容器がほとんど割れていない状態で出土することはまれなのです。
大概、土圧で割れてしまうのです。
その点、この遺跡は中世の遺跡なこともあって深く埋まっていなかったのか、あまり破損のない状態で遺物が見つかっていることは驚きです。
あと、人為的に埋められた容器は割れることが少ないことはよく知られています。縄文時代の埋甕炉の土器が完全な形で出土するのはそういう理由です。
だから蔵骨器が完形に近い形で出土するのは、まあ、当たり前なのです。それにしても骨董品としてもいい状態のものが多くて、見ていて興奮してしまいます。
さて、今回のシリーズ最終回は「堂山下遺跡に暮らした人々はどこへ行ってしまったのか」と、「残っていたら追加指定されただろうに/残っているから今後追加指定されるだろう」毛呂山町内以外の鎌倉街道上道の遺跡を紹介します。
ブログが気に入ったらクリックをお願いします