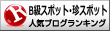今回も当ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

今回は「鎌倉街道上道」の最終回。前回からの続きで
゛堂山下遺跡の集落を出た人々はどこへ行ってしまったの?”
というお話をまず致します。続いて先見の明として
゛遺構が今後追加指定されそうな場所”
が数か所あるのでご紹介します。
さらに、遺跡マニアとしては悔しいことに
゛近年まで遺構が残っていたのに破壊されてしまった街道跡”
がありますので、これを読んでくださる皆様に文化財保護の機運を広めていただくため紹介いたします。
鎌倉街道上道(今回の指定部分:青いライン)と八王子道(桃色のライン)、黒色で囲った部分は大類の町並み
さて堂山下遺跡の出土品からすると、16世紀には人々は集落を放棄し、どこかへ移住していきました。13~15世紀の出土品は多いのに16世紀の遺物は全く発見されないことから推測されるとか。
ただ、その変化も
①15世紀までの遺物は大量に発見されたのに、16世紀の遺物は全く発見されない。突如として集落が消え去ったかのように遺物が失われている。
場合と、
②15世紀に入ってからの遺物は徐々に減っていっており、16世紀の遺物に関しては全く発見されない。集落は徐々に放棄されていった。
場合とがあると思います。堂山下遺跡ではどちらのパターンだったのでしょう?
私はおそらく後者だったと想像しています。街道の路面敷を発掘調査したところ、ほぼ同じ時期に街道が徐々に利用されなくなっていったことがわかっているそうです。
なんでも、この時期を境に道路が補修されなくなり徐々に埋もれていったそうで。
一方、16世紀にはいると小田原の後北条氏による関東支配がはじまり、新たな道が整備されたのだそうです。
その道を゛八王子道”と呼んだそうで、その一部は現在も県道として利用されています。
毛呂山町歴史民俗資料館の方の話では「中世の人々は後北条氏の関東支配が始まり、新たに整備された街道沿いに移住し古い集落を放棄したのでしょう」ということでした。
堂山下遺跡の近所には現在「大類」という集落があります。
この集落こそ八王子道沿いに築かれた、その新しい集落なんです。
実際に訪ねてみると今でも短冊状の屋敷割が街道に沿って連なっており、往時の面影をよく伝えていました。
サラッと述べていらっしゃいましたが、すなわちこの集落の人々が堂山下遺跡の集落を築いた人々の子孫、ということではありませんか。
なんか感慨深いものがありませんか?堂山下遺跡を築いた人々は、今も近くに集落を築いて子々孫々、脈々と世代を継いでいるのです。
毛呂山町内の鎌倉街道上道の歴史が現代にも連綿と続いている事実に胸を打たれつつ、遺跡を後にしました。
ところで、鎌倉街道上道の遺構は毛呂山町内だけに残されているわけではありません。ほかにも埼玉県内には鎌倉街道上道の遺構が残っている場所があるのです。
特に深谷市内(旧大里郡川本町内)や比企郡小川町内に残る3か所の遺構は状態がよく、遺跡として発掘調査も行われているので今後、国指定史跡へ追加指定されるかもしれないとのことでした。
そのような理由から、今回は小川町内の3か所の遺跡を訪ねました。
各遺跡の位置関係は下図の通りです。
こちらの遺構群は私的には毛呂山町内に残る遺構より中世の道路の雰囲気が強く漂っていると思うので、ぜひここで紹介したいのです。ぜひ見ていってください。
まずは一番南に位置する天王原北遺跡からご紹介します。
上の写真では分かりにくいですが、堀割状遺構が杉林の中に続いているのです。
一見したところでは城跡のようにも見えます。
一番北側の遺構が途切れる位置は台地の辺縁なので、遠くを望むことができました。
そこには、普済寺東遺跡の南端部が見えました。
林内の遺構の状態はとてもいい感じで、いかにも失われた街道の雰囲気があるのです。中世街道ファンには一見の価値があります。
ただ、ここから低地へ降りる経路は開墾で失われていて、痕跡はありません。鎌倉街道は台地の間に横たわる幅広い谷地をどうやって越えていたのでしょうか?
その痕跡が見られないは残念です。
では、続いて普済寺東遺跡へ行ってみましょう。
ここでも堀割状遺構が林の中に延びているのが見られます。
この遺跡も痕跡がハッキリと残っていて、ぜひ見ていただきたい遺跡です。
特にここの遺構は今までの遺跡より堀割の幅が広く、一段高い所から望むと全体に浅いことがわかります。
このまま街道は台地の最高部を目指して登ってました。
その最高所を過ぎると遺構は能増 門跡裏遺跡まで途切れています。ただ、その痕跡は辿ることができ、今は町道として整備されています。
では遺構が残る能増 門跡裏遺跡まで行ってみましょう。
普済寺東遺跡からそのまま街道跡の町道を北へ辿ってしまうと民家に突き当たってしまいます。こちらからは遺跡へたどり着けません。
ここは北側に回り込まないと遺跡に入れないので、だいぶ遠回りに歩くことになりますが北側へ回り込みましょう。
遺跡は一見すると荒れた竹藪となっていて、薄暗く不気味でした。しかし、その中に堀割状遺構が続いていて中世の道路跡らしい雰囲気が漂っていました。
そのまま堀割を進むと先ほどの民家の裏に突き当たるので通り抜けられません。
ここから再び不気味な竹藪の中を戻ってくることになりました。
小川町内のほかにも、大里郡寄居町と現・深谷市の境界付近や、東京都国分寺市内にも鎌倉街道上道の遺構とされる堀割遺構が残っています(国分寺の遺構は「武蔵国分寺跡 附東山道武蔵路跡」の一部として国指定史跡になっているので、別の機会に紹介します)。
鎌倉街道上道は、このような遺構が残っている場所がある一方で、ほとんどの部分は遺構が失われています。積み重なる歴史の中で開墾や宅地開発が進んだり、今でも道として利用されているため道路整備されている場所が大半です。
有名なところでは、東京都町田市内にある都道があります。ここは「鎌倉街道」の通称があり、道路わきに標識もあります。当時のルートをほぼ踏襲していますが拡幅や改良で遺構は失われています。
で、最近までよく当時の雰囲気を伝えていたにもかかわらず、調査もされずに破壊されてしまった場所も多いです。一例として埼玉県日高市内に残っていた遺構を紹介します。
JR川越線武蔵高萩駅から南西方向に約20分ほど歩くと、その現場はあります。
「日高市女影の鎌倉街道跡」として、ものの本では堀割遺構の痕跡が残った場所として紹介されていて有名な場所でした。
上の写真中央に移るクリーム色の建物のところには、堀割の一部がありました。しかし、近年になって破壊されました。
ここは中先代の乱の戦場として有名な「女影ヶ原古戦場跡」として埼玉県指定旧跡となっているのですが、指定範囲はおそらく写真左手に鎮座している「霞野神社」の境内だけなのでしょう。範囲外の場所は保護されませんでした。
この周辺ではやや南下した高萩地内の市道沿いに、まだ雰囲気が残されていました。
さらに南下すると「鎌倉街道上道碑」が、そして大谷沢地内に入るとその名も「鎌倉街道」交差点がありました。
ここは鎌倉街道上道と旧千人同心日光街道(日光街道脇往還)の交差する場所でした。脇往還沿いには杉並木が残っていますが、これも以前に比べるとだいぶ破壊が進んでいます。
開発の波が迫るのも時代の趨勢では仕方がないことかもしれないのですが、失われてしまったものは二度と元に戻すことはできません。なるべくなら残しながら開発も進められるようになればいいのですが、二軸並立は難しいのでしょうね。
-----------
鎌倉街道上道(令和4年11月・国指定史跡 埼玉県入間郡毛呂山町大類、市場ほか)
鎌倉街道は鎌倉時代から室町時代にかけて整備された、鎌倉と関東諸国を通って各地を結んだ主要道路の総称です。特に鎌倉から武蔵や上野を抜け、越後谷氏なのを結んだルートを上道と呼んでいました。中世には鎌倉街道上道と呼ばれず、単に「上道」あるいは「鎌倉大道」などと呼ばれており、「鎌倉街道」といわれるようになったのは後世になってからとみられています。
毛呂山町内には総延長約1.3㎞の中世の道路跡が残されていて、さらに現在の大類グラウンドと特殊支援学校の敷地では道路敷に面した中世の集落跡が発見されています(堂山下遺跡)。この集落は中世史料に名前が現れる「苦林宿」だとされています。そして集落や街道と密接な関係があるとみられる宗教施設の跡(崇徳寺跡)や、集落や街道整備に際して村境や街道のルートを決定するのに重要な役割を果たした古墳群(川角古墳群)などもあります。
それらが鎌倉街道上道と密接に関連する遺跡群として、このたび国指定史跡として指定されました。
ブログが気に入ったらクリックをお願いします