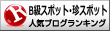今回も当ブログをご覧いただき、ありがとうございます。
今回も私の地元・埼玉県の史跡、「鎌倉街道上道」を紹介します。
鎌倉街道上道の指定範囲(2か所の「推定ライン」を除く)
前回、「そもそも鎌倉街道とはどんな街道?」という話をしておりませんでした。鎌倉街道を初めて知ったという方にも知っていただけるようにお話しします。
鎌倉街道とは日本で武家政権が始まった鎌倉時代に、鎌倉幕府が中心となって整備した道路網です。
私が中学・高校生の頃は「鎌倉幕府有事の際に地方の御家人が鎌倉へはせ参じることができるようにほぼ直線で鎌倉へ向けて整備された街道」と歴史の授業で習った覚えがあります。「いざ、鎌倉!」がキーワードでした。
特に上道は鎌倉から北上して久米川(東京都東村山市)、藤沢、小手指ヶ原(埼玉県所沢市)、堀兼、入曽、広瀬(狭山市)、大谷沢、高萩、女影(日高市)、森戸(坂戸市)、そしてここ市場、大類(毛呂山町)を抜けて笛吹峠、菅谷(嵐山町)、奈良梨(小川町)、鉢形(寄居町)をとおり上野国(群馬県)、越後国(新潟県)方面へ抜けていました。鎌倉街道では最も利用されていた道とされています。
鎌倉幕府滅亡の際、新田義貞が上州新田荘から鎌倉へ向けて南進した際の進路もこの道でした。
今は当時より研究が進んで、もっと認識が変わっているかもしれませんが、素人的にはこの程度の認識でいいだろうと思っています。
さて、前回の続きから。
崇徳寺跡に続いては、川角古墳群を見て回りました。というか、鎌倉街道を歩いていると台地の平坦部にボコボコと多数のマウント(塚)が見られます。
中には葺石が残っているものもあり、これこそが古墳だな、と一目でわかります。これらを総称して川角古墳群と呼んでいるのです。
いかにも「群集墳」でしょう?
鎌倉街道はこれらの古墳を破壊することなく中央を横切り、苦林宿(堂山下遺跡)は古墳群を村の境界として規制していたことが窺えるのです。
だから古墳群も合わせて指定されました。
さあ、今度は街道を南下してみましょう。
下の写真は川角古墳群や堂山下遺跡の方向を南から遠望したものです。鎌倉街道B遺跡を県道川越坂戸毛呂山線からやや北に入ったところで、ここは台地の最上部の平坦面なので掘割遺構は見られません。写真に写っている雑木林は川角古墳群です。
さらに県道を越え、教会の前の道を南下します。ここは鎌倉街道C遺跡にあたります。
舗装道路は町道で、この下に往時の鎌倉街道とみられる遺構が発掘調査で見つかっています。
町道をさらに南下します。
いよいよ、鎌倉街道上道を急きょ史跡指定して保護しなければならないきっかけとなった問題の施設が見えてきました。
大規模ソーラー発電所です。
このソーラー発電所の建設により、鎌倉街道周辺に開発に対する規制が何もないことが問題視されたそうです。歴史の道100選にも選ばれたのに、下手したら遺構が破壊されかねませんでした。
最初は毛呂山町の指定文化財を目指したそうですが、町指定だと補助金が出ないのだとか。保存事業を進めていくためにもお金が必要。切実な問題ですね。
そのため、国指定史跡になるように3年ほど前から申請する手続きを進めていたんだそうです。
史跡は、例えば堂山下遺跡を復元整備するとか、そういった大規模な整備事業は行わず現状のままとするそうですが、史跡範囲の公有地化などの保存事業を進めるそうです。見境のない開発からは保護されることになったそうで、とりあえず一安心、といったところです。よかった、よかった。
確かに、鎌倉街道上道は埼玉県内にもともと多くの場所で痕跡が残っていました。しかしこの数十年で保存されずに開発の手が入ってしまい、破壊された場所が増えました。
ちなみに、指定名称が「鎌倉街道上道」となったのも、数少なくなってしまった中世の名残を残している地域を追加指定していきやすいように、との配慮があるそうです。
掘割状の遺構が見られたのに破壊されてしまった場所や、今ならまだ遺構が残っているので今後追加指定されるかもしれない場所については4回目以降、紹介したいと思います。
さて、鎌倉街道は特別支援施設「育心会」の前を通過します。街道跡と重なって南東方向へ進んでいた町道(舗装路)は急に南の方向へ進路を変えます。現地では急に右へカーブしているように見えます。
直進方向には掘割状に長く続く草地が見通せました。ここが鎌倉街道C遺跡とA遺跡が接する場所になります。
掘割状の草地の部分が鎌倉街道A遺跡になります。
こんな掘割状遺構こそ中世の街道遺跡らしいですね。
ちょっと草地に入らせてもらって、掘割遺構を堪能します。
上の入り口部分から見ただけでは右手ばかりが高くなっているように見えますが、奥へ来るとちゃんと左側も高くなっていて掘割状になっているんだとわかります。
こういう発見があると嬉しくなります。遺跡に来たんだなぁ、と実感するのです。
この掘割はやがて消滅し、その先は竹やぶを通して向こうに畑が見えました。
ここから先は開墾などによって街道の道筋が仏坂遺跡に至るまではっきりしないそうです。とりあえず通り抜けるのはやめて資料館まで戻ることにしました。
この後、仏坂遺跡へ向かいます。歩くと少々距離がありますので、次回に紹介します。
ブログが気に入ったらクリックをお願いします
今回も当ブログをご覧いただき、ありがとうございます。
今回も私の地元・埼玉県の史跡、「鎌倉街道上道」を紹介します。
鎌倉街道上道の指定範囲(2か所の「推定ライン」を除く)
前回、「そもそも鎌倉街道とはどんな街道?」という話をしておりませんでした。鎌倉街道を初めて知ったという方にも知っていただけるようにお話しします。
鎌倉街道とは日本で武家政権が始まった鎌倉時代に、鎌倉幕府が中心となって整備した道路網です。
私が中学・高校生の頃は「鎌倉幕府有事の際に地方の御家人が鎌倉へはせ参じることができるようにほぼ直線で鎌倉へ向けて整備された街道」と歴史の授業で習った覚えがあります。「いざ、鎌倉!」がキーワードでした。
特に上道は鎌倉から北上して久米川(東京都東村山市)、藤沢、小手指ヶ原(埼玉県所沢市)、堀兼、入曽、広瀬(狭山市)、大谷沢、高萩、女影(日高市)、森戸(坂戸市)、そしてここ市場、大類(毛呂山町)を抜けて笛吹峠、菅谷(嵐山町)、奈良梨(小川町)、鉢形(寄居町)をとおり上野国(群馬県)、越後国(新潟県)方面へ抜けていました。鎌倉街道では最も利用されていた道とされています。
鎌倉幕府滅亡の際、新田義貞が上州新田荘から鎌倉へ向けて南進した際の進路もこの道でした。
今は当時より研究が進んで、もっと認識が変わっているかもしれませんが、素人的にはこの程度の認識でいいだろうと思っています。
さて、前回の続きから。
崇徳寺跡に続いては、川角古墳群を見て回りました。というか、鎌倉街道を歩いていると台地の平坦部にボコボコと多数のマウント(塚)が見られます。
中には葺石が残っているものもあり、これこそが古墳だな、と一目でわかります。これらを総称して川角古墳群と呼んでいるのです。
いかにも「群集墳」でしょう?
鎌倉街道はこれらの古墳を破壊することなく中央を横切り、苦林宿(堂山下遺跡)は古墳群を村の境界として規制していたことが窺えるのです。
だから古墳群も合わせて指定されました。
さあ、今度は街道を南下してみましょう。
下の写真は川角古墳群や堂山下遺跡の方向を南から遠望したものです。鎌倉街道B遺跡を県道川越坂戸毛呂山線からやや北に入ったところで、ここは台地の最上部の平坦面なので掘割遺構は見られません。写真に写っている雑木林は川角古墳群です。
さらに県道を越え、教会の前の道を南下します。ここは鎌倉街道C遺跡にあたります。
舗装道路は町道で、この下に往時の鎌倉街道とみられる遺構が発掘調査で見つかっています。
町道をさらに南下します。
いよいよ、鎌倉街道上道を急きょ史跡指定して保護しなければならないきっかけとなった問題の施設が見えてきました。
大規模ソーラー発電所です。
このソーラー発電所の建設により、鎌倉街道周辺に開発に対する規制が何もないことが問題視されたそうです。歴史の道100選にも選ばれたのに、下手したら遺構が破壊されかねませんでした。
最初は毛呂山町の指定文化財を目指したそうですが、町指定だと補助金が出ないのだとか。保存事業を進めていくためにもお金が必要。切実な問題ですね。
そのため、国指定史跡になるように3年ほど前から申請する手続きを進めていたんだそうです。
史跡は、例えば堂山下遺跡を復元整備するとか、そういった大規模な整備事業は行わず現状のままとするそうですが、史跡範囲の公有地化などの保存事業を進めるそうです。見境のない開発からは保護されることになったそうで、とりあえず一安心、といったところです。よかった、よかった。
確かに、鎌倉街道上道は埼玉県内にもともと多くの場所で痕跡が残っていました。しかしこの数十年で保存されずに開発の手が入ってしまい、破壊された場所が増えました。
ちなみに、指定名称が「鎌倉街道上道」となったのも、数少なくなってしまった中世の名残を残している地域を追加指定していきやすいように、との配慮があるそうです。
掘割状の遺構が見られたのに破壊されてしまった場所や、今ならまだ遺構が残っているので今後追加指定されるかもしれない場所については4回目以降、紹介したいと思います。
さて、鎌倉街道は特別支援施設「育心会」の前を通過します。街道跡と重なって南東方向へ進んでいた町道(舗装路)は急に南の方向へ進路を変えます。現地では急に右へカーブしているように見えます。
直進方向には掘割状に長く続く草地が見通せました。ここが鎌倉街道C遺跡とA遺跡が接する場所になります。
掘割状の草地の部分が鎌倉街道A遺跡になります。
こんな掘割状遺構こそ中世の街道遺跡らしいですね。
ちょっと草地に入らせてもらって、掘割遺構を堪能します。
上の入り口部分から見ただけでは右手ばかりが高くなっているように見えますが、奥へ来るとちゃんと左側も高くなっていて掘割状になっているんだとわかります。
こういう発見があると嬉しくなります。遺跡に来たんだなぁ、と実感するのです。
この掘割はやがて消滅し、その先は竹やぶを通して向こうに畑が見えました。
ここから先は開墾などによって街道の道筋が仏坂遺跡に至るまではっきりしないそうです。とりあえず通り抜けるのはやめて資料館まで戻ることにしました。
この後、仏坂遺跡へ向かいます。歩くと少々距離がありますので、次回に紹介します。
ブログが気に入ったらクリックをお願いします