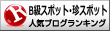最近、鉄道車両の文化財指定が相次いでいます。
今年の3月にも、愛知県のリニア・鉄道館にある蒸気動車が重要文化財に指定されました。
鉄道関連の遺物、遺構も文化財として見直されつつあるのですね。
さて、東日本であれば鉄道関連の展示施設といえばもちろん、鉄道博物館ですね。
最近、映画にもなった『翔んで埼玉』の主題歌、“埼玉県のうた”にも
埼玉の自慢といえば、快晴日数が日本一
埼玉の人におすすめのスポットを聞いたら
「鉄道博物館!」
まさかの屋内!
と歌われた“てっぱく”です。
ここには5件もの重要文化財があるんです。
そのうちの1件は『鉄道古文書』という書類です。
鉄道創業期の貴重な書類のようですが、写真で紹介するようなものではなさそうなのでここでは紹介しません。
それ以外の貴重な鉄道車両を写真付きで紹介したいと思います。
鉄道博物館に展示されている車両といえば1号機関車などは有名ですね。
それ以外にはどのような車両が指定されているのか。ワクワクしながら館内へ向かいました。
エントランスから入って早速目の前にその威容を誇っていたのが1号機関車でした。
さすが目玉展示品。一番いいポジションを占めています。
1号機関車
1号機関車は有名なので、ご存知の方も多いと思います。
日本で初めて開業した新橋~横浜間を走った機関車です。
ですが、“1号機関車”は実は、1両だけではなかったようです。
明治5(1872)年、初の鉄道開業に合わせてイギリスから5形式、10両の蒸気機関車が輸入されました。
この10両、日本政府から5つのメーカーに発注されており、そのうちの1両がこの機関車、というわけです。
これらの機関車は1号~10号と番号が振り分けられたそうですが、この機関車がなぜ、1号とされたのかは分らないそうです。
一説には、日本へ到着した順番だったとか。
1号機関車 側面
イギリス製だけあって、なかなか紳士風な、洗練されたデザインではないでしょうか。
機関車の側面には発注されたメーカーの一つ、バルカン・ファウンドリー社の銘板が貼られていました。
この機関車はバルカン社製150形式というそうです。
1号機関車 「バルカン・ファウンドリー」銘板
「No.614」は製造番号だそうです。
この機関車を見て、まず思ったのは
「きかんしゃトーマス」あるいは
「きかんしゃ やえもん」みたいだな、
でした。
1号機関車 正面
「トーマス」は今でも放映されてるから、皆さんご存知でしょう。
イギリス製なので、イギリスが原作のトーマスに似ているのは当たり前といえば当たり前ですよね。
「きかんしゃ やえもん」は、これを言えば私の年代がバレてしまいますが、私が子どもの頃よく読んでいた絵本です。
「やえもん、みたいだよな」と思ってたら、やえもんはこの機関車がモデルだったと聞いて納得しました。
1号機関車 ボディ部
全国で使われたのち、九州の島原鉄道に譲渡され使われていたそうです。
その後、昭和の初めに国鉄(当時は鉄道省)に返還されて保存されていました。
交通博物館などで展示されたのち、こうして今では鉄道博物館のエントランスを飾るまでになりました。
続いて、ED40形式電気機関車です。
ED40形式電気機関車
こんなごっつい電気機関車の何が貴重なのか、わかりますでしょうか?
実は、日本最初の国産電気機関車なんです。
ED40形式電気機関車 後部
そこで問題です。わが国最初の本線電化区間はどこだったでしょうか
答えは、今では廃線となった信越本線・横川~軽井沢間の碓氷峠越えの区間だったんです。
当初、急勾配が続くこの区間はアプト式の蒸気機関車が採用されていました。
しかし、この区間はトンネルも続くため運転士も乗客もひどい煤煙に悩まされていました。
それを解決するために電化は急務でした。
ただ、当時は電力供給自体が今ほど普及していなかったため、自前の発電設備が必要となりました。
そのために横川に発電所、丸山と矢ケ崎の2ヶ所に変電所が設けられました。
そのうち、丸山変電所は今でも建物や設備が残っています。
そして、アプト式に対応した初の国産電気機関車が製造されました。
それがED40形式電気機関車だったのです。
ED40形式電気機関車 アプト式レールと基台部
アプト式 ラックレールと歯車(ピニオンギア)
日本最初の本線電化区間が碓氷峠で、そこを走った国産最古の電気機関車。
ちょっと意外な鉄道史の片鱗でした。
全部で14両製造されたそうですが、現存するのはこの1両のみだそうです。
ピニオンギアを外して、東武鉄道で昭和43(1968)年まで活用されていたそうで、その後保存のため国鉄に返還されたそうです。
鉄道博物館ではピニオンギアなどが復元されて展示されています。
ED40形式電気機関車 電動機
ED40形式電気機関車 構造模型
ED40形式のそばには内部構造がわかるように模型も展示されていて、たいへんわかりやすいです。
まだまだあります。
続いては、現存最古の“電車”ナデ6110形式です。
ナデ6110形式6141号電車
私はこの電車に一番の親しみを感じました。
なんか、山手線に走ってそうですから。サラリーマンの性(さが)ですかねぇ…。
ナデ6110形式6141号電車(正面から)
と思ったら、山手線や中央線の乗客の増加に対応するために造られた、初めてのボギー車(車体の前後に2軸台車を装着した電車)なんだそうです。本当に山手線を走ってたんだ!
この車両は大正3(1914)年に製造されたものだそうです。
一番の特徴が、統括制御装置を採用し重連運転を可能にした点だとか。
つまり、今の通勤電車では当たり前の「○○両編成」を可能にした最古の電車ということですか。
ナデ6110形式6141号電車の内部
今では当たり前のロングシートも、この頃採用されたのだそうです。
こうやって見ていても、古さを感じさせません。
そうですよね。これらの特徴は今の通勤電車に受け継がれているんですから。
ナデ6110形式は、いわば最古の“通勤電車”なんです。
ナデ6110形式6141号電車の屋根
一方、架線からの通電がパンタグラフでなくトロリーポールだったんですよ。
見てください。
この当時は交流電流でなく直流電流を採用していたため、2本のトロリーが必要だったんだそうです。
こういうところには歴史を感じますね。
そして最後に紹介するのは、1号御料車です。
1号御料車
明治9(1876)年に神戸で製造されました。先のナデ6110形式と違い、ボギー台車ではなく2軸車なのです。
1号御料車 正面から
鉄道創業期に使用された客車としては唯一の現存例なんだそうです。
とはいえ、こんな特殊な客車が唯一の現存例では、イマイチ思い入れが湧きません。うーん…。
1号御料車 屋根周りの装飾
外装はすべて漆塗り、社内の御座所壁面は繻子張り、天皇玉座は絹張りと、とにかく当時の一流の工芸技術が用いられた超豪華な造りなのです。
1号御料車 天皇玉座
これは工業製品ではなく、巨大な伝統工芸品です。
ガラス張りの部屋に入れられて保存されているため、写真写りがイマイチなのが申し訳ありません。
それだけ一流の工芸品なんだなー、工業製品ではなくて。
その意味ではなんか、思い入れが湧かない逸品でした。
でもこれだけの規模となると、相当な工芸技術が必要だったでしょう。それはそれですごいですね。
いかがでしたか?鉄道史に残る鉄道車両の数々。さすが鉄道博物館です。
関東では他にも、国産最初の量産型電気機関車と、最初の地下鉄車両が重要文化財に指定されました。
それらについては、またいずれ紹介したいと思います。
--------
1号機関車(平成9年4月・重要文化財 さいたま市大宮区大成町)
明治5(1872)年、新橋~横浜間に日本で最初の鉄道が開通した際に使用された10両の蒸気機関車のうちの1両です。日本最初の鉄道車両はイギリスの5つのメーカーに発注されました。唯一現存するこの機関車は、そのうちの1両です。バルカン・ファウンドリー社に発注された、150形式といわれるものです。今でも機関車のボディの銘板でそのことが確認できます。
ED40型電気機関車(平成30年10月・重要文化財 さいたま市大宮区大成町)
本文でも述べましたが、日本最初の本線電化区間は蒸気機関車の煤煙にひどく悩まされていた群馬県・横川~長野県・軽井沢にまたがる碓氷峠越えの区間でした。ここは最大勾配67‰という急こう配の区間だったため、アプト式が採用されました。はじめはドイツ製の電気機関車が導入されましたが、輸送量の増大に伴い国産電気機関車の導入が進み、その初期タイプがED40型電気機関車でした。すなわち、このごっつい電気機関車は日本で最初の国産電気機関車だったのです。そのため大変貴重な鉄道車両として重要文化財に指定されました。
ナデ6110形式電車(平成29年10月・重要文化財 さいたま市大宮区大成町)
本文でも述べましたが、今でこそ東京や大阪などの都市近郊区間で採用されているボギー台車、統括制御装置による重連運転、ロングシートの採用など、現在の通勤電車にも引き継がれている大量輸送に適応した構造が、すべてこの電車に採用されています。都市の拡大に伴う大量輸送の需要に対応した電車車両として最初に造られたのがこのナデ6110形式でした。すなわち、最初期の通勤電車ということで、重要文化財に指定されました。
1号御料車(平成15年5月・重要文化財 さいたま市大宮区大成町)
絹張りの玉座、漆塗りの外装など、日本における最高の工芸技術を駆使した、天皇が乗車するために造られた最初の客車でした。明治9(1876)年にイギリス人技師ウォルター・M・スミスの指導によって神戸の鉄道工場で製造されました。鉄道創業期の客車として唯一の現存例でもあり、その工芸技術レベルの高さもあって重要文化財に指定されました。
参考文献:
久保田 博 『日本の鉄道車輛史』 グランプリ出版(2001)
白川 淳『御召列車』 マガジンハウス(2010)
鉄道博物館 ホームページ http://www.railway-museum.jp/
ブログが気に入ったらクリックをお願いします