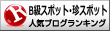夏休みの北伊豆ドライブ、最後は願成就院、北条氏邸跡、伝堀越御所跡を紹介します。
これらの遺跡、なぜここでまとめて紹介するかというと…
遺跡として見られるところがほとんどない!からです。
旧伊豆長岡町は中世の時期、歴史的にとても熱い場所だったんです。
この周辺は、守山という独立した山を中心にして中世期の貴重な遺跡が展開している場所なのです。
にもかかわらず、です。
例えば伝堀越御所跡などは、足利幕府と古河公方の対立で、幕府方から東下した足利政知が鎌倉に入ることができずに拠点を構えた場所なんです。
遺跡としても、広大な苑池や建物跡が出土しているんです。
なのに、少なくとも30年は、↓この状態のままです。
伝堀越御所跡
…空き地。まったく空き地です。遺跡の保存方法として埋め戻されている土地は何度も見ました。
そのまま何年も放置されている場所も何ヶ所も知っています。
ココもそれか!
保存のために埋め戻すのは仕方ないとはいえ、歴史的には非常に重要な場所なのに。
とても残念ですが、ただ、鎌倉の永福寺跡のように、30年たって史跡整備が完了した場所もあります。
予算や土地の権利関係など、難しい問題もあるのでしょう。いずれ遺跡が見られるようになるかもしれません。
それまで気長に待ちます。
近くには鎌倉幕府の初代将軍、源頼朝の正妻だった北条政子の産湯の井戸といわれる井戸跡がありました。
北条政子の産湯の井戸
北条政子の産湯の井戸(井戸枠)
堀越御所とは時代が違うし、関係もありませんが、数少ない守山周辺の見どころです。
そこから歩いていける距離に北条氏邸跡(円成寺跡)が残されていました。
ここも、鎌倉幕府の執権として権力をふるった北条氏の邸宅跡なんです。
しかし、ここも少なくとも20年以上、↓このままです。
北条氏邸跡(円成寺跡) 谷の入り口
北条氏邸跡(円成寺跡)。背後が守山
…空き地です。あえて言うなら谷状の地形に館が築かれたことがわかるだけです。
歴史的にも貴重な遺跡なんだから、遺構の一つでも、どんなものなのか見たかったですね。
いずれ見られるようになることを期待して待ちます。
そういえば、これらの遺跡を調査した際の出土遺物はどこにあるのでしょう?
地元の自治体は、それらを展示する施設だけでも先に建てないでしょうか?
まだ見られる遺跡だったのが願成就院でした。
願成就院といえば、国宝に指定された5体の運慶仏が有名です。
運慶作と確認された数少ない仏像群ですから、文化財マニアとしては必ず押さえておきたい仏像です。
今回、もちろんこれらもしっかりと拝ませていただきました。
噂にたがわず、平安期に比べて鋭い眼光、よりスリムな体躯など、典型的な鎌倉時代の仏像でした。
もっと写真付きで紹介したいのですが、なにぶん撮影禁止だったので、このくらいしか書くことができません。
現在の願成就院、背後の山は守山
現在の山門を入ると正面に見えるのが、運慶作の5体の仏像を安置する大御堂です。
願成就院境内
願成就院本堂
古風な茅葺屋根の本堂は、大御堂の左手にありました。
境内には、初代執権の北条時政の墓(供養塔)がありました。
北条時政公の墓
境内奥には堀越公方・足利政知の子、足利茶々丸の墓も残っていました。
足利茶々丸の墓
願成就院は鎌倉時代、広大な苑池を伴った浄土式庭園の広がるお寺でした。
裏山の守山は庭園の借景だった可能性があります。
そのためか、隣の守山八幡宮境内を含めた守山斜面は史跡指定範囲に含まれています。
守山八幡宮
なお、願成就院と守山八幡宮は位置関係から、いわゆる別当と神宮寺の関係だったのでしょうね。
ここにも、時代の流れを感じることができます。
発掘調査で浄土式庭園の跡も発見されているそうです。
しかし、その池の跡は住宅地となってました。
それでも、境内とその周辺には遺構が見られる場所がありました。
中世に整地された痕跡
大御堂と守山八幡宮の間にあたる山の斜面には、斜面を削って平地を作り出した痕跡が残っていました。
また、山門の左手には「史跡 願成就院跡」の標柱があり、遺構保存のための広場と石積基壇の跡が残されていました。
「史跡 願成就院跡」の標柱
この石積基壇跡が、南塔跡と思われます。巨大な塔が建っていたんですね。
南塔跡
これらが鎌倉時代の歴史書『吾妻鑑』の記述と一致しているらしいのです。
ただ、そのことに関しては、確認していません。
文献で遺構を確認できるとしたら、とても貴重じゃないですか。
日本の中世以前の遺跡では、あまり例のないことです。
本当に、日本はせっかく文化財保護の制度があるというのに、その顕彰が足りないと思います。
もっと一般に、その存在の貴重さを訴え、周知していくことが必要なのではないでしょうか。
このほかにも頼朝が潜伏したという「蛭が小島」、函南町にある慶派仏師・実慶の作とされる薬師如来像を展示する「かんなみ仏の里美術館」も訪問しました。
北伊豆は自然も歴史も、非常に濃厚な軌跡が残された場所でした。
--------
伝堀越御所跡(昭和59年10月・国指定史跡 静岡県伊豆の国市寺家・御産所四日市町)
堀越御所は、堀越公方と呼ばれた足利政知の館跡です。15世紀半ば、関東では足利成氏の古河公方の勢力と、室町幕府に従う勢力との対立が激しくなっていました。関東の直接支配をもくろんだ将軍・足利義政は庶兄・政知を鎌倉公方として関東へ派遣しましたが、抵抗勢力の勢いが強く鎌倉へ入ることができず、伊豆国・堀越の地に館を構えました。そのため、足利政知は堀越公方と呼ばれました。館跡とされた場所からは広大な苑池や建物跡の遺構が出土し、伝堀越御所跡として国指定史跡となっています。
北条氏邸跡(円成寺跡)(平成8年9月・国指定史跡 静岡県伊豆の国市寺家・御産所中条上河原)
北条氏邸跡(円成寺跡)は鎌倉時代、執権として権勢をふるった北条一族の邸宅跡です。発掘調査で平安時代末~鎌倉時代初めの遺物や遺構が確認されました。また北条氏滅亡後、生き残った北条一族の妻や娘が韮山に戻り、一族の円成尼が邸宅跡に寺院を立てて北条一族の冥福を祈る生活をしたとされています。その円成寺跡も出土しており、江戸時代まで続いたことがわかっています。この遺跡は平安時代から鎌倉時代にかけての武家の邸宅を知ることができ、北条氏の興亡を物語る史跡としても重要なことから、史跡に指定されました。
願成就院跡(昭和48年2月・国指定史跡 静岡県伊豆の国市寺家)
願成就院跡は鎌倉初代執権・北条時政が建立した浄土式庭園を持つ寺院で、源頼朝が東北方面へ逃亡した源義経を匿った奥州藤原氏を責めた際、戦勝を祈願して建てられたといわれています。寺院にはその時納められた運慶作の阿弥陀如来、不動明王などの5体の仏像が残され、国宝に指定されています。境内には建立当初の建物跡とみられる礎石建物跡、石積み基壇建物跡、苑池跡、斜面を整地した段状遺構などが見つかっており、その一部は現在も見ることができます。
参考文献:
峰岸純夫 『享徳の乱 中世東国の「三十年戦争」』 講談社選書メチエ(2017)
和歌森 太郎 『日本史跡辞典 2 東海近畿編』 秋田書店(1976)
伊豆の国市 ホームページ https://www.city.izunokuni.shizuoka.jp/
天守君山 願成就院 公式ホームページ https://ganjoujuin.jp/
ブログが気に入ったらクリックをお願いします