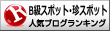ここしばらく、北伊豆地方の文化財を続けて紹介しています。
今回はその中でもメインディッシュといいますか、世界遺産にも登録された韮山反射炉と、それを設計・築造した伊豆の名代官、江川太郎左衛門英龍の役宅だった韮山役所跡(江川邸)を紹介します。
世界遺産「明治日本の産業革命遺産」の構成遺産の一つとなった韮山反射炉ですが、ネットなどで紹介されている反射炉というと巨大な煙突が建っている風景が紹介されていることが多いですね。
韮山反射炉
結構誤解されていると思うんですが、この煙突が反射炉本体だと思われている方が多いんじゃないでしょうか?
少なくとも私はそう思ってました。
実はちょっと違うんです。それについては後ほど。
周囲には今でこそ、どこでも見られるような田園風景が続きます。そんな中、突然レンガ積みの煙突が4基、聳えているのが見えてきました。
それこそが韮山反射炉でした。
観光客に配慮した、広い駐車場や物産館、展示施設が充実していてキレイに整備されていました。
韮山反射炉の煙突
韮山反射炉を見てまず目を引くのが、トラスに組んだ鉄骨のある煙突ではないでしょうか。
鉄骨はすっかり反射炉になじんで一体感すら感じます。しかしこの鉄骨、あくまで補強のために組まれたもので、時代もずっと下って昭和のものだとか。
先に紹介した北伊豆地震の際に崩壊した部分があったため、昭和32(1957)年に保存工事が行われた際、耐震補強のために組まれたものだそうです。だから、鉄骨がない状態がもともとの姿だったんですね。
韮山反射炉全景(南から)
でも、やはり韮山反射炉と言ったら今や鉄骨のある煙突ですよね。
さて、この煙突が反射炉の本体ではない、と上で述べましたが、では一体、どこが反射炉の本体なのでしょうか。
実は、反射炉本体は煙突の下部にあります。
伊豆石と耐火レンガで組まれた、外観が四角い部屋こそが炉本体なのです。
反射炉の本体(空気取り入れ口)
反射炉本体(原料投入口および燃料投入口)
反射炉はそもそも溶鉱炉の一種で、韮山反射炉は鋳鉄を作るため築かれました。
幕末に度重なった外国船の来航に対し、国防の危機を憂いた伊豆国韮山の代官・江川太郎左衛門英龍が築造したものです。
燃料となるコークスを燃やし、その燃焼熱で金属を溶かすのですが、特に輻射熱を内部に反射させて熱の損失を抑える構造になっています。
なるほど、だから「反射炉」なんですね。
煙突は燃焼に必要な空気の通り道を確保するためのものだったのです。熱を逃しては本末転倒なので、炉本体に対して巨大な煙突が必要だったようです。
そうなると煙突ばかり眺めていては反射炉を見て理解したことにはならない!
炉の中を見なくては!
そんなわけで、空気の取り入れ口を下から覗いてみたのでした。すると…
反射炉の内部
反射炉の天井は写真のようにドーム型になっているではありませんか!
設計図でも、ドーム状になっている反射炉内の様子が詳しく描かれていました。
今回、運が良いことに偶然、江川邸が所有していた設計図が期間限定で江川邸に展示されていて、撮影させてもらうことができました。
韮山反射炉の設計図(炉本体の部分)
天井が曲面になっているということは、やはり輻射熱を反射させるためということですね。なるほど!
もっと奥まで見たかったのですが、現状で覗けるのはここまででした。残念…
見学していた人の中で、この中まで覗いていた人はほとんどいませんでした。
これから韮山反射炉を訪ねる皆さんには、ぜひ奥までご覧になることをお勧めします。
そして、溶鉄(湯・溶湯ともいいます)は反対側の出湯口から取り出されたそうです。
出湯・出滓口と鋳台跡
出湯口にはあらかじめ鋳型が据え付けられていて、溶湯を直接鋳型に注げるようになっていたそうです。
今、鋳台の跡は鉄滓で埋められてますが、もともとは地下に深く掘りくぼめられて鋳型が置かれていたそうです。そうしないと湯を注げませんもんね。発掘調査がされたようですが、3m以上掘られていたそうです。
ここでは鋳鉄製の大砲が実際に作られ、試射まで行われた記録があるそうです。
実際に稼働した記録がある反射炉が残っているのは世界で唯一ここだけという話です。
韮山反射炉を見ていると日本の近代化の途上、外国の脅威に何とか対処しようとした当時の人々の感覚が生々しく伝わってくるようです。
ここから北へ向かって車で15分ほど行った所に、ありふれた農村風景が広がる韮山集落があります。
江川邸(指定名称は江川家住宅)は、この韮山集落の中心にあります。
その敷地は戦国~明治時代という長期に渡って地方行政の中心地だった類まれなる史跡として近年、「韮山役所跡」の名称で国指定史跡となりました。
韮山役所跡(江川邸)
敷地は史跡指定、建物のほとんども重要文化財、しかも古民家として重要文化財に初めて指定されたのがここの主屋ときたら、どれだけすごい所なのか緊張してきました。
入口にて入場料を支払い、いざ中へ。
まず出迎えてくれたのが、重要文化財の表門でした。
江川邸表門
表門(敷地内側から)
寺院の入口のような印象です。立派な四脚門ですからね。さすが。
そしていよいよ、江川邸の主屋へ。
江川邸主屋
立派な式台ですね。屋根が入母屋型になっていて、重厚な構えを見せています。
こちらは重要なお客様をお出迎えする入り口なので、私のような下賤の者は勝手口から入ることになります。
江川邸の土間
ところが、勝手口から入っても土間の広い空間が待っています。どれだけ立派なお屋敷なんだろう。
江川邸の見どころは土間から見上げた屋根裏の小屋組みではないでしょうか。
江川邸の小屋組み
柱間に梁を掛け、その上に細く縦横に走る貫とそれを支える太い束を立てて、この巨大な空間が生み出されているのが圧巻です。
そしてさらに、この建屋の一部は古く室町時代にまで遡る部分があるとされています。
その一つが、この土間にある“生柱”と呼ばれる掘立柱だそうです。
生柱(右の注連縄が掛かる柱)
また、現在管理室になっているため非公開部分の部屋も室町時代に建てられた個所だそうです。
土間から中の口に靴を脱いで上がります。ここには江川家に関する文書や解説が展示されていました。
撮影禁止だったので写真はありません。
左手にはさっきの式台があり、右手には台所があります。
御台所
そして式台に向かって進み左に曲がった先には、江川英龍が興した私塾“韮山塾”に使われていた部屋がありました。
韮山塾とその展示
英龍は先に述べたように国防に危機感を抱いており、特に海岸線の防衛(海防)に強い関心を抱いていました。
東京都の「お台場海浜公園」は、今ではアミューズメント施設で有名ですね。
その名前の由来になったのは、この頃に築かれた品川台場という堡塁です。英龍は、その品川台場の建造でも中心的な役割を果たしています。
その流れで高島流砲術を学び、免許皆伝を受けました。そして学んだ砲術を教授するために私塾を開きました。
それが韮山塾でした。全国から数多くの門人が集まったようです。
重要文化財に指定された建物はまだあります。
主屋から続く建物は書院です。
書院
19世紀頃に建てられたそうです。見学不可なんで、外観だけ。建物内部まで見たいですね。
主屋から外へ出ると、肥料蔵がありました。
肥料蔵
やはり19世紀のものだそう。内部は見られません。
附指定の南・北米蔵です。
南・北米蔵
他にも非公開の文化財指定建物があるようです。いずれ全部見てみたいものです。
いかがでしたでしょうか。実は私、歴史には疎く、江川太郎左衛門英龍さんも韮山反射炉について調べている途中で初めて知ったくらいです。
私はむしろ、考古学的なことや建築史、美術史的な部分に興味があるものですから、江川英龍さんについて興味があった方には物足りない内容かもしれません。その点は大変申し訳ありません。
ただ今回の訪問で、江川英達さんの業績にはとても興味が湧いたので、現地で韮山反射炉について書かれた本と英龍さんについて書かれた本を買ってきてしまいました。
これが今回の北伊豆ドライブにおける、唯二つのお土産です。奥さんと息子には何もありません。ごめんね、奥さんと息子よ。
次回訪問するときは、重要文化財に指定されている韮山代官江川家関係資料、そして江川家関係写真などもぜひ見てみたいものです。今のところ非公開のようですが。
北伊豆の文化財についてはもう4ヶ所訪問しています。それらについては次回、まとめて紹介します。それではまた。
--------
韮山反射炉(大正11年3月・国指定史跡 静岡県伊豆の国市中字鳴滝入)
韮山役所跡(平成16年9月・国指定史跡 静岡県伊豆の国市韮山韮山)
江川家住宅(昭和33年5月・国指定重要文化財 静岡県伊豆の国市韮山韮山)
韮山反射炉は伊豆・韮山の代官、江川太郎左衛門英龍とその息子・英敏によって築かれました。オランダの反射炉に関する文献をもとに、先に反射炉によって大砲の鋳造に成功していた肥前国佐賀藩の協力を得て安政2(1855)~4年にかけて築造されました。文中にも記しましたが、実際に稼働した記録が残る反射炉としては世界で唯一残された反射炉だそうです。
韮山役所跡はその韮山代官の住宅兼役所だったところで、代官は代々世襲だったため、戦国時代から明治にかけて長きにわたり役所として機能しました。その世襲代官が江川家であり、代々太郎左衛門を名乗っていました。中でも江川英龍の功績は大きく、江川太郎左衛門といえば江川英龍を指すほどでした。その住宅だった建物が江川家住宅でした。古民家では最初に重要文化財に指定され、さらに表門や書院、蔵、武器庫、敷地が追加指定されています。
参考文献:
公益財団法人 静岡県文化財団 『幕末の産業革命 韮山反射炉』 しずおかの文化新書17 静岡県文化財団(2015)
堀内永人 『わかりやすい 韮山反射炉の解説』 文盛堂書店(2015)
日本建築学会・編 『日本建築史図集』 彰国社(1949)
吉澤政己 『東海・中央高地の住まい』 INAX ALBUM 34 日本列島民家の旅6(1996)
橋本敬之 『幕末の知られざる巨人 江川英龍』 角川SSC新書 KADOKAWA(2014)
ブログが気に入ったらクリックをお願いします