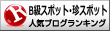以前、那須神田城について紹介しました。
実は那須神田城を訪ねた時、他にもいろいろな遺跡を見てきました。
それらを全く紹介しなかったものですから、なんか物足りない感じになってました。
これからしばらくは、ぜひ見ていただきたい、那須の文化財について書いていきます。
なお、これらで記載する内容は2018年秋頃のものです。お出かけの際には情報を再度ご確認ください。
この時の那須文化財探訪のコースは
駒形大塚古墳(那須小川古墳群)→那須神田城跡→那須八幡塚古墳(那須小川古墳群)→
観音堂古墳、吉田温泉神社古墳(那須小川古墳群)→吉田富士山古墳(那須小川古墳群)→
唐の御所横穴→湯津上資料館→那須国造碑→那須官衙遺跡(那珂川町なす風土記の丘資料館)
でした。
東北自動車道を矢板インターで降り、那珂川町へ向かいます。
最初に訪ねたのは駒形大塚古墳という古墳です。
駒形大塚古墳(北から)
見えてきたのは巨大な塚でした。
前方部が削られていて円墳のように見えますが、前方後方墳です。
前方後方墳ということは、4世紀代に築かれたということになります。古墳としてはとても古いものですね。
その時代にこれほど巨大な墳墓を築いたということ自体、驚きです。
周辺は広場になっていて、駐車場もありました。
車を止めて古墳へ近づいていきました。
駒形大塚古墳(後方部を東から)
その大きさを改めて実感しました。葺石も見られます。
後方部(西側)
西側からだと、後方部の角がきちんと観察できました。前方後方墳であることを実感できました。
後方部墳頂
巨大な古墳だけに、墳頂からの眺望がいいです。
墳頂には祠がまつられていました。古墳に祠はは付き物ですね。
後方部墳頂から前方部の痕跡を眺める
後方部墳頂からは、前方部と周堀の痕跡が眺められました。
そこから全長が想像できます。かなり大きな古墳です。
前方部が残っていたら、もっと良かったのに。
そして、訪問の順ではありませんが、なす風土記の丘資料館には駒形大塚古墳の出土品が展示されていました。
駒形大塚出土品
鉄器が目立ちますね。当時の権力者は、やはり鉄の流通を押さえていたのですね。
駒形大塚古墳出土の銅鏡
駒形大塚古墳からは銅鏡も出土しています。画文帯神獣鏡ですね。
駒形大塚古墳出土品(土器)
そして土器群。供奉用の器形が多いでしょう。
高坏の台の部分が立ち上がらずに末広がりに広がるのは4世紀の土師器の特徴の一つです。
那須神田城跡の時にも書きましたが、私は“最古の~”とか“初期の~”という言葉に反応してしまいます。
だから改めてこの古墳の古さに、すごいなー、の一言しか出てきません。
ちなみに駒形大塚古墳は、以前は別個に史跡指定されていました。
しかしその後、周辺の調査が進んでいろいろ明らかになってきたこともあり、那須八幡塚古墳、吉田温泉神社古墳などを含めて
『那須小川古墳群』
の名称で1件の史跡として追加指定、名称変更が行われたという経緯があります。
次に、那須八幡塚古墳を訪ねました。
駒形大塚古墳よりさらに那珂川の河岸段丘縁に近い所にあります。
こちらは史跡整備が行われて墳丘が見学しやすくなっていました。
駐車場がありません。周辺の道も農道なので狭いです。ご注意ください。
那須八幡塚古墳(北西から)
前方部、後方部とも高く、くびれ部分が低くなっていることがはっきり見て取れます。
これらの特徴が典型的ですね。4世紀代の前方後方墳です。
ただ、前方部は削平されていたらしく、整備にあたって復元したそうです。
那須八幡塚古墳(後方部)
墳丘表面の葺石
葺石も復元したらしいのですが、バラストを撒いたのではないでしょうか。
なんかちょっと違う…気がする。
前方部
眺めがいいですね。
田園風景に心が癒されます。
ここから北へ歩くと、観音堂古墳や吉田温泉神社古墳があります。
これらの古墳は那須八幡塚古墳からも見渡すことができました。
吉田温泉神社古墳(奥の木立)と観音堂古墳(手前の木立)
続いて観音堂古墳を訪ねました。
観音堂古墳
方墳のようです。
保存状態は結構いいです。
観音堂古墳の墳頂
墳頂には観音堂が建てられてました。主体部は破壊されたでしょうね。
それも歴史ですから、しょうがない。
観音堂古墳の周濠
その代わり、周濠がまだ残っています。
藪が深く、底も深いようなので降りることはしませんでした。
こういうのが残されていると、嬉しくなってしまいますね。
観音堂古墳から那須八幡塚古墳を見る
そして吉田温泉神社古墳へ。
吉田温泉神社古墳(北から)
発掘調査で前方後方墳と判明したそうで、前方部は手前の畑の下から発見されたそうです。
しかし、こちらも後方部しか残されていません。
吉田温泉神社
しかも神社が建っていることで墳頂も墳丘もだいぶ削られています。
それでもまだ、墳丘の名残がありました。
吉田温泉神社古墳の墳丘
ただ後方部の形状を確認することはできないほど削られています。
吉田温泉神社古墳の保存状態は悪いですが、それでも那須小川古墳群は、巨大な前方後方墳が3基も残されていることが特徴的です。
東日本では、古式古墳といわれるものは前方後方墳が多い。その前方後方墳が規模もさることながら3基も残されている。
そこにこの古墳群の貴重さがあると思います。
さらに言えば、これらは那珂川上流の侍塚古墳群に続いていく、その侍塚の近くに那須郡衙が造られる。
そして郡衙の後に神田城が造られる。
この歴史的な流れが遺跡で残され、読み取れることがこの地域の特殊性を示しているんだと思うのです。
最後に、少し離れたところにある吉田富士山古墳へ向かいました。
吉田富士山古墳
こちらの古墳、工場の敷地内にあります。
駐車場はあります。ただ工場の来客用なので、ここに駐車したままにするのは遠慮しました。
事務所に受付があります。記名帳に記名して、古墳に向かいました。
吉田富士山古墳の近景
庭園として整備されていました。ただ、墳形はハッキリとわかります。
方墳です。2段に築かれている様子も残っていました。保存状態は大変いいように思います。
周りの池は周濠を利用したもののようです。ただどの程度、原形を保っているかはわかりません。
吉田富士山古墳(東から)
松の木がいい雰囲気ですね。これから訪ねる下侍塚古墳のようです。
植えられた目的は全く違うでしょうが。
吉田富士山古墳の墳丘(南東から)
工場敷地内であるにもかかわらず、たとえ庭園の築山としてでも古墳がきちんと保存されているのは大変珍しいのではないでしょうか。
こちらの会社は文化財保護に理解があるのでしょう。
吉田富士山古墳の墳丘(南西から)
吉田富士山古墳の2段築造(墳頂から)
那須小川古墳群、見ごたえのある古墳群でした。
初期古墳を堪能した後は末期の古墳、唐御所横穴へ向かいます。
--------
駒形大塚古墳(昭和54年3月・国指定史跡、平成14年12月・指定変更 栃木県那須郡那珂川町小川)
前方後方墳。全長64m、後方部は長さ30m、幅32m、高さ8m、前方部は幅約16mあります。昭和49(1974)年に発掘調査が行われ、後方部には長さ3.2m、幅0.75mの木炭槨が検出されていて、おそらく同規模の割竹型木棺が埋葬されていたと推測されています。墳形や出土品から4世紀中頃に築造されたと推定されています。
那須小川古墳群(平成14年12月・国指定史跡 栃木県那須郡那珂川町小川・吉田)
4世紀代に築かれたと推定される3基の前方後方墳と2基の方墳から成る古墳群。発掘調査で、吉田温泉神社古墳からは殯に関連する施設と推定されている竪穴式住居が発見されています。その築造年代や遺跡の内容から、古墳時代前期の那須地方の特色を示す古墳群として、国指定史跡に指定されました。以下に各古墳の特徴を示しました。
那須八幡塚古墳(栃木県那須郡那珂川町吉田)
前方後方墳。全長62m、後方部の幅31m、高さ約6m、前方部幅は約17m。後方部頂上から主体部が出土し、東西端を粘土で固定した割竹型木棺で埋葬されたと推定されています。副葬品は銅鏡、鉄剣、鋸、鉋、鉄斧が朱で覆われて、また周濠からは祭祀に使われたとみられる土師器が出土しました。
吉田富士山古墳(栃木県那須郡那珂川町吉田)
一辺が約7m、高さ約3mの方墳。周濠が残されていますが庭園の池として利用されており、原形のままの濠とは思えませんでした。
吉田温泉神社古墳(栃木県那須郡那珂川町吉田)
全長約47mの前方後方墳。後方部墳頂は削平されて吉田温泉神社が祀られています。発掘調査で、殯に関連する施設と推定されている竪穴式住居が発見されています。
観音堂古墳(栃木県那須郡那珂川町吉田)
一辺約30mの方墳。墳丘や周堀が残されています。発掘調査で器台や装飾壺が見つかっています。
参考:
那珂川町 ホームページ http://www.town.tochigi-nakagawa.lg.jp/
ブログが気に入ったらクリックをお願いします