わたくしに訊かれてもトンと判断はつかないが、ホモサピエンスという種族の動物が、コミュニケーションを軸に発達してきたという事実からしても、ある程度の知能さえあれば、そのコミュニケーションの一環として暴力をふるって脅すよりも、おどけて笑わせるほうが自分の地位を一定に保てるという事実には気付いていたはずだ。
音楽のそもそもも、石と石をぶつけてリズムを取ることが言語を持たぬ彼らにとっていいコミュニケーションツールになったことが始めとされる。
種族同士が争っても、種族が絶えるだけなので、種族間の交渉に音楽や、また笑いが実に重要だったかは想像してみるだけでもお分かりいただけるであろう。
ちなみに、古代中国の思想家・孔子も、学問に重要なのは「礼楽」のふたつであると言った。
「礼」とは礼儀作法。「楽」とは、その礼儀作法がスムースに実行できるための社会づくりのことを指す。だが、これは単に音楽と言い換えてもいい。なにしろ、孔子は生涯にわたって肌身離さず琴を携えて、勉強の暇を見つけては爪弾いていたという。勉強しているふりをしてアコースティックギターを掻き鳴らしたりした団塊の世代や、自作の曲を初音ミクに歌わせたりしているゆとり世代とあまり変わりないような気もする。
話が逸れたが、音楽が時代が経っても、鳴り響く音を楽しむというスタイルが変わらないように、お笑いも、基本的には古代からの演芸がほぼそのまま現代にわたって伝わってきたものだと言って過言ではない。
そのなかで一番古い形態であろうと思われるのが、この「ものまね芸」である。
動物は生まれてから、両親の庇護の下、両親のまねをすることで生きていく知恵を体得していく。それができないものは地上から消え去るのみ。人間も、親の身振り手振りの真似や口真似などをして、生きていくために必要な最低限の言語や習慣を身に付ける。よく親になった大人が「子供って、オレの悪い癖ばかり真似するんだよね。しつけの本とか読んで正しい所作を教えても、結局オレのコピーになってしまう」なんという愚痴をよく聞くが、そういう能力は誰しもある。ならば、その能力を有史以前の人間も笑いのためのツールとして使っていたはずである。
日本書紀には、ホスセリノミコトという神が、人が水におぼれる様を演じて笑いを取ったという記述があるという。
中国では、鶏鳴狗盗の故事にもあるように、鶏の鳴きまねだけで歴史に名を刻んでしまった人もいる。
時代が下ると、ものまねを取り入れて一つの演劇の形態としてものがある。鎌倉時代後期に大成した狂言はそのひとつである。
この『柿山伏』のなかでは、ものまねがくすぐりのひとつとしてあらわれるが、ものまねそのものが演芸として確立するようになったのでは江戸時代からである。
江戸家一門が興ったのは明治時代からであるが、こういう動物の鳴き声の物まねを単独の演芸として見せるものまね芸は、江戸時代から存在していた。
幇間(たいこ)芸は、酒宴の際に、そこにいる人々の会話がスムースになるように間を取り持つ幇間が行う芸のことで、歌や踊りとともに、物まねができることは重要なスキルの一つ。これはその一例である。
これは一般庶民の間でも大ブームとなり、歌川豊国・山東京伝共著『腹筋逢夢石(はらすじおうむせき)』は、道具を使ったものまねの教科書のようなものであり、ベストセラーとなった。
裸に帯を背負って、蛇のまね。これなら誰でもできそうだ。(笑)
また、歌舞伎の一場面の物まねや、時の権力者の物まねなど、今でも芸として行われているものや、中川家がよくやる「日常でよく見る光景のものまね」「細かすぎて伝わらないものまね」などは「浮世ものまね」と称されて、独自のジャンルを形成していた。
歌川国芳作『延喜吉相百面双六』は、日常の何気ない風景を、あるあるネタとしてちりばめたテキスト。
右下のふりだしから始まり、サイコロを振って出た目に従って指定されたコマに進み、そこに書いてあるものまねを絶対にしなればならない。
ふりだしに「一、おしゃべり。二、お歯黒。……」などとある。たとえば一が出てると、ふりだしから横に二つ先にある「おしゃべり」のコマに移動。絵にあるとおり、おしゃべりなおばさんの物まねをしなくてはならない、
バラエティ番組などでよく見かける「罰ゲーム双六」の走りのようなものだ。
そういえば、中川家もこういうちょっとした日常のあるあるネタをものまねする場合が多い。
双六にある「おくびょう」(下から二段目、右から三番目)の顔が、まさしく「びっくりした」の顔と言える。
江戸時代からのものまね芸がこうも現代と呼応しているのだと思うと、あらためてこの世界の深淵さに驚かされる。
むろん、海外にも、ものまねは存在する。
一番有名なのは、チャップリンが『独裁者』で演じたヒンケル。
ヒトラー批判のために、徹底的にヒトラーの映像を研究して仕上げた完璧なものまね。でたらめなドイツ語、オーバーな所作。悪意たっぷり。
どうも海外では、ものまねは独立した演芸としては低いものとして扱われているようだ。俳優たちが余技として行うものとしてとらえられている傾向にある。
これは、俳優のケビン・スペイシーが『アクターズ・スタジオ』というトークショーで披露した様々な俳優のものまね。ジャック・レモン(1:40)→クリント・イーストウッド(3:03)→マーロン・ブランド(3:56)→クリストファー・ウォーケン(4:50)→アル・パチーノ(5:00)の順。
演劇や音楽においても、ものまねはその根幹をなすものだ。
ものまね芸の奥の深さを知ることで、エンターテイメントがさらに深く掘り下げられることは言うまでもない。
その奥の深さをここに紹介していきたい。
青島玄武推薦
まずはわたくしが推薦するものまねの至芸をいくつか。
桜井長一郎
わたくしが初めて見たときはものまねなんだけど、もう元ネタはわからない状態でした。
今思うと至芸ですね。歴代の総理大臣の映像を見ていると、この人のことがオーバーラップすることが多いです。(笑)
栗田寛一
言わずと知れた「ものまね四天王」のひとり。ものまねを一大エンターテインメントにまで押し上げた実力者。
四天王の中でも技巧派。ルパン三世の物まねは、山田康雄から「俺が死んだあとはお前に託す」と言われたほど。もう彼のことを、ルパンの声優として認知している人も多いのではないでしょうか? 本当はものまねだったんです。
清水ミチコ
武道館での公演を去年と今年に入ってからも行った、女性ものまね師のなのでもトップスターの一人。
この人の物まねを見る限り「ものまねって悪意がないとできないんだな」って思います。(^^;)
牧田知丈
この人、ものまね芸人ではありません。愛知県の製薬会社に務めるサラリーマン。芸能人でもないただの一般人。でも、雨垂れ石を穿つと言いますか、ものまね番組でひたすら中日の落合選手のものまねばかりやっていたらいつの間にか、有名人に。
落合家公認という、栄誉もいただいたようで、ものまねもたかがものまねとバカにできないですね。
山本耕史
日本でも、俳優が余技に行うものまねが存在します。
山本耕史さんは、大河ドラマ『新撰組!』の土方歳三や、時代劇『陽炎の辻~居眠り磐音~』シリーズで有名な俳優さん。
- 新選組 ! 完全版 第弐集 DVD-BOX/香取慎吾,佐藤浩市,江口洋介
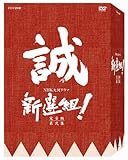
- ¥32,400
- Amazon.co.jp
- 陽炎の辻 ~居眠り磐音 江戸双紙~ DVD-BOX/山本耕史,笛木優子,原田夏希
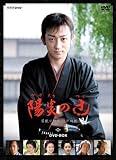
- ¥23,940
- Amazon.co.jp
ものまね芸人・ペレ草田さんとの、本物のものまね芸人と余技のものまねとの共演。どちらかというと余技のほうに目が行ってしまうのはわたくしだけでしょうか? (笑)
コブラ塾長推薦
ここでは、わが盟友「コブラ塾」塾長・コブラさん推薦の至芸を紹介いたしたいと思います。
松村邦洋
演芸に全く興味のない友人が、テレビから聞こえたこの松村のビートたけしのものまねに「本人じゃないんだ!」と、テレビ画面を見て驚いていたほど似ている至芸。
わたくしも当時は、「たけしってものまねされる人なんだ」と意識したのはやはりこのものまねが最初でしたね。
太平サブロー
ものまね芸であれば、たとえものまねされた本人が亡くなったとしても、また立体で再生されるというのがこの芸の強みであります。
この横山やすしのものまねはつとに有名ですが、わたくしとしては、なんかいつもよりも生き生きとしている西川きよし師匠のほうに目が行ってしまいます。(笑)
春一番・神奈月
プロレス好きのコブラさんならではのプロレスものまねの至芸をチョイス。
春一番さんは、去年の七月に47才という若さでお亡くなりになられた、アントニオ猪木一筋のものまね芸人。
神奈月さんは、様々なプロレスラーのものまねで有名。両人ともにこんな若いころから共演していたんですね。知りませんでした。(^^;)
ビタミンS
兄妹コンビ。兄のほうが小林旭などのものまねで有名。ものまねを使ったコント芸や漫才が売り。
ヒガシ逢ウサカ今井&ヒップ☆スター小西
わたくし、存じ上げませんでした。こんな人がいるんですねー。
もとは笑い飯のネタ。
目の付けどころだけで勝負できるのが、ものまね芸の強みだと思います。
あらためて奥の深さに感じ入ってしまいました。
如何だったでしょうか?
視点を転換させることで、同じものが全く違って見えるようになる。同じ長方形でも、縦にしてみるか、横にしてみるか、その違いに面白さを見出すのがものまねの面白いところだと思います。究極は「似ている・似ていない」に限らないということです。見方が面白いかどうか、ここに尽きると思います。
コロッケの五木ひろしがロボットだって、そういう視点の転換をした究極だと思います。
つまることろ、これはお笑いの根幹をなすものだと思います。
一つの物事にとらわれてしまうとき、ふと視点を変えるだけで笑えてしまう。お笑いは人生の教書でもあるような気がしました。
- 陽炎の辻 ~居眠り磐音 江戸双紙~ DVD-BOX/山本耕史,笛木優子,原田夏希


