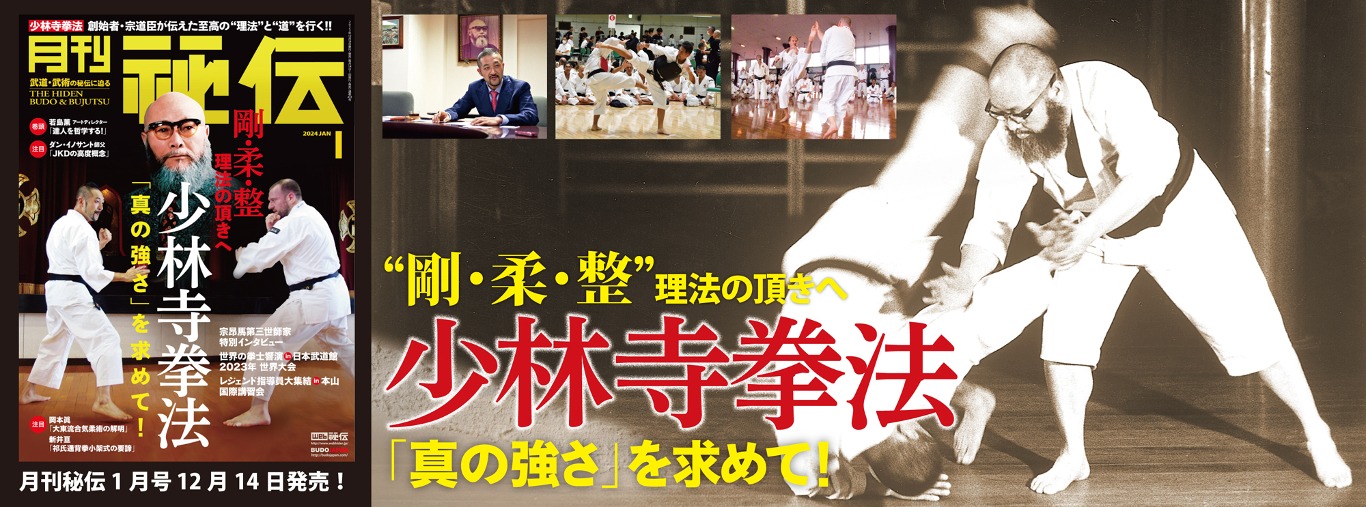年末は、日頃使っているもののお手入れをする時期でもある。
というわけで、今日は念珠のお話し。
念珠は一番身近な法具のひとつ。
一見同じように見える念珠でも、じつは宗旨により、また本山によって微妙に違う。
我々金剛禅にも、金剛禅式念珠がきちんとあって、儀式行事のときに用いています。
正規のものは108珠(煩悩と同じ数)で「本連」と呼ばれていますが、
使っているうちに紐がゆるんできたりするので、ときどき締め直す必要があります。
ワタシも、川崎稲田道院の綾邊先生に教わりながら、一度締め直したことがあるのですが、この紐もいわば消耗品で、経年劣化で切れることが珍しくないそうです。
念珠の紐が切れると、「縁起が悪い・良くないことが起こる予兆」と思うかもしれませんが、本来は、人間の煩悩の数と同じ数の珠を繋いだものなので、それを繋いでいる紐が切れるという事は、悪因縁が切れた現れとされているとのこと。
それはともかく、念珠の紐が切れると、珠が飛び散り大変なことになるし、それが儀式中であれば、儀式を中断せざるを得ない状況になるので、それだけは避けたいところ。
そこで今月、長年使った念珠の紐を交換しました。
細かくいうと、金剛禅式念珠は着用資格ごとに四種類あり、
これまで使っていた「僧階を有する大拳士以上」用の本連は、
珠が菩提樹、房が茶色、地珠がオニキス、天珠が隕石(テクタイト)、二連珠がオニキスという構成。
それが「僧階 少法師以上、または僧階を有する正範士以上」になると、
珠が菩提樹、「房が紫色」、地珠がオニキス、天珠が隕石、「二連珠が隕石・オニキス」となります。
拙僧も、11月に少法師、12月に正範士を允可されたので、このタイミングで念珠をオーバーホールがてら、アップデートしていただきました。
こちらがアップデートした念珠



房と二連珠(糸のついた部分が、オニキスから隕石に)が変更箇所。
アップデート前はこちら↓


ほとんど違いはわからないかも知れませんが、少なくとも房が新品になったことでしばらく切れる心配はありませんし、これで安心して新年が迎えられます。
せっかくですので、法具についてもうひとつ、袈裟について。
袈裟(けさ)とは仏教の僧侶が身につける布状の衣装のこと。梵語で「壊色・混濁色」を意味するカーシャーヤ (kāṣāya) を音訳したもの。
出家修行者が所有を許された3種類の衣と鉢=「三衣一鉢」のひとつ。
その略式の袈裟=輪袈裟は、金剛禅でも仏弟子の証として、儀式の際、威儀を正すために着用します。
禅宗では、輪袈裟の一種「絡子」(らくす)も身につけますが、
金剛禅では、僧階 少法師以上の者は、この絡子を着用することになっています。

(金剛禅の絡子)
ワタシも最近まで知らなかったのですが、
この絡子、首の後ろのサオの部分とマネキの部分を繋ぎとめる、しつけ糸の形に、宗派ごとの違いがあるとのこと。
例:曹洞宗では「折れ松葉」、臨済宗では「鱗」、黄檗宗では「六つ鱗」。
さて、我々金剛禅では???
本山に確認したところ、金剛禅では「人」の形を取り入れたとのこと。


(金剛禅のしつけ糸のモチーフは「人」)
※絡子のしつけ糸は、取らずに使用する※
またひとつ勉強になりました。
なお、「衣鉢を継ぐ」という言葉があるが、
禅宗では袈裟は嗣法(釈迦以来の仏法が師匠から弟子に正しく伝えられること)の重要な証とされてきた。
師匠は弟子の修行が十分に達成されたと判断した時、仏法の核心を伝授しその証として祖師伝来の袈裟と持鉢を与えてきた。
「衣鉢を継ぐ」は、これに由来した言葉。


これは、開祖が先師である北少林義和門拳第二十代師父、
文太宗老師から授けられた傳法允可之證(絡子)と念珠一連、如意棒一本。
法具はあくまで「形」であって、本質・中身ではありませんが、
開祖は「金剛禅の修行はまず形から入れ」と教えられ、形も重視されたそうです。
2024年は形も中身も充実させられるよう、修行に励む所存です。
本日の「身体の知能指数」 (PQ=physical quotient) 『101』