この映画はとても変わっている。「臨死体験」と「死後(あの世、彼岸)」を題材にしているのだが、どうみてもクリント・イーストウッドが「あの世」というものを信じているとは感じられないのである。「あの世」の描き方に熱意が感じられないのである。マット・デイモンの「霊」との交流などは、まあ、実際の交流がどういうものか私は知らないが、単に他人と一瞬手を触れあっただけで、その人のではなく、その人とゆかりのある人の霊と交流できるというのだから、あまりにも非現実的である。(憑依状態になったり、霊に呼び掛けたりというのが「現実的」というわけではないのだけれど。--でも、これまでの「常套的」な映画なら、そういうシーンを撮っただろう。)
では、なぜ、こんな映画を撮ったのか。
「臨死」や「あの世」がテーマではないのではないのか。ひとには誰でも「過去」がある。そして、過去が違うと、ひとは他人とうまく「いま」を生きることができない。一緒に生きることができない。それをどうやって乗り越えるか。そのことがテーマであり、「臨死」(あの世)は、いわば「特異な過去」なのだ。肉体が衝撃的なダメージを受ける。それは精神にも影響してくるだろう。「現実」の見え方が、当然違ってくる。それを、ひとはどうやって乗り切って(修正して)、他人と出会い、交流して行けるか、そのことを描いているのではないのだろうか。
だから、というわけでもないのかもしれないが、「臨死」が一様ではないのがとてもおもしろい。ここにイーストウッドの独創性というか、工夫がある。「臨死」のあり方が一様ではないということは、「いま」の見え方が一様ではないということでもある。
実際に映像として描かれているのはセシル・ド・フランスの津波での「臨死」だけである。彼女は、その後、現実に集中できなくなる。かといって、「霊」と交信できるわけでもない。ふと、「あの世」をかいま見た瞬間を思い出し、引きずられてしまう。マット・デイモンの場合は子供時代のこととして「ことば」で語られる。彼は「臨死」を体験することで、他の霊と交信することができるようになり、他のひとから、交信してくれるよう頼まれる。現実に生きている人間としてマット・デイモンが他人と交流するのではなく、生きているひとと死者の仲介者としての「現実」しか生きられなくなる。彼は、そういう生き方が嫌になっている。双子の兄弟の場合は、兄が「臨死」ではなく実際に死んでしまう。それがなぜ「臨死」かといえば、残された一卵性双生児の弟にしてみれば、「同じ肉体(遺伝子学的に同じ)」が消えるわけだから、遺伝子の立場からすれば「半分の死=半死=臨死」になるのだ。弟は、そして、やはり死んでしまった兄の精神(こころ)が気になってしようがないのである。
で、実際に、どうやって「現実」を「現実」として回復させるか。ふつうの「現実」を取り戻し、「いま」「ここ」を生きることができるか。
「ことば」が、ここでテーマとして浮かび上がってくる。
マット・デイモンの登場するシーンの描き方が、特にそのこと鮮明に語る。マット・デイモンは霊と交信するのだが、その交信はひたすら「聞く」ことである。マットは霊には質問しない。質問するのは霊と交信したがっている生きている人間に対してだけである。ただし、その質問は「イエス・ノー」だけをもとめるものであって、マットは生きているひととは実際に対話せず、ただ霊の「ことば」を伝達するのである。ふつうのひとが聞くことのできない声を聞き、それを誰かにつたえる。そういうことをするために「ことば」がある。映画なのだから、本来ならば霊は映像となってスクリーンに登場してもかまわないのだが、イーストウッドはそういう演出をとらず、ただ「ことば」として霊を登場させる。「ことば」だけが霊の存在を語っている。
セシル・ド・フランスの場合も「ことば」が問題となる。彼女は最初はニュースキャスターである。「現実」をことばと映像でつたえる職業である。「臨死」体験後は、彼女だけが知っている世界を「ことば」で明確にする。映像は採用しない。彼女自身見たものがあるのだが、それは彼女の記憶として彼女にだけ見える形で存在する。他人が(映画の観客以外が)見えるように絵にしてみるというようなことはしない。あくまで「ことば」で語る。書くことで、「ことば」を確立しようとする。
双子の弟の場合はもっと極端である。彼が出会うのは地下鉄の帽子以外では、いつでも「ことば」である。「ことば」だけである。そして、彼は「ことば」を聞くことで、その「ことば」が語ることがほんとうかどうかを正確に判断する。マット・デイモン以外の霊媒者の「ことば」に嘘を感じ、信じない。死んでしまった兄と出会うのもマットの語る「ことば」として出会うだけである。
あ、これでは映画ではなく、「小説」だ。「ことば」と向き合う世界だ。
ところが……。こうやって感想を書いていると「小説」向きとしか思えないテーマであり、またストーリーの展開なのだが、映画を見ているときはたしかに映画だと思ってみている。不思議な違和感を感じながらも、映画だなあ、と思ってみている。
なぜだろう。映画の作り方がイーストウッドは天才的にうまいのだ。「ことば」をテーマにかかげながら、ことばを映像にもぐりこませてしまうのだ。たとえばマット・デイモンは不眠症(?)のため、夜中にラジオを聞いている。なんだかよくわからない物語がそこでは語られている。「ことば」が現実にただ散らばっているという状態を、ふつうに映画にしてしまう。そのラジオの朗読のことばのあり方のようにして、霊との交信のことばをスクリーンに繰り広げるのだ。マット・デイモンがラジオを聞いているシーンがなかったら、マットの語る「霊のことば」は「捏造」になってしまうが、ラジオの存在が「霊のことば」を遠くからやってくることばに変えてしまうのだ。あ、うまい、うまいなあ。
セシル・ド・フランスが巻き込まれる津波のシーンもうまい。なにがうまいといって、出してくるタイミングがうまい。映画がはじまってすぐに、いわばクライマックスがある。スペクタクルがある。観客の目はまだ映像に慣れていない。慣れる前に「嘘」を見せてしまうのだ。華々しいシーンは最初でつかいきって、封印し、あとは地味に「ことば」に関心が向かうように派手な映像をつかいきってしまうのだ。
ごくふつうの処理といえばふつうの処理なのだが、双子の弟が多くの霊媒者のことばに嘘を感じ、がっかりするというのも、少年の肉体の動き、顔の表情で引き受け、ことばを否定してしまうのも、あ、きちんとできているなあと感心してしまう。
たぶんイーストウッドが霊とか死後というものを信じていないせいだと思うのだが、霊や死後の世界の描き方はそっけなく、おもしろみに欠けるのだが、映画のなかにおける映像とことばの処理の仕方というか、映画技術としては、すごいなあ、とうなってしまう映画である。映画を楽しむ、とういより、映画の作り方を学ぶ、イーストウッドの映画技術を吸収するという意味では非常にいい作品である。
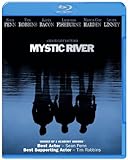 | ミスティック・リバー [Blu-ray] |
| クリエーター情報なし | |
| ワーナー・ホーム・ビデオ |