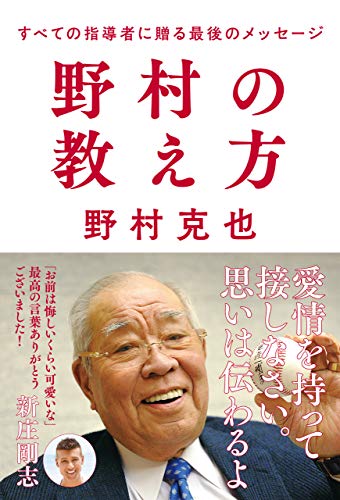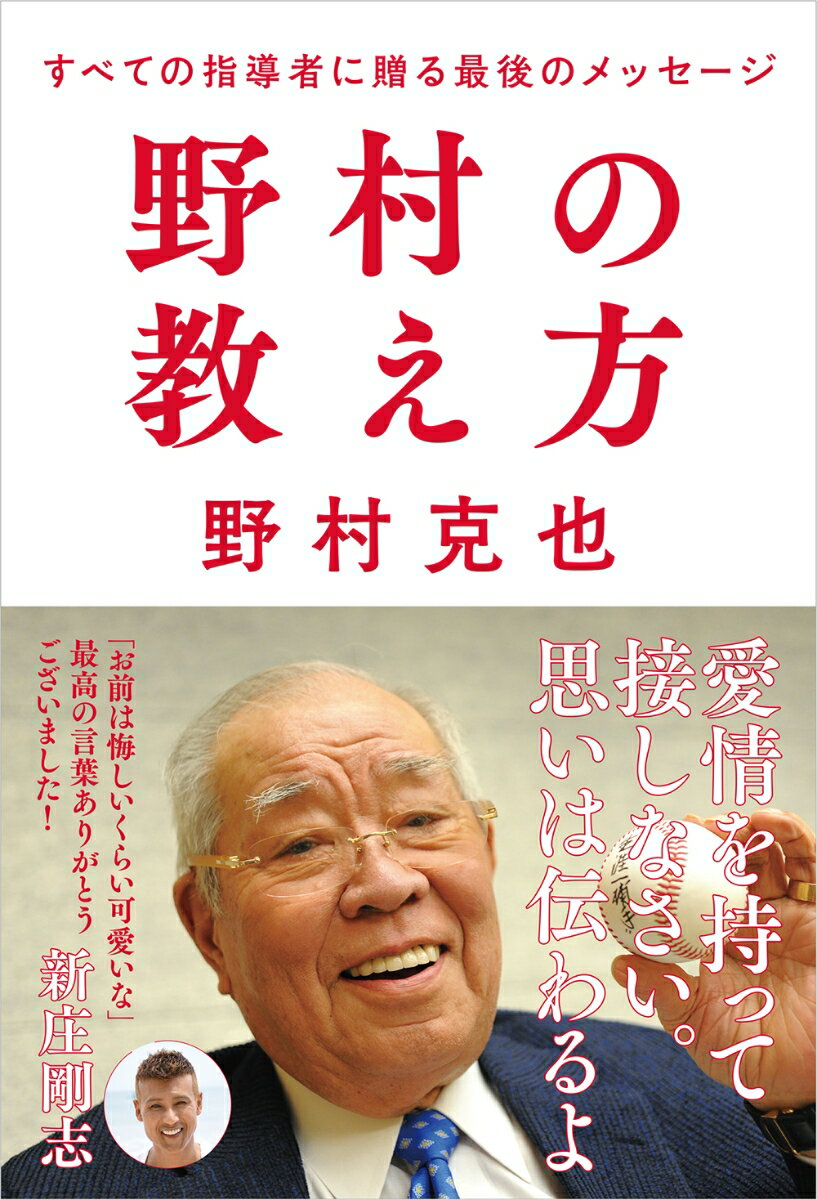高度2000mを超える山岳地帯。
森林限界を超えたその世界は、
凍てつくようなマイナスの気温、
容赦なく吹きすさぶ強風、
じりじりと照りつける太陽と紫外線、
貧弱な養分の土壌、
全てを氷の世界で覆う白い悪魔の降雪
に支配された過酷な世界。
「逆境」という言葉だけでは表現しきれない、
およそ生物の生育環境とは思えないような
世界においてさえ、
根をはり、茎を伸ばし、花を咲かせ、
そして種を残していく高山植物たち。
荒涼とした山岳地帯で、
苛烈な環境に身を痛めつけられながらも
じっと耐え、
試練の過ぎ去る時をじっと待ち、
その苦しみを乗り越えた末に
誇り高く花を咲かせるその姿は、
優しさ、美しさ、
そして気品に満ちあふれて見えますよね。
そんな高山植物の中で、
ヨーロッパでもっとも有名なもの。
それが
ドイツ語の
edel(高貴な、気高い)と
weiß(白)にその名が由来する
エーデルワイス
といっていいかもしれません。
スイスの国花であり、
花言葉にもなっている
「純潔」
の象徴としてもさまざまな事物に
その名が引用され、
多くの人たちに愛されている
エーデルワイスですが、
19世紀ヨーロッパのアルプス地方では
『アルプスの植物ローレライ』
(ローレライはその声で漁師を誘惑し
破滅へと導く水の精霊です)
と不吉な名でも呼ばれたそうです。
・・・それはさておき、
他の植物が生育しえない環境の下でも
生きのびるために、
地上部を綿毛で緻密に覆い
寒気から遮断し、
強い日差しや紫外線から身を守る
仕組みを持つなど
「与えられた環境に負けない。
その中で生きていく!!」
という
命の力強さもまた感じさせる
エーデルワイスをはじめとした
高山植物たちの姿は、
決して恵まれているとは言えない
戦力のチームを渡り歩き、
負けても負けても、
「この戦力を最大限に活かして戦い抜く!!」
と決めて24年間にわたりプロ野球の
南海ホークス(現在のソフトバンクホークス)、
ヤクルトスワローズ、
阪神タイガーズ、
楽天ゴールデンイーグルス
の監督を歴任して戦い続けた
野村克也さんの姿に
重ねられるかもしれません。
(このブログでは以降、あえて「野村監督」と呼ばせて頂きます。
【現役時代の野村監督】
/////////////
カレンダーをめくり続ける。
寒い日も、暑い日も、
平日も、休日も、祭日も、
来る日も来る日も、
負け続け・・・
だったのではないかと思えるような、
日本プロ野球の歴代記録の中でも
ダントツの、監督しての敗戦数
その数、
1563敗!!
現在のプロ野球のリーグ戦の
年間試合数143試合
(2020年度は特別ルールにより120試合です)
のおよそ11年分にあたる敗戦数は、
歴代2位の三原脩監督の1453敗を
100敗以上も上回るダントツのワースト記録。
ただし1563敗もできたのは、
24年間で3204試合の監督を務めて
長く戦い続けたからこそであり、
そしてその負け数の多さは、
監督として1563回も負けることを
許されたという偉大さの裏返し
ともいえますよね。
野村監督が監督を引き受けたチームの
前年の成績は、
南海 4位
ヤクルト 4位
阪神 6位
楽天 6位
野村監督が呼ばれたチームは
順風満帆の強豪チームであったことは
一度もなく、
ゼロどころか、下手したら
マイナスから立て直す必要のある
状態だったチームばかり。
それでも、
与えられた環境の中で
負けることを恐れず、
「勝つためにどうしたらいいのか」
を考え続け、
そして
勝った
(監督としての通算勝利数、
歴代5位の1565勝、リーグ優勝5回、日本一3回)
プロ野球界最高の
「偉大な敗者」
野村監督はどのようなことを
考えて戦い続けたのか。
彼の遺志は私たちに何を伝えてくれるのか、
彼の残した言葉から考えてみたいと思います。
【南海監督時代 (選手兼任監督)】
///////////
【敗北を恐れるな】
「成功や勝ちからよりも、失敗や負けから得るもののほうがはるかに多い」
(野村克也/「負けかたの極意」より)
「一流とは、より多くの疑問を抱き、失敗からたくさんのことを学び取る能力に優れた人間」
(「野村の極意 人生を豊かにする259の言葉」より)
誰もが勝利に向かって
死に物狂いで努力を重ね
戦い続けるプロ野球の世界。
そしてそこに勝者がいれば
その数だけ敗者がいる世界。
勝者と敗者を分けるもの。
それは運や才能だけでなく、
負けた時、
その敗北に下を向くことなく、
自信をなくし明日の敗北をも恐れることなく、
「自分のやり方はおかしいのではないか」
と疑問を抱き、
明日の勝利をつかむために、
何か新しいやり方を見つけようとする
姿勢の有無。
その姿勢は、
勝つことだけでは手に入らない、
新しい力を自分に与えてくれるもの。
そして
それこそが「敗者の特権」。
だから敗北を恐れるな!
その特権をムダにするな!!
「『もうダメだ』とあきらめてしまえば、
それ以上の成長はない。
『どうすればこの状態を突破できるか』
と考えることができれば、
必ず道は拓ける」
(「ノムラの教え 弱者の戦略99の名言」より)
敗北は決して「終わり」ではない。
敗北を「終わり」にしてしまうのは、
自分自身の弱い心。
敗北した今、必要なもの。
それは、
現実を見つめ、
次に勝つ方法を考えながら、
もう一度立ち上がる勇気。
「勇気に支えられた使命感を忘れないでくれ。
ここ一番というとき、
覚悟を決めるのは勇気だ。
三振してくるのも勇気だ」
(「野村の流儀 人生の教えとなる257の言葉」より)
敗北を恐れるな!
勇気を持て!
覚悟を決めろ!
立ち向かえ!!
【リーグ優勝4回、日本一3回を飾ったヤクルト監督時代】
//////////////
【考えろ】
「勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし」
(「野村の流儀 人生の教えとなる257の言葉」より)
敗北を敗北で終わらせない。
今日は負けても明日は勝つ!!
そのためには考えること。
たまたま勝つことはあっても、
不運なだけの負けはない。
負けるには負けるだけの理由がある。
うなだれている暇があったら
明日は負けないように、しっかり考えろ!
「私は精神野球を嫌悪する。
精神野球とは、気力・体力・知力のうち、前のふたつ、特に気力を重視する野球のことである」
(「野生の教育論──闘争心と教養をどう磨くか」より)
「テーマのない努力ほどムダなものはない」
(「凡人を達人に変える77の心得」より)
「自分は正しい努力をしているのか、毎日自分に問いかけよ」
(「ノムラの教え 弱者の戦略99の名言」より)
「気合だ!」
も結構だが、気力や体力など
プロとして持っていて当然。
何も考えずに行動するのは楽なことだし、
表面的な満足感も得られる。
実際、
努力せずに勝利を得ることはできないが、
そのエネルギーは使い方を考えること。
自分のやり方に欠陥があるのに、
気合でそのやり方を繰り返し続けることに
何の意味があるのか?
ムダな努力に時間を使うくらいなら、
自分が頭に描く勝利を実現するためには
何をしたらいいのか?
自分には何が足りないのか?
いつも考えていること。
「一日3ゲームを
自分に課していた。
1ゲーム目は、
試合前に頭の中で完全試合をイメージする「予測野球」。
2ゲーム目は、
実際の試合の「実戦野球」。
そして3ゲーム目は、
試合全体をもう一度振り返り、
予測野球(理想)と実戦野球(現実)の差を検証して次に活かすための「反省野球」である。」
(「そなえ 〜35歳までに学んでおくべきこと〜」より)
時間も体力も才能も全ては有限なもの。
だけど考える力は無限。
自分の中の無限の力を使わずして、
人のしないことをやらずして、
人に勝とうなどと思わないこと。
たとえ、
それが明日の勝利につながらなくても、
考えた先につかんだものの積み重ねは、
必ず未来の勝利につながるもの。
だから、
いつでも勝利のために
「自分のすべきこと」
「あるべき姿」
を考え続けること。
【結果を出せなかった阪神監督時代。
だけど彼の築いた礎が、後に阪神を立ち直らせました】
/////////////
【そして、勝て】
「戦いには、
気機(指揮官と兵士の闘志)、
地機(天地の利)、
事機(組織としてのまとまり)、
力機(戦力)の四つがある。
その中で最も重視されるのは、気機である」
(「野村の流儀 人生の教えとなる257の言葉」より)
考えることは大切だが、
戦うために最後に必要なものは、
戦う意思、気力、そして闘志。
知力に加え、
これらがあるから
人は勝利に向かってまっすぐ
かけ出すことができるのだ。
そして戦うことができるのだ。
「『敵に勝つより、もっと大事なことを忘れてはいけない』
と言い続けてきた。それは
『常に自分をレベルアップすることを忘れるな』
ということ」
(「野村の流儀 人生の教えとなる257の言葉」より)
目先の勝利に満足するな。
慢心するな。
本当の敵は自分自身の中にある。
勝つためでなく、
勝ち続けるために、
常に自分を磨き続けろ。
「人間は何のために生きているのか。幸せになるためだ」
(「野村克也 100の言葉」より)
そして
幸せは誰かがくれるものではない。
自分の力でつかみ取るものだ。
高みを目指せ!
勝利をつかめ!
そして幸せになれ!!
【2009年10月24日
監督最終戦の試合終了後、
敵味方 両軍の選手に胴上げされる野村監督】
/////////////
【こちらの記事も是非どうぞ】
【その他の名言記事へのアクセスは】
ここからアクセス!/過去の名言集記事 (# 251~# 260)
////////////
ヨーロッパでは古くから薬草として
多量に使用されていたエーデルワイスは、
19世紀のロマン主義の台頭によって
神秘的なものへのあこがれとして
愛や操、堅信など
「不死・不滅のシンボル」
として祝典や恋愛などに
用いられるようになり、
次々と採取されたそうです。
その結果、
山岳の険しい場所でしか見られなくなり、
採集者が転落死するケースが続発し、
『アルプスの植物ローレライ』
と呼ばれてしまったそうです。
その声で漁師を誘惑したローレライと、
その毒舌でも有名な野村監督。
ここでもイメージが重なるのかもしれませんね。
【さよなら、そしてありがとう、野村監督】
(今回のブログは2020年3月10日に公開した内容を加筆修正したものです)