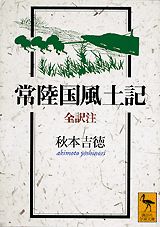①国府跡碑
①国府跡碑 ②總社宮社殿
②總社宮社殿 ③境内社群
③境内社群 ④日本武尊腰掛石
④日本武尊腰掛石 ⑤神門
⑤神門 ⑥鳥居
⑥鳥居
訪問日:2023年4月
所在地:茨城県石岡市
平貞盛は延喜年間(901-923)に平国香(良望)の子として生まれた。母は正室の常陸大掾・源護の娘あるいは藤原村雄の娘。祖父は桓武平氏の祖・平高望(高望王・桓武天皇の孫もしくは曾孫)。
下総の平将門は従兄弟にあたる(国香の弟・良将の子)。父は岳父・源護の跡を継いで常陸大掾となったが、承平5年(935)将門と源護らの抗争に巻き込まれて石田館(筑西市)を焼かれ死亡する。
この戦いで護の子の扶・隆・繁も討死した。この時、京都で左馬允の地位にあった貞盛は急遽常陸に帰国し、将門と融和しようとした。まもなく父の後継の常陸大掾に任ぜられる。
だがともに叔父の良正(護の婿)が将門に敗れ、高望の上総介を継いだ将門の岳父・良兼(この人の後室も護の娘)も不介入の方針を変えて甥の貞盛を説得して将門と対立した。
しかし戦局は常に将門が優位で、承平8年(938)貞盛は将門に追撃されながらも身一つで上洛し、将門の横暴を訴え、将門の召喚状を得て帰国するが、将門はこれに応じなかった。
天慶2年(939)6月には良兼が病没、11月には常陸国衙から追捕令が出ていた藤原玄明をめぐり、常陸国府が将門に宣戦布告(貞盛の画策か)したものの、逆に攻められて国衙は陥落、貞盛は身を隠した。
ただこれにより、これまでの平家一族の私闘から将門の朝廷に対する反乱と見なされ、さらに12月将門は下野・上野の国府を占領し、独自に関東諸国の国司を任命し、「新皇」を自称する。
これに対し貞盛は藤原村雄の子で下野国押領使の藤原秀郷(母方の叔父か)と合力して兵を集め形勢は逆転、ついに天慶3年(940)2月、将門を追い詰めて討ち取った。
貞盛は功により常陸に多くの所領を得た上、良将(鎮守府将軍であった)・将門父子の奥州の勢力基盤をも引き継ぎ、自らも鎮守府将軍、丹波守、陸奥守を歴任し、従四位下に叙せられて「平将軍」と称した。
貞盛は弟・繁盛の子・維幹を養子とし、常陸の所領を相続させた。(多気)維幹は常陸大掾職に任ぜられ、その子孫が代々大掾職を世襲したことから「大掾氏」と呼ばれるようになったとされている。
実際は建久4年(1193)に失脚した維幹の来孫・義幹までは大掾職であった記録はなく、義幹に代わり源頼朝から所領を与えられた同族の吉田資幹が常陸大掾に任ぜられ、大掾氏の祖となったと考えられている。
一方、貞盛の実子で4男の維衡は藤原道長のもとで源頼信らとともに道長四天王と呼ばれ、伊勢国に地盤を築き、伊勢平氏の祖となって平清盛らを輩出した。
また、次男・維将の孫・平直方の裔には北条氏(鎌倉幕府執権)や熊谷氏(直実など)がおり、直方の娘は源頼義(頼信の子)の正室となり、源義家らを産んでいる。
以下、現地案内板より
国指定史跡 常陸国府跡
所在地 石岡市総社1丁目2番
常陸国衙の成立は、8世紀初頭前後である。国府の下に郡衙が置かれ、多珂・久慈・那賀・新治・白壁・筑波・河内・信太・茨城・行方・鹿島の11郡を統括していた。国衙には、国内の政務に携わる行政官の勤務する役所や倉庫群などさまざまな建物があった。昭和48年、石岡小学校の校舎改築に伴い発掘調査が実施され、多くの大型の柱穴が発見された。その後、平成10年から平成11年にかけてのプール建設に伴う発掘調査では、掘立柱建物跡、溝跡などが発見された。この調査は引き続き平成13年度から6次にわたり行いその結果、この石岡小学校の校庭に国庁が存在していたことが判明した。
国庁は南向きに建てられており、東西に平行して脇殿がある。正殿の南に前殿を配し、四方を築地塀で囲んでいる。また一時期、東西には楼閣が建てられた時代もあったものと思われる。全国の例と同様に、それらの建物配置は左右対称である。さらに時代が下ると掘立建物から礎石建物に変わっていく。
◇大掾氏との関わり
大掾氏は代々「常陸大掾」という役職を世襲し、それがやがて家名となったものであるが、大掾という役職は在庁官人のトップであり、時代の変遷はあるものの実質的に国衙機能を掌握していた。
◇エピソード〜大掾氏と府中城
府中城は、戦乱の続く南北朝時代初期の正平年間(1346〜1369)に第15代平詮国によって築城されたといわれている。規模は東西約5町(約500m)南北約4町(約400m)という広大なものであった。成り立ちについては、石岡城(外城・市内田島地区)から本拠を府中城に移したという説があるが、府中城と石岡城は、二城一体の城塞として「内城」と「外城」という関係で機能していたのではないかと考えられている。
平成21年2月 石岡市教育委員会
常陸國總社宮
所在地 石岡市総社2丁目8番
常陸國總社宮は大宝令に制定された神祇官に相当するもので、神祇の祭祀を掌り国内の諸社を挿管した神社である。古くは国衙の近くに設けられ、国府の宮と称されていたが、延喜年間(901~922)に天神地祇の六柱の神が祀られ、六所の宮と呼ばれるに至り、さらにその後、総社の名が使用され今日に至った。
社伝んによると、始め国家鎮護の社として全国のうち、常陸・武蔵・甲斐・駿河・長門・対馬の国府が選ばれ、常陸国府に第一創建あるべしの勅令により建てられたとある。
◇大掾氏との関わり
総社は、国内の諸社を総括したもので、国府との関係から大掾氏とも深い縁がある。
◇エピソード〜常陸總社文書と大掾氏
總社宮には、常陸總社文書という貴重な文書が残っており、県指定文化財となっている。この文書は治承3年(1179)から、天保年間に至る中世及び近世の文書であり、源頼朝挙兵の前年(治承3年)の文書、永仁5年の徳政令に関する文書など、資料価値の高い文化財で50通が指定されている。
その中には大掾氏に関する記述も見られ「總社敷地田畠坪付注文断簡」には、第12代時幹の名が見られ、總社敷地に対する知行権を有している様子などがわかる。
市指定有形文化財(建造物) 常陸國總社宮本殿
平成17年4月14日指定
總社宮本殿の特徴のひとつに、内陣と外陣間仕切りの桟唐戸の仕様がある。観音開きの桟唐戸で、普段見る機会のない扉である。現状は、赤漆塗り仕上げで、その上に3~4寸角の連続模様の痕跡がある。これは金箔が剥げた痕跡で、金箔が貼られた造りは、県内のほかの神社に類例を見ることはできないといわれている。また、この扉の裏面には、天和3年(1683)寄進の年号と寄進者9名の名前が刻まれており、本殿の建築時期を特定する貴重な資料である。
平成21年2月 石岡市教育委員会
常陸國總社宮 由緒
~国府と総社の物語~
約1300年前の7世紀、現在の茨城県は常陸国と呼ばれていました。
広大で海山の幸に恵まれたこの国は全60余国のうち最上の「大国」とされ常世の国とも称される憧れの聖地でした。
常陸国の中心地である国府があった場所が旧茨城郡、現在の石岡市です。
茨城の県名はここに由来します。国府の長官である国司が執務した国衙跡の遺跡は近年の大規模な発掘に伴い国指定史跡に登録されました。
国衙の南側にかつて倭武天皇(ヤマトタケルノミコト)が腰掛けたと伝わる「神石」があります。日本百名山の一つ「筑波山」、日本第二の湖「霞ヶ浦」の悠々たる美景を同時に望めるこの場所に創建された「総社」が常陸國總社宮です。
総社とは、それぞれの律令国に鎮まる八百万の神々を国衙近くの一ヶ所に合祀した神社であり、全国で55社が確認されています。国司たちは総社を拝することで自らが治める国の数多の神々に祈りを捧げたのです。
徳川光圀が『大日本史』編纂のために参照したと伝わる社宝「総社文書」は連綿と続く当宮の歴史を今に伝えています。
長大な歴史の波に翻弄され祭祀を中断せざるを得なかった総社もある中で、当宮は創建以来絶えることなく「国府の神祭り」を続けて参りました。その現在の形が最大の祭典である9月の例大祭です。地域を挙げて祝われるため「石岡のおまつり」とも呼ばれ、全国から数十万人もの参拝者が訪れます。
境内最古の建造物である本殿は平成28年に大規模修復を完遂し、人々の崇敬を集めています。
~常陸国の神々~
常陸國總社宮は常陸国の神々をお祀りしています。
国学者・本居宣長が主著『古事記伝』に述べるように「神」とは海川山野に宿る霊など、人間には理解しがたい力を持つあらゆる存在を指します。常陸国の神々とは『常陸国風土記』に記された常陸国の豊かなる自然そのものと言えるかもしれません。
常陸国府では当国一宮・鹿島神宮に対し現在まで続く「青屋祭」を営み、格別の崇敬を示してきたことが伺えます。
また二宮・静神社、三宮・吉田神社を始め、当国の延喜式内二十八社との関係が示唆されます。
江戸時代に祭神の再考証が行われ、現在では特に以下の6柱の神々を称え、境内の12末社には特に著名な神々を個別にお祀りしています。
伊邪那岐命・須佐之男命・邇邇藝命・大国主命・大宮比賣命・布瑠大神