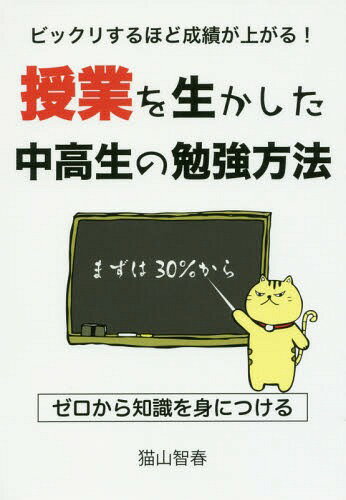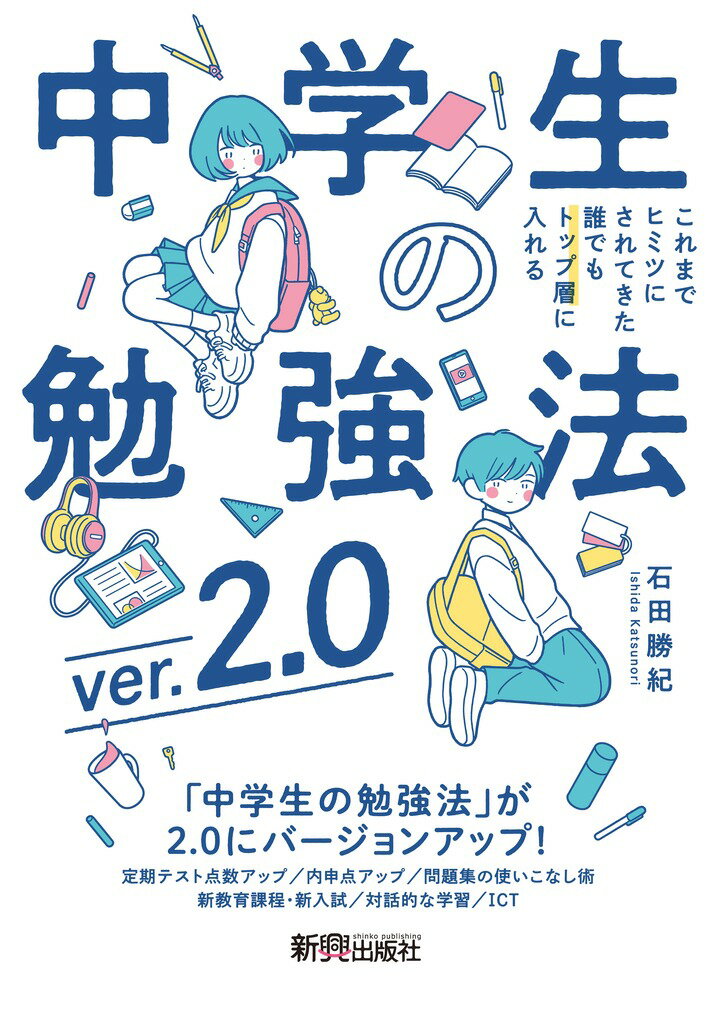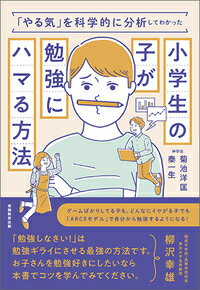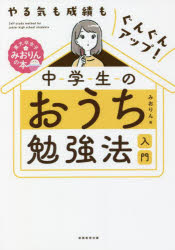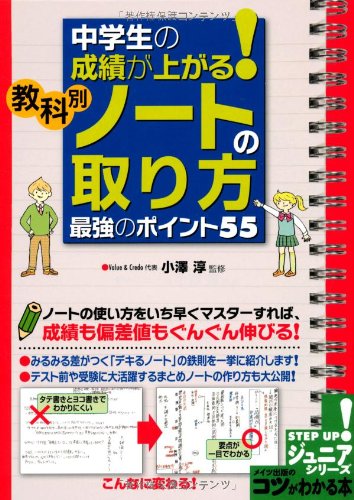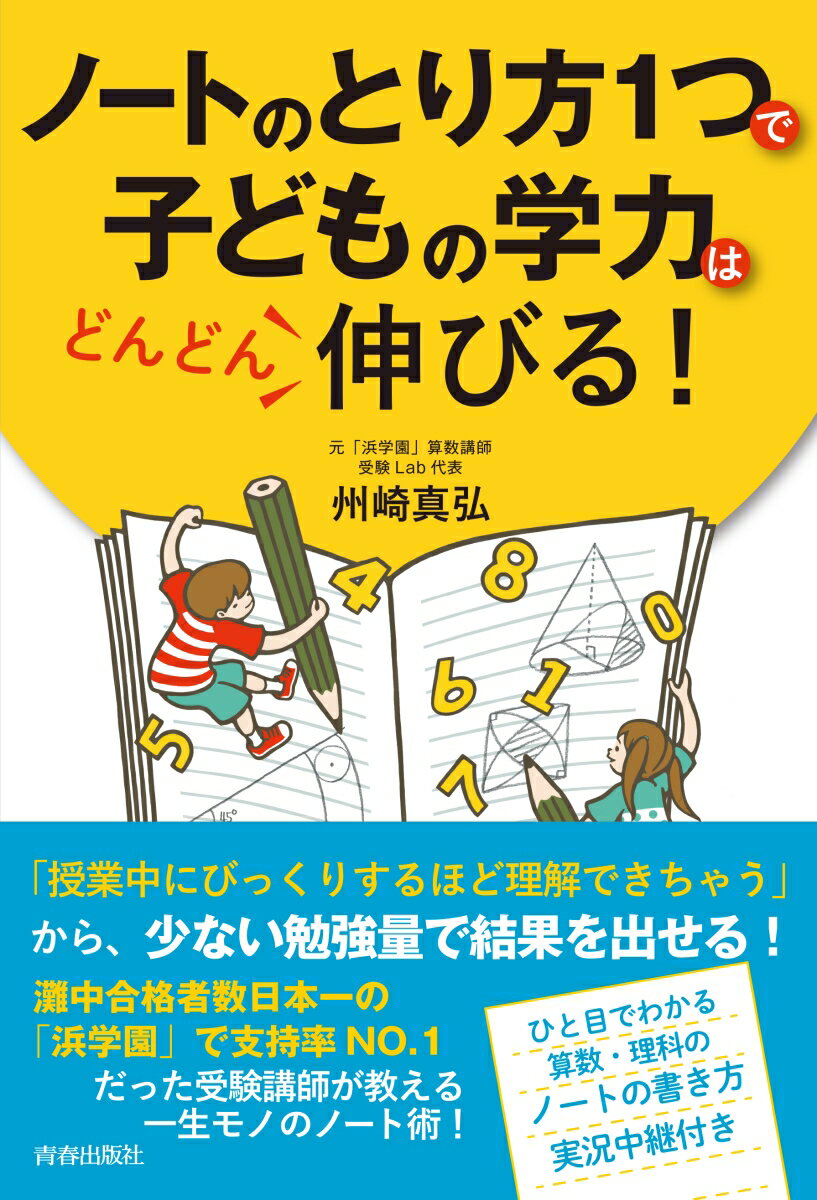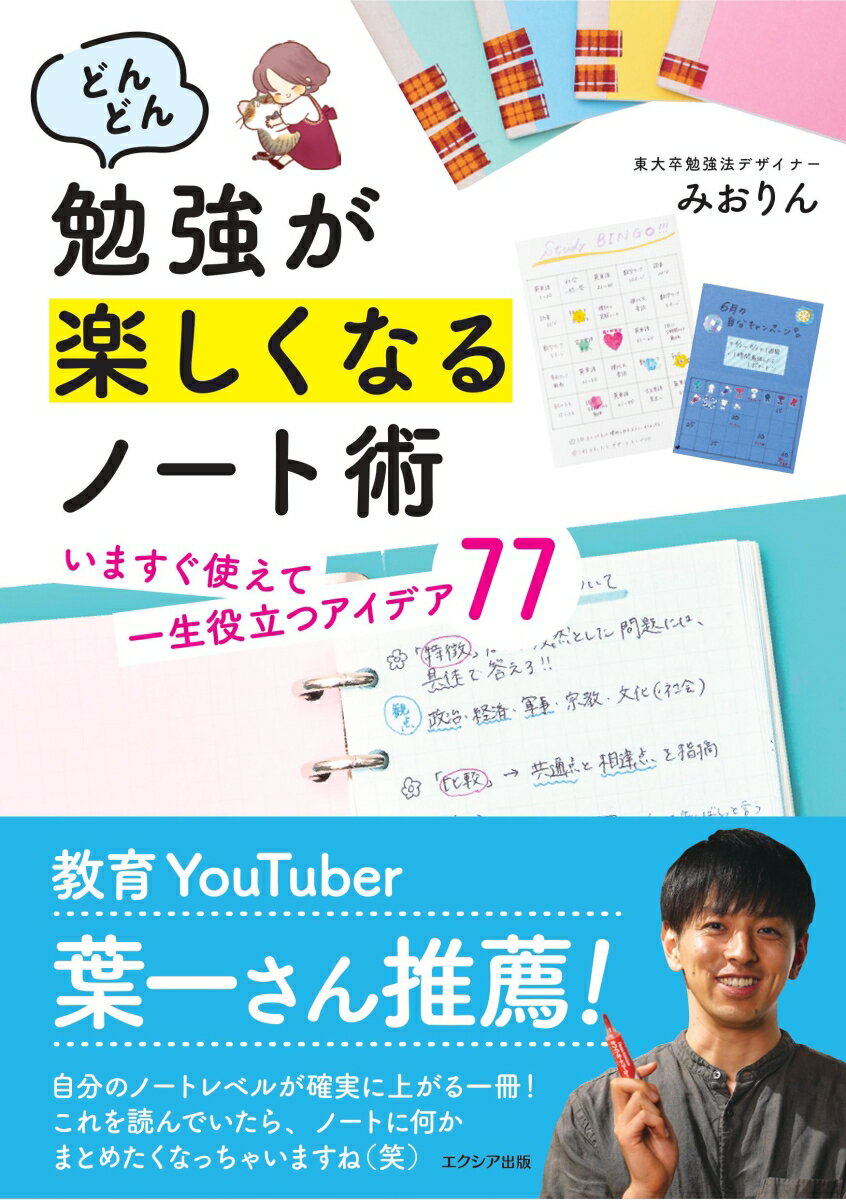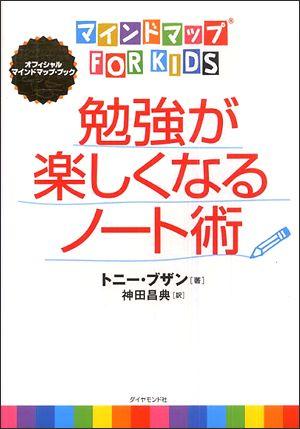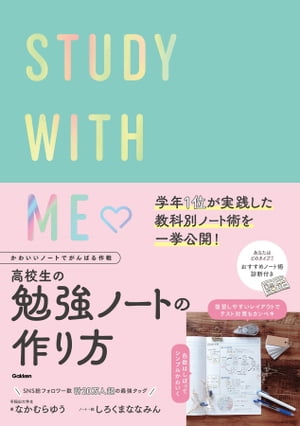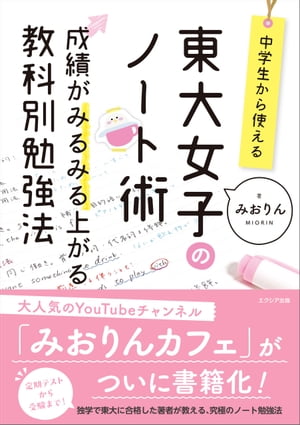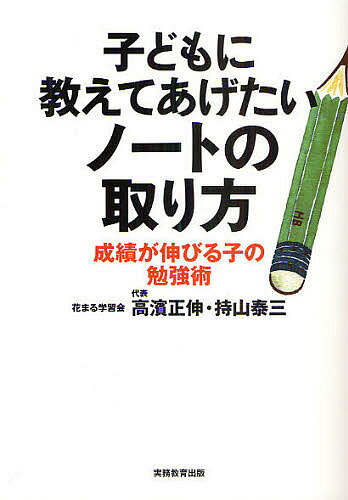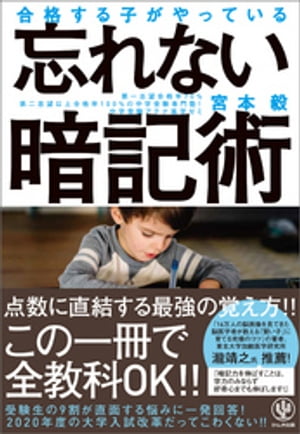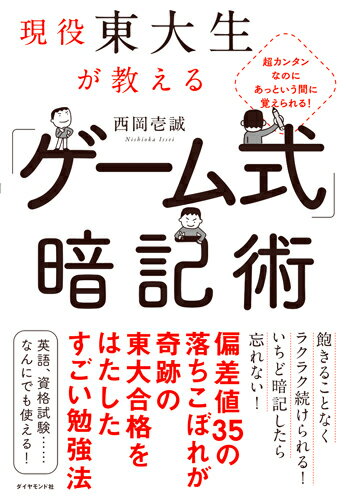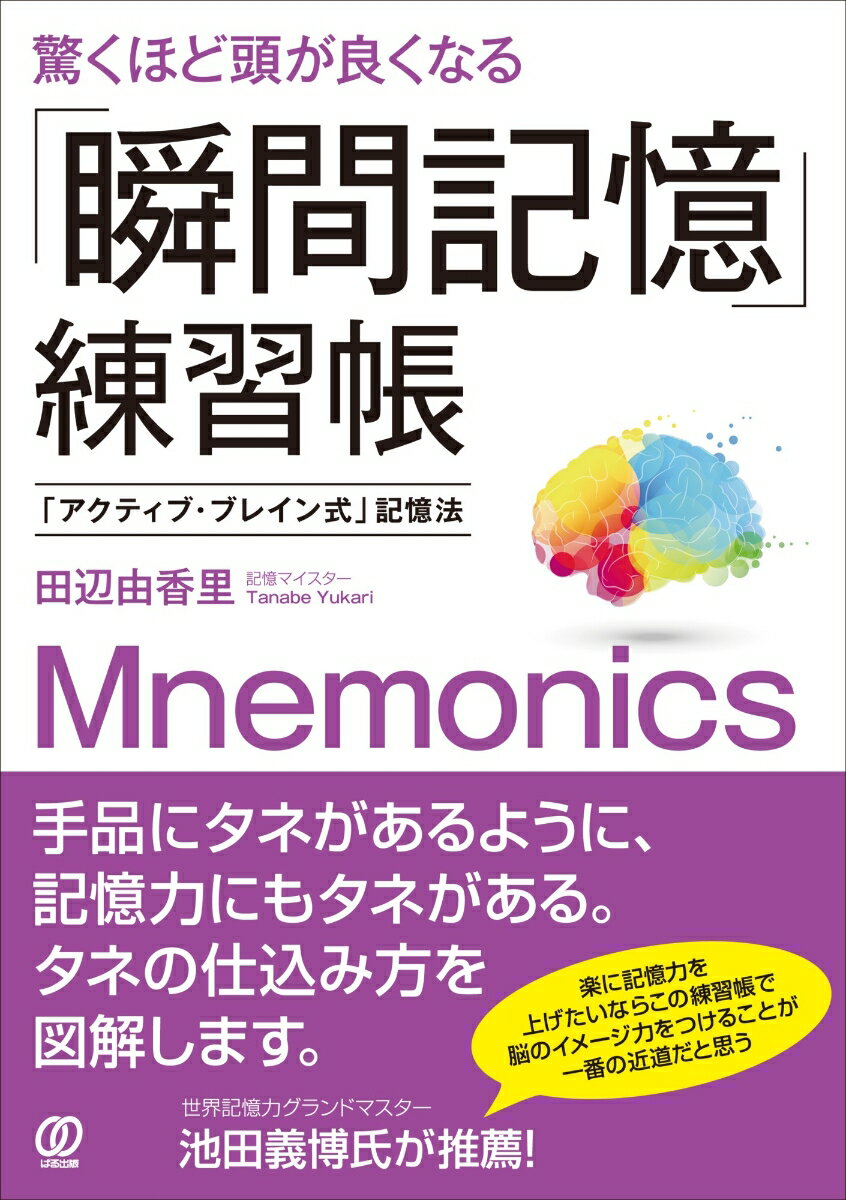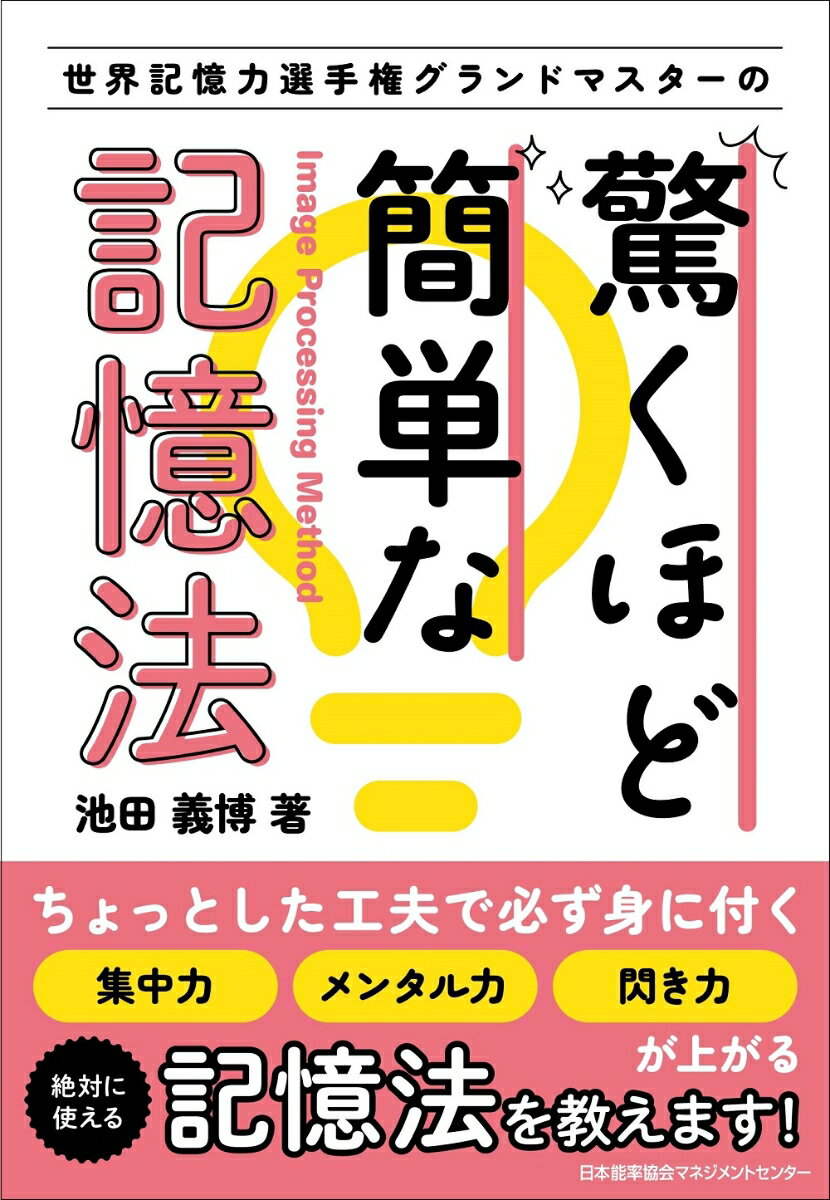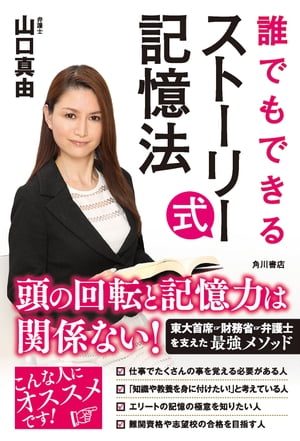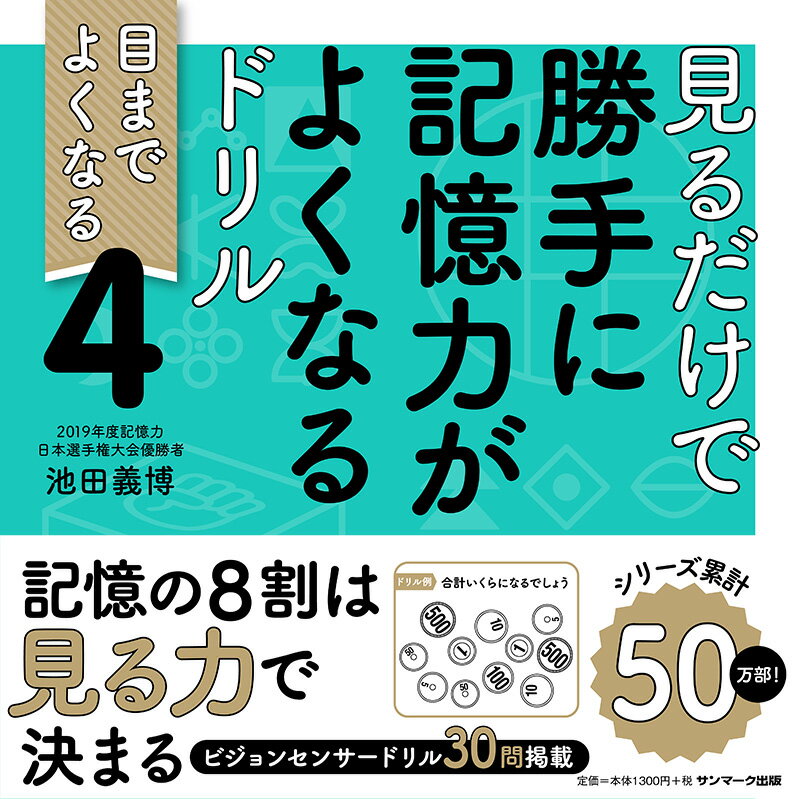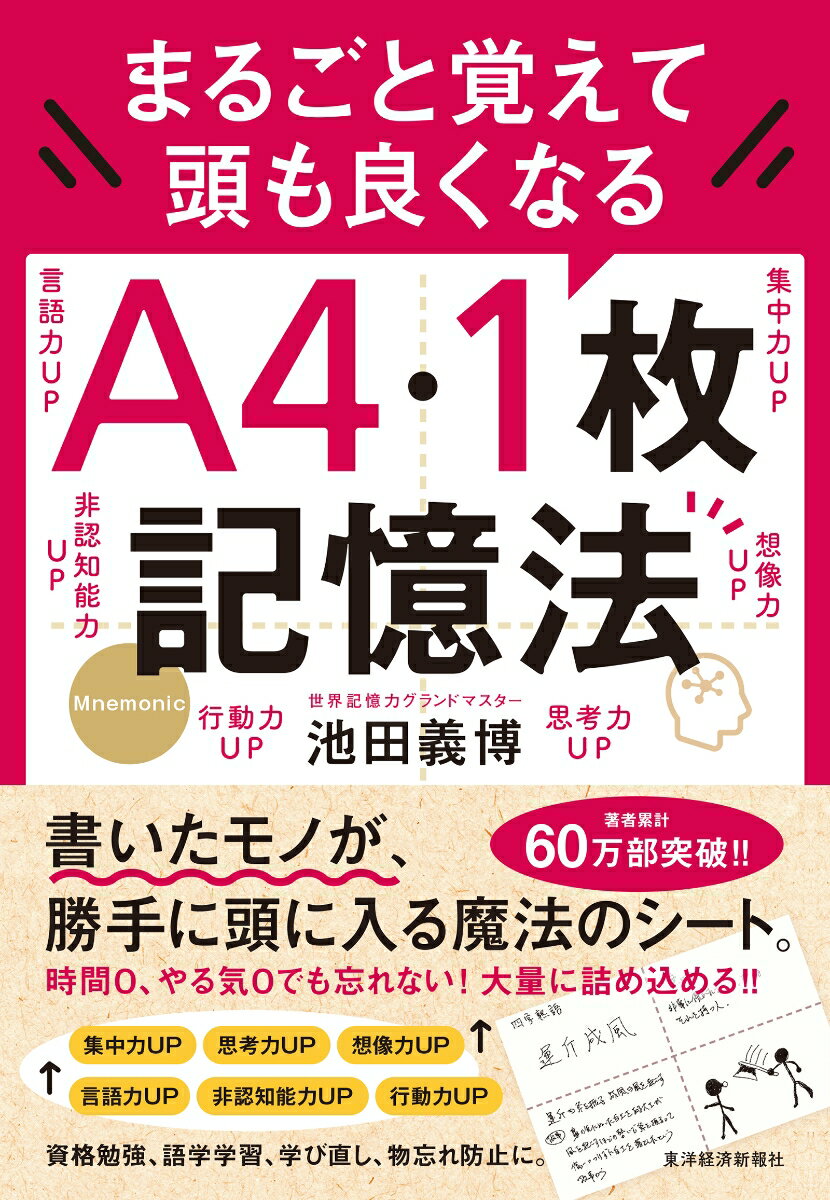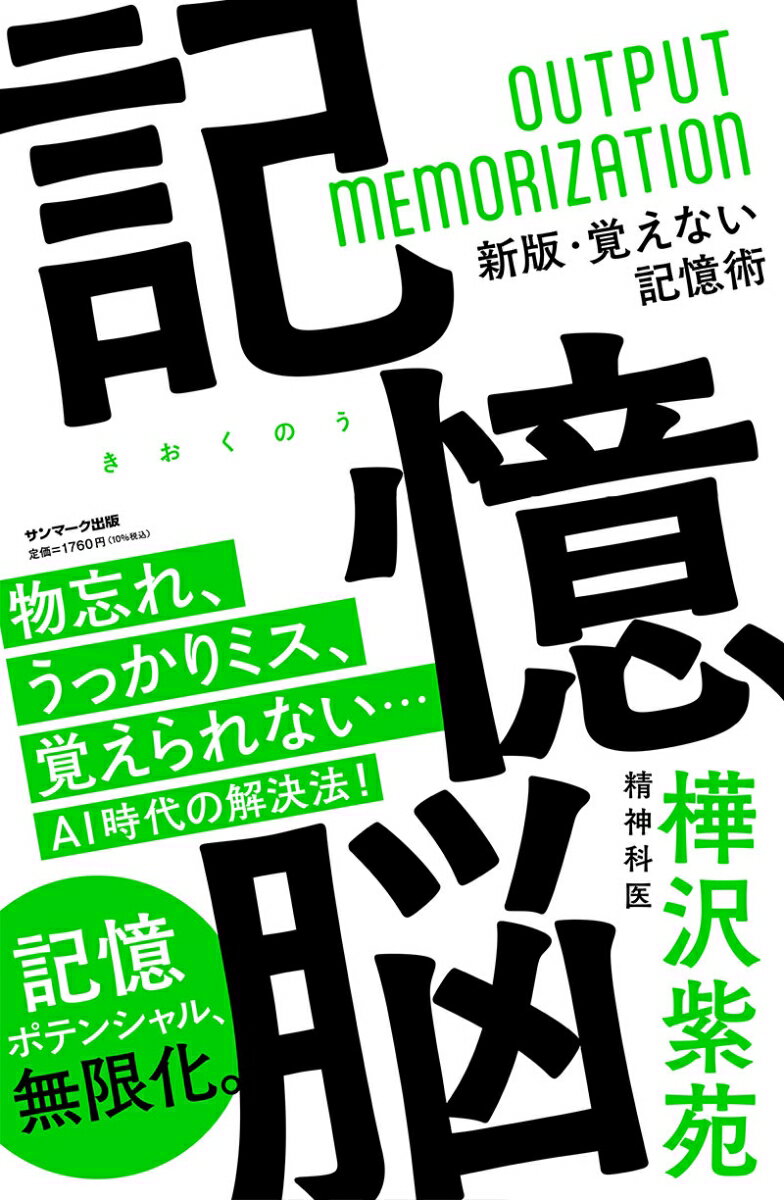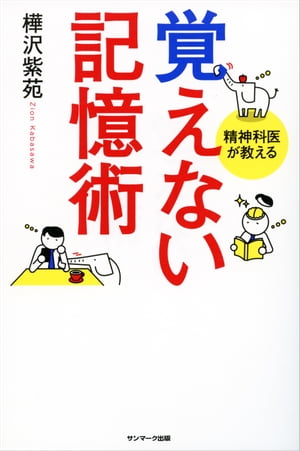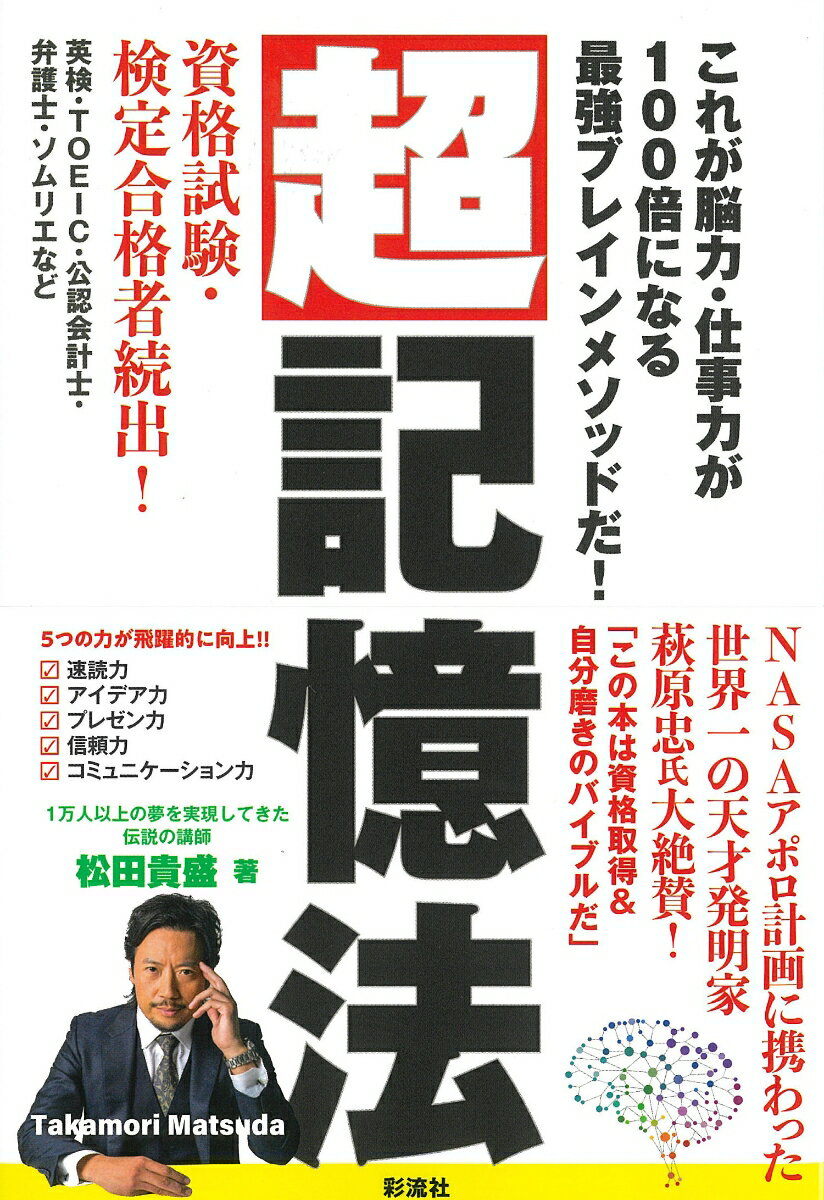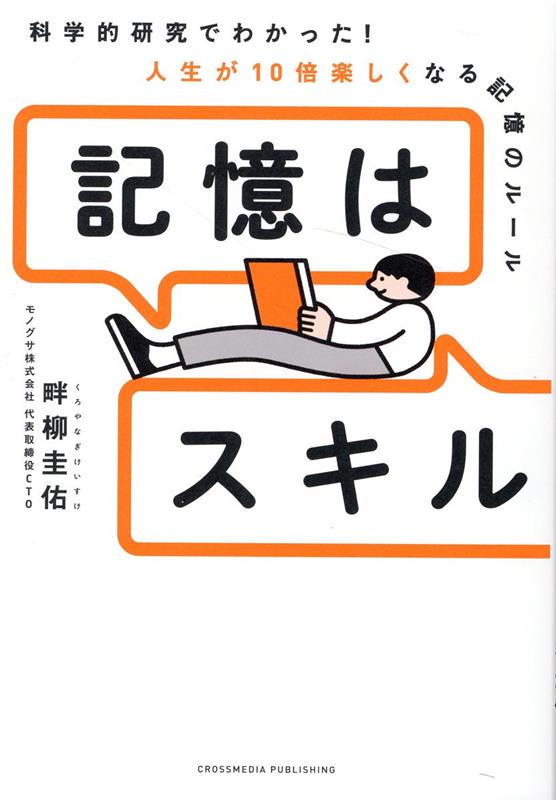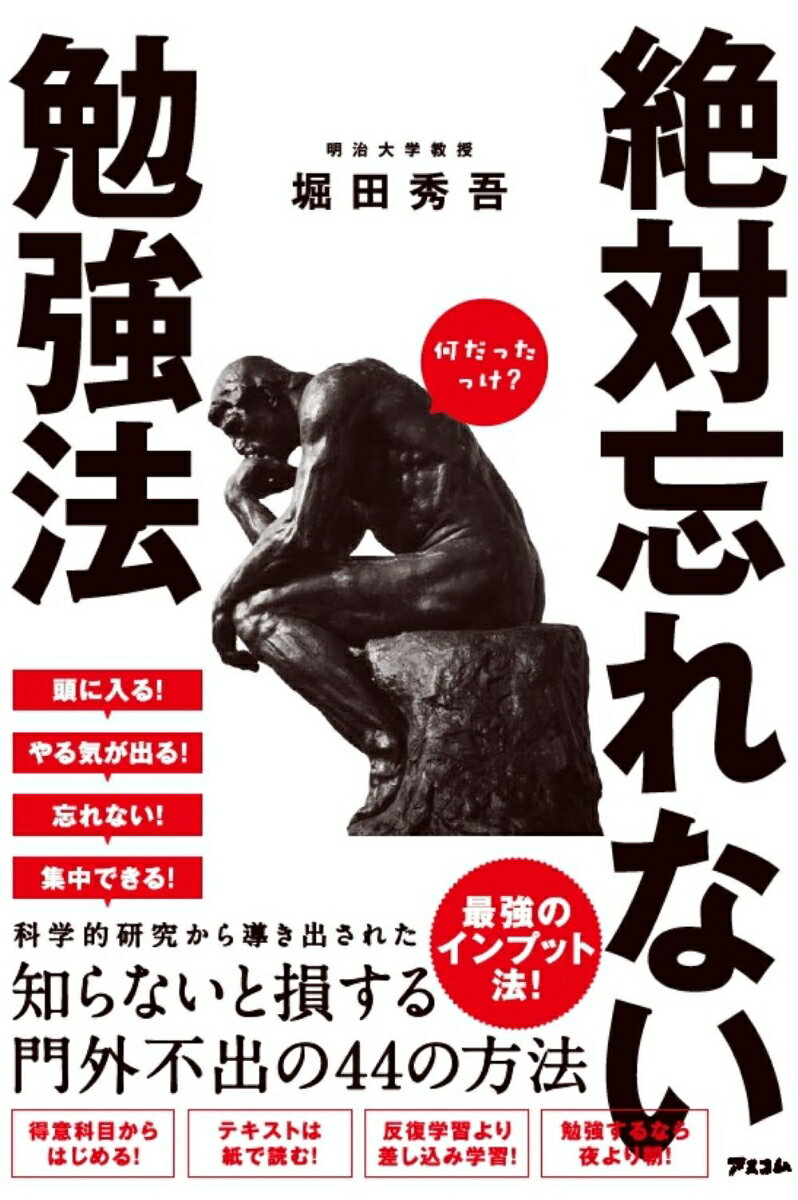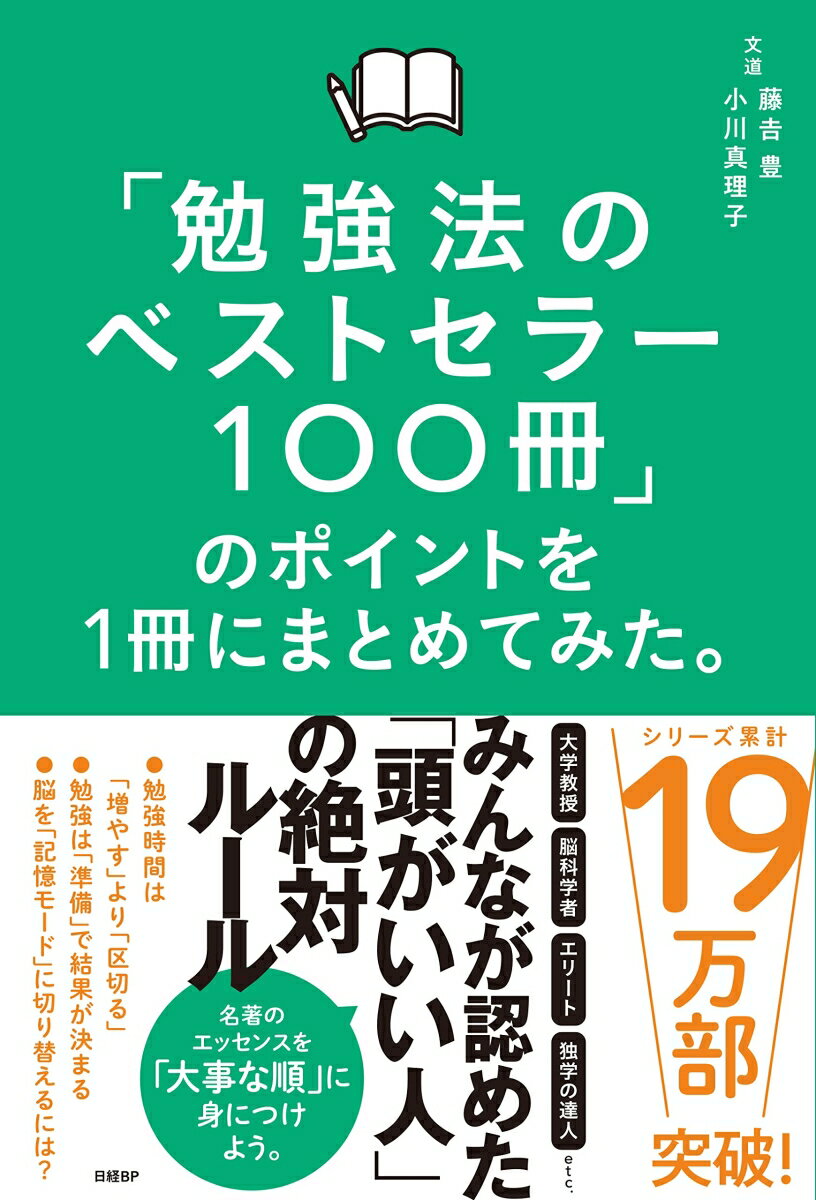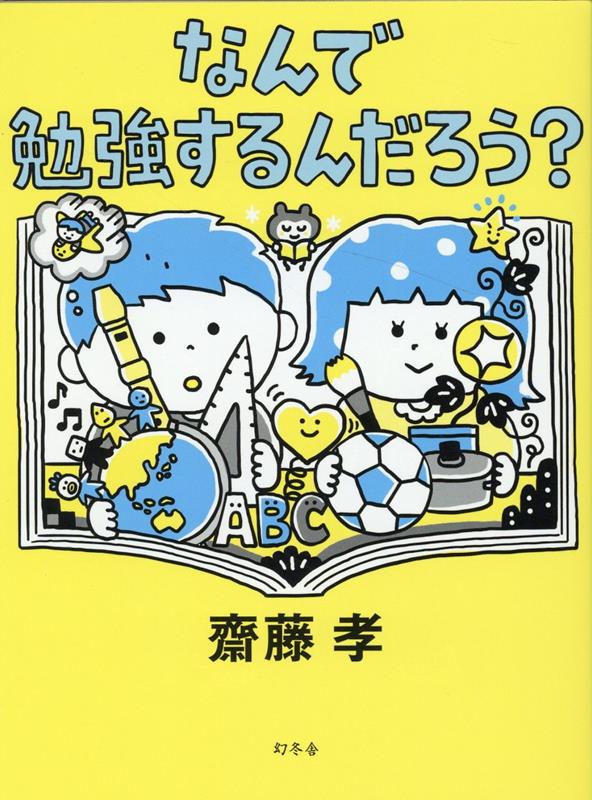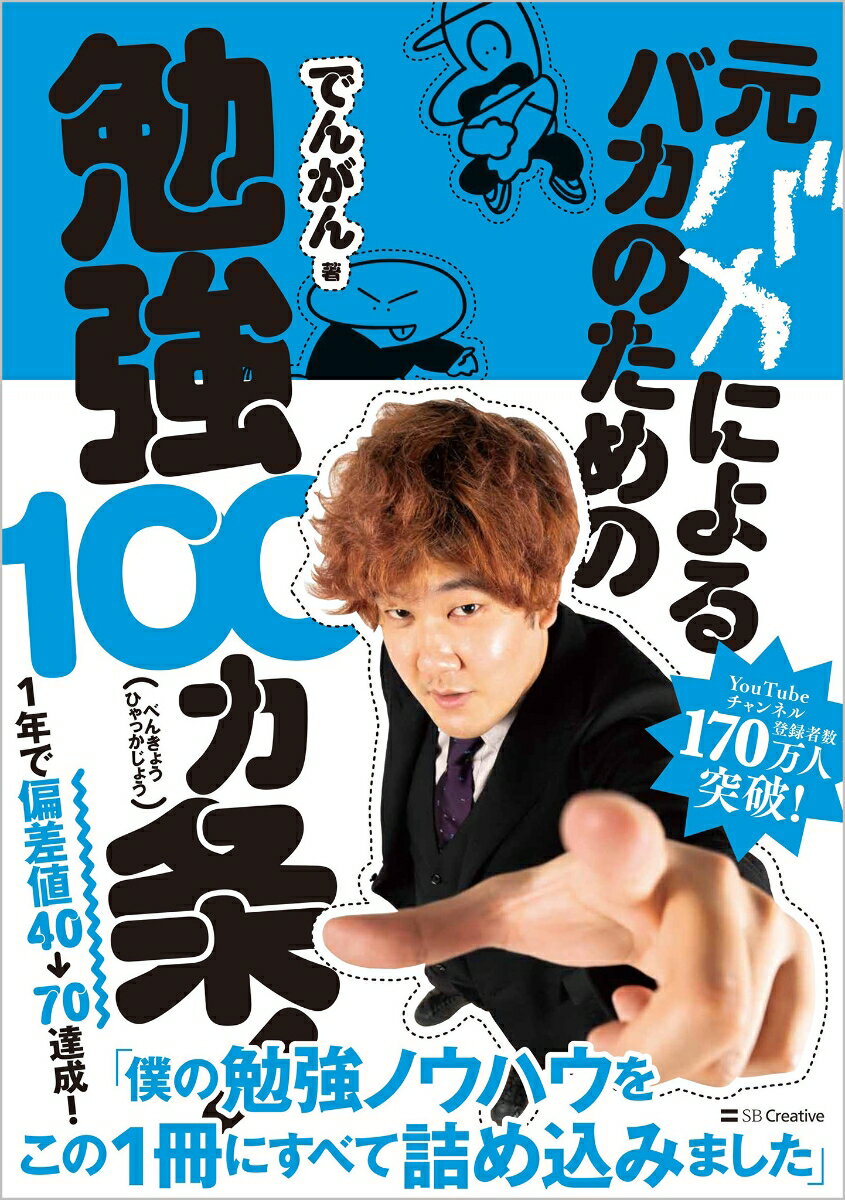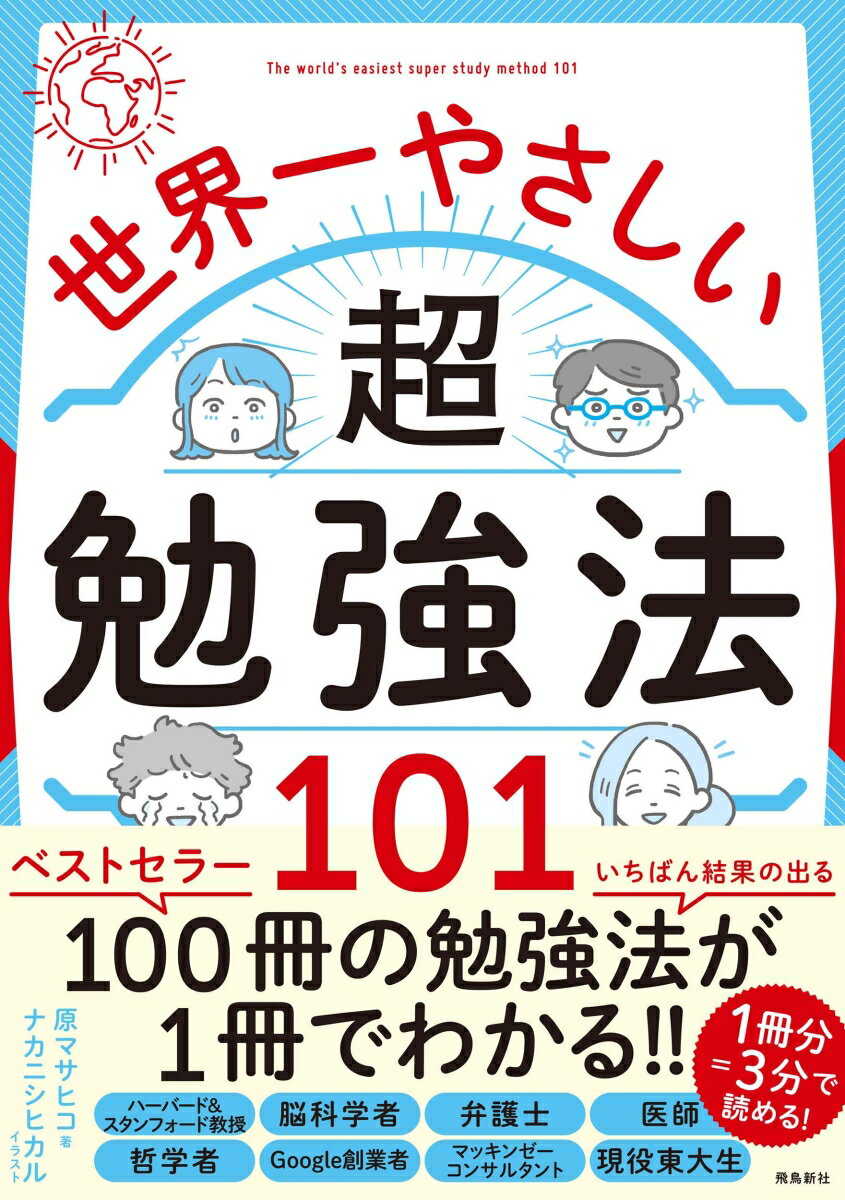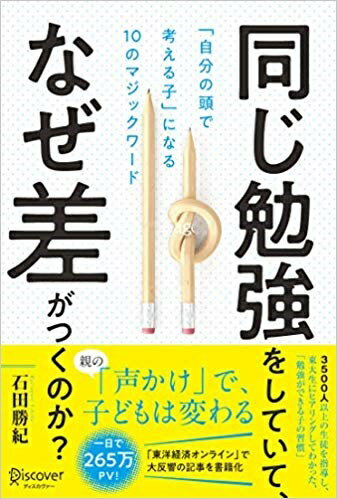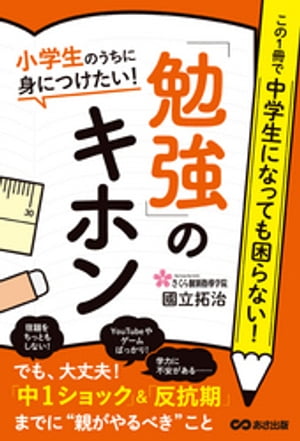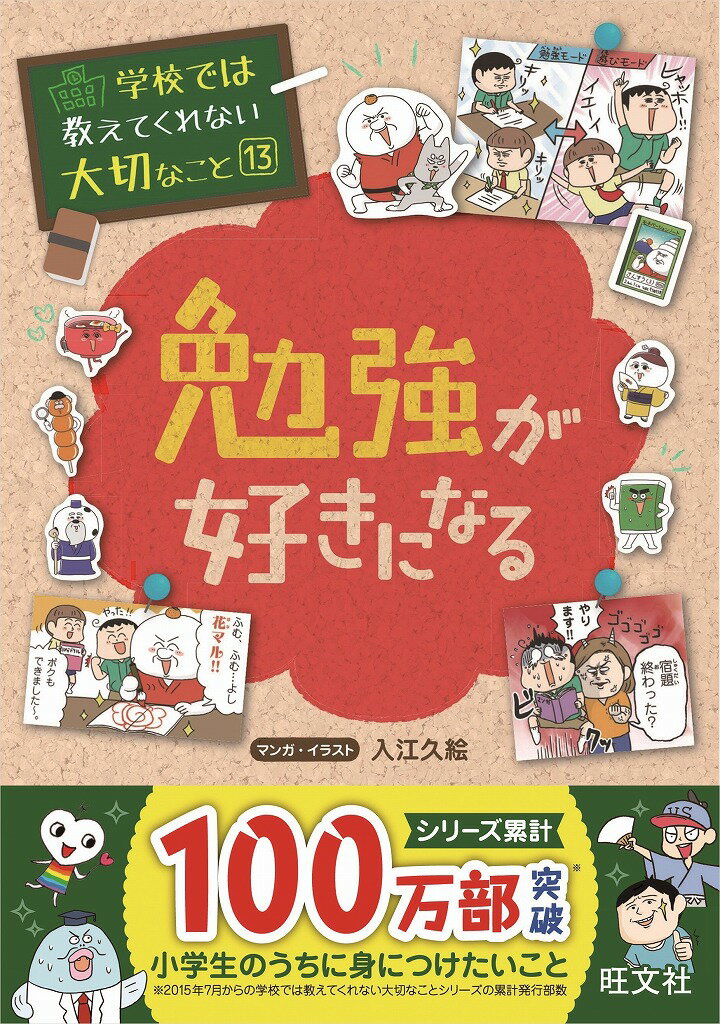前回の追加をしたいと思います!(笑)
ノートを自分の言葉で書くというのは、言語化しない限り書けません。
言語化をしてノートを書くと、3つの力が鍛えられます。
1.「理解の穴」が可視化される
頭の中だけでは気づけなかった「理解の曖昧さ」が、書くことでハッキリと浮かび上がります。
書こうと思った瞬間に、意外と説明できない部分がでてきます。
その「穴」を埋めるために再び思考し、理解が深まる。
これが「勉強」です!!(笑)
2.知識が「つながる」
言語化すると、単発の知識が線になってつながります。
似ている問題の共通点、公式の背景、手順の理由――
これらを自分の言葉で整理することで、学んだことが「意味のある情報」へ変わります。
「わかったつもり」が「わかった」に変わる瞬間です!
この塾生も、以前はバラバラだった知識、あやふやだった内容が、ノートをまとめることでつながり、
「あ、そういうことか!」という言葉が増えてきました。
理解した瞬間の言葉ですね!(^^)v
3.「再現性のある力」になる
まとめたノートは、「未来の自分への説明書」になります。
テスト前に読み返すと、単なる丸暗記ではなく、考え方そのものが記録されています。
これが、勉強において最も強力な武器になります。

ノートは「成功の記録」であり「成長の証」です。
なにせ、解けなかった問題、間違えた問題、または重要事項というものをまとめてある、世界に一つのツールですから、この味を覚えると、急に勉強が好きになります!(笑)
誰かに言われたからではなく、自分からまとめ始めたという行動自体に、大きな意味があります。
今、この塾生のノートには、消しゴムの跡や書き直したメモがたくさんあります。
そして、それを見返す度に蜜の味がよみがえるのです!(笑)
この「自分でまとめる」という小さな一歩が、踏み出せるかどうか。
これをやり始めることができるかどうか!
「自分の頭で考えられる子」になるための、とても大きな一歩なのです。
それには、やはりコーチングが大事です!
強制では無く、自分から書けるように意識を持って行く!
是非、子供達にこの蜜の味を早く覚えて貰えるよう、話をしていきたいと思います!
***********************