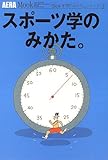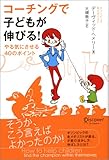昨日のドラフト会議をテレビで見て
いましたが、またプロの卵がたくさん
生まれたことに嬉しく感じます
もとはみな純粋な野球少年
だったはず。
その気持ちを忘れず、野球だけでなく
人間的にも成長した子たち。
そういう子たちがこうやって認められて、
プロの門をくぐっていくのは非常に感慨
深いものがあります
また、ドラフト中継後のドキュメンタリー
番組も良かった・・・
みなさん見ました
ドラフト緊急生特番!お母さんありがとう 夢を追う母と子の壮絶人生ドキュメント
それぞれ辛く、苦しい人生を乗り越えて
晴れてプロ選手になった子たち。
そこには必ず親の支えなくしては語れ
ないものがあるということですね。
もちろん、「良き師」とのめぐり逢いも
欠かせない要素です。
当番組に柴田章吾くんという明治大学から
読売巨人軍に育成枠で指名された選手が
出演していました。
彼はベーチェット病という難病と闘いながら
も夢を諦めずに野球を続けました。
そして愛工大名電時代には甲子園に出場し、
大学でも活躍したサウスポーです。
私も4年前に、柴田くんの投打に活躍する
勇姿を実際の甲子園で観ました。
彼の気迫・精神力を感じさせるプレーが
印象に残っています
彼がここまでになるのには、親の支えが
あったことはもちろんのこと。
そして「良き師」との出会いがあったことも
事実です。
愛工大名電硬式野球部監督の倉野光生さん。
倉野さんは、彼を本当の自分の息子の
ように愛情を持って接していたようです。
それをうかがわせるのが、4年前の
ドキュメンタリー番組でのインタビュー
でのこと。
倉野さんは、柴田くんが病気を克服して
初マウンドに上がった時のことを回想し
ながら、涙を流されていました。
本当に人柄を感じさせる方で、
「息子もこういう人のもとで野球をやらせたい」
と思わせるような方でした。
そしてまた自分も指導者として、そうありたい
と感じています
ちなみに、息子は県外の私立の強豪校に
行きたがっているようなので、「それなら
名電行けば」って言うんです
愛知県はかなり遠いですが・・・
息子にどこに行くって言われても経済的に
耐えられるように、親としても頑張らねば


いましたが、またプロの卵がたくさん
生まれたことに嬉しく感じます

もとはみな純粋な野球少年

だったはず。
その気持ちを忘れず、野球だけでなく
人間的にも成長した子たち。
そういう子たちがこうやって認められて、
プロの門をくぐっていくのは非常に感慨
深いものがあります

また、ドラフト中継後のドキュメンタリー
番組も良かった・・・

みなさん見ました

ドラフト緊急生特番!お母さんありがとう 夢を追う母と子の壮絶人生ドキュメント
それぞれ辛く、苦しい人生を乗り越えて
晴れてプロ選手になった子たち。
そこには必ず親の支えなくしては語れ
ないものがあるということですね。
もちろん、「良き師」とのめぐり逢いも
欠かせない要素です。
当番組に柴田章吾くんという明治大学から
読売巨人軍に育成枠で指名された選手が
出演していました。
彼はベーチェット病という難病と闘いながら
も夢を諦めずに野球を続けました。
そして愛工大名電時代には甲子園に出場し、
大学でも活躍したサウスポーです。
私も4年前に、柴田くんの投打に活躍する
勇姿を実際の甲子園で観ました。
彼の気迫・精神力を感じさせるプレーが
印象に残っています

彼がここまでになるのには、親の支えが
あったことはもちろんのこと。
そして「良き師」との出会いがあったことも
事実です。
愛工大名電硬式野球部監督の倉野光生さん。
倉野さんは、彼を本当の自分の息子の
ように愛情を持って接していたようです。
それをうかがわせるのが、4年前の
ドキュメンタリー番組でのインタビュー
でのこと。
倉野さんは、柴田くんが病気を克服して
初マウンドに上がった時のことを回想し
ながら、涙を流されていました。
本当に人柄を感じさせる方で、
「息子もこういう人のもとで野球をやらせたい」
と思わせるような方でした。
そしてまた自分も指導者として、そうありたい
と感じています

ちなみに、息子は県外の私立の強豪校に
行きたがっているようなので、「それなら
名電行けば」って言うんです

愛知県はかなり遠いですが・・・

息子にどこに行くって言われても経済的に
耐えられるように、親としても頑張らねば