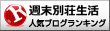(すっかり冬山になった北岳)
今日は冬至。
三週間ぶりの八ヶ岳南麓大泉で迎えた冬至の朝の日の出時刻は6:54である。
ちなみに東京の今日の日の出は6:48。小学校で習ったように我が国の標準時は東経135度の地点での南中時刻を12時と定めているから、より東にある東京は八ヶ岳南麓に比べて日が昇るのも日が沈むのも6分ほど早くなる。
(午前8時の太陽 夏には金峰山方面(写真の左の方)から上がってくるがこの時期は茅ヶ岳方面から
ノロノロと顔を出す)
では「昼間が一番短い冬至=日の出が一番遅い日」かというと、そうではないというからややこしい。
我が八ヶ岳南麓においては、
日の出が一番遅い日 1月6日 6:56:42
日の入りが一番早い日 12月6日 16:32:32
と、冬至から二週間ほどずれているのである(いずれも2021年実績)。
ずれが生じる理由、これは地球から見える太陽の位置が年間を通じて「8の字ダンス」をしているからであ~る(←言うまでもなく受け売りです)。
(アゼルバイジャンで観測された正午の太陽の位置 年間を通じてダンスをしている NASA提供)
ではなぜ太陽は8の字ダンスをするのだろうか。
タテ方向(上下方向)の動きは分かりやすい。地球の自転軸(地軸)が23度ちょっと傾いているからだ。
これによって夏と冬が生じるわけである。
それでは横方向(=東西方向)に動くのは何故だろう。
答は簡単、地球の公転軌道が楕円形であることによる(簡単じゃないだろ、これ)。
冬至の頃、地球は太陽に最も近い軌道上(近日点という)にある。この時地球の移動速度(=公転速度)がとても速くなることは「ケプラーの法則」で皆さんご存知のとおり(ホントか)。このため23時間56分
4秒をかけて自転した我が地球が昨日と同じ時間に太陽を見ると、公転で位置がずれた分のリカバリー
が普段よりも間に合わないものだから太陽はより東に位置しているように見える。これが日の出が一番遅い日が冬至より後に来る最大の原因である(ほかにもコマコマあるけどカット)。
(国立天文台資料より)
この近日点、現在は1月6日頃、つまり日の出が一番遅い日と一致する。
近日点は少しずつ移動していて約21000年の周期で遠日点と入れ替わるそうで、今から800年前、グレゴリオ暦や宣明暦がこさえられた当時は冬至と近日点はほぼ一致していたのだという。
う~む。
まあ800年かけて二週間ほどずれただけだから、我々が生きている間は「日の出が一番遅い日は
1月6日」、ということでいいでしょう。