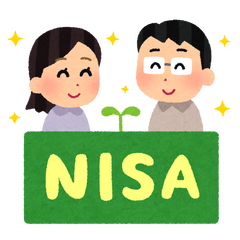なぜFANG+なのか
はじめの記事に書きましたが、なぜFANG+なのかと言うと、伸びそうだからの一言に尽きます。
伸びそう、というのは長期的な目線で見た時の金額面の話です。
当然リスクはあります。
よく比べられるであろう、S&P500とNASDAQ100と比べても値動きが激しいですし、さらに信託報酬も0.7755%と高い値になっています。
ただ、以下の点から、リスクをとるということ自体にはFANG+と比較される商品のどれを見ても、以下の理由から同じと考えています。
・リスクがあるのはどの信託商品でも同じ
・信託報酬が高いといっても、大きな成功を狙うのなら些細な割合
・S&P500とNASDAQ100のグラフとFANG+のグラフは、上げ下げの大きさはあれど、動きはほぼ同じ
・長期的に見れば、S&P500とNASDAQ100とFANG+のどれも右肩上がり
S&P500とNASDAQ100の構成銘柄を見てみると、FANG+の面々が大きい比重になっています。
その上で、実際の運用履歴を見ると、FANG+の方が上昇幅が大きいことがわかります。
つまり、S&P500やNASDAQ100はFANG+銘柄を除くと上昇幅が小さくなることになります。
FANG+銘柄が今後伸びるかどうかはわかりませんが、それはどの銘柄にも言えますし、成功を信じてリターンを期待するならなおさら、同じような動きをしている中で一番大きなリターンが得られるFANG+を選ぶべきであり、今までの実績で低調なものが入っているインデックスを選択する必要はありません。
テクノロジーが伸びると思う理由
伸びそうだから決めた、ということは書きました。ではなぜ伸びそうと思っているのか。
それはFANG+のラインナップです。次世代をけん引していくテクノロジーを有している企業群だらけです。
今年のリバランスで米国企業だけになったことも大きなポイントです。
今までの歴史を見ていると、お金が絡むものはテクノロジーが引っ張っています。
今後AIや自動運転など、まだまだIT系に関しては未来に希望が持てる見通しが数多くあります。
FANG+が落ちるときは他のインデックスファンドも落ちるでしょう。その時はその時です。
未来を見る目がなかったと自分を恨むしかありません。
だとしても、いわゆるシンギュラリティ(技術的特異点)と呼ばれるものが訪れると予想されている時期まではこの伸びは続くはずです。
シンギュラリティがいつ訪れるか、2030年や2045年など様々な説が言われ、実際にシンギュラリティが訪れるのかもわかりませんが、そういったことが予想される程度にはITは発展し続けるはずなのです。
運用開始が2024年。仮に2030年がシンギュラリティの年としても6年あります。
その6年あれば、FANG+の過去の利回り大体30%として計算すれば、倍程度の資産になると見込めます。
毎月30万計算で5年で1800万限度後に放置し、計10年であれば、遊んで暮らせる金額になります。
信託報酬の0.7755%が高いと言えど、遊んで暮らせるのであれば些細な数値です。喜んで支払いましょう。
また、個別株でいいのではないか、というものについては以下の理由があります。
・NISAの場合、投資枠が翌年復活のためリバランスの際に枠を有効活用できない
・FANG+は投資枠自体を変えずに内部で定期的に自動でリバランスを行ってくれる
・最低限の分散投資になる
・運用の楽をしたいためにインデックスファンドを購入している
まとめ
本当に突き詰めたいのなら、FANG+は買うべきではないでしょう。しかし、今までの歴史を信じるなら勝率が高いと踏んでいます。
当然運用会社としても儲けたいですからまじめに運用してくれるでしょうし、リーマンショックにコロナや戦争といったことが幾度となく起こっても、一時的に落ちることはあれど、現時点では信託商品は上がり続けています。
ゼロになることがあれば、それは世界全体が分断されていたり世界大戦にでもなっているのではないでしょうか。
それにもし世界を巻き込む何かがあったとしても、日本は安全保障戦略的に米国寄りという大きなメリットがあります。
投資する時点で、投資したお金が最悪ゼロになるつもりで預けてはいますが、引き出せなくなるような事態になるタイムリミットは比較的猶予があると言えるでしょう。
そしてギャンブルをするのなら、リターンが大きいものにかけたい。
それがFANG+を選んだ理由です。