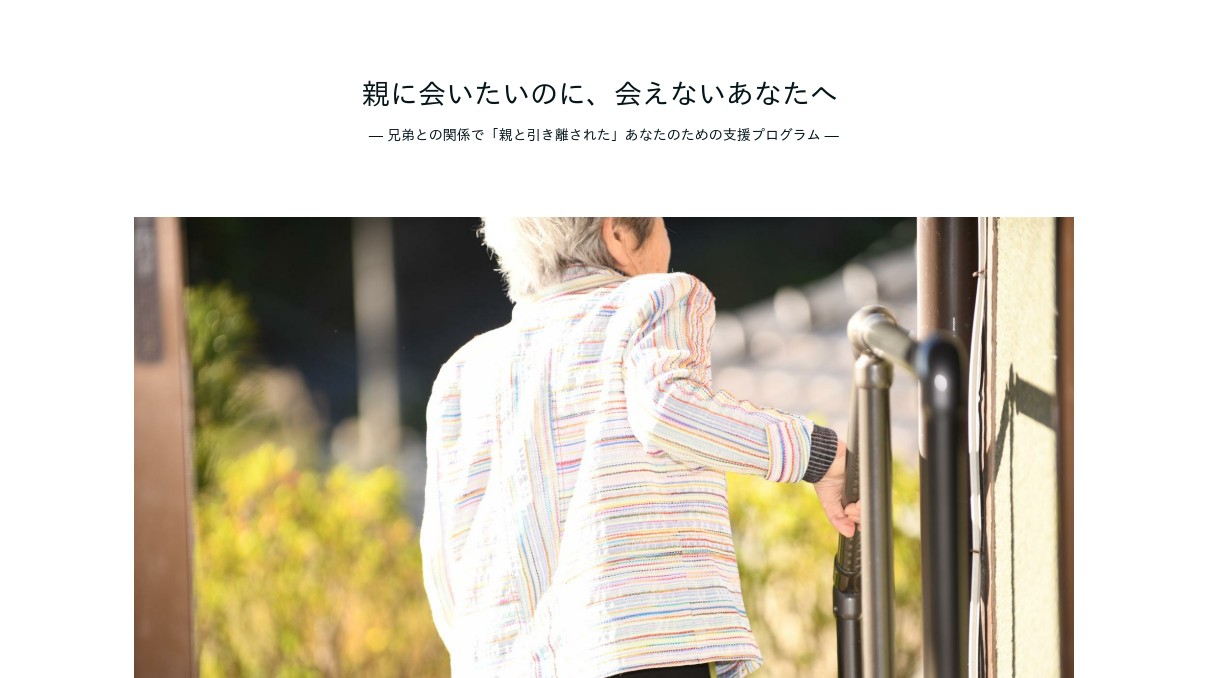高齢親の囲い込み解消コンサルタント 公認会計士・税理士、白岩俊正(静岡市・全国オンライン)です。
認知症高齢親の「囲い込み」問題に関する調査報告をChatGPT Deep Researchで作成してもらいました。
無料オンライン相談 受付中
I. 親の囲い込みとは何か(定義と態様)
「親の囲い込み」とは、認知症や重い病気などで判断能力が低下した高齢の親について、同居する子ども(兄弟姉妹のうち一人)などが親を自宅や施設に囲い込み、他の兄弟姉妹や親族との面会や連絡を一方的に遮断する行為を指します。
典型的には、高齢の親と同居する子ども(場合によっては複数の兄弟姉妹が共謀)が親を自宅に引き取ったり介護施設に入所させた上で、他の兄弟姉妹に親の居場所や容態を知らせず、一切面会させないというケースです。このように親を孤立させることで、外部(特に他のきょうだい)との接触を断つ行為が「囲い込み」の本質です。
囲い込みにはさまざまな類型があります。主な態様として以下が挙げられます。
外部との接触遮断
他の兄弟姉妹や親戚・友人が高齢親に連絡・面会することを意図的に妨害します。具体的には、親の電話を同居家族が代わりに出て他のきょうだいとの会話を遮ったり、訪問を拒否したりする、介護施設に入所させて施設名や所在地を秘密にし、他の家族が居場所を知らないようにするといった手段です。
情報・連絡の独占
親の介護先(施設や病院)のキーパーソン(連絡窓口)を囲い込んだ子が独占し、施設職員やケアマネジャーに「自分以外の家族には情報提供しないでほしい」「許可なく面会させないでほしい」と指示するケースです。残念ながら「費用を負担している人(=同居家族)がキーパーソンだから、その意向に反して他の兄弟と会わせるわけにはいかない」と考える施設管理者やケアマネも多いのが実情です。
財産管理の独占
囲い込んでいる子が親の通帳やキャッシュカード、実印等を管理し、他の兄弟には一切財産状況を開示しない状態です。親名義の預貯金を代理で引き出して使い込んだり、親の不動産を無断で処分・名義変更する事例も報告されています。極端な場合、囲い込んだ子が親に自分に有利な遺言書を書かせたり、判断能力が低下した親と任意後見契約を結んで自分を後見人に指名させてしまうケースもあります。
介護・契約手続の独占
親の介護サービスや入院・入所手続を囲い込んだ子が単独で行い、他の兄弟には相談しません。例えば親を急に遠方の施設に入所させ、「親は施設に入ったから」と他の兄弟に教えずに事後報告もしない、面会制限がある特殊な施設を選んで実質的に外部交流を断つ、などの手法があります。
こうした囲い込み行為により親本人も他の家族も交流を断たれ、親は晩年を孤独に過ごし、他の兄弟姉妹は親の安否確認すら困難になるという深刻な問題が生じます。
II. 発生件数・統計:広がる囲い込み問題の実態
近年、このような高齢親の囲い込みトラブルは全国的に増加傾向にあり、社会問題化しつつあります。弁護士や各種相談機関には「兄(姉)が親を会わせてくれない」「親と連絡が取れない」といった相談が年々増えているとの報告があります。具体的な件数の全国統計は存在しないものの、相続や介護に関する相談の中で「囲い込み」や親の財産の「使い込み」をめぐる内容が最近特に増えていることが指摘されています。
参考までに関連するデータとして、高齢者虐待(家族による虐待)の届出件数は年々増えており、令和5年度には全国で17,100件もの養護者(主に同居家族)による虐待事案が市町村によって「虐待あり」と認定されています。
これは施設職員等による虐待1,123件の約15倍にも上り、多くが家庭内で起きていることを示しています。この中には身体的虐待だけでなく、経済的虐待(財産の搾取)や心理的虐待(無視・隔離など)も含まれます。囲い込み事案の多くはこうした経済的・心理的虐待の側面を持つため、高齢者虐待の一形態として潜在的に数多く発生していると考えられます。
また、家庭裁判所で扱われる相続紛争も増加傾向にあります。司法統計によれば2020年の遺産分割事件は14,617件に上り、このうち生前の親の財産処分や介護に絡む争い(いわゆる「生前相続トラブル」)が増えています。
従来であれば親が存命中は表面化しにくかった紛争が、親の存命中から「囲い込み」や「財産の使い込み」を巡って兄弟間で火種が生じるケースが増えていると報道されています。以上から、明確な統計は無いものの囲い込みは全国で多数発生していると推測され、専門家も「近年このような事例が増えてきている」と警鐘を鳴らしています。
III. 囲い込みが生じる背景・原因
囲い込みが行われる背景には、主に相続・財産に関する利害関係と家族内の対立が存在します。具体的な要因として以下が指摘されています。
相続財産の独占・有利な遺産分割の狙い
囲い込みをする子は親の財産に強い関心を持っている場合が多く、親の財産を自由に使いたい、あるいは自分に有利な遺言を書かせたいといった思惑が背景にあります。
高齢親を自分の管理下に置き、他の相続人を遠ざけることで、親の預貯金を生活費名目で引き出したり、自宅や土地を自分名義に移す、生前贈与を受けるなどの行為が容易になるからです。実際、囲い込みが行われている場合、親の通帳から毎月不自然な高額引き出しがある、親名義の不動産が知らぬ間に処分されていた、といった経済的虐待(財産の食い物)が伴うことが多いと指摘されています。
囲い込む子にとって、他の兄弟姉妹と親が接触すれば自分のしている財産侵害行為が露見するおそれがあるため、何かと理由をつけて交流を遮断しようとするのです。
介護負担と見返り意識
囲い込みをする子には「自分だけが親の面倒を見ているのだから、親の年金や財産を使うのは当然」という意識があるケースもあります。介護の負担が偏った家庭では、介護者が「自分はこれだけ苦労しているのに他の兄弟は何もしない」という不満を抱え、その埋め合わせとして親の財産を使い込んだり相続分を多く取ろうとする心理が働くことがあります。
一方、疎遠な兄弟から見れば「介護と称して親の財産を勝手に使っているのではないか」「虐待しているのでは」と疑念を持つため、両者の不信感が募りやすい環境です。このように介護の過重負担と経済的見返りへの欲求が絡み合い、囲い込みと財産トラブルに発展することがあります。
家族間の不和・対立
もともと兄弟姉妹間に不仲や価値観の違いがある場合、親の介護方針や財産管理を巡って衝突し、その延長で「もう○○(他の兄弟)には会わせない」と囲い込みが始まるケースもあります。一度対立が深刻化すると、親の世話をする側は「他の兄弟に口出しされたくない」「親も○○には会いたがっていない」と主張し、他方の兄弟は「何か隠しているのではないか」と疑心暗鬼になる悪循環に陥ります。家族内のコミュニケーション不足や信頼関係の崩壊が囲い込みを助長する土壌となっています。
高齢親の意思判断力低下
認知症などで判断能力が落ちている親自身が、囲い込む子から一方的に吹き込まれた内容を信じてしまい、結果として他の子と会うことを拒否してしまう場合もあります。例えば囲い込んでいる子が親に「他の兄弟は財産目当てで近づいてくる」等の悪口を日常的に吹き込むと、高齢の親はそれを真に受け、自ら外部との連絡を絶ってしまうことがあります。年齢による心身の衰えや周囲の吹き込みにより、親本人が客観的判断を下せない状況も、囲い込みが成立しやすい背景と言えます。
以上のように、主たる原因は経済的な動機(遺産・財産)であり、それに介護負担の偏りや兄弟間の不仲が複合的に絡んで囲い込みが生じています。特に親の認知症に乗じて財産上の利益を得ようとする行為は高齢者虐待防止法上「経済的虐待」に該当し行政による介入の対象にもなり得ますが、後述のように実際の救済は容易ではありません。
IV. 法的な扱い:成年後見制度・民法の規定・裁判例・弁護士会の見解
成年後見制度による対応
親が認知症などで判断能力を欠く場合、家庭裁判所に申立てて成年後見人を選任し、親の財産管理や身上監護を第三者(専門職後見人など)に委ねる方法があります。成年後見人が付けば、親名義の預貯金や不動産の処分は家庭裁判所の監督下に置かれ、囲い込みをしている子が勝手に財産を動かすことを防止できます。実際、親の財産が使い込まれる危険を察知した他の兄弟が、親の保護のため後見開始を申し立てるケースもあります。
しかし、囲い込みをしている親族が手続に非協力的だと問題が生じます。例えば後見申立てには医師の診断書が必要ですが、同居の子が親を医療機関に連れて行かず診断書取得に非協力的なため、手続きが進まない事例があります。そのため、「囲い込んだ親族が反対しても必要性が認められる場合は、裁判所が病院や施設に調査嘱託を行うなど運用改善が必要」との指摘もあります。
また、冒頭で触れた任意後見契約が結ばれている場合(親が判断能力低下前に特定の子を将来の後見人に指名している場合)には、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して契約を発動させることになります。しかし、囲い込んだ子が任意後見人になっている状況では、既に当該子が親の財産管理権を掌握しているため、他の兄弟が関与しにくい状態です。このように後見制度は財産保全の有力な手段ですが、囲い込む側の妨害により機能しづらい側面があります。
民法上の扱い(不法行為・面会権
親子の面会交流は通常、未成年の子どもの親権に関する文脈で論じられますが、近年の裁判例は親が高齢の場合でも、実子が親と会う権利は法的に保護されるとの立場を明確にしています。
民法上明文の規定はありませんが、裁判所は「たとえ子が成人した後でも、子が親と面会・交流したいと願うのは自然な感情であり、それ自体が法秩序上尊重されるべき利益である」と判示し、正当な理由なくその機会を奪う行為は社会的相当性を逸脱し不法行為(民法709条)を構成すると判断しました。
つまり、囲い込みによって他のきょうだいから親との交流機会を奪うことは、人格的利益の侵害として損害賠償の対象になり得るということです。
面会妨害に対する法的措置
上記のような考えに基づき、実際の裁判でも囲い込み行為への法的対応が行われています。主な方法は
①面会妨害禁止の仮処分
②損害賠償請求(慰謝料請求)
の二つです。
まず①について、親と会えない子が裁判所に申し立てて、他の兄弟による親との面会妨害を禁じる仮処分命令を出してもらうことが可能です。これは緊急の救済手段で、仮処分命令が出れば同居家族や施設は子との面会を拒めなくなります。
例えば横浜地方裁判所平成30年6月27日付決定(および同年7月の保全異議決定)では、親と施設で暮らす両親に会えないよう長男が妨害していた事案で、裁判所は「長女は両親と面会する権利がある」として長男および施設側に対し面会妨害禁止を命じました(下表①参照)。
次に②の損害賠償請求では、囲い込みによって受けた精神的苦痛に対する慰謝料を求めて提訴する方法です。
東京地方裁判所平成30年12月6日判決では、母親と面会できなかった三女が長女・次女を訴え、裁判所は「合理的理由もないのに親子の交流機会を奪う行為は不法行為に当たる」として、長女らに計110万円の賠償(慰謝料)支払いを命じました(下表②参照)。このように民事上の法的手段によって囲い込みを是正した例が現れ始めています。
● 判例の概要(面会権を巡る裁判例): 近年の代表的な裁判例を整理すると以下の通りです。
|
裁判例(年月) |
概要と判断 |
出典・注釈 |
|
① 横浜地裁決定(平成30年6月27日) |
長男が施設入所中の両親に長女を面会させなかった事案。長女が面会妨害禁止の仮処分を申立て。裁判所は「両親の意思に明確に反し平穏を害しない限り、長女には両親と面会する権利がある」と認定し、長男および施設に面会妨害の禁止を命じた。
|
横浜地裁平成30年6月27日決定(平成30年(ヨ)第◯号) |
|
② 東京地裁判決(平成30年12月6日) |
三女に母との面会を一切許さなかった長女・次女に対し、三女が提起した慰謝料請求訴訟。東京地裁は「親と自由に面会・交流する利益は法的保護に値する」「正当理由なくそれを侵害することは不法行為」と判断し、長女らによる面会拒絶行為の違法性を認定。長女・次女に対し110万円の損害賠償支払いを命じた。
|
東京地裁平成30年12月6日判決(平成29年(ワ)第◯号) |
これらの裁判例により、親族による囲い込みは法的に看過できない違法行為であることが示されています。裁判所は「親と会いたいという子の素朴な感情・利益」は法律上保護されると明言し、囲い込んだ側に対し面会させる義務や損害賠償責任を認めています。
刑事法による対応の難しさ
他方で、刑事面での追及は限定的です。親の財産を同居の子が勝手に使い込んでいた場合、本来は横領罪や窃盗罪に該当し得ます。
しかし刑法257条には「親族相盗例」という特例があり、被害者が直系血族や同居親族の場合は加害者が窃盗・横領をしても刑が免除される規定があります。
つまり、親と同居する子が親の預金を引き出して私的流用しても、刑事罰を科すことは難しいのです。
実際、囲い込みに伴う財産使い込みは家族間の問題として扱われ、警察は介入しにくい傾向があります。このため刑事ではなく民事・家事手続で解決を図る必要があるのが現状です。
行政(高齢者虐待防止法)と弁護士会の見解
高齢者虐待防止法では、家族が認知症の親の財産を不当に処分する行為は「経済的虐待」とされ、市町村など行政が高齢者の権利擁護に努める義務が定められています。
しかし実際には、自治体が積極介入できるケースは命の危険や介護放棄など緊急性の高い事案に限られる傾向があります。親に十分な資産や年金収入があり、一見生活に困っていないような場合、多少の財産流用では「親の生存自体が危うくなる恐れ」は低いと判断され、行政介入は期待しにくいと指摘されています。
つまり、囲い込みによる経済的虐待は親が亡くなった後に初めて発覚するケースも多く、その段階では行政も介入できず結局は相続時の争いとして表面化するのです。
こうした現状を踏まえ、日本弁護士連合会(日弁連)や各地の弁護士会は高齢者の財産保護や見守り体制の強化を提言しています。日弁連が提唱する「ホームロイヤー」制度もその一つで、これは弁護士と契約して高齢者の日常生活や財産管理を定期的にサポート・チェックしてもらう仕組みです。ホームロイヤーを利用すれば、親族間の信頼関係が損なわれていても専門家の目が入ることで不正や孤立を防ぎ、安心した老後を送れる可能性があります。
実際、弁護士会と社会福祉士会が連携して「高齢者虐待対応専門職チーム」を組織し、高齢者の権利擁護に当たっている地域もあります。弁護士会としては、「親の囲い込み」に気付いた周囲の親族は一刻も早く法律専門家に相談し、仮処分申立てや後見申立てなど適切な法的対応を検討すべきと助言しています。
V. 囲い込み事例の実態と代表例
最後に、実際に起きた囲い込み事案の実態をいくつか紹介します。これらの事例から問題の深刻さを具体的にうかがうことができます。
事例A:妹夫婦と同居の母に会えない長男
父を亡くした後、86歳の母親は妹夫婦と同居することになりました。遠方に住む長男が母に電話をかけても母が出ず、代わりに妹が電話口に出て「お母さんはお兄さんに会いたくないと言っている。連絡もしないでほしい」と一方的に告げて電話を切ってしまいました。長男には身に覚えのない話であり、一度直接会って誤解があるなら解きたいと願っていますが、訪問も拒まれている状況です。
このケースでは、妹側が母の携帯電話や日常生活を完全に管理しており、長男は母の安否すら確認できない状態に追い込まれています。典型的な囲い込みの初期段階の事例であり、第三者を交えた話し合いや調停が必要とされています。
事例B:亡父の財産を巡る兄の使い込み疑惑
要介護状態の父を長年同居して世話していた兄と、別居していた弟のケースです。
父の死後、弟が父名義の預金通帳を見ると、父が入院してから亡くなるまでの間、毎日のようにATMで限度額いっぱいの現金が引き出され、総額1千万円近くに及んでいたことが判明しました。弟が兄を問いただすと、兄は「親の面倒を見たのは俺だ。介護の苦労も知らないお前にとやかく言われる筋合いはない」と怒り、話し合いになりませんでした。
このケースでは父の生前、兄が父のキャッシュカードを使って多額の金銭を引き出していた疑い(財産の使い込み)が強く、兄弟仲は決定的に悪化しました。法律的には、亡くなった親が特定の子に渡していた金銭は「特別受益」として相続財産に持ち戻し請求できる可能性がありますが、実際には引き出された金が何に使われたか兄が「親が自分で使った」などと言い張れば立証は困難です。
本事例は、囲い込みと並行して財産の使い込みが行われ、最終的に遺産分割の場で揉める典型例と言えます。兄弟間の協議が不調なら調停や審判となりますが、感情的対立が激しいため解決は容易でありません。
事例C:横浜地裁仮処分事件
前述の横浜地裁平成30年決定に至ったケースの具体像です。認知症を患う両親の財産管理を巡り長男と長女が対立し、長女は両親と話し合おうとしたものの長男に拒まれました。長女が両親の入所する介護施設を訪ねても、施設側が長男の意向を忖度して面会を認めない状況でした。
さらに長男は両親の預金を取り崩している疑いがあり、長女は両親を守るため家庭裁判所に成年後見人選任を申し立てましたが、長男が協力しないため手続きが妨げられていました。追い詰められた長女は地方裁判所に仮処分を申し立て、ようやく「長女と両親との面会を妨害してはならない」との決定を勝ち取ったのです。裁判所は「両親の意思に明確に反しない限り長女には面会権がある」と判断し、長男の主張する「面会させないのは親の意向」との抗弁を退けました。この決定は「囲い込み」に風穴を開ける画期的な判断と評価されており、今後同種事案の救済の先例になると期待されています。
事例D:東京地裁損害賠償事件
前述の東京地裁平成30年判決に至る事案です。
80代の母をめぐり、近隣に住む長女・次女と遠方の三女がいました。母が自力で移動困難になった頃、長女と次女が母をある日突然自宅から連れ出し、それぞれの自宅や介護施設で三女に居場所を知らせずに母を交互に預かる形となりました。この間、姉二人は判断能力が低下した母と任意後見契約を結んで任意後見人に就任し、母の財産管理権を握りました。孤立無援となった三女は母に会えないまま5年が経過し、姉たちは「母はあなたに会いたくないと言っている」と三女に約束させようともしました。
母が亡くなる前に何とか面会しようと三女は訴訟を提起し、東京地裁(令和元年11月22日判決)は「合理的理由もなく親子の面会交流の機会を奪うことは不法行為である」として、姉二人に対し計110万円(判決によっては100万円)の慰謝料支払いを命じました。判決は「親と自由に面会・交流する利益はそれ自体法的保護に値する」との一般論を示した上で、姉たちの行為がその利益を徒に侵害したと認定したものです。三女はようやく母と最期の面会を果たすことができました。
この事例は、囲い込みによる親子断絶が長期間続いた悪質なケースであり、裁判所が明確に違法と断じて賠償を命じた点で注目されます。
以上の事例から明らかなように、親の囲い込みは家族の絆を引き裂き、高齢者の人格的利益(家族と交流する権利)を侵害する深刻な問題です。他の兄弟姉妹が親の最期に立ち会えなかったり、死亡後に巨額の使途不明金が判明して泥沼の相続争いに発展するなど、当事者全員が不幸になる結末を招きかねません。弁護士会などは「やった者勝ち」にさせないためにも早期相談と法的手段の活用を呼びかけており、社会全体で高齢者の権利と家族のつながりを守る仕組みづくりが求められています。
参考文献・出典: 本報告書で引用した情報は、厚生労働省の調査結果、公的機関の発表、信頼できる報道記事および専門家(弁護士)による解説などを出典としています。
ブログのご紹介
ブログ主宰 しらいわ は以下のブログも作成しています。併せてご覧ください。
1. EQモンスター対策室 ~感情的な人に振り回されている方向け~
2. あなたのメンタルを守りたい ~心が少し軽くなるメンタルケアの情報を発信中~
3. インナーチャイルド解放コーチ しらいわとしまさ 幼少期の心の傷が未処理のため大人になっても生きづらさを感じる方へ
4. 感情の地図 〜EQナビゲーターが届ける“心の航海術”~感情と向き合う「心の航海術」を発信中
5. 高齢親の囲い込み 解放アドバイザー ~介護が必要になった高齢親が自分以外のきょうだいに囲い込まれて会えなくなった方へ~
6. 女性起業家×アドラー心理学(準備中)