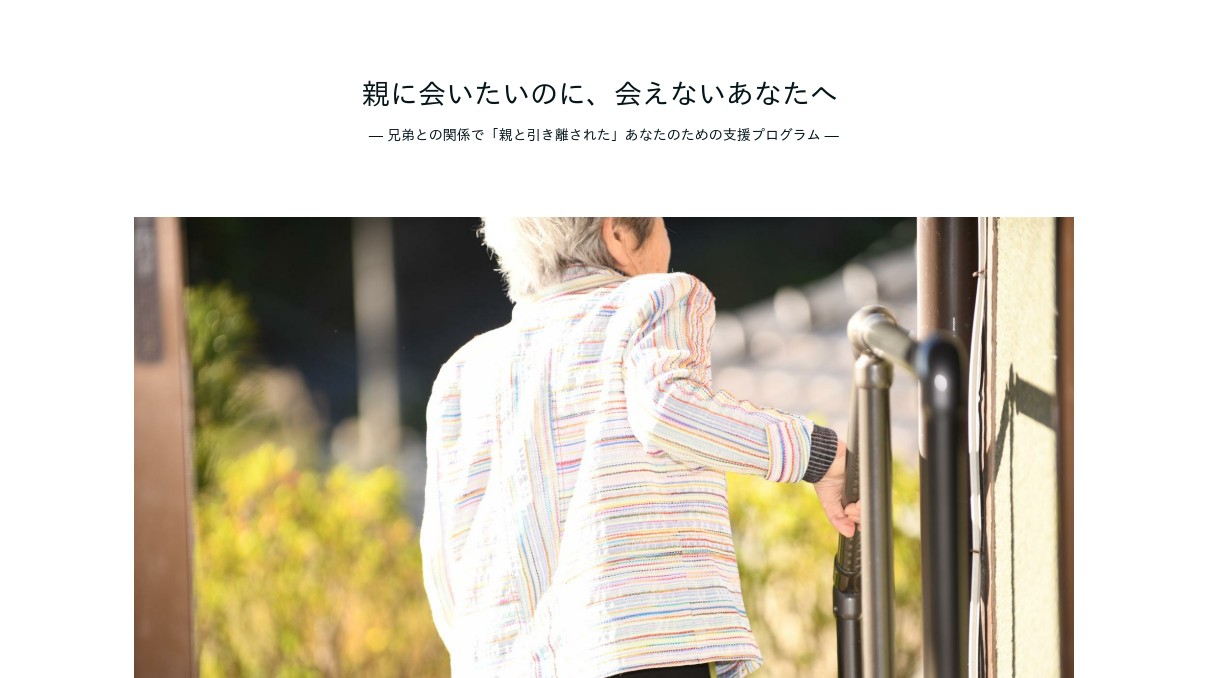公認会計士・税理士、高齢親の囲い込み解消コンサルタント 白岩俊正/静岡市・オンラインです。
無料オンライン相談 受付中
はじめに:親の認知症が家族関係に与える“見えない影響”
親が認知症と診断されたとき、家族にとって最初に迫られるのは「介護どうする?」という現実的な問いです。しかし、問題は介護の方法や施設選びだけではありません。
その瞬間から、家族というチームのバランスが大きく崩れ始めることがあるのです。
「本当は仲がよかったはずのきょうだいが、親の認知症をきっかけに絶縁状態になってしまった」
そんな相談が、私のもとには数多く寄せられます。
この記事では、なぜ親の認知症が“家族の分裂”を引き起こすのか?その心理的・構造的な背景をひも解いていきます。
1. 認知症がもたらす「決断の空白」
認知症になると、親本人の意思決定能力が徐々に低下していきます。
・病院はどこにする?
・施設に入れる?それとも在宅介護?
・通帳や不動産は誰が管理する?
こうした「大人としての判断」を、誰かが代わりに担う必要が出てきます。
ここで起きるのが――
“誰が親の意思を代弁するのか”を巡る対立です。
きょうだいのうち、誰かが先に動いて介護や金銭の管理を始めたとします。すると他のきょうだいから、
「なんで勝手に決めるの?」
「親の意見をちゃんと聞いたの?」
と、不信感が募るのです。親の判断力が弱くなっているからこそ、誰かの“代行”が始まり、それが「主導権争い」として表面化してしまうのです。
2. 介護の「見えない格差」と感情の蓄積
もう一つ、分裂の要因として見逃せないのが“介護の分担感覚のズレ”です。
・実際に親の世話をしている子ども
・遠方に住んでいて何もできない子ども
・たまにしか連絡しない子ども
それぞれに“立場の違い”があるのは当然ですが、当事者意識の差が積もると、
「私はこんなに頑張ってるのに!」
「あの人は何もしてないくせに口ばかり出す!」
といった感情の爆発につながっていきます。
特に、在宅介護をしている子が親の財産を管理しはじめた場合、「お金を勝手に使っているのでは?」といった疑念が他のきょうだいに生まれ、深刻な不信へと発展することもあります。
3. 家族のなかにある“未解決の感情”が噴き出す
親の認知症は、子どもたちにとって「老いや死に向き合う現実」を突きつける出来事です。そのストレスのなかで、長年くすぶってきた家族内の未解決な感情が吹き出すことがあります。
たとえば…
- 昔、親に贔屓された・されたと思っている
- 長男だからといって期待ばかりかけられた
- 親に認められなかったという想いが残っている
こうした子ども時代の心の傷やこだわりが、認知症という出来事を引き金に“今ここ”に噴き出すのです。
つまり、認知症による分裂は「介護やお金の問題」だけではなく、家族がこれまで抱えてきた心理的負債の表面化なのです。
4. 分裂を防ぐには「感情」ではなく「仕組み」で考える
親の認知症が進行していくなかで、きょうだい間の感情対立を完全に防ぐことは難しいかもしれません。
しかし、分裂を深めないための工夫はあります。
● 家族会議を開く
感情的なやり取りになる前に、事実の共有と方針のすり合わせを定期的に行うことが重要です。
● 第三者を交える
ケアマネジャーや包括支援センター、専門家など、中立的な立場の支援者を入れることで、感情的な衝突を和らげる効果があります。
● 任意後見・信託などの制度を活用
将来の判断能力低下に備え、法的な仕組みで財産管理や医療同意を整理しておくことで、「誰が親の代理人なのか」が明確になり、争いを防ぎやすくなります。
おわりに:「親の介護」は、家族の関係性の“通信簿”
親が認知症になるという出来事は、ただの医療問題ではありません。
それは、家族というシステム全体の問題をあぶり出す「試金石」なのです。
これまで曖昧にされてきたきょうだい関係、感情のすれ違い、役割の不平等――
それらが一気に表面化してしまうからこそ、冷静な対話と制度的な備えが必要なのです。
あなたの家族が分裂しないように。
その第一歩は、「感情ではなく、構造を見る」視点を持つことです。
ブログのご紹介
ブログ主宰 しらいわ は以下のブログも作成しています。併せてご覧ください。
1. EQモンスター対策室 ~感情的な人に振り回されている方向け~
2. あなたのメンタルを守りたい ~心が少し軽くなるメンタルケアの情報を発信中~
3. インナーチャイルド解放コーチ しらいわとしまさ 幼少期の心の傷が未処理のため大人になっても生きづらさを感じる方へ
4. 感情の地図 〜EQナビゲーターが届ける“心の航海術”~感情と向き合う「心の航海術」を発信中
5. 高齢親の囲い込み 解放アドバイザー ~介護が必要になった高齢親が自分以外のきょうだいに囲い込まれて会えなくなった方へ~
6. 女性起業家×アドラー心理学(準備中)