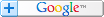漢城在陣の日本軍は碧蹄館の合戦で勝利を得たが、傷病者の数が多く、兵糧も四月上旬までに尽きる。
文禄二年三月二十日、三奉行は漢城在陣の将兵総数が五万三千人であると確かめた。小西隊がもっとも損耗多く、日本を出陣したとき一万八千七百人であったが、健在でいる者はわずかに6,626人である。
宇喜多勢八千人も、5,352人が減耗していた。
碧蹄館の戦いを契機に明鮮軍、日本軍の和議への機運が高まって、明側の沈惟敬が和議を持ち込んできた。
沈惟敬の講和条件は、先に加藤清正に捕らえられた二王子の返還と釜山までの撤退であり、日本側は明国からの講和使の派遣と明国軍の遼東への撤収を求めた。
四月一日いちおうこの条件で和議がまとまり、日本軍は渡りに船とばかりに四月十八日から撤退をはじめた。
日本軍の撤退を受けて、四月二十日明国軍が漢城に入城した。だが主要な建物は焼きつくされていた。
平壌が明国軍によって回復されたとき怒った日本軍は、また民衆が内応することを疑い、正月の二十四日に漢城の民衆を虐殺し、建物・住居に火を放った。
戦争が始まって二年目の春は、悲惨な飢餓の春だった。百姓は種をまくことも耕すこともできず、餓死していった。
朝鮮政府の首脳部は徹底的に戦うことを主張したが、明国首脳はすでに講和に傾いていた。明国軍の駐留が長びくほど、兵糧を供給する朝鮮の官民は疲弊することになる。
和議の間、秀家は二月に三万の兵を率いて、幸州山城を攻めた。城が難攻不落の要害であったのと、朝鮮水軍の応援で日本軍は落城させることができなかった。
秀吉は自分の国書が順調に明側に受け入れられると信じていた。同時に朝鮮の南半分の割譲という要求を確実なものとするために、晋州城の攻撃を厳命した。
前年の十月、晋州城攻めが失敗したのち、一万五千の義兵の根拠地の城として、釜山から漢城にいたる道筋に「一揆」が横行して、日本軍を苦しめていた。
六月、秀家を総大将として、加藤清正、小西行長らが晋州城を攻めた。日本軍五万余人でこの城を包囲した。朝鮮側は兵七千と五万余の民衆でたて籠っていた。
六月二十に日、日本軍の攻撃が始まり、七日間掛かって陥落した。明軍はこの戦闘に傍観の立場をとった。
日本軍は、秀吉の命令で城中の兵、民衆すべて虐殺した。生き残った者はごく一部だった。
晋州城を落としても、和平推進、撤兵のほうは変わらない。朝鮮に留まる諸将に対して七月二十七日付の軍令が出され、本格的な城普請とそこでの在番を命じられる。
朝鮮にひきつづき在陣する軍勢は、加藤清正、鍋島直茂、小西行長ら四万余人となった。
帰国の諸将は、船の数がたりないのでクジ引きで乗船の順番を決めるありさまだった。
この戦いを総称して[文禄の役]という。
フロイスは、この戦争で朝鮮に渡った将兵と輸送員合わせて十五万人のうち、三分の一にあたる五万人が死亡した、と推定している。
敵によって殺されたものはわずかであり、大部分の者は飢餓、寒気、疾病によって死亡したのである。
敵も味方も、戦闘と飢えと病気の恐怖にさいなまれた悲劇の二年間だった。
イラストは文禄二年の普州城の戦い
「宇喜多秀家:慶長の役」へ続く