Essential Mediaから1月発売予定のCD その2
まず最初に注意書きを。今回のEssential Mediaからのリリースは、amazonによると「この商品はマニュファクチャー・オン・デマンド(以下、MOD)商品として発送される場合があります。MOD商品は、音源をCD-Rに録音しジャケットをプリントしてお届けいたします。ジャケットデザイン・歌詞・解説等、表記の内容・仕様などがオリジナルとは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。」とのことです。
さて、60~70年代に、いわゆる「企画もの」レコードを量産した謎のプロデューサー、Johnny Kitchen(以下JK。その実体は西海岸のジャズプレーヤー/アレンジャーだったJack Millman)に関連するタイトルが大量にエントリーされています。
彼が手がけたレコードは、よくあるグルーヴィインストにとどまらず、ジャズ、ロックンロール、R&B、サーフミュージック、サイケ、フォーク、ラウンジ、ラテン、アフロ、ファンク、カントリー、歌入りのヒッピーロック、アバンギャルド・・・などなど、あらゆるジャンルに及び(それらが一枚のアルバムに散りばめられていることも多い)、良くいえば万華鏡、悪くいえばガラクタ置き場のような様相を呈しています。
その多くは、(時期や演奏者の異なる)スタジオプロジェクト録音や、有名無名の既存の音源の流用・転用・サンプリング(複数のアルバムでの使い回しあり)や、それらに時にはサウンドコラージュやエフェクトを施して、ひとつの作品にまとめあげたものと推測されます。しかし、後述のSurf RidersやVictims of Chanceの2ndのように、そのまま他人のレコードを「産地偽装」したものもあり、いってみれば「なんでもあり」の「キング・オブ・企画もの」みたいな膨大なカタログを形作っています。
今回アップされているタイトルは、まだまだその氷山の一角だと思われます。(トラックリストおよび試聴はリンク先のamazonのページ、または登録情報の「その他のエディション:MP3 ダウンロード」のリンクページで。)

Crazy People
Bedlam (Johnny Kitchen Presents the Crazy People)
JK関連では、おそらくサイケファンには最も有名なタイトル。以前Gear FabからCDが出ていました。1968~69年ごろにカナダのCondorレーベルからリリースされた一連のタイトルのひとつ(そのため今でも「Johnny Kitchenはカナダ人らしい」という記事を見かける)。
本作は前述のJK流プロダクションによる「ごった煮」作品の好例なのですが、いつもよりちょっとやりすぎたら、はからずも「サウンドコラージュサイケの隠れた名作」と過大評価されてしまった、という感じでしょうか。ファズギターやハモンドオルガンによるグルーヴィチューン(歌入り)に、ナレーションや爆発音、悲鳴、ファンファーレ、鳥や虫の鳴き声、手回しオルガン、口琴、どこかのレコードから流用したとおぼしきオーケストラトラック、テープの逆回転などなど、さまざまなコラージュやエフェクトをほどこした「似非サイケ」な迷作。
これはJK物一般にいえることですが、「あれ?どっかで聴いたことあるぞ」というシークエンスが飛び出してきたりするので、そういう元ネタ探しみたいなことでも楽しめると思います。

Blues Train
Blues Train (Johnny Kitchen Presents the Blues Train)
こちらもCondorからのリリースでGear FabからCD再発されていたタイトル(Gear Fabの記述によるとオリジナルは1970年リリース)。
ファズギター入りのブルースロックがメインで、"Hoochie Koochie Man"や"Got My Mojo Workin"などのスタンダードカバーもやってます。Steppenwolfみたいな曲や、Country Joe & the Fishを連想させるシスコサウンド風ヒッピーサイケロックもあり。わりとちゃんとした歌入りバンドサウンド(に聴こえる)作品です。

Surf Riders
Ten Tons of Wet (Johnny Kitchen Presents the Surf Riders)
のちにMoby Grapeに参加するPeter Lewisが在籍していたLAのバンド、Cornellsの1963年のサーフインストアルバム"Beach Bound"を、中身はそのままに別の作品に仕立て上げてCondorからリリースしたもの。でも、オリジナルはモノなのに、こちらはステレオです。
ところで、先頭の曲はBeach Boysの"Sloop John B"みたいに聴こえますが、あれは1966年の"Pet Sounds"の曲で、こっちは1963年・・・。といっても、もちろんBeach BoysがCornellsをパクったわけではなくて、どちらも西インド諸島の民謡を元ネタにしているからだと思います。

Johnny Cole Unlimited
Hang on Sloopy
商品の説明では1970年のリリース(Condorレーベル)となっていますが、ほかにも1960年とか1965年とか、バラバラな記述が見られます。また、Johnny Coleではなく、Jimmy Cole Unlimitedと表記されたジャケットもあり、よくわかりません。ジャケットの女性?でボーカルを担当しているのは、JKの奥さんだったLudmilaという人とのことですが、あきらかにトラックごとに録音メンツ・音源が異なっているように聴こえます(胡散臭い)。
以下の4作も同じくCondorからのリリース。"Trio of Time / This World"はPeter, Paul & Maryタイプのフォークアルバム。"Jimmy Herald / Ride On"はカントリー~ロカビリー作品。"Los Choros Latinos / Latin Holiday"はラテンジャズアルバム。"Soul Mates / Black Strap Molasses"はR&B~ソウル/ファンク(歌入り)作です。
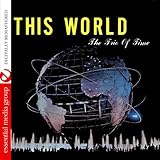
Trio of Time
This World (Johnny Kitchen Presents the Trio of Time)

Jimmy Herald
Ride on (Johnny Kitchen Presents Jimmy Herald)

Los Choros Latinos
Latin Holiday (Johnny Kitchen Presents Los Choros Latinos)

Soul Mates
Black Strap Molasses (Johnny Kitchen Presents the Soul Mates)
以下、次回に続く。
さて、60~70年代に、いわゆる「企画もの」レコードを量産した謎のプロデューサー、Johnny Kitchen(以下JK。その実体は西海岸のジャズプレーヤー/アレンジャーだったJack Millman)に関連するタイトルが大量にエントリーされています。
彼が手がけたレコードは、よくあるグルーヴィインストにとどまらず、ジャズ、ロックンロール、R&B、サーフミュージック、サイケ、フォーク、ラウンジ、ラテン、アフロ、ファンク、カントリー、歌入りのヒッピーロック、アバンギャルド・・・などなど、あらゆるジャンルに及び(それらが一枚のアルバムに散りばめられていることも多い)、良くいえば万華鏡、悪くいえばガラクタ置き場のような様相を呈しています。
その多くは、(時期や演奏者の異なる)スタジオプロジェクト録音や、有名無名の既存の音源の流用・転用・サンプリング(複数のアルバムでの使い回しあり)や、それらに時にはサウンドコラージュやエフェクトを施して、ひとつの作品にまとめあげたものと推測されます。しかし、後述のSurf RidersやVictims of Chanceの2ndのように、そのまま他人のレコードを「産地偽装」したものもあり、いってみれば「なんでもあり」の「キング・オブ・企画もの」みたいな膨大なカタログを形作っています。
今回アップされているタイトルは、まだまだその氷山の一角だと思われます。(トラックリストおよび試聴はリンク先のamazonのページ、または登録情報の「その他のエディション:MP3 ダウンロード」のリンクページで。)

Crazy People
Bedlam (Johnny Kitchen Presents the Crazy People)
JK関連では、おそらくサイケファンには最も有名なタイトル。以前Gear FabからCDが出ていました。1968~69年ごろにカナダのCondorレーベルからリリースされた一連のタイトルのひとつ(そのため今でも「Johnny Kitchenはカナダ人らしい」という記事を見かける)。
本作は前述のJK流プロダクションによる「ごった煮」作品の好例なのですが、いつもよりちょっとやりすぎたら、はからずも「サウンドコラージュサイケの隠れた名作」と過大評価されてしまった、という感じでしょうか。ファズギターやハモンドオルガンによるグルーヴィチューン(歌入り)に、ナレーションや爆発音、悲鳴、ファンファーレ、鳥や虫の鳴き声、手回しオルガン、口琴、どこかのレコードから流用したとおぼしきオーケストラトラック、テープの逆回転などなど、さまざまなコラージュやエフェクトをほどこした「似非サイケ」な迷作。
これはJK物一般にいえることですが、「あれ?どっかで聴いたことあるぞ」というシークエンスが飛び出してきたりするので、そういう元ネタ探しみたいなことでも楽しめると思います。

Blues Train
Blues Train (Johnny Kitchen Presents the Blues Train)
こちらもCondorからのリリースでGear FabからCD再発されていたタイトル(Gear Fabの記述によるとオリジナルは1970年リリース)。
ファズギター入りのブルースロックがメインで、"Hoochie Koochie Man"や"Got My Mojo Workin"などのスタンダードカバーもやってます。Steppenwolfみたいな曲や、Country Joe & the Fishを連想させるシスコサウンド風ヒッピーサイケロックもあり。わりとちゃんとした歌入りバンドサウンド(に聴こえる)作品です。

Surf Riders
Ten Tons of Wet (Johnny Kitchen Presents the Surf Riders)
のちにMoby Grapeに参加するPeter Lewisが在籍していたLAのバンド、Cornellsの1963年のサーフインストアルバム"Beach Bound"を、中身はそのままに別の作品に仕立て上げてCondorからリリースしたもの。でも、オリジナルはモノなのに、こちらはステレオです。
ところで、先頭の曲はBeach Boysの"Sloop John B"みたいに聴こえますが、あれは1966年の"Pet Sounds"の曲で、こっちは1963年・・・。といっても、もちろんBeach BoysがCornellsをパクったわけではなくて、どちらも西インド諸島の民謡を元ネタにしているからだと思います。

Johnny Cole Unlimited
Hang on Sloopy
商品の説明では1970年のリリース(Condorレーベル)となっていますが、ほかにも1960年とか1965年とか、バラバラな記述が見られます。また、Johnny Coleではなく、Jimmy Cole Unlimitedと表記されたジャケットもあり、よくわかりません。ジャケットの女性?でボーカルを担当しているのは、JKの奥さんだったLudmilaという人とのことですが、あきらかにトラックごとに録音メンツ・音源が異なっているように聴こえます(胡散臭い)。
以下の4作も同じくCondorからのリリース。"Trio of Time / This World"はPeter, Paul & Maryタイプのフォークアルバム。"Jimmy Herald / Ride On"はカントリー~ロカビリー作品。"Los Choros Latinos / Latin Holiday"はラテンジャズアルバム。"Soul Mates / Black Strap Molasses"はR&B~ソウル/ファンク(歌入り)作です。
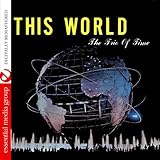
Trio of Time
This World (Johnny Kitchen Presents the Trio of Time)

Jimmy Herald
Ride on (Johnny Kitchen Presents Jimmy Herald)

Los Choros Latinos
Latin Holiday (Johnny Kitchen Presents Los Choros Latinos)

Soul Mates
Black Strap Molasses (Johnny Kitchen Presents the Soul Mates)
以下、次回に続く。
Essential Mediaから1月発売予定のCD その1

Twentieth Century Zoo
Thunder on a Clear Day
ヘヴィサイケ特集でも取り上げたTwentieth Century Zooは、アリゾナ州フェニックスで結成後、西海岸に出て活動していた5人組。"Thunder on a Clear Day"は1968年にVaultからリリースされた唯一のアルバムです(以前SundazedやRadioactiveからCD再発されていた)。
激歪ファズギターにチープなオルガン。ナイーブ系のボーカル。イノセントなガレージフィーリングあふれる楽曲・・・。まったりとしたメロウチューンからヘヴィサイケナンバーまで、サイケファンには堪らない「ど真ん中」のサイケデリアを堪能させてくれます。
トラックリストと試聴はこちら。

Ashes
Ashes
AshesはPeanut Butter Conspiracyの前身で、Spencer DrydenがJefferson Airplaneに参加する前に在籍していたことで知られるLAのバンド。本作は1970年にVaultからリリースされた唯一のアルバムです。
PBCの前身なのになぜ1970年かというと、AshesがPBCへと発展して1967~68年に2枚のアルバムを発表したのち、創成メンバーのJohn Merrillが1968年にAshesをリユニオンして本作をレコーディング。しかし、リリースは2年近く棚上げされてしまっていたためです。
オリジナルメンバーとしてはベースのAlan Brackettもクレジットされていますが、看板の歌姫Barbara "Sandi" Robisonは参加しておらず、かわりにPat Taylorという女性がリードボーカルをつとめています。でも、Patの歌声も決してSandiに引けを取らない素晴らしいもので、こちらも60s男女混声グループファンにはマストな内容となっています。
トラックリストと試聴はこちら。

Pugh Rogefeldt
Ja, Da a Da
Pugh Rogefeldtはスウェーデンのシンガー&ギタリスト。"Ja, da a da"は1969年のデビューアルバムです。
本作の最大の特徴は、全編スウェーデン語で歌われていて、「辺境サイケ」なムードが横溢していること。「北欧版Erkin Koray」といった感じでしょうか。ワールドワイドにはあまり名は知られていないようですが、ロックセンスやソングライティング、個性的な歌声にとても非凡(というか変態!)なものがあり、トルコ勢同様、一度ハマると中毒になりそうな危険アイテムといえるかもしれません。後半はアコギをフィーチャーしたアシッドフォークロックチューンが主流となりますが、特に前半に登場するサイケなファズギターは聴きもの。
トラックリストと試聴はこちら。
Kismetから1月発売予定のCD

Alexander's Timeless Bloozband
For Sale
Alexander's Timeless Bloozbandはサンディエゴ出身の5人組。"For Sale"は1968年にUniからリリースされたセカンドアルバムです。
バンド名から推測されるように、サイケ風味のブルースロックが基本で、フルートやホーンの入ったよりジャジーなナンバーや、エキゾなインプロ主体の曲、ジャグバンドチューンなどもやっています。Electric Flag、Canned Heat、初期のGrateful Deadといったところに類するアルバムで、シスコサウンド的なテイストもあります。
実際彼らはよくシスコのステージにも立っていたようで、1968年のAvalon BallroomのポスターにSons of Champlinらとともに名前が載っているのを見たことがあります。なにより、本作はサイケデリックポスター風のジャケットが素晴らしく、ちょっと残念な「やさぐれ」系のリードボーカルや、スタジオライブ的なラフな作りの内容を差し引いても、コレクションに加えておきたい一枚です。
1967年のセルフタイトルのデビュー作はレアなプライベートイシューらしく、私は聴いたことがありません。ちなみに、メンバーのCharles Lamontは1969年にソロアルバム、"A Legend in His Own Mind"をリリースしています(→動画)。
Track Listing :
1. Love So Strong
2. Horn Song
3. Plastic Is Organic
4. Swannanoa Tunnel
5. Rosie
6. Front Man
7. Tight Rope Walker
8. Life
9. Darlin'
10. Help Me
11. Firefly

Tripsichord Music Box
Tripsichord Music Box
これはレココレ・サイケ号でも、サイケ本「サイケデリック・ムーズ」でも紹介されていた基本アイテムのひとつ。以前、こちらのヘヴィサイケ特集でも取り上げたことがありました。
TripsichordはもともとはNowという名前で活動していたLAのバンド。シスコサウンドのキーパーソンのMatthew Katz(*1)に見出され、サンフランシスコに移ってTripsichord Music Boxとして再出発したのでした。
アルバムは1969年に録音され、1970年にKatzのSan Francisco SoundレーベルからデモLPが(数十枚?)プレスされるも発売には至らず、翌71年にJanusというレーベルから微妙にミックスが異なるバージョンで、ようやく正式にリリースされました。ジャケットの表にはTripsichordとのみ表記されていますが、これは彼らが1970年にバンド名を短くTripsichordと改めたため。
アルバムは大雑把にいうとQuicksilver Messenger ServiceとMoby Grapeの中間あたりの音。でも、それらを昇華してさらに高めたような印象があり、忘れがたい楽曲とギターオリエンテッドなバンドアンサンブルと独特のムードが三位一体となったユニークなものです。シスコサイケ的なファズギターによるヘヴィネスに、どこかミステリアスなメロウ&メランコリックさと浮遊感を兼ね備えたサウンドは、多くのサイケレビューでも絶賛されています。
今回の再発は以前出ていたAkarma盤と同内容のようで、San Francisco Soundレーベルのコンピ"Fifth Pipe Dream"(1968)収録の3曲(1967年ごろの初期の録音といわれるノンLP曲)と、1969年のシングル2曲によるボーナストラック5曲が収録されています。これらのボーナス曲も本編に劣らず素晴らしいので、なぜこのバンドがアルバム一枚だけで終わってしまったのか謎です。
*1
San Francisco Sound Recordsのオーナー。Jefferson Airplane, Moby Grape, It's a Beautiful Dayらのマネージメントをつとめた。結構アクの強い人物だったようで、アーティストとのトラブルが絶えず、JAを含む多くのバンドと訴訟沙汰になっている。Tripsichordとも「Fake Grape事件」(彼らにニセMoby Grapeとして公演させた)を起こしている。
Track Listing :
1. On The Last Ride
2. We Have Passed Away
3. Black Door
4. The New World
5. Son Of The Morning
6. Short Order Steward
7. The New World
8. Fly Baby
9. Everlasting Joy
Bonus Tracks :
10. You're The Woman
11. It's Not Good
12. Family Song
13. Times & Seasons
14. Sunday The Third

Sandy Coast
Shipwreck
Sandy Coastはオランダのバンド。その歴史は古く、JanとHansのVermeulen兄弟が1961年に結成したスキッフルグループに遡ります。1965年にシングルデビューした彼らは、時代とともに、ビートポップからフォークロック、アートロックやプログレの要素を取り入れたサウンドへと変遷しながら、1967年から1973年の間に5枚のアルバムを発表しています(80年代以降も活動している模様)。
本作"Shipwreck"は1969年にリリースされたサードアルバム。オープニングのロックオペラ的な14分に及ぶタイトルナンバーを聴くと、オルガンヘヴィサイケからプログレにいたる途上のアートロック作品・・・かと思うと、そのあとの曲はいたって「まっとう」なブリティッシュ系のロックという印象です。違和感のない英語で歌われる、サイケ期ビートルズへのオマージュを秘めた、(時にはヘヴィ、時にはメロウな)ポップサイケ風味の良質な楽曲が続きます。そのへんの、冒険的な前半と、安定志向の後半のチグハグ感が賛否を分けるアルバムかもしれません。
今回の再発は、以前オランダPseudonymから再発されていたCDと同じ、ノンアルバムトラックのボーナス4曲が収録されています。
Track Listing :
1. Shipwreck a) Overture 3:20 b) Departure c) Shipwreck d) Saved e) Hope & Despair f) Land g) The End
2. I May Happily Forget
3. North Canadian Paradise
4. Blue Blackman's Blues
5. Advice
6. Timothy
7. Re Re Le Loup
Bonus tracks :
8. Deep Deep Down
9. Back To The City
10. Eleanor Rigby
11. In My Opinion
Amory Kaneの2nd再発

Amory Kane
Just To Be There (韓国盤, 紙ジャケット仕様)
Amory Kaneが1970年に英CBSからリリースしたセカンドアルバム、"Just to Be There"が韓国Big PinkからCD再発されています。
Amory Kane(本名Jack Daniel Kane)は1967年にロンドンで音楽活動をはじめ、MCAからのデビュー作"Memories of Time Unwound"(1968)も英国で録音・リリースされたためFuzz, Acid & Flowersには載っていないのですが、もともとはサンフランシスコ生まれのアメリカ人。父親が軍関連の仕事に就いていたため、子供の頃はロンドンの学校に通ったり、またアメリカに戻ってテキサスで過ごしたりしています。
その後ふたたびサンフランシスコに戻って、ベイエリアの北のNovatoで十代後半を送り、1967年1月のHuman Be-Inに参加。その時なぜか彼は、全米の若者が目指そうとしていたサンフランシスコを離れて、ヨーロッパに向って旅立つことを決意したのでした。
というわけで、シスコサウンド関連の裏アイテムともいえなくない本作。特に前半(A面)は、Dino ValentiやAlexander Spenceにもつながる、メロウ&メランコリックなアシッドフォーク大会となっています。でも、現代音楽系アーティストで、Pink FloydやBridget St Johnとの仕事でも知られるRon Geesinによるものと思われるアレンジやエフェクトが、シスコ(アメリカン)サイケとはまた少し異質なサイケデリアを演出しているのが聴きもの。
Dino作の"Get Together"ではじまる後半(B面)はアシッド感がゆるんで、カントリー風味のおだやかな曲調が主流となるのですが、それでもアルバムは古くからアシッドフォークファンに人気のアイテムだったようです。ちなみに、バックにはFairport ConventionのDave Peggらが参加しています。
ところで、ZepのJohn Paul Jonesが参加しているという68年のデビュー作の方は、わりと普通っぽいポップなSSW作品という印象です。We Fiveのヒットでお馴染みの"You Were On My Mind"(オリジナルはIan & Sylvia)のカバーや、ポップサイケチューン、アシッドフォークな曲もやってるんですが、メインストリーム寄りでやや過剰なストリングアレンジがサイケ感を殺いでしまっている感もあります。
Track Listing :
1. Evolution
2. Llanstephan Hill
3. Four Ravens
4. Golden Laces
5. Get Together
6. After Vytas Leaves
7. Childhood's End
8. The Inbetween Man
9. The Hitchhiker's Song
10. Tenderly Stooping Low
Caravanの"Man & Buffalo"再発

Caravan
Man & Buffalo (アナログLPはこちら)
ハンスポコラ本で「六つ星」が付けられていた、タイのCaravan(カラワン)による70年代の激レア作が、Strawberry Rainからリイシューされます(11月20日発売予定)。
カラワンは70年代タイの学生運動とともに生まれた政治色の強いフォークロックユニット。それがゆえに、グループのメンバーは一時国外逃亡を余儀なくされたこともあったようです。私はこれまで聴いたことなかったんですが、こちらで試聴した限りでは、日本の70年代フォークを思わせるような内向きの哀感があったり、Trafficの"John Barleycorn"(原曲はトラッド)のカバーらしき曲をやっていたり、アシッドフォーク度も高そうで、なかなか良さげです。
Del Shannonの"Home & Away"再発(続)

Del Shannon
Home & Away (from UK)
少し前にこちらでお知らせした、Del Shannonの"Home & Away"のCD再発(Now Soundsから11月27日発売予定)ですが、ボーナストラックの5曲を含めて、2006年のEMI盤と同じ内容になっている模様です。でも、ジャケットはサイケなものから差し替えられていて、ちょっと残念・・・。
詳細はリリース元のNow Soundsのページで。
TRACKS :
1. IT'S MY FEELING
2. MIND OVER MATTER
3. SILENTLY
4. CUT AND COME AGAIN
5. MY LOVE HAS GONE
6. LED ALONG
7. LIFE IS BUT NOTHING
8. EASY TO SAY
9. FRIENDLY WITH YOU
10. HE CHEATED
11. RUNAWAY '67
BONUS TRACKS :
12. LED ALONG (Mono 45)
13. MIND OVER MATTER (Mono 45)
14. RUNAWAY '67 (Mono 45)
15. HE CHEATED (Mono 45)
16. SILENTLY (Mono 45)
Fred Neilの2タイトル再発
Tim Buckley, Dino Valente, Richie Havensらに多大な影響を与えた「アシッドフォークの父」Fred Neil。Jefferson Airplaneをはじめ、60年代のフォークロック~サイケバンドの定番曲だった"Other Side of This Life"や、映画"Midnight Cowboy"(「真夜中のカーボーイ」)の主題曲としてニルソンが歌った "Everybody's Talkin"など、後年さまざまなアーティストにカバーされ続ける名曲を数多く生み出しました。
Fred Neil自身は、ソロ名義としては1965~71年の間に4枚のアルバムを出しているんですが、一般に知られているのは実質上のソロデビュー作"Bleecker and MacDougal"(1965)と、1966年の次作"Fred Neil"("Everybody's Talkin'"のタイトルで1969年にリイシュー)くらいではないでしょうか。
その不当に無視されていた?(*1)2枚のアルバム、"Sessions"(1967)と"Other Side of This Life"(1971)が11月にCD再発されます。

Fred Neil
Sessions
タイトルが示唆するように、数本のアコースティックギターとウッドベースによる即興的なセッションが主体となっている作品。いまでいう「デモ音源集」みたいなアルバムなんですが、これほど野太いデモ録音も他にないだろうと思えるような、確信に満ちたアシッドフォーキーぶりは、もうこの人の独壇場という感じです。
単純なコード進行でとりとめもなく続く催眠的なセッションの中に、アシッドフォークの本源のようなスゴ味を聴き取ることができます。シンコーのディスクガイド「アシッド・フォーク」で、「フレッド・ニールによるトリップ・ミュージックの新たな座標」と評されていたように、彼のアルバムの中でも最もアシッド度の高い作品ではないでしょうか。
Tracks:
1. Felicity
2. Send Me Somebody To Love
3. Merry Go Round
4. Look Over Yonder
5. Fools Are A Long Time Coming
6. Looks Like Rain
7. Roll On Rosie

Fred Neil
Other Side of This Life
LPのA面にあたる前半の6曲はWoodstock(NY)のElephant Clubでの実況録音。Fredの弾き語り+Monte Dunnのアコースティックギターというシンプルな編成で代表曲を披露しています。後半の5曲は、Dino Valente, Stephen Stills, Gram Parsonsらが参加した、さまざまなスタジオセッション音源が集められています。
こちらもレアトラック集みたいなアルバムですが、特に前半のライブは、思わずスピーカーの前で固まってしまうような強い磁力を秘めています。
Tracks:
1. Other Side Of This Life
2. Roll On Rosie
3. The Dolphins
4. That's The Bag I'm In
5. Sweet Cocaine
6. Everybody's Talkin'
7. Come Back Baby (with Les McCann)
8. Badi-Da (with Vince Martin)
9. Prettiest Train
10. Ya Don't Miss Your Water (with Gram Parsons)
11. Felicity
*1
とはいってもCD化されていないってことではなく、"Sessions"は日本でCDが出ていたし、同じジャケのRev-Olaのコンピ"The Sky Is Falling"は、"Other Side of This Life"に4曲のボーナストラックを追加した内容だったし、Collectors' Choiceの2枚組コンピ"Many Sides of Fred Neil"には、この2作が同じ曲順でまるまる全曲収録されていた。「不当に無視されている」というのは、あくまでも私の主観です。
Fred Neil自身は、ソロ名義としては1965~71年の間に4枚のアルバムを出しているんですが、一般に知られているのは実質上のソロデビュー作"Bleecker and MacDougal"(1965)と、1966年の次作"Fred Neil"("Everybody's Talkin'"のタイトルで1969年にリイシュー)くらいではないでしょうか。
その不当に無視されていた?(*1)2枚のアルバム、"Sessions"(1967)と"Other Side of This Life"(1971)が11月にCD再発されます。

Fred Neil
Sessions
タイトルが示唆するように、数本のアコースティックギターとウッドベースによる即興的なセッションが主体となっている作品。いまでいう「デモ音源集」みたいなアルバムなんですが、これほど野太いデモ録音も他にないだろうと思えるような、確信に満ちたアシッドフォーキーぶりは、もうこの人の独壇場という感じです。
単純なコード進行でとりとめもなく続く催眠的なセッションの中に、アシッドフォークの本源のようなスゴ味を聴き取ることができます。シンコーのディスクガイド「アシッド・フォーク」で、「フレッド・ニールによるトリップ・ミュージックの新たな座標」と評されていたように、彼のアルバムの中でも最もアシッド度の高い作品ではないでしょうか。
Tracks:
1. Felicity
2. Send Me Somebody To Love
3. Merry Go Round
4. Look Over Yonder
5. Fools Are A Long Time Coming
6. Looks Like Rain
7. Roll On Rosie

Fred Neil
Other Side of This Life
LPのA面にあたる前半の6曲はWoodstock(NY)のElephant Clubでの実況録音。Fredの弾き語り+Monte Dunnのアコースティックギターというシンプルな編成で代表曲を披露しています。後半の5曲は、Dino Valente, Stephen Stills, Gram Parsonsらが参加した、さまざまなスタジオセッション音源が集められています。
こちらもレアトラック集みたいなアルバムですが、特に前半のライブは、思わずスピーカーの前で固まってしまうような強い磁力を秘めています。
Tracks:
1. Other Side Of This Life
2. Roll On Rosie
3. The Dolphins
4. That's The Bag I'm In
5. Sweet Cocaine
6. Everybody's Talkin'
7. Come Back Baby (with Les McCann)
8. Badi-Da (with Vince Martin)
9. Prettiest Train
10. Ya Don't Miss Your Water (with Gram Parsons)
11. Felicity
*1
とはいってもCD化されていないってことではなく、"Sessions"は日本でCDが出ていたし、同じジャケのRev-Olaのコンピ"The Sky Is Falling"は、"Other Side of This Life"に4曲のボーナストラックを追加した内容だったし、Collectors' Choiceの2枚組コンピ"Many Sides of Fred Neil"には、この2作が同じ曲順でまるまる全曲収録されていた。「不当に無視されている」というのは、あくまでも私の主観です。
Jerry Coleの"Surf Age"再発

Jerry Cole
Surf Age
サイケファンにはThe IdやAnimated Eggの「立役者」として知られるギタリスト、Jerry Coleによる1964年のアルバム、"Surf Age"がSundazedからCD再発されます(11月27日発売予定)。
本作は彼がCrownからCapitolに鞍替えしてリリースした、Jerry Cole & His Spacemen名義の3枚のアルバムの中の1枚。バックにはHal Blaineら西海岸の名セッションマンが参加しているようです。
60年代前半のサーフインスト作品ということで、サイケな音はあまり期待できませんが、それでもAnimated Eggのトラックを連想させるような、あのパキパキなギターが随所で楽しめます。下のトラックリストは、Sundazedから先にリリースされたアナログ盤のものです。
1. Surf Age
2. Martian Surf
3. Night Rumble
4. Rosarita Surf
5. Movin’ Surf
6. Power Surf
7. Bronze Surfer
8. Deep Surf
9. Ride-Um!
10. Jerry’s Jump
11. One Color Blues
12. Racing Waves
Orphan Egg 再発

Orphan Egg
Orphan Egg
以前RadioactiveからリイシューされていたOrphan Eggの唯一作(1968)が、ボーナス2曲を追加してCD再発されます(Pilot から11月20日発売予定)。
Orphan Eggは西海岸(サンノゼ)のハイスクールバンドを起源とする5人組。1967年のVox Battle of the Bands(全米)コンテストに優勝し、その審査員をつとめたGuy Hemricらによってプロデュースされたのが本作です。ヘヴィサイケあり、メロウチューンあり、ブルースジャムあり、かと思えば英国ビートポップ風の曲が幅をきかせる、といった具合で、アルバムとしてはおせじにも名盤とは言いがたい、ややピントのズレた作品。
それでも、Blue CheerやQMSらシスコサイケからの影響がはっきりと聴き取れるファズギターチューンには耳を惹くものがあり、特にオープニングナンバーの "Falling"では私好みの必殺リフを披露してくれます。歌や演奏にキラリと光る才能があり、もっと方向性を練ったアルバムをじっくりと制作していれば、かなり成功できたかもしれないという残念さも感じます。
ちなみに、前述のバンドコンテストのご褒美として、映画サントラへのエントリーが約束されたのですが、その作品が先ごろReel TimeからCD再発された"Cycle Savages"(1969)なのでした(→過去記事)。
ところで、ボーナストラックの2曲ですが、ミックス違いの"Falling"と"We Have Already Died"ということで、これらはその"Cycle Savages"の音源から取られたものだと思います。過去記事でも指摘したように、"We Have Already Died"はオリジナルLPの表記間違いによってOrphan Eggの曲とされてしまったのですが、実際はBoston Tea Partyの曲(→動画)です。
Track Listing :
1. Falling
2. That's The Way
3. Mourning Electra
4. Bird Dog
5. It's Wrong
6. Ain't That Lovin' You Baby
7. Look At Me
8. Deep In The Heart Of Nebraska
9. Don't Go To Him
10. Circumstance
11. Unusual State Of Mind
12. Rock Me Baby
Bonus Tracks :
13. We Have Already Died
14. Falling (alt. mix)
Paper Garden再発

Paper Garden
Paper Garden
レココレ・サイケ号の巻頭カラー頁にジャケットが載っていたNY産のポップサイケ佳作、"Paper Garden"(1969)がRelicsからCD再発されます(10月23日発売予定)。
コアとなっているのは、サージェントペパーズからの影響が色濃い英国風のポップサイケナンバーなんですが、同じ東海岸のFaine Jadeとも共通する、どこか醒めたようなクールな響きがします。ジプシースウィングのようなグッドタイミーな要素や、"Electric Psychedelic Sitar Headswirlers Vol.2"にも収録されていた"Man Do You"のようなシタール入り似非東洋風の曲。メロウ&メランコリックなソフトサイケチューンからファズギターによるヘヴィな曲まで、ストリングスやホーンやエフェクト満載の、ジャケのイメージにたがわぬカラフルなアルバム。それなのに、なんだか上の方から俯瞰して世界を眺めているような「距離感」があって、そのへんが私には気持ち良いです。
全曲バンドのオリジナルで、音楽的才能やアイディアがありあまりすぎて、一枚のアルバムには収めきれなかった、みたいな心残りな余韻を残すのもニクいところ。いま聴いても不思議に古さを感じさせない好盤。
Track Listing :
1. Gypsy Wine
2. Sunshine People
3. Way Up High
4. Lady's Man
5. Mr. Mortimer
6. Man Do You
7. Raining
8. I Hide
9. Raven
10. A Day















