40年前の今年を振り返る
いよいよ暮れも押し迫ってまいりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
今年を振り返ってみると、1月にこのブログを始めたということもあって、いつにも増して60sサイケを中心とした「後ろ向き」な音楽ライフだったなと自負しております。そんなこんなで「2005年のベスト」みたいな企画ができるほど新譜を聴いてないし、実際のところ、リイシュー物やボックスなんかも含めて、これといって目立った収穫のない年だったような気がします。(映画も、なんだかパッとしなかったし・・・。)
というわけで、2005年は「サイケデリック生誕40周年」だったという因果で、40年前の1965年の出来事をシスコの(黎明期)サイケデリックシーンを中心に追ってみることにしました。
1月
・ジョンソン大統領、年頭教書で「偉大な社会」(Great Society)建設を提案。(人種や性などの差別を撤廃した福祉社会実現の理想をかかげる。)
2月
・21日、Malcolm X 暗殺される。
3月
・米軍、ベトナムの「北爆」(ローリングサンダー作戦)を開始。
・Bob Dylan、フォークからロックへの過渡的作品となる"Bringing It All Back Home"を発表。
4月
・Grateful Deadの前身、Warlocks 結成。
・Beau Brummels、デビューアルバムの"Introducing"発売。
5月
・Byrdsが4月に出したシングル"Mr. Tambourine Man"が全米(全英)で1位の大ヒットとなる。(ボーカルパートを除いて、この録音に参加しているのは12弦ギターのロジャー・マッギンのみで、あとはレオン・ラッセル、ハル・ブレインなどのスタジオミュージシャンが演奏しているというのは有名な話。)
6月
・21日、Byrdsのデビューアルバム"Mr. Tambourine Man"発売。ボブ・ディランとビートルズを融合した「フォークロック」は、やがて本家のビートルズも影響されるほどのインパクトを与え、後継者が続出した。
・同21日、ヴァージニア・シティのRed Dog SaloonでCharlatansがデビューアクト。LSDとライトショーをステージで用いた最初の「サイケデリック」パフォーマンスとされる。また、このショーのポスターはのちに"The Seed"と呼ばれ、サイケデリック・ポスターの第一号となる。(詳細はこちら。)

The Byrds
Mr. Tambourine Man
7月
・The Doors 結成。
・25日、ニューポート・フォーク・フェスティバルでBob Dylanがフォークギターをエレキギターに持ち替える。それはまさに、フォークからロックへの転換の瞬間だった。ちなみに、このときバックをつとめたのはポール・バターフィールド・ブルース・バンド。
8月
・Beatles、映画の公開に続いて、アルバム"Help!"を発売。
・13日、シスコのMatrixオープン。初ステージを務めたJefferson Airplaneがデビュー。
・Bob Dylan、史上に燦然と輝く革命的ロックアルバム"Highway 61 Revisited"を発表。

Bob Dylan
HIGHWAY 61 REVISITED
9月
・シスコのライター、Michael Fallonが記事で初めて"hippie"に言及。
10月
・16日、Family Dog主催の"A Tribute to Dr. Strange"と題する「ダンスパーティー」がLongshoreman's Hallで開かれる。これはシスコで最初のサイケデリックなダンス&ミュージック&ライトショーの「ハプニングス」だった。出演したのはJefferson Airplane, Charlatans, (Grace Slickの)Great Societyなど。
11月
・3日、WarlocksがシスコのAutumn Recordsで、Emergency Crewとして6曲のデモを録音。その音源は"Birth of the Dead"で聴くことができる。
・ケン・キージー、最初のアシッドテストを開催。ハウスバンドとしてWarlocksが参加。
・13th Floor Elevators 結成。

The Grateful Dead
Birth of the Dead
12月
・10日、ビル・グラハムのFillmoreコンサートの原形(Mime Troupe Benefit - Appeal II)開催。Warlocksから改名したGrateful DeadやJefferson Airplane, Great Society, Mystery Trendなどが出演。
・Beatles、"Rubber Soul"をリリース。

ざっと見渡しただけですが、激動の時代の息吹が感じられると思います。特に象徴的なのが、リンドン・ジョンソンの年頭教書。"Great Society"という高邁な理想をかかげながらも、現実には「北爆」によるベトナム戦争がますます泥沼化していく・・・。理想と現実が極度に分裂した「サイケデリック」な60年代後半へと雪崩れ込んでゆくのでした。
今年を振り返ってみると、1月にこのブログを始めたということもあって、いつにも増して60sサイケを中心とした「後ろ向き」な音楽ライフだったなと自負しております。そんなこんなで「2005年のベスト」みたいな企画ができるほど新譜を聴いてないし、実際のところ、リイシュー物やボックスなんかも含めて、これといって目立った収穫のない年だったような気がします。(映画も、なんだかパッとしなかったし・・・。)
というわけで、2005年は「サイケデリック生誕40周年」だったという因果で、40年前の1965年の出来事をシスコの(黎明期)サイケデリックシーンを中心に追ってみることにしました。
1月
・ジョンソン大統領、年頭教書で「偉大な社会」(Great Society)建設を提案。(人種や性などの差別を撤廃した福祉社会実現の理想をかかげる。)
2月
・21日、Malcolm X 暗殺される。
3月
・米軍、ベトナムの「北爆」(ローリングサンダー作戦)を開始。
・Bob Dylan、フォークからロックへの過渡的作品となる"Bringing It All Back Home"を発表。
4月
・Grateful Deadの前身、Warlocks 結成。
・Beau Brummels、デビューアルバムの"Introducing"発売。
5月
・Byrdsが4月に出したシングル"Mr. Tambourine Man"が全米(全英)で1位の大ヒットとなる。(ボーカルパートを除いて、この録音に参加しているのは12弦ギターのロジャー・マッギンのみで、あとはレオン・ラッセル、ハル・ブレインなどのスタジオミュージシャンが演奏しているというのは有名な話。)
6月
・21日、Byrdsのデビューアルバム"Mr. Tambourine Man"発売。ボブ・ディランとビートルズを融合した「フォークロック」は、やがて本家のビートルズも影響されるほどのインパクトを与え、後継者が続出した。
・同21日、ヴァージニア・シティのRed Dog SaloonでCharlatansがデビューアクト。LSDとライトショーをステージで用いた最初の「サイケデリック」パフォーマンスとされる。また、このショーのポスターはのちに"The Seed"と呼ばれ、サイケデリック・ポスターの第一号となる。(詳細はこちら。)

The Byrds
Mr. Tambourine Man
7月
・The Doors 結成。
・25日、ニューポート・フォーク・フェスティバルでBob Dylanがフォークギターをエレキギターに持ち替える。それはまさに、フォークからロックへの転換の瞬間だった。ちなみに、このときバックをつとめたのはポール・バターフィールド・ブルース・バンド。
8月
・Beatles、映画の公開に続いて、アルバム"Help!"を発売。
・13日、シスコのMatrixオープン。初ステージを務めたJefferson Airplaneがデビュー。
・Bob Dylan、史上に燦然と輝く革命的ロックアルバム"Highway 61 Revisited"を発表。

Bob Dylan
HIGHWAY 61 REVISITED
9月
・シスコのライター、Michael Fallonが記事で初めて"hippie"に言及。
10月
・16日、Family Dog主催の"A Tribute to Dr. Strange"と題する「ダンスパーティー」がLongshoreman's Hallで開かれる。これはシスコで最初のサイケデリックなダンス&ミュージック&ライトショーの「ハプニングス」だった。出演したのはJefferson Airplane, Charlatans, (Grace Slickの)Great Societyなど。
11月
・3日、WarlocksがシスコのAutumn Recordsで、Emergency Crewとして6曲のデモを録音。その音源は"Birth of the Dead"で聴くことができる。
・ケン・キージー、最初のアシッドテストを開催。ハウスバンドとしてWarlocksが参加。
・13th Floor Elevators 結成。

The Grateful Dead
Birth of the Dead
12月
・10日、ビル・グラハムのFillmoreコンサートの原形(Mime Troupe Benefit - Appeal II)開催。Warlocksから改名したGrateful DeadやJefferson Airplane, Great Society, Mystery Trendなどが出演。
・Beatles、"Rubber Soul"をリリース。

ざっと見渡しただけですが、激動の時代の息吹が感じられると思います。特に象徴的なのが、リンドン・ジョンソンの年頭教書。"Great Society"という高邁な理想をかかげながらも、現実には「北爆」によるベトナム戦争がますます泥沼化していく・・・。理想と現実が極度に分裂した「サイケデリック」な60年代後半へと雪崩れ込んでゆくのでした。
第41回 The Litter

The Litter
Distortions
ガレージパンクの基本中の基本としては、(レココレのサイケ特集もそうでしたが、)The Sonicsがその筆頭に挙げられていることが多いようです。もちろん、パンクファンの私はSonicsも大好きですが、そのスタイルはガレージパンクのコアな部分そのもの、あまりにもローでプリミティブで、サイケ的な「ゆらぎ」や「ねじれ」をすべて剥ぎ取ったような攻撃的な音は、同じ60sサウンドという嗜好のもとで聴かれているとはいえ、ある意味サイケとは正反対の感覚ではないか?と思ったりもします。
そういう意味で、一般のサイケファンには、こちらのThe Litterの方をお勧めしたいと思います。(逆にいうと、純粋なガレージパンカーには不満な部分もあるかもしれません。) The Litterといえば、Pebblesの第1集の1曲目に収録されているガレージパンク・クラシック"Action Woman"があまりにも有名ですが、そういったパンキッシュなものだけではなく、多くの曲から音の隙間やギターのディストーション/フィードバックに、サイケ的な間合いや歪みを容易に聴き取ることができます。(当時のサイケ定番の"Codine"や、これはボーナストラックですが"Hey Joe"なんかもやってたりします。)
代表作のデビューアルバム"Distortions"(1967)の特徴としては、まず、The WhoやSmall Faces, YardbirdsにCreamといった英国バンドのカバー曲が目立つこと。しかし、それらも違和感なく自らのガレージサイケサウンドにしていて、(数少ない)オリジナルと同じくらい力強く響きます。
レココレのサイケ特集号の解説には、どういう根拠からか本作に対して、「米サイケデリック最高作の呼び声高き」なんて形容がされていますが、これはかなり割り引いて受け取ってもいいでしょう。それでも、ガレージパンクとサイケデリックの美味しいところを抽出したような"Distortions"は、傍に置いて末永く聴ける一枚であることに間違いありません。
ちなみに、セカンドの"$100 Fine"(1968)では、ほとんどがオリジナル曲になっていて、こちらもなかなか良いです。サードの"Emerge"(1969)になると、プレ・ハードロック的なサウンドになって、なんだか2nd以降のBlue Cheerみたいな中途半端な感じになるのですが、(私のように)B級ヘヴィサイケも好きという人間にとっては、これはこれでまた面白かったりします。

Litter
$100 Fine

Litter
Emerge

The Litter
Distortions/$100 Fine
第40回 We the People

We the People
Mirror of Our Minds
ガレージパンクといえば、サイケファンの中でも、あまり得意ではないという人が結構おられるようですが、幸か不幸か、私はパンクロック全般いけるクチでありまして、以前は70sパンクなんかもよく聴いていました。60sにのめりこんで、ガレージパンクをはじめ多くのプロトパンクの音を聴くようになると、ほとんどの70sパンクは60sパンクの表面だけを焼き直したものに過ぎないということがわかってきて、ますます60sの面白さ・スゴさを再確認したのですが・・・。ガレージパンク/プロトパンク的な音が苦手という方は、そういう70sパンクのイメージによる部分も多少はあるのかな?と思ったりする次第です。
そのへんのイメージで損をしてるのではないかと思う筆頭が、このWe the Peopleです。NuggetsやPebblesをはじめ、数多くのガレージパンクのコンピに彼らの曲が収録され、記事やショップでもたいていガレージパンクバンドと紹介されているからです。しかし、1998年にSundazedから出た2枚組の決定盤的コンピレーション"Mirror of Our Minds"を聴くと、その曲想のバリエーションの豊かさに驚かれると思います。
チープなオルガンパンクから初期Kinks風ナンバー、R&Bに60sポップ、ラーガロック的サイケチューンやBeau Brummelsのような原初フォークロック、はたまた美しいハーモニーやメランコリックな風情を持ったソフトロックナンバーまで、60sサウンドのあらゆる相を展示させたかのような多彩さ。しかも、それらの曲のクオリティがどれも一級品であるところがスゴい。
結果的にはマイナーなガレージバンドで終わってしまったのですが、パンキッシュな部分と繊細さ・ポップさを併せ持つという意味では、Electric Prunes, Strawberry Alarm Clock, Chocolate Watchbandといったメジャー級のバンドに近いかもしれません。逆に、彼らが売れなかったのは、そのような多才さが災いしたのかもしれないし、ラジオから流れてきて「あ、○○だ」とすぐにわかるような強烈な個性にいまひとつ欠けていたのが原因かもしれません。
それでも、Tommy TaltonとWayne Proctorというふたりの優秀なソングライターが、その能力を競うように書いた楽曲群は素晴らしく、"In the Past"や"St. Johns Shop"など、一度聴いたら忘れられないような魅力的な曲にあふれています。(ラーガポップサイケの名曲でベストテン級マイフェイバリットソングの"In the Past"はChocolate Watchbandのカバーバージョンの方がお馴染みかもしれません。)
ふつうなら、このような方向性の一貫しない多様さは寄せ集め的な感じになるのでしょうが、別テイクで重複するものが数曲あることなどを差し引いても、このコンピは60s(ガレージ)ミュージックの魅力を凝集したような強力な響きがします。
第39回 Music Machine

The Music Machine
Turn On: The Best of the Music Machine
このバンドは、いまではKeith Olsen(一般にはFleetwood Mac等を手がけたプロデューサーとして有名)や、Ron Edgar、Doug Rhodesといった、Millennium ~ Sagittarius関係のメンバーが在籍していたということで言及されるほうが多いかもしれません。
しかし、その音はMillennium関連の音源を渉猟する純ソフトロックファンの期待を見事に裏切るであろう、極上にチープなフラワーパンクで、Seeds ~ ? & the Mysteriansといったバンドに目のない私のようなファンにとってはマストアイテムといえる、「かゆいところに手がとどく」音を聞かせてくれます。
1966年のデビュー作"Turn On"はガレージパンク・クラシックの超名曲"Talk Talk"で始まりますが、それに続く"Trouble"などは、これまた大好きなIron Butterflyなんかも、このバンドから大きな影響を受けたんだろうなということが窺えます。
強力なオリジナルナンバーに加え、Mysteriansの"96Tears"や
なお、上記CDのタイトルには"The Best of ~"とありますが、内容はオリジナルの"Turn On"の末尾に4曲のボーナストラックを加えたものです。
ちなみに、2ndの"Bonniwell Music Machine"(1967)がWarnerから発売された時には、すでにバンドは解散状態になっていました。曲想はより複雑で陰影と表情に富んだものになっていますが、1stのノリは決して失われていません。この2ndはSundazedのコンピ"Beyond the Garage"に(曲順はバラバラですが)ボーナストラックとともに全曲が収録されています。Sundazedからはもう一枚、

The Bonniwell Music Machine
Beyond the Garage

Bonniwell Music Machine
Ignition
Doors - Live In Philadelphia

Rhino Handmadeから、The Doors - Live In Philadelphia '70が発売されました。"Absolutely Live"と同時期のツアーから採られたものですが、すべて未発表音源とのことです。CD2枚組で、数量限定盤(Limited Edition)ではないようです。
何度か言ってると思いますが、私はドアーズが大好きでして、無人島にたった一枚だけアルバムを持っていけるとしたら、やはりドアーズの1stを選ぶと思います。どこが好きかと聞かれると、かなり個人的・情緒的な感情とかも混じってくるので、なかなか記事には書けないのですが・・・。
さて、ドアーズのライブアルバムというと、スタジオ作に比べてなんだか音が薄っぺらいという印象をお持ちではないでしょうか? ご存知のとおり、ドアーズは専任のベースプレーヤーがいないバンドでありまして、スタジオ作では、(ベースレスの曲もありますが、)多くはバンドメンバーやHarvey Brooks、Douglas Lubahnといったセッションプレーヤーによって、ベースのパートが加えられています。
ライブではベースのパートをレイ・マンザレクがキーボードで弾いているのですが、普通ならフットペダルを使うところを、レイはベース用のキーボード(Rhodes Piano Bass)をオルガンの上に載せて左手でベースパートを弾き、コードやメロディはほとんど右手だけで弾いています。そのへんが、あの独特のチープなサウンドの要因となっています。しかし、好きになると、それもメジャーデビュー前のクラブサーキットでの演奏をイメージさせてくれて、なかなかオツなもんです。
ドアーズのライブ盤はたくさん出てまして(以下はその一部)、私も全部は把握しておりません。

The Doors
Absolutely Live

Doors
In Concert

The Doors
Live in Hollywood - Aquarius

The Doors
Live at the Aquarius Theatre: The First Performance

The Doors
Live at the Aquarius Theatre: The Second Performance

The Doors
Live in Detroit (Cobo Hall, 05/08/1970)

ドアーズ
ブライト・ミッドナイトーライヴ・イン・アメリカ
Anthem to Beauty

只今、パソコンテレビGyaOの洋楽番組"THE VINTAGE"にて、マスター・オブ・サイケデリック、Grateful Deadのドキュメンタリーフィルム"Anthem to Beauty"が放映されています(配信は1月1日まで)。
http://www.gyao.jp/music/hits/vintage/
内容は、実験的で最もサイケ色の強い"Anthem of the Sun"(1968)から、珠玉のルーツロックアルバム"American Beauty"(1970)に至る道のりを辿ったもの。1967年当時のヘイト・アシュベリーの様子(デッドのメンバーが住んでいたビクトリアンハウスの内部など)や野外フリーコンサート、ニール・キャサディの「マジック・バス」ツアー、アシッドテストの模様、メンバーが撮ったプライベートフィルムなど貴重な映像満載で、60sサイケファン必見という感じです。
GyaOといえば、夏頃だったか、(これは「音楽」ではなくて「映画」の番組だったと思いますが、)「それはビートルズから始まった」というドキュメンタリー(1974年、米国作品)が放映されていました。60年代のさまざまなアーティストを当時の政情やファッションなどの社会的背景を交えながら紹介する、なかなか充実した内容でした。気づいて観たのが配信終了の前日だったので、こちらで報告しそこなってしまいましたが、いずれまた再放送されるのではないかと思います。

コロムビアミュージックエンタテインメント
メイキング・オブ・アメリカン・ビューティ
昔はサイケで出てました その10
今回は「サイケデリックと言えるかどうかは微妙だけど、そのつもりで聴けば確かにその香りがする」という感じのラインナップです。(いずれもFuzz, Acid and Flowersにエントリーされています。)
Stone Poneys
リンダ・ロンシュタットが60年代に男性二人と組んでいたトリオ。67年のファーストアルバムは、同じ編成のピーター・ポール&マリーを連想させるようなモダンフォーク的作品です。ほとんどを占めるオリジナル曲はデビュー作とは思えないくらいしっかりしていて、ややトラッド寄りの、正統的で凛々しいフォークソングという感じ。しかし、リンダのボーカルがチャーミングな上に強力なので、地味な印象はあまりなく、60sフラワーな雰囲気の好盤となっています。
その後Stone Poneysとして2枚を出しています(*1)が、ドラムにジム・ゴードンが参加してたり、ストリングスやハープシコードを入れたソフトロック的アレンジの曲やポップチューン、70s時代を思わせるようなカントリー風味の曲も散見されるなど、しだいに多様化していきます。
サイケ的には、シタール入りの曲があったり(2~3作目)、"Let's Get Together"やTim Buckley作品を3曲カバーしてたり(3作目)といったところでしょうか。ポップス的には、モンキーズのマイク・ネスミス作で、全米Top20のヒット曲となった"Different Drum"(2ndに収録)が有名です。
*1
サードアルバムは制作途中でグループが分裂して、残りをリンダとセッションマンによって完成させたという事情もあって、アルバムのクレジットは"Linda Ronstadt - Stone Poneys and Friends Vol.III"となっています。

Linda Ronstadt
The Stone Poneys Featuring Linda Ronstadt

Stone Poneys
Evergreen, Vol. 2

Stone Poneys
Stone Poneys & Friends, Vol. 3
Warren Zevon
2年前にガンと闘病の末亡くなったことはいまだ記憶に新しいウォーレン・ジヴォンですが、ハードボイルド・ロックとも呼べるような独自のスタイルとシンガーソングライターとしての才能は、もっと評価されてもいいのにと残念に思います。
ここで取り上げるのは1969年制作のデビューアルバム"Wanted Dead or Alive"で、一般には評価は低く、発売当時もほとんど話題にならずに、その後1976年の再デビュー作まで空白期間となってしまう、いわば鬼っ子的な作品なのですが、60s好きの目から見ると結構面白いし、作品的にも決して悪くないと思います。
全体的にややとっちらかっていてユルいところとか、ファズギターやテープ逆回転のエフェクトとか、アシッドロック的なインストナンバーとか、"Traveling in the Lightning"のような、のちのスタイルを思わせるエスニックなリフの曲が60s的なチープさで響いたりとか、ByrdsのSkip Battynが参加してたりとかで、サイケ的にも興味深い内容になっています。
ちなみに、本作収録の"She Quit Me"は映画「真夜中のカーボーイ」(1969)のサントラに使われています。また、1967年のTurtlesの大ヒットシングル"Happy Together"のB面の"Like the Seasons"は、まだ20歳頃のジヴォンが書いた曲です。

Warren Zevon
Wanted Dead or Alive
Rising Sons
Taj MahalとRy Cooderが在籍していた伝説的なバンド。他に、のちにSpiritを結成するEd Cassidyや、Byrdsに加入するKevin Kelly(どちらもドラム)などもメンバーでした。バンドは1965年から66年にかけて活動し、Columbiaでアルバム用の曲を録音しますが、結局シングルを1枚出しただけでLPは発売されませんでした。その後、1992年にSonyから"Rising Sons Featuring Taj Mahal & Ry Cooder"として正式にCD化され、いまでは全22曲の貴重な音源を聴くことができます。
私はTaj Mahalといえば、Jesse Ed Davisがバックの時代の初期リーダー作が大好きなのですが、それに比べるとユルくてアシッド感のあるRising Sonsの音も素晴らしい。ルーツロック好きならマストといえるような充実した内容です。プロデュースがTerry Melcherということもあるのでしょう、当時のトレンドだったByrds的なフォークロックナンバーが混じってたりするのも面白いところ。

Rising Sons
Rising Sons Featuring Taj Mahal & Ry Cooder
Stalk-Forrest Group
Blue Oyster Cultの前身。このグループ(またの名のOaxaxaおよびSoft White Underbelly)にまつわるレコーディングの経緯はかなり複雑なので、ここでは省略しますが、要するにBOCデビュー前に伝説的なアンリリースド・アルバムが存在したということです。その音源(1969~70)をまとめたものが2001年にRhinoからCD化されました。
BOCというと、Black Sabbathがゴシックホラー的な要素をロックに持ち込んだのに対して、モダンホラー的な感覚を取り入れたバンドとして、初期の作品などはサイケファンにもアピールする要素があるのではないかと思います。そして、このStalk-Forrest Groupの音源を聴くと、BOCよりまったりとした時間感覚や、Arthur LeeのLoveを思わせるようなねじれたテイストの楽曲群、アシッドロック的なインプロの展開と、もうはっきりサイケデリックと呼んでもいいくらいです。(BOC時代に再録された"I'm on the Lamb"なんかを聴き比べてみるのも一興かもしれません。)

Stalk-Forrest Group
St. Cecilia: The Elektra Recordings (試聴はこちら)
Stone Poneys
リンダ・ロンシュタットが60年代に男性二人と組んでいたトリオ。67年のファーストアルバムは、同じ編成のピーター・ポール&マリーを連想させるようなモダンフォーク的作品です。ほとんどを占めるオリジナル曲はデビュー作とは思えないくらいしっかりしていて、ややトラッド寄りの、正統的で凛々しいフォークソングという感じ。しかし、リンダのボーカルがチャーミングな上に強力なので、地味な印象はあまりなく、60sフラワーな雰囲気の好盤となっています。
その後Stone Poneysとして2枚を出しています(*1)が、ドラムにジム・ゴードンが参加してたり、ストリングスやハープシコードを入れたソフトロック的アレンジの曲やポップチューン、70s時代を思わせるようなカントリー風味の曲も散見されるなど、しだいに多様化していきます。
サイケ的には、シタール入りの曲があったり(2~3作目)、"Let's Get Together"やTim Buckley作品を3曲カバーしてたり(3作目)といったところでしょうか。ポップス的には、モンキーズのマイク・ネスミス作で、全米Top20のヒット曲となった"Different Drum"(2ndに収録)が有名です。
*1
サードアルバムは制作途中でグループが分裂して、残りをリンダとセッションマンによって完成させたという事情もあって、アルバムのクレジットは"Linda Ronstadt - Stone Poneys and Friends Vol.III"となっています。

Linda Ronstadt
The Stone Poneys Featuring Linda Ronstadt

Stone Poneys
Evergreen, Vol. 2

Stone Poneys
Stone Poneys & Friends, Vol. 3
Warren Zevon
2年前にガンと闘病の末亡くなったことはいまだ記憶に新しいウォーレン・ジヴォンですが、ハードボイルド・ロックとも呼べるような独自のスタイルとシンガーソングライターとしての才能は、もっと評価されてもいいのにと残念に思います。
ここで取り上げるのは1969年制作のデビューアルバム"Wanted Dead or Alive"で、一般には評価は低く、発売当時もほとんど話題にならずに、その後1976年の再デビュー作まで空白期間となってしまう、いわば鬼っ子的な作品なのですが、60s好きの目から見ると結構面白いし、作品的にも決して悪くないと思います。
全体的にややとっちらかっていてユルいところとか、ファズギターやテープ逆回転のエフェクトとか、アシッドロック的なインストナンバーとか、"Traveling in the Lightning"のような、のちのスタイルを思わせるエスニックなリフの曲が60s的なチープさで響いたりとか、ByrdsのSkip Battynが参加してたりとかで、サイケ的にも興味深い内容になっています。
ちなみに、本作収録の"She Quit Me"は映画「真夜中のカーボーイ」(1969)のサントラに使われています。また、1967年のTurtlesの大ヒットシングル"Happy Together"のB面の"Like the Seasons"は、まだ20歳頃のジヴォンが書いた曲です。

Warren Zevon
Wanted Dead or Alive
Rising Sons
Taj MahalとRy Cooderが在籍していた伝説的なバンド。他に、のちにSpiritを結成するEd Cassidyや、Byrdsに加入するKevin Kelly(どちらもドラム)などもメンバーでした。バンドは1965年から66年にかけて活動し、Columbiaでアルバム用の曲を録音しますが、結局シングルを1枚出しただけでLPは発売されませんでした。その後、1992年にSonyから"Rising Sons Featuring Taj Mahal & Ry Cooder"として正式にCD化され、いまでは全22曲の貴重な音源を聴くことができます。
私はTaj Mahalといえば、Jesse Ed Davisがバックの時代の初期リーダー作が大好きなのですが、それに比べるとユルくてアシッド感のあるRising Sonsの音も素晴らしい。ルーツロック好きならマストといえるような充実した内容です。プロデュースがTerry Melcherということもあるのでしょう、当時のトレンドだったByrds的なフォークロックナンバーが混じってたりするのも面白いところ。

Rising Sons
Rising Sons Featuring Taj Mahal & Ry Cooder
Stalk-Forrest Group
Blue Oyster Cultの前身。このグループ(またの名のOaxaxaおよびSoft White Underbelly)にまつわるレコーディングの経緯はかなり複雑なので、ここでは省略しますが、要するにBOCデビュー前に伝説的なアンリリースド・アルバムが存在したということです。その音源(1969~70)をまとめたものが2001年にRhinoからCD化されました。
BOCというと、Black Sabbathがゴシックホラー的な要素をロックに持ち込んだのに対して、モダンホラー的な感覚を取り入れたバンドとして、初期の作品などはサイケファンにもアピールする要素があるのではないかと思います。そして、このStalk-Forrest Groupの音源を聴くと、BOCよりまったりとした時間感覚や、Arthur LeeのLoveを思わせるようなねじれたテイストの楽曲群、アシッドロック的なインプロの展開と、もうはっきりサイケデリックと呼んでもいいくらいです。(BOC時代に再録された"I'm on the Lamb"なんかを聴き比べてみるのも一興かもしれません。)

Stalk-Forrest Group
St. Cecilia: The Elektra Recordings (試聴はこちら)
昔はサイケで出てました その9
Holy Modal Rounders
Steely Dan ~ Doobie BrothersのJeff Baxterも60年代の一時期、Ultimate SpinachやHoly Modal Roundersといったサイケ関係のグループでプレイしていたことがありました。Ultimate Spinachは以前こちらに書いたので、Holy Modal Roundersのことを少し・・・。
このグループはサイケファンにもそれほどポピュラーではないと思いますが、サイケとは無縁の一般の人も(知らないうちに)聞いたことがあるという・・・そのココロは、映画「イージー・ライダー」の挿入歌として彼らの曲が使われ、サントラ盤にも収録されているからです。ジャック・ニコルソンがアメフトのヘルメットをかぶってピーター・フォンダのオートバイに乗るシーンで流れる「イフ・ユー・ウォナビー・ア・バ~~~~~~ド」(*1)と言えば、「ああ、あれか」と思われるかもしれません。
60sサイケのタイトルとしては1967年のサードアルバム"Indian War Whoop"と、それに続く68年の"The Moray Eels Eat the Holy Modal Rounders"が有名ですが、どちらもかなりフリーキーな内容で、コアなサイケファンでも聴く人を選ぶのではないかと思います。フリー・ジャズならぬフリー・トラッドというか、ザッパ&マザーズのジャグバンド版といった趣きで、ラリってるというより、タチの悪いヨッパライのノリに近いです。
Holy Modal Roundersというのはバンドというより、Peter Stampfel(バンジョー、フィドル、ボーカル)とSteve Weber(ギター、ボーカル)のデュオをコアにしたプロジェクト(*2)という感じなんですが、1964年の1stと2ndは二人のアコースティック楽器と歌によるシンプルなもので、(トラッド曲をアレンジだけでなく勝手に歌詞を変えたりした、これもフリーフォームなものらしいですが、)ヨレたボーカルはともかく、3~4枚目を先に聴いた私には「まとも」なルーツミュージックに聴こえてしまいます。
あと一枚、1975年に出た"Alleged in Their Own Time"を聴きましたが、こちらも最初の2枚に近い「おとなしい」印象でした。なお、CDは1stと2ndがカップリングされたものが出ています。
*1
「イージー・ライダー」での曲名は"If You Want to Be a Bird"ですが、オリジナルアルバムの"The Moray Eels ~"収録時のタイトルは"Bird Song"。
*2
このふたりは、Fugsの"First Album"などでもフリークアウトしています。ボーカルスタイルなどを含め、"I Feel Like I'm Fixin' to Die"のカントリー・ジョーなんかも、かなり彼らから影響を受けているのではないでしょうか?

The Holy Modal Rounders
1 & 2

Holy Modal Rounders
Indian War Whoop

The Holy Modal Rounders
The Moray Eels Eat the Holy Modal Rounders

サントラ, ステッペン・ウルフ, スミス, ザ・バーズ, ザ・ホリー・モダル・ラウンダーズ, フラタニティー・オブ・マン
イージー・ライダー<リマスター・エディション>
Steely Dan ~ Doobie BrothersのJeff Baxterも60年代の一時期、Ultimate SpinachやHoly Modal Roundersといったサイケ関係のグループでプレイしていたことがありました。Ultimate Spinachは以前こちらに書いたので、Holy Modal Roundersのことを少し・・・。
このグループはサイケファンにもそれほどポピュラーではないと思いますが、サイケとは無縁の一般の人も(知らないうちに)聞いたことがあるという・・・そのココロは、映画「イージー・ライダー」の挿入歌として彼らの曲が使われ、サントラ盤にも収録されているからです。ジャック・ニコルソンがアメフトのヘルメットをかぶってピーター・フォンダのオートバイに乗るシーンで流れる「イフ・ユー・ウォナビー・ア・バ~~~~~~ド」(*1)と言えば、「ああ、あれか」と思われるかもしれません。
60sサイケのタイトルとしては1967年のサードアルバム"Indian War Whoop"と、それに続く68年の"The Moray Eels Eat the Holy Modal Rounders"が有名ですが、どちらもかなりフリーキーな内容で、コアなサイケファンでも聴く人を選ぶのではないかと思います。フリー・ジャズならぬフリー・トラッドというか、ザッパ&マザーズのジャグバンド版といった趣きで、ラリってるというより、タチの悪いヨッパライのノリに近いです。
Holy Modal Roundersというのはバンドというより、Peter Stampfel(バンジョー、フィドル、ボーカル)とSteve Weber(ギター、ボーカル)のデュオをコアにしたプロジェクト(*2)という感じなんですが、1964年の1stと2ndは二人のアコースティック楽器と歌によるシンプルなもので、(トラッド曲をアレンジだけでなく勝手に歌詞を変えたりした、これもフリーフォームなものらしいですが、)ヨレたボーカルはともかく、3~4枚目を先に聴いた私には「まとも」なルーツミュージックに聴こえてしまいます。
あと一枚、1975年に出た"Alleged in Their Own Time"を聴きましたが、こちらも最初の2枚に近い「おとなしい」印象でした。なお、CDは1stと2ndがカップリングされたものが出ています。
*1
「イージー・ライダー」での曲名は"If You Want to Be a Bird"ですが、オリジナルアルバムの"The Moray Eels ~"収録時のタイトルは"Bird Song"。
*2
このふたりは、Fugsの"First Album"などでもフリークアウトしています。ボーカルスタイルなどを含め、"I Feel Like I'm Fixin' to Die"のカントリー・ジョーなんかも、かなり彼らから影響を受けているのではないでしょうか?

The Holy Modal Rounders
1 & 2

Holy Modal Rounders
Indian War Whoop

The Holy Modal Rounders
The Moray Eels Eat the Holy Modal Rounders

サントラ, ステッペン・ウルフ, スミス, ザ・バーズ, ザ・ホリー・モダル・ラウンダーズ, フラタニティー・オブ・マン
イージー・ライダー<リマスター・エディション>
昔はサイケで出てました その8
Amboy Dukes
ボブ・シーガーほどメジャーではありませんが、デトロイトロッカーでサイケ出身者といえば、「どんどん、どぎーどー」のTed Nugentも忘れてはいけません。1968~70年の間にAmboy Dukesというバンドで5枚ほどアルバムを出しています。
ガレージパンク~ヘヴィサイケ系とはいえ、70年代以降のテッドのイメージからすると、おとなしい感じもしますが、デビューアルバムからすでに「パオ~」という象の鳴き声みたいなフィードバックが炸裂しています。全米Top20ヒット曲で、Nuggets等コンピ常連の"Journey to the Center of the Mind"は有名ですが、アルバムはかなり分裂気味で、どこがいいのかあまりよくわかりません。でも、なぜか買ってしまって、都合4枚ほど(ほぼ全作)所有しております。(オリジナルタイトルのCDは韓国Won-Sinから再発されています。)
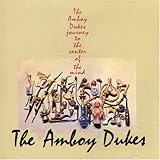
The Amboy Dukes
Journey to the Center of the Mind

Ted Nugent & the Amboy Dukes
Loaded for Bear: The Best of Ted Nugent & the Amboy Dukes
Nazz
これは有名ですね。トッド・ラングレンのバンドです。のちのソロ時代にリライトされてヒットした代表曲の"Hello It's Me"は元々Nazzの曲で、1stアルバムに収められています。スタイルをひとことで言うと「プレ・ハードロック的ポップサイケ」という感じで、当時のアメリカのバンドよりも、英国のSmall FacesとかThe Moveといったバンドのテイストに近い音です。(実際彼らはモッズなどの英国ロックの崇拝者で、バンド名はYardbirdsの曲から取ったとか・・・。)
アルバムは1968年から1970年の間に3枚出しています。特に最初の2枚は、すべての面でクオリティの高い佳品で、すでにトッドの非凡なポップセンスが光っています。ただ、1970年の"Nazz III"の時にはトッドはバンドを抜けていて分裂状態にあり、本来は2枚組となるはずだった2ndアルバム"Nazz Nazz"のアウトテイクなどから構成されています。

The Nazz
Nazz

The Nazz
Nazz Nazz

The Nazz
Nazz III

The Nazz
Open Our Eyes: The Anthology
ところで、トッドが抜けたあとの一時期、レコードは出していませんが、のちのCheap TrickのRick NielsenとTom Peterssonが、Nazzのメンバーと共に"New Nazz"として、Sick Man of Europeなどのバンド名で活動していました。その頃に残されたデモ曲の中にはCheap Trickのナンバーの元になったものもあります。
さらにそれ以前には、RickとTomはFuseというヘヴィサイケバンドを組んでいました。1968年作の唯一のアルバムはサイケというより、ヴァニラファッジのようなアートロックや、第一期ディープパープルをもっとヘヴィにしたようなオルガンハードロックで、ギターなんかほとんどブリティッシュ・ハードロックしています。

Fuse
Fuse (試聴はこちら。)
ボブ・シーガーほどメジャーではありませんが、デトロイトロッカーでサイケ出身者といえば、「どんどん、どぎーどー」のTed Nugentも忘れてはいけません。1968~70年の間にAmboy Dukesというバンドで5枚ほどアルバムを出しています。
ガレージパンク~ヘヴィサイケ系とはいえ、70年代以降のテッドのイメージからすると、おとなしい感じもしますが、デビューアルバムからすでに「パオ~」という象の鳴き声みたいなフィードバックが炸裂しています。全米Top20ヒット曲で、Nuggets等コンピ常連の"Journey to the Center of the Mind"は有名ですが、アルバムはかなり分裂気味で、どこがいいのかあまりよくわかりません。でも、なぜか買ってしまって、都合4枚ほど(ほぼ全作)所有しております。(オリジナルタイトルのCDは韓国Won-Sinから再発されています。)
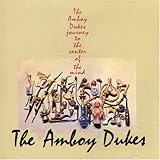
The Amboy Dukes
Journey to the Center of the Mind

Ted Nugent & the Amboy Dukes
Loaded for Bear: The Best of Ted Nugent & the Amboy Dukes
Nazz
これは有名ですね。トッド・ラングレンのバンドです。のちのソロ時代にリライトされてヒットした代表曲の"Hello It's Me"は元々Nazzの曲で、1stアルバムに収められています。スタイルをひとことで言うと「プレ・ハードロック的ポップサイケ」という感じで、当時のアメリカのバンドよりも、英国のSmall FacesとかThe Moveといったバンドのテイストに近い音です。(実際彼らはモッズなどの英国ロックの崇拝者で、バンド名はYardbirdsの曲から取ったとか・・・。)
アルバムは1968年から1970年の間に3枚出しています。特に最初の2枚は、すべての面でクオリティの高い佳品で、すでにトッドの非凡なポップセンスが光っています。ただ、1970年の"Nazz III"の時にはトッドはバンドを抜けていて分裂状態にあり、本来は2枚組となるはずだった2ndアルバム"Nazz Nazz"のアウトテイクなどから構成されています。

The Nazz
Nazz

The Nazz
Nazz Nazz

The Nazz
Nazz III

The Nazz
Open Our Eyes: The Anthology
ところで、トッドが抜けたあとの一時期、レコードは出していませんが、のちのCheap TrickのRick NielsenとTom Peterssonが、Nazzのメンバーと共に"New Nazz"として、Sick Man of Europeなどのバンド名で活動していました。その頃に残されたデモ曲の中にはCheap Trickのナンバーの元になったものもあります。
さらにそれ以前には、RickとTomはFuseというヘヴィサイケバンドを組んでいました。1968年作の唯一のアルバムはサイケというより、ヴァニラファッジのようなアートロックや、第一期ディープパープルをもっとヘヴィにしたようなオルガンハードロックで、ギターなんかほとんどブリティッシュ・ハードロックしています。

Fuse
Fuse (試聴はこちら。)
