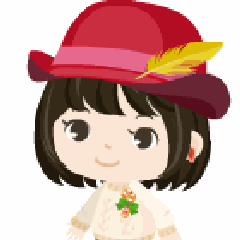1983年9月1日に野村義男さんらと「気まぐれ One Way Boy」でデビューしたヤッチンこと
曾我泰久さん。80年代はバンド活動以外にもドラマや映画等多数の作品に出演されて
いましたが、何時しかテレビであまり見かけなくなり気になり追ってみました。
2011年「大人の音楽専門TV◆ミュージック・エア(現:ミュージック・エア)」において
「リアル・ミュージック・スタジオ『Music Life』」のパーソナリティーを務められました。(2011年6月終了)
2015年、A.B.C-Zの舞台「ABC座 2015」に音楽担当と出演!
因みにこの時は、ジャニーズ事務所と関わるのは独立以来初めてだったそうです。
結婚は?
2008年3月3日に入籍したことが7日デイリースポーツの取材で分かりました。
お相手は17歳年下のバイオリニストの方で、挙式・披露宴は近親者のみで行われたそうです。
野村義男さんや、「アポロ-」のメンバーで山田まりやさんと結婚したばかりの草野徹さんにも報告済みで、曾我は「草野君が結婚したばかりで、1カ月違いでの結婚になります。夏にはライブもあるので、ダンナになった2人を見にきて」と喜びいっぱいにコメントされていました。
現在の曾我さんは?
舞台ABC座 2015 (2015年)や陣内の門 〜1st ACT〜(2018年)に出演されていました。
またYouTubeも配信されています。
ジャニーズの送り出した本格派バンド「THE GOOD-BYE」のリーダーで野村義男さんと
フロントマンをつとめていた「やっちん」こと曾我泰久の音楽活動関連のチャンネルです
最後に・・・。
via www.facebook.com
曾我さんは、1993年公開の映画「くまちゃん」小田切卓 役が最後で、
ドラマや映画に出演されていません💦
個人的には、役者としての曾我さんも好きだったのでドラマや映画でも見てみたいですね。
来年は結成40周年を迎えるThe Good Bye(以下グッバイ)。ジャニーズ出身のロックバンドとしてアイドル的な側面を持ちながら、ロックバンドの矜持で音楽性を深め、1990年の活動休止
までに9枚のアルバムを残す。そして、ここにきての再プレスで評価は高まる一方だ。
このタイミングでグッバイのリーダー、曾我泰久さんにインタビューを試みた。
ジャニーズ出身、アイドルをキャリアのスタートにしながらも、ギターと出会い、作曲に目覚め、自らの音楽性を深めていくと同時に、グッバイはアルバムごとに深化を遂げる。
それはグッバイが日本のビートルズと言っても過言ではないほどのクオリティの高さゆえだ。
曾我は言う。「本物を目指すと芸能界は人気がなくなってくる」と。それでも音楽に寄り添い、現在に至る。このインタビューは、グッバイの音楽性を紐解くと同時にミュージシャン、
曾我泰久の音楽への愛情の深さ、エンタテインメントと向き合うプロの生き様を感じ取る
ことが出来るだろう。全ての音楽ファン必読のインタビュー、スタート!
30年以上前に作ったアルバムが、今評価されるThe Good Bye
曾我泰久(以下曾我):まずは嬉しいですね! 30年以上前に作ったアルバムたちが
当時バンドでデビューする人が、最初から自分たちの演奏でレコーディングさせてもらえると
― デビュー曲も自分たちの楽曲でデビューしたいという思いがあったのですね。
曾我:ありましたね。最初に楽曲のコンペがあって、とにかく「曲を作って持って来い」と。
― ただ、歌謡曲が好きな人たちにも刺さる作り方をファーストからしているな、という印象はありました。先ほど、「気まぐれONE WAY BOY」の話をされていましたが、今グッバイの
曾我:そうですよね(笑)。デビューシングルのバージョンはスタジオミュージシャンの
― シングルの方は、職業編曲家の先生の手腕というか、幅広い層に届けようという
曾我:そこは大きなうねりと言いますか、トシちゃんが出て、マッチが出て、
ジャニーズ事務所からデビュー、グッバイまでの道のり
― 曾我さんもジャニーズでアイドルとしてやられていたわけですよね。曾我:僕は、グッバイの前にANKH(アンク)というバンドをやっていて、フォーライフから
そんな経験をしながら、当時は同時並行でドラマにも出演していました。
ドラマをやりながら、自分で曲を作っていました。ANKHというバンドは、中学生ぐらいから
― すごくシンプルな疑問として、曾我さんって何でも出来ますよね。
曾我:僕はリトル・ギャングという二人組で中学1年の時にデビューしたのですが、相方の松原秀樹が変声期になってしまって、シングル2枚、アルバム1枚で終わりました。
だから、バンドに憧れてギターを始めた訳ではなく、半ば無理矢理
― そこで、自分には適性があったと感じたとか?
曾我:いやいや、とにかく仕事としてやらなくてはいけない状況でした。川崎麻世君のデビューは決まっているし、そのデビュー曲を演奏しろ、と言われたら演奏しなくてはいけないんです。当時、何曲やったのかな? ロックフェスなんかにも出演したのですが、チューニングも
― ちなみにその時、曾我さんはおいくつですか?
曾我:中学3年か… 高校1年か、そのぐらいですね。
― ジャニーズは、グッバイ以前にもバンドに力を入れようという動きがあったのですね。
曾我:ジャニーズでは昔からフォーリーブスのバックバンドであったり、郷ひろみさんのバックバンドであったり、デビューは出来なかったのですが、いくつかのユニットがありました。
それで、川崎麻世君が入ってきた時にバンドを始めるのですが、楽器も初心者なので、
The Good Bye デビュー。
この姿かたちでやりたいことをやるのがロックだと
― その後がグッバイですよね。当時は、アイドル的な立ち位置を求められると思います。
曾我:僕は11歳からジャニーズなので、バンドらしさとかっていうのもよく分からなかった。当時、自分たちよりももっとアイドルっぽい人たちが、ロックバンドとしてロックの雑誌に
いや、今ここに出たい、と言っても、うちの事務所からはそこには出せない、
― ジャニーズってキー局に出演するのが当たり前で、『レッツゴーヤング』なんかに出ているイメージがありました。確かにミュートマに出れば、そこからジワジワと音楽好きに浸透する
曾我:そうですね。だから雑誌だと、『明星』『平凡』『セブンティーン』などもいいですが、『GB』とか『PATi・PATi』とか、ロック系の雑誌にも出たかった。
そういう中で暴れていたのがメンバーの中では僕ひとりで、事務所に掛け合っても
― グッバイのデビューは1983年ですよね。その頃は日本のロックがどんどん成熟していく
曾我:僕は、そっち側に行きたいと思っていました。そっち側で正当に評価していただきたいという思いが常にありながらも、やはり事務所でブッキング出来る番組は決まっていて、昔ながらの付き合いの出版社も決まっている。そうなると、僕が求めるラインは引いてくれなかった…。それでも、毎日のようにテレビ局に行って、取材を受けて、という忙しい時間が過ぎていき
当時、コンサートも、当たり前のように1日2回公演でした。それを、1回にして欲しい。
― グッバイってチェッカーズと同期ですよね。僕は、グッバイもチェッカーズも普通に好きになれました。そのきっかけは、「モダンボーイ狂想曲」でした。ちょっとストレイ・キャッツっぽい感じが良かったです。ちゃんと色々な音楽を取り入れてやっているんだなと、子供心に思えて。それから良いシングルをどんどんリリースして…。だけど、男の子はジャニーズに嫉妬と
いうわけじゃないけれど、そういう気持ちがありますよね。それがすごくもったいなかった。
曾我:でも、だからこそ、30年以上経って、評価してもらえることは嬉しいことですよね。
(取材・構成 / 本田隆)
The Good-Bye 曾我泰久インタビュー ②
野村義男などバンドメンバーの素顔は? 1985年9月5日
普遍的なポピュラーミュージックをやっていた
グッバイは古くならない
― 先日行われた、曾我さんとプロデューサーだった川原伸司さんのイベント(『祝!CD
再プレス!素晴らしきThe Good-Byeの世界!』@渋谷LOFT HEAVEN)で、すごく印象に
残っているのが、「The Good-Bye(以下グッバイ)は、新しい音楽をやっているというバンドではなかった。普遍的なポピュラーミュージックを再現している。だから古くはならない」と
いう川原さんのコメントでした。それは、ビートルズが古くならないのと一緒でグッバイも
古くならない。当時から、そういうことを考えていましたか?
曾我:いや、考えてはいないです。ただ、大瀧詠一さんの「流行を追ったらビリになるよ」と
いう言葉には共感していて、売れたいというよりも、自分たちがやりたいこと、表現したいことをやりたいという気持ちが強かった。バンドなので、アルバムの四隅、A面の1曲目、A面の
ラスト、B面の1曲目、B面のラストを誰が押さえるかが競争でした。だから、アルバム全体を象徴するようなA面の1曲目を作りたいという気持ちがみんな大きかった。外に向けてという
より、バンドの中での勝負だったと思います。もちろん、表に向けて「これ聴いて」というのも大切ですが、アルバム制作は、自分が「これ最高!」と思えるものを作っていきました。
― 4人の音楽性は一致していましたか?
曾我:その辺のバランスを上手くとってくれたのが川原さんだと思います。最初の頃は僕と川原さんでバンド全体のバランスを考えていきました。途中3枚目、4枚目ぐらいから野村義男君、加賀八郎君も自分の個性を分かりやすく打ち出した曲を作るようになりました。
そういうのをメンバーみんなでブラッシュアップしてアルバムに収めていく。
そういう風にやっていたので、1枚目から9枚目まで聴いてもらうとメンバーそれぞれの
成長もバンドの成長も手に取るように分かる。だからグッバイは面白いのかなとも思います。
― アルバムごとの深化も、初期のアルバムが初々しく、キャッチーなのもビートルズに似て
いるなと感じます。そこにハードロックテイストやパワーポップ的な解釈などもあって、
メンバーが聴いていた音楽が増えるごとにアルバムが深くなっていくという、ロックバンドの
あるべき姿が感じられました。
曾我:そうですね。川原さんと出会って、毎晩川原さんの家に遊びに行って、曲を作って、
レコードを聴いて…。とにかく色々な音楽を教えてくれて。南青山にパイド・パイパー・ハウスというレコード店があって、ここに行って、店内でかかっている曲を「この曲誰ですか?」とか訊きながらレコードを買っていました。そうやって昔の音楽を掘り返していって、吸収していって。多分、僕が掘り下げた音楽、野村義男君が掘り下げた音楽、加賀八郎君が掘り下げた音楽というのは全然違っていた。僕はビートルズがメインの掘り下げ方で、義男はヴァン・ヘイレンであったり、そこからクリームやジミヘンに行ったりとか。加賀君はアメリカンロックでした。
― ブリティッシュとアメリカン。そこはグッバイの演奏にも出ていましたよね。
加賀さんはアメリカンのカラッとした感じが好きなんだな、というのが分かりました。
野村さんは本当にハードロック少年だな、とか。でも、取材される雑誌が決まっていると、
そういう話はなかなかできないですよね。
曾我:そうなんですよ。ただ、取材してくださる記者の方は音楽好きが多いので、
色々な情報を教えてもらいました。みなさん世代的には上なので、60年代の良い音楽を
たくさん知っていて。
― すると、業界の中でグッバイの音楽性に気づいていた人がいっぱいいたと。
曾我:そうですね。「面白いことやってるね!」って応援してくれていました。
川原伸司とのコンビネーション。グッバイの音は誰も真似できない
曾我:夜通しやって明るくなったら、一回ここで終わろうとなって、その日に録音した音源を
― ジャニーズ事務所も理解してくれていたのですね。
曾我:ジャニーさんが結成当時、僕にリーダーをやれと言った時点で僕に一任してくれていたと思います。僕がやりたいと思ったことは、その通りにやらせてもらえたし。
― その中でシングルは売れる曲を作らなくてはいけない… などの苦悩はありましたか?
コード進行のコードひとつを変える、変えないで、川原さんと言い合いになってスタジオが
― 新曲としてリリースした時は気づかなかったけど、何年も経って、
曾我:ひと手間掛けるか掛けないか… というのは、自分たちにしか分からないことですが、
ベースの加賀君も、放っておいたら泥臭いアメリカンロックになりがちですが、
― イビツというか混沌というか、優れたロックには、そういう側面がありますよね。
曾我:僕は、川原さんしか出会っていないのですが、でも、ジョージ・マーティンのように
― 川原さんは、洗練されている音楽がお好きなんですね。
曾我:そうですね。だから僕は川原さん直系のそういう音楽で、90点以上取らなくては
― それで、鍵盤やサックスを入れたりしたのですね。
曾我:グッバイはギターバンドなのに、ピアノの占める割合が多いんですよ。
― グッバイがデビューした1983年当時は、プロデューサーが全面に出るという発想があまり
なかったですよね。でも、メンバーのひとりとして川原さんがいたという認識が強いですよね。
曾我:川原さんは全体を俯瞰していました。リーダーみたいなものですよね。僕よりひと回り
上なので、とにかく色々な知識が豊富なので、自分がやってみたかったこともグッバイを通して表現していったと思います。僕も川原さんと組んで「なるほどね」ということを教えてもらっていたし、逆に川原さんがやりたいことも理解していった。そこで、「すごいな! こんな面白いことがあるんだ」という共通の認識で進めていけたと思います。
― そこは、曾我さんが今まで音楽を続けてきたバックボーンになっていますよね。
曾我:そうですね。ありがたいことにジャニーズ事務所でギターを無理矢理やらされたんですが、それをきっかけに曲を作るようになったし、自分でレコーディングすることにもなった。
グッバイの7年間というものが、とにかく好きにやらせてもらっていました。
ディレクションだとか、コーラスの重ね方、スタジオを円滑に進める方法なんかも
川原さんに教えてもらいました。途中からは、川原さんはスタジオに来なくなりましたから。
― それは、いつぐらいからですか?
曾我:真ん中ぐらいからですかね。4枚目、5枚目ぐらい。
スタジオは僕がうまく回していくような感じで。
リーダー曾我泰久が語るメンバーの個性とエピソード
― 曾我さんから見て、野村さん、加賀さん、衛藤さんは、どんなタイプの
ミュージシャンですか?
曾我:みんな素直です。バンド内でぶつかり合ったことは一度もないですね。
僕が「こうした方がいいんじゃない?」というアイディアを出すと、みんな従ってくれるし。
だからエゴがぶつかり合ったことは一度もないです。
― 逆に信頼されていたということですね。
曾我:当時、僕はすごく尖っていたので(笑)。だから、なかなかモノを言えなかったという
のもあったかも。一言言えば100個ぐらい返ってくるみたいな(笑)。
― そこまで真剣だったということですよね。
曾我:そうなんです。当時は自分に厳しい分、他人にも厳しくなっていたんですね。
お酒も飲まなかったし。他のメンバーは飲みに行っていました。
だから「お酒を飲む暇があるならいい曲書けよ!」って平気で言っていましたから(笑)。
― 音楽だけの生活だったと。
曾我:そうですね。それが楽しくて仕方がなかった。
やらなくちゃいけないし、やれることが楽しかったし。
― 素晴らしい環境だったと思います。
曾我:自分がやりたいことを表現して形にすることが出来たので、それは楽しいですよね。
― 自分の好きな音楽を納得のいくクオリティに仕上げていく中で
「もっと売れなくてはダメだろう」みたいな部分もありましたか?
曾我:それは常にありましたね。当時のメインはシングルだったので、
シングルリリースの時は「売れる曲を書かなくては」というプレッシャーはありました。
― メンバー4人のバランスも良かったですよね。
曾我:そうですね。加賀八郎君と衛藤浩一君が元々ジャニーズにいたタレントで、踊りも踊れるような子だったら、あのグッバイではなかったと思います。結成当時から、二人ともある程度のレベルまで来ていたミュージシャンなので。当たり前ですけど、ジャニーズと言いながら
ジャニーズっぽさが全くない二人なので、良い意味でバランスが良かったと思います。
― お二人はオーディションですか?
曾我:“ヨッちゃんバンド” ( グッバイの前身 )で何度もオーディションをやったのですが、
結局 “この人!” という人には出会えなくて…。と言いながらもデビューの日が
近づいてきてしまって…。
衛藤君は九州のヤマハから、こういう人材がいるという話がビクター側に入ってきて。
それで上京してもらいました。その時は、ずっとチューニングしていて。それを見た義男は
「チューニングにこんな時間をかけるなんてすごい人だな」って思ったらしいのですが、
本人は恥ずかしくて、前を向けなくて、ずっとチューニングをしていたという話でした(笑)。
ちょうどその頃、たのきん映画で『 嵐を呼ぶ男 』の撮影があって。それで、ジャニーさんが
いきなり衛藤君に「来週からハワイ行ってくれる?」と切り出して(笑)。
バンドのメンバー役に衛藤君を指名したんです。ジャニーさんはいつもそういう人だから。
でも衛藤君は全くそういう経験がないのでビビってしまい、九州に帰っちゃったんです。
九州から出てくる時は、九州の先輩たちに、「アイドルやるために音楽やっているのか」
みたいなことを散々言われて…。それでおずおずと帰ったら、その先輩たちに「何で帰ってきたんだ! そんな勿体ない話はないだろ」と言われたらしく(笑)。それで思い留まってグッバイに入るのですが、タイミングを逃したので彼は、『 嵐を呼ぶ男 』には出ていないんです。
― 野村さんはどのようなタイプでしたか。
曾我:僕の中では、すごく大人しい印象がありました。合宿所でギターの練習をする時に、
彼にコードカッティングしてもらって、スケールの練習をしていたんです。今でこそ、すごい
ギタリストですが、最初はそんなに弾けなかったかな。すごく引っ込み思案でしたね。
― それで、サードシングルからレノン=マッカートニーのように、ソングライティングには、
野村義男=曽我泰久(当時)というクレジットが並ぶわけですよね。
そのコンビネーションはいかがでしたか?
曾我:義男は独特な詞を書くし、詞を書くのが得意というか、早かったですね。
パッと書けてしまう。言葉遊びも上手だし。当時は、義男が定時制の高校へ行っていて、
昼間からレコーディングの時は、義男が学校へ行く時間は休憩時間にしていたんです。
それで、義男が戻ってくると「詞が出来たよ」って持ってくるから、そこで歌入れをしました。
― グッバイはメロディが先ですよね。
曾我:全曲メロディが先です。
― そこに野村さんの独特な歌詞を重ねて、グッバイの世界が出来上がるということですね。
曾我:嬉しいことに、最近、義男が「デモテープから歌詞が聴こえる」って
言ってくれるんです。これまでにいろんな人の詞を書いたけどヤッチンが録った
デモテープからは詞が聴こえてくると。やはり長年の付き合いだと思います。
― 長年の付き合いでもあるし、コンビネーションの良さですよね。
野村さんしか言えない言葉だと思います。
曾我:義男はすごくナイーブな性格です。その反動でおちゃらけたりもしますが、
本当に心を開くまでにすごく時間がかかるんです。だけど、今となっては、
こんなに長い付き合いになってしまいました。
The Good-Bye 曾我泰久インタビュー ③
いつだってジャニーさんに褒められたい! 2004年8月21日
ジャニーさんに褒められたい。その気持ちで頑張ってきた
― これまでのお話を聞いていると、ジャニーさんは、絶対売れなくてはいけない、
そのためにはどうやって売り出すのか? を常に考えている方だと思っていたのですが、
それぞれの性格をちゃんと見極めてバンドメンバーにするなど、そういう部分も
プロデューサーとしてすごい人ですね。
曾我:ジャニーさんは、全体が見えていて、ヨッちゃんがデビューするなら、子供の頃から芸能界にいて責任感が強い僕に任せておけば、何とかなるだろうという思いもあったと思います。
最終的には僕が追い込まれて、「年間3本ドラマを入れてくれたら義男とやるよ」って
ジャニーさんに言ったんです。そしたら、「分かった。3本入れるから」と。
それで、ジャニーさんはやたらと人を褒めるんですよ。
僕はジャニーさんに褒められて、褒められて育ってきた人間なので。だから、ジャニーさんに
褒められたいという気持ちがずっとあって頑張ってこれたと思います。
― ドラマ3本のお話を聞くと、役者としてやっていく気持ちも強かったのですね。
曾我:強かったですね。当時、リトル・ギャングでデビューして、ジャニーズが低迷している時、子供番組の体操のお兄さんもやりながら、楽器をやりながら、いろんなことをやってきた
中で、ドラマに出た時、「この世界って素晴らしい」と思えたんですね。
歌謡界とは違う新しいことをやろうというクリエイティブな面が見えたんですね。
役者さんひとりひとりの役作りも曲作りとは違って、自分の人生を賭けている姿にインスパイアされて、これは素晴らしい! と思えました。それで役者っていいな、と思えました。
― 役者とミュージシャン、舞台というエンタテインメントの仕事を曾我さんは経験されて
いるわけですよね。その中でミュージシャンという仕事をずっと続けてきた
根本的な理由はありますか?
曾我:好きだからとしか言いようがないですね。好きなことを続けていられるのは幸せですが、ジャニーズにいる時は、締め切りまでに作らなくてはいけないという中でやってきました。
自分ひとりになった時には、好きなことをやるために離れたわけだから、自分のペースで
やりたいことをやりたい。ノルマもなければ締め切りもない。
自分のやりたいことをやりたい時にやるというスタイルでソロ活動を始めて。
ソロになった最初の頃はミュージカルの仕事が非常に多くて、コンサートをやる時間が
なかなか取れなくて。そのミュージカルもジャニーさんが敷いてくれたレールでした。
ある日突然レコーディングスタジオにジャニーさんがいて。普段はあまり来ないんですよ。
だから「あれ、どうしたの?」って言ったら、モジモジしながら「ヤッチン、これやるから」って言いながらチラシを渡してくれたんです。そのミュージカルのチラシに僕の写真も
載っていて(笑)。常に本番主義というか。ジャニーさんはいつもいきなりなんです。
それで「僕、ドラマはやるって言ったけど、ミュージカルをやるなんて言ってないじゃない」って言うと、「しょうがないじゃない。決まったんだから」と(笑)。
それは『 イカれた主婦 』という木の実ナナさん主演のミュージカルでした。
それまで『 ショーガール 』という二人芝居の作品を続けてきて、初めて違うスタイルで
勝負に出るという作品で僕が息子役で出ることになりました。
ミュージカル界の第一人者の息子役というので僕はビビりました(笑)。
でも、それが大ヒットして、次から次へとオファーが来るようになりました。
ジャニーズ事務所を辞める時もジャニーさんに、「ヤッチン、ミュージカル頑張って
いくんだよ」って送り出してもらいました。
1990年に活動休止。感じていた音楽的な到達点
― The Good Bye(以下グッバイ)は1990年に活動を休止して、
その時と言うのはどういうお気持ちでした?
曾我:それこそ、25の時に『 イカれた主婦 』に出て、このままでいいんだろうか? と思ってしまったんですね。ミュージカルですけど、芝居の世界は自分でその空間を作っていく。ドラマは、演出家が動きを決めていきますが、ミュージカルは、動から全てを自分が作っていく。
そういう世界に出会って、大人としてこの先、三十代、四十代、役者として生きていくなら、
今これだけ守られている環境が果たして正解なのか? と思えてしまって。
僕は11歳からジャニーズ事務所にいたので、外の世界を見たことがなかった。でもミュージ
カルで初めて外の世界の人たちと触れ合って、自分の足で外に一歩出てみないと、この先楽しいと思っている音楽さえも続けていけなくなるのではないかと思えて。自分が過保護に思えたんですね。それで荒波に一度出てみたいと。バンドとしてもやり切った感があったのも確かでした。
― グッバイとしてコンスタントにアルバムを出されて、1990年は時代の節目として音楽の
流れも変わっていったと思います。バンドサウンド的なものが成熟しきった時期だと思います。その時期に活動休止というのは、ある程度の達成感があったのでは?
曾我:この時期は、メンバー全員が自分のデモテープも凝るようになってきました。
チャンネル数も増えてくるし。凝ったデモテープほど自分で愛着があるので、それをバンドと
して表現した時、デモテープの方がいいじゃん、と思ってしまう自分もいて、バンドとしての
意味があるのだろうか? となるんです。それで、今後もミュージシャンとしてやっていく
なら、一度ここで止めた方がいいと思ってしまったんです。それで、メンバーに伝えました。
これからみんながグッバイを続けていくなら、必ず僕の代わりを探すからと。
― それは曾我さんから始まった話だったのですね。
曾我:そうです。そしたらみんなも同じ気持ちで、音楽的にも到達点を感じていたので、
ここでケジメをつけた方がいいよねと。それで僕が事務所に話を持っていきました。
グッバイの4人がこの先もミュージシャンとしてやっていくには、この事務所ではなく、
それぞれの道を歩いていきたいんです、と言って。それで理解していただいて。
再始動したグッバイ、ベーシスト加賀八郎との早すぎる別れ
― それで2003年に活動を再開しますよね。
曾我:そうです。その間、僕のソロで義男には詞を書いてもらって。ある時、レコーディングでフルアコのギターが必要だったので、それを義男に借りたんです。で、返すのに原宿の駅の
近くで待ち合わせして、車を2台停めてギター返したら、「あのさぁ、グッバイでコンサート
やらない?」っていきなりあいつが言い出して。「解散コンサートやりたいんだよね」と。
でも解散って出来ないよ。活動休止しているわけだし。生々しいですが、グッバイという名前は事務所が持っているものだから、僕らがどうのこうの出来るわけではない。
もし、コンサートをやるなら、事務所に話をしに行って、グッバイという形でやらせてもらう
ように許可を取ってくるからと。それでジャニーさん、メリーさんからOKをもらって。
メリーさんは「あの子たちだったらいいから」と言ってくれて。それで、一日限りで「再会」というタイトルのコンサートをやりました。その時は、グッバイにいろいろな思いがあったんですね。大事なものでもあるし、当時の自分たちには負けたくない。俺たちはその先を行っている
から、という思いがありました。それはメンバーみんな同じだったと思います。
でも、オープニングでステージに上がった瞬間に、いろんな思いが溶けていったんですね。
だから、あの時、ステージ上で演奏している4人はすごくピュアでした。
ただただ、自分たちが作ってきた音楽を楽しんでやれた。僕はそんな経験が初めてでした。
ミュージシャンとして、懐かしさだけではやりたくないし、あいつには負けたくないという
思いが、それぞれあったと思うんです。でも、それがステージに上がった瞬間、すべて消えて、あの空間がすごく綺麗でした。邪念がないというか。ただただ楽しかった。
それで、その日の打ち上げで、「またやろうか?」となったんです。
ーアニバーサリーのライブを続けながら、2013年には、加賀さんがお亡くなりに…
曾我:本当に「まさか…」という思いで。病名を最初に聞いた時に、ネットで調べたら、えっ? と思って。生存の確率も低いし、信じられない思いでした。でも、本人は「今は医学も日進月歩だから、新しい薬ができるのを楽しみにしているんだ」なんて言って前向きでした。そこから、重いベースは持てないからヘフナー(ポール・マッカートニーも使っていた通称バイオリン・ベース)を欲しいと。それで義男が八つぁん(加賀八郎)のベースを売ってヘフナーを買いました。そこから毎月のように彼の家に集まって「こんなデモテープ作ったんだ」とか聴きながら、「アルバムどういう風にしようかな」なんて言って、飲みながらしゃべっていたんですね。
― 最後までバンドだったんですね。
曾我:そうですね…。
アルバムの再評価。そして2023年は結成40周年
― そして、今もコンスタントにやられていて、来年が結成40周年ですね。
曾我:八つぁんがいないというのは今でも信じられないし、新譜というのはこの前の10枚目で、全てやり切ったという思いがあるので、グッバイとしての新しい曲は、そうそう簡単に
手を出せないというか…。もうやるだけのことはやった。あれで完結と僕は捉えています。
ただ40周年を楽しみにしてくださっているファンも多いので、何らかの形で、
コンサートツアーはやろうと思っています。新しい音源に関しても、どういう形なら
出来るのかというのも考えています。
― こないだのイベント(『祝!CD再プレス!素晴らしきThe Good-Byeの世界!』
@渋谷LOFT HEAVEN)でも感じたのですが、グッバイのファンというのは、
音楽についてすごく詳しいですよね。
曾我:最初の頃というのは、アイドルファンがたくさんいて、途中、『FIFTH DIMENSION』
あたりで、そういう人たちが篩(ふるい)にかけられ、音楽好きな人たちが残ったんです。
今いるファンの人たちは、僕らが “こういう音楽が好きなんだ” ということを全て掘り下げて
聴いてくれています。それに最近、グッバイのライブに何十年ぶりに来ましたという人がすごく多いんです。僕は、ジャニーズ事務所を辞めてから一切メディアに出ていません。普通なら
メディアに出なくなると「あの人どうしているんだろ?」となりますよね。それでもネットで
調べて、「まだライブやっているんだ」ということで観に来てくれる。嬉しいですよね。
― これから、グッバイの音楽の若い人に響かせたいという気持ちはありますか?
曾我:全くないです。逆に僕が若い人たちが聴くような音楽を聴いているかといえば、聴いて
ないですから。ヒット曲を狙う職業作家は、常に勉強をしていないとダメだと思うんです。
たまたまグッバイの新譜を作る前に鷺巣(詩郎)さんに会った時、「ヤッチン、今の音楽なんか聴かなくていいよ。今の音楽を聴く時間があるのだったら、まだ聴いていない60年代、70年代の音楽、宝物が山ほどあるから。それを勉強した方がいいよ」と言われました。
萩原健太さんからは、「ヤッチンはいいなー。まだまだ宝物があって」なんて言われます。
それは裏を返すと勉強をしてないだろ、ということなんですけど(笑)。
― 最近はどんな音楽を聴いていますか?
曾我:ジェリー・フィッシュのメンバーの人が作ったザ・リカリッシュ・カルテットですね。
あとは(山下)達郎さんの新譜かな。
― 基本的にポップなものがお好きなんですね。ELOとかも。
それがグッバイに反映されていますよね。
曾我:当時のアルバムは声も高いし、テンポも速いし、恥ずかしい部分もいっぱいあるんです
けど…。その時代をしっかり記録したものなので。
― これからグッバイを聴く人に聴いて欲しいアルバムはありますか?
曾我:どうですかね。1枚、1枚歴史があるというか、ストーリーがあるので、1枚目から
聴いてもらいたいですね。変わっていく様子が分かりますから。これだけ下手っぴだったのが、徐々に上手くなって、最後には、ちゃんとコンセプトのあるアルバムを作っていくという
部分に着地できているので。そして、その落とし前として10枚目をキチッと作れているので。
グッバイは解散することはないので、愛してくれるファンもいるし、メンバーはめちゃめちゃ
仲が良いし。だから、やれる時にはやりたいなと思っています。
― 来年7月に、中野サンプラザがなくなってしまいますよね。
最後にはグッバイにやって欲しいです。
曾我:本当に! やりたいですね。グッバイでも何度もステージに立ったし、
グッバイでの初ミュージカルがサンプラザでした。
― 最後にファンへのメッセージをいただけますか。
曾我:アイドル全盛、バンドブーム全盛の中でどっちつかずのグッバイを見つけてくれて、
ずっと変わらず応援してくれていて、「えっ? グッバイ?」って周りから言われることも
多かったと思います。ジャニーズの中でもアイドルしていないし。ロックバンドの中で、
ロックじゃないだろ、って言われていながら、僕らは難しい立ち位置にいたと思います。
それをちゃんと変わらず、支持して応援してくれた人たちは、本当に尊いと思うんです。ありがたいなと。今は音楽好きな人たちが応援してくれていると思いますが、感謝しかないです。
そして、今、30年以上経って、過去のアルバムが評価されていて、それを自分たちのことの
ように喜んでくれているファンの方がたくさんいることは、本当に幸せだと思います。
引き続き40周年も盛り上げていきたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。
(取材・構成 / 本田隆)
アイドル時代から長きにわたる曾我さんのキャリア。そして、その中心にあったグッバイの
メンバーとしての活動。いろんな思いが交差する良いインタビューになったと思います。
これだけの話を語ってくれた曾我さんには感謝しかありません。そして来年はThe Good Bye
デビュー40周年。どのようなアニバーサリーになるのか今から楽しみです!
曾我泰久インタビュー「一度の人生、突き進んでいきたい」
~後編~ 1 一部抜粋
今までにない斬新な舞台! 僕の楽曲を元に作られた5つのラヴストーリーを、5組の男女が
演じます。僕は俳優というよりもシンガーとして芝居に存在していて、弾き語りを担当。
そして役者が演じて、ストーリーが展開していきます。水木英昭プロデュースとの新企画で、
水木さんはずっと前から「曾我さんの曲で芝居を作りたい!」と言ってくれて、それが実現
しました。僕の曲を聞き続けてくれた人も、新鮮な感覚になると思う。上旬にファーストアクトが終わって、21日から27日までがセカンドアクトです。ミュージシャンと役者を同じスタンスでやってきて、良い所も悪い所もわかっていますから、この作品で橋渡しができるのではないかな、と思っています。ぜひ見に来ていただきたいですし、VOL.2以降も続けていく計画です。
――11月にも舞台が1本……。
福島三郎さんの主宰劇団、丸福ボンバーズの「フナバシTOYS」に出演します。立ち上げの頃からの劇団員なのですが、念願叶ってやっと舞台に立てます。今まではスケジュールが合わず、ゲスト参加でしたから。過去のリメイク作となる「フナバシTOYS」は、大好きな作品!
「絶対再演してほしい」と、10年位福島さんにリクエストしていたんです。笑って泣いて幸せな気分になって、気持ちがキレイになりますよ。今のこの世の中に、こんな美しいストーリーがあることを感じ取れると思います。この劇団はみんなボランティアで参加していて、チケット代は2000円。11月1日から10日まで、東京・千歳船橋のアポックシアターで開催して、仙台公演もあります。小さな劇場で、目の前でお芝居が見れてすごい贅沢! ぜひお越しください。
――そして在籍するバンド、The Good-Byeの30周年記念コンサート
( 11月17日、東京国際フォーラム ホールCにて開催 )も近付いてきましたね。
今でもこうやって僕が演奏して歌えるのは……僕の曲を聞いてくださる方たちがいてくれる
のは、グッバイの頃がんばったからだと思っているんです。ジャニーズ事務所所属の中で異色
だった僕らを、事務所が容認して、好きなように音楽作りをさせてくれた。それがあるから今がある、と改めて感じる30周年ですね。当時は目の前のスケジュールをこなすだけで大変で、
まさか30年経ってコンサートを開くとは思わなかった。先のことを考える余裕がありません
でした。でも中途半端なことをやらなかったから、今の環境や状況があるんですよね。グッバイの頃に作った作品は、僕の宝物。7月にベーシストの加賀八郎くんがひと足先に旅立ってしまいましたが、見守ってくれると思うし、彼の曲をメンバーで歌いつないでいきます! 記念コンサートをドカンとやって、この1年内に記念アルバムも作ります。グッバイは解散しません!
――グッバイの大型コンサートや舞台を控え、最近はどんなことを考えていますか?
運命を変えることはできないと感じ、やりたいことをやれる時に実行しなきゃもったいない。精一杯やることが生きている証……そんな風に考えています。12月にはクリスマス・ライヴを開催しますが、素敵でかわいいクリスマスの新曲があるので、発表できるといいなと思って
います。そして来年は芸能生活40周年を迎えます。たった1回の人生、悔い無きように
突き進んで、音楽を続けていきたいですね。(取材・文責:饒波貴子)
私、高校時代 ”The Good-Bye” のファンでLIVEに行ったりしていました ![]()
これからも ”The Good-Bye” を大切に、また活動してほしいです。応援しています ![]()
![]()
![]()
最近、また純ちゃんに嫌な事 (首や頭を痛くしない) をしてくるの止めて ![]()
![]()
【 ボードゲームの禁じ手 】を使わないで!
いくつかのゲームには、ルールで定められた禁じ手が存在する。
禁じ手を打った(指した)場合、即座に負けとなるのが一般的である。
スポーツやゲームのように明確な規則で禁じられたものだけでなく、
「使うべきでない」とされる手法についても「禁じ手」と呼ばれることがある。
※ このルールを違反した時点で、ゲームオーバー及びゲームアウト!
人の脳の中枢神経を触らない、潜在意識などに入ってコントロールしないで ![]()
![]()
![]()
( 目の錯覚、老眼近視。思考が低下、停止にしない。記憶が出来ない、出てこない、忘れる。人に自分の考えを言わさない。理性を失わせないで。胸などにモヤモヤとさせないで。口臭も
人の仕事の邪魔をしないで、人の後ろに憑かない憑依しない。喉、頭や首の神経を痛くしない。
特に、乗り物を運転している時は、絶対に頭を低下やボーっとさせないで!体調不良にしないで
人を縛らない、人をコントロールしないで、もっと自由にさせて。人のモノマネや水晶禁止。
人に嫌なことをしたり、言って脅さない。人に必要以上に執着や嫉妬しない。過保護にしない。
人にお金を使わさないで( 家や外食、テイクアウト、旅行仕事も含む )。プライバシー侵害、
個人保護法。人を嵌めないで。楽天、ソフトバンクグループに嫌な事はしないで、手塚にも。
その力、仕事にだけ使って、自分勝手に使わないで。みんな(全部)に対して良い様に使って。
人に対して完璧主義を押し付けないで(暴言や自分勝手な言動行動は慎んで、人を縛らない)
毎日、深夜に連絡してこないで。自分が言った言葉に責任を持って、高圧的に言ってこない、
考えが甘い、ワガママを言わないで。トイレ関係。唇びるを痺れさせない。こけさせない。
顔や身体を熱く冷たくしない )吸い上げない。怒りの感情を倍増しない、笑い上戸にしない。
人のアイデアを盗ったり、利用しないで自分で考えて。パワーや感情を抑えたり取らないで。
やる気を取らない。ちゃんと直して。職権乱用しない。全責任は、お母さん達に取ってもらう。
解散や休止、脱退、独立、業務提供解消させないで。離婚も。言論や表現の自由が法で定められている)今まで我慢してきたけど、人のPCやスマホにハッカーみたいに侵入してこないで ![]()
![]()
3つの約束やルール、個人的に約束した事、日本の常識は必ず守 って。みんなに対して ![]()
![]()
![]()
( 私の言うことを聞くように・命関係は打ち止め・引退をさせない。契約書、反故にしない )
いつもありがとうございます。
最後までお読みいただきありがとうございました ![]()
![]()