カラマーゾフの兄弟〈上〉 (新潮文庫)/新潮社
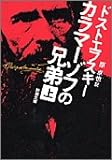
¥907
Amazon.co.jp
カラマーゾフの兄弟〈中〉 (新潮文庫)/新潮社
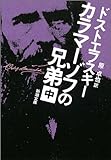
¥853
Amazon.co.jp
カラマーゾフの兄弟〈下〉 (新潮文庫)/新潮社
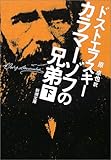
¥907
Amazon.co.jp
皆さんこんばんは。
当ブログはザ☆活字離れ世代で完全な読書難民の私が面白おかしく本を読んでいけたらいいなぁと完全に誰特でお送りしているのですが、今日はね、記念すべき日になるかもしれませんよ。
なぜなら本日の本は『カラマーゾフの兄弟』だから!!!
おいおい待てよと。おめーいつからそんなまともな本を読むようになったんだと。
確かに私にはちょっとまだ早い気がする……というかこんな本を読むほど高尚な考えを持つ日は一生来ない気がする……。でもほら、一応ほら、死ぬまでには読んでおきたいじゃないっすか!!!というわけで2015年の目標にしたんです。『カラマーゾフの兄弟』を読む!と。
■読み始める前に
もちろんこんな長い本。しかもあんまり知らない国ロシアの、しかも150年も前のお話に丸裸で挑んだら三行で撃沈してしまうでしょう。そう、私は読書離れ世代。自分にとても甘いのです。そこで以下の対策を立ててみました。
①人物相関図を手に入れる
http://www013.upp.so-net.ne.jp/hongirai-san/kids/k-soukanzu.html
こちらのサイト様にものすごい分かり易い相関図が載っています。この小説の一番のネックは登場人物が多いことと、一人の人物に対して呼び方がたくさんあること。(例:アリョーシャとアレクセイ、ドミートリィとミーチャ等)しかしこの相関図はそれらをすべて網羅してくれています。ありがてえ!!!
②読む内容を絞る
『カラマーゾフの兄弟』が名作だといわれる理由のひとつに、様々な小説の要素が味わえるというものがあります。推理小説、家族小説、群像劇、歴史小説、宗教小説、教育文学……でもこれらを一遍に味わおうとすると食あたりを起こしてしまいます。なので、「今回は○○に着目して読む!」と決めるといいと思います。先ほどのサイトには読書感想文なんかに生かせそうな面白着目ポイントが書いてあります。重ね重ねありがてぇありがてぇ……。
③イケメンを想像する(腐女子限定か……?)
本作の重要人物は何と言っても三兄弟とそのパパ。この人たちの人物をリアルに思い描けるか描けないかで面白さはきっと変わってくるはず。そこで、この人たちを自分の好みの顔で思い浮かべましょう。実在の俳優さんを想像してみるのもいいでしょう。幸いこの小説は映像化されています。宝塚バージョンでもよし、映画バージョンでもよし。私は想像しやすいので日本でドラマ化されたキャストで想像していました。
ドミートリィ→斉藤工さん
イワン→市原隼人さん
アリョーシャ→林遣都さん
フョードル→吉田鋼太郎さん
これでぐぐっと読みやすくなるはず。なんてったって皆さんイケメンですものペロペロペロペロ^p^
④キリスト教の基本について知る
このお話はキリスト教の考え方がキモになってきます。そのため、ある程度のキリスト教的な知識があったほうがより楽しめると思います。ロシアのキリスト教はロシア正教といってヨーロッパ的なカトリック信仰とはまた別なもの、とかね。私はキリスト教系の学校に行っていたので大丈夫だったのですが、「イエス・キリストって何した人?」という方はさらーっと勉強しておくといいと思いますよ!
さぁ、後は読むだけです!きっとすばらしい読書体験が皆さんを待っているでしょう!
以下ネタバレ感想
■人物描写と三兄弟について
大体一般的な小説に出てくる人物って、一言で言い表せる性格の人が多いと思うんです。「情に厚いが無鉄砲」だとか「ニヒルだが優しい心を持っている」だとか「家族想い」とかね。なんというか、作品に生かせそうな人間の一面だけを抽出し書いている感じ。
でもこの小説は人間の複雑なところ、両極端な部分を持ち合わせているところまでものすごく丁寧に書いているんです(だから長いんでしょうけど……)。読み始めはミーチャ→刹那的に生きる堕落したダメ人間、イワン→冷徹で理性的な頭脳派、アリョーシャ→信仰に厚い天使という分かり易い人たちだと思っていたのですが全然違いました。
特にミーチャは話が進むにつれてどんどん印象が変わってきます。三兄弟の仲で一人だけ母親が違い、父親からぞんざいに扱われて金を無心して酒におぼれることしか知らずに生きてきたミーチャは純粋な部分を発掘されることなく暴力的な部分ばかりが成長していってしまったんですね。
一人冷静にカラマーゾフ家から距離を置いていると思われたイワンは、実は誰よりもフョードルに似ていることを自覚し、父親に殺意を抱いていると同時に愛していることを知るという難しい性格。
■大審問官と神の不在について
ここが一番やっぱり面白かったです。
神様がいるのにこの世に悪がはびこっているのは、神様が人間たちに自由意志を与えたからだというのが現在では定説です。イエスは十字架にかけられて死ぬ直前、ピラトに「神の子なら自分で十字架からおりれるはずだ」と言われるのですが、それをしなかったのですね。それは、そこでもし自分を助けてしまったら、その奇跡に民衆が傅くことになるから。でもそれは本来の信仰ではなくて、抑圧されたものだとしてそれをしなかったんです。
でも大審問官は言うわけです。神様は人間を信じているからそんなことをなさったに違いないが、人間は神のありがたい言葉よりも目の前のパン一切れをありがたがる。貴方が期待してくださっているほどすばらしいものではない、と。
神様を信じたいがゆえにこう言ってしまうイワンの気持ちはものすごく良く分かります。その後悪魔が彼の元に現れてイワンに揺さぶりをかけるシーンも心に残ってます。曰く、人間の信仰に躓き(サタンに邪魔されて信仰を捨てようと思ってしまうこと)が無ければ、真の信仰は得られないと。苦難あって恋燃え上がるじゃないですけれど、障害を乗り越えてこそ真の信仰が得られるんですね。うーん、なるほど。
■アリョーシャとコーリャ
コーリャという中学生がこれらまたマセガキなんですけども、アリョーシャの前で自分を大きく見せようと必死なんですね。実際に賢い子なんですけども。いろんな本を読んで得た知識だとか偏った思考だとかに傾倒して、それをあたかも自分の意見であるかのように錯覚して吹聴してしまうんです。でもアリョーシャが「それは君の言葉じゃないね」と見抜くんですよね。
先日読んだ『教育の根底にあるもの』の中で林先生が「子供が自分の言葉で言っているかいないか、自分で考えているかいないかを見抜かなければならない」見たいな意味のことをおっしゃっていたことを思い出しました。
■ミーチャの裁判と許しについて
さて、最後の感動的なミーチャの裁判。もうね、逆転裁判ばりにアツい!!意義あり!あと検察と弁護士の人台詞長い。
ここで管理人の心を打ったのがフェチュコーウィチがアリョーシャを許そうと民衆に呼びかけるシーン。大審問官のところでも問題になった「人間は神様に信頼されているから自由意志を持っている」というところとも関係するのだと思うのですが、彼はいろんな罪を犯してきたミーチャを神からもらったその信頼に報いるために許そうというのですね。そしてその許すという行為がロシア全体を良くしていうのだ、というのです。ここはね、もう泣けるね……。
管理人が心に残ったのはこの部分でしたが、皆さんはいかがだったでしょうか。恋模様に注目して読んだ人はグルーシェニカとカテリーナという二人の女性についてもっと思うところがあったかもしれませんね。
ずっとアリョーシャ天使ペロペロと不純な動機で読み進めていましたが、こんな私でもとても面白かったので、きっと皆さんはもっと多くのことを感じていらっしゃるでしょう!カラマーゾフ万歳!
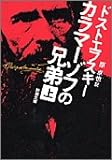
¥907
Amazon.co.jp
カラマーゾフの兄弟〈中〉 (新潮文庫)/新潮社
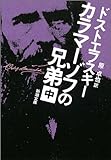
¥853
Amazon.co.jp
カラマーゾフの兄弟〈下〉 (新潮文庫)/新潮社
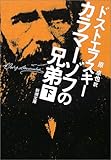
¥907
Amazon.co.jp
皆さんこんばんは。
当ブログはザ☆活字離れ世代で完全な読書難民の私が面白おかしく本を読んでいけたらいいなぁと完全に誰特でお送りしているのですが、今日はね、記念すべき日になるかもしれませんよ。
なぜなら本日の本は『カラマーゾフの兄弟』だから!!!
おいおい待てよと。おめーいつからそんなまともな本を読むようになったんだと。
確かに私にはちょっとまだ早い気がする……というかこんな本を読むほど高尚な考えを持つ日は一生来ない気がする……。でもほら、一応ほら、死ぬまでには読んでおきたいじゃないっすか!!!というわけで2015年の目標にしたんです。『カラマーゾフの兄弟』を読む!と。
■読み始める前に
もちろんこんな長い本。しかもあんまり知らない国ロシアの、しかも150年も前のお話に丸裸で挑んだら三行で撃沈してしまうでしょう。そう、私は読書離れ世代。自分にとても甘いのです。そこで以下の対策を立ててみました。
①人物相関図を手に入れる
http://www013.upp.so-net.ne.jp/hongirai-san/kids/k-soukanzu.html
こちらのサイト様にものすごい分かり易い相関図が載っています。この小説の一番のネックは登場人物が多いことと、一人の人物に対して呼び方がたくさんあること。(例:アリョーシャとアレクセイ、ドミートリィとミーチャ等)しかしこの相関図はそれらをすべて網羅してくれています。ありがてえ!!!
②読む内容を絞る
『カラマーゾフの兄弟』が名作だといわれる理由のひとつに、様々な小説の要素が味わえるというものがあります。推理小説、家族小説、群像劇、歴史小説、宗教小説、教育文学……でもこれらを一遍に味わおうとすると食あたりを起こしてしまいます。なので、「今回は○○に着目して読む!」と決めるといいと思います。先ほどのサイトには読書感想文なんかに生かせそうな面白着目ポイントが書いてあります。重ね重ねありがてぇありがてぇ……。
③イケメンを想像する(腐女子限定か……?)
本作の重要人物は何と言っても三兄弟とそのパパ。この人たちの人物をリアルに思い描けるか描けないかで面白さはきっと変わってくるはず。そこで、この人たちを自分の好みの顔で思い浮かべましょう。実在の俳優さんを想像してみるのもいいでしょう。幸いこの小説は映像化されています。宝塚バージョンでもよし、映画バージョンでもよし。私は想像しやすいので日本でドラマ化されたキャストで想像していました。
ドミートリィ→斉藤工さん
イワン→市原隼人さん
アリョーシャ→林遣都さん
フョードル→吉田鋼太郎さん
これでぐぐっと読みやすくなるはず。なんてったって皆さんイケメンですものペロペロペロペロ^p^
④キリスト教の基本について知る
このお話はキリスト教の考え方がキモになってきます。そのため、ある程度のキリスト教的な知識があったほうがより楽しめると思います。ロシアのキリスト教はロシア正教といってヨーロッパ的なカトリック信仰とはまた別なもの、とかね。私はキリスト教系の学校に行っていたので大丈夫だったのですが、「イエス・キリストって何した人?」という方はさらーっと勉強しておくといいと思いますよ!
さぁ、後は読むだけです!きっとすばらしい読書体験が皆さんを待っているでしょう!
以下ネタバレ感想
■人物描写と三兄弟について
大体一般的な小説に出てくる人物って、一言で言い表せる性格の人が多いと思うんです。「情に厚いが無鉄砲」だとか「ニヒルだが優しい心を持っている」だとか「家族想い」とかね。なんというか、作品に生かせそうな人間の一面だけを抽出し書いている感じ。
でもこの小説は人間の複雑なところ、両極端な部分を持ち合わせているところまでものすごく丁寧に書いているんです(だから長いんでしょうけど……)。読み始めはミーチャ→刹那的に生きる堕落したダメ人間、イワン→冷徹で理性的な頭脳派、アリョーシャ→信仰に厚い天使という分かり易い人たちだと思っていたのですが全然違いました。
特にミーチャは話が進むにつれてどんどん印象が変わってきます。三兄弟の仲で一人だけ母親が違い、父親からぞんざいに扱われて金を無心して酒におぼれることしか知らずに生きてきたミーチャは純粋な部分を発掘されることなく暴力的な部分ばかりが成長していってしまったんですね。
一人冷静にカラマーゾフ家から距離を置いていると思われたイワンは、実は誰よりもフョードルに似ていることを自覚し、父親に殺意を抱いていると同時に愛していることを知るという難しい性格。
■大審問官と神の不在について
ここが一番やっぱり面白かったです。
神様がいるのにこの世に悪がはびこっているのは、神様が人間たちに自由意志を与えたからだというのが現在では定説です。イエスは十字架にかけられて死ぬ直前、ピラトに「神の子なら自分で十字架からおりれるはずだ」と言われるのですが、それをしなかったのですね。それは、そこでもし自分を助けてしまったら、その奇跡に民衆が傅くことになるから。でもそれは本来の信仰ではなくて、抑圧されたものだとしてそれをしなかったんです。
でも大審問官は言うわけです。神様は人間を信じているからそんなことをなさったに違いないが、人間は神のありがたい言葉よりも目の前のパン一切れをありがたがる。貴方が期待してくださっているほどすばらしいものではない、と。
神様を信じたいがゆえにこう言ってしまうイワンの気持ちはものすごく良く分かります。その後悪魔が彼の元に現れてイワンに揺さぶりをかけるシーンも心に残ってます。曰く、人間の信仰に躓き(サタンに邪魔されて信仰を捨てようと思ってしまうこと)が無ければ、真の信仰は得られないと。苦難あって恋燃え上がるじゃないですけれど、障害を乗り越えてこそ真の信仰が得られるんですね。うーん、なるほど。
■アリョーシャとコーリャ
コーリャという中学生がこれらまたマセガキなんですけども、アリョーシャの前で自分を大きく見せようと必死なんですね。実際に賢い子なんですけども。いろんな本を読んで得た知識だとか偏った思考だとかに傾倒して、それをあたかも自分の意見であるかのように錯覚して吹聴してしまうんです。でもアリョーシャが「それは君の言葉じゃないね」と見抜くんですよね。
先日読んだ『教育の根底にあるもの』の中で林先生が「子供が自分の言葉で言っているかいないか、自分で考えているかいないかを見抜かなければならない」見たいな意味のことをおっしゃっていたことを思い出しました。
■ミーチャの裁判と許しについて
さて、最後の感動的なミーチャの裁判。もうね、逆転裁判ばりにアツい!!意義あり!あと検察と弁護士の人台詞長い。
ここで管理人の心を打ったのがフェチュコーウィチがアリョーシャを許そうと民衆に呼びかけるシーン。大審問官のところでも問題になった「人間は神様に信頼されているから自由意志を持っている」というところとも関係するのだと思うのですが、彼はいろんな罪を犯してきたミーチャを神からもらったその信頼に報いるために許そうというのですね。そしてその許すという行為がロシア全体を良くしていうのだ、というのです。ここはね、もう泣けるね……。
管理人が心に残ったのはこの部分でしたが、皆さんはいかがだったでしょうか。恋模様に注目して読んだ人はグルーシェニカとカテリーナという二人の女性についてもっと思うところがあったかもしれませんね。
ずっとアリョーシャ天使ペロペロと不純な動機で読み進めていましたが、こんな私でもとても面白かったので、きっと皆さんはもっと多くのことを感じていらっしゃるでしょう!カラマーゾフ万歳!

