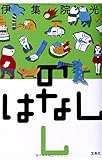初秋 (ハヤカワ・ミステリ文庫―スペンサー・シリーズ)/早川書房

¥864
Amazon.co.jp
みなさんこんばんは。
最近教養のためと思ってクラシックなんぞをiPodで聞いている私ですが、昔の作曲家さんのヅラってよくよく考えると非常に興味深い形をしていますよね。そもそもまずそれなんでかぶろうと思ったの??っていう疑問が頭から離れません。ハゲ隠すなら小粋な帽子でいいんじゃない??っていう。それとも何か別の理由があるのかしら。あれ、オーダーするときなんていってオーダーするのかしら。「ちょっとバッハのアレよりボリュームある感じで。うん、巻き毛は5段」とかってカスタマイズすんのかしら。いらないだろ。それ。
さて、本日の本はロバート・B・パーカー『初秋』です。
スペンサーシリーズと呼ばれる人気ハードボイルドものの一作。解説を読んでみますと、もう男の中の男!という感じのハードボイルド探偵にも関わらず、ハメットといった典型的な探偵とはまた一味違った特徴があるそうな。ハードボイルとといやぁ酒とタバコと女に目が無く、不規則な生活で、無口……というかっこいいんだけれどもネガティブというイメージを伴います。しかし、このスペンサー。体は鍛えるわ、めちゃくちゃおしゃべりだわ(彼女に演説しまくり。これ彼女嫌じゃないのかなww)、料理はするわ、お節介だわでものすごい健全な生活を送っています。それが、彼の思う男道を全うするために必要なことだからなのでしょう。
今回彼のところに舞い込んできたのは旦那に息子のポールを誘拐されたので取り戻してほしいという奥様・パティからのご依頼。しかし、スペンサーはポールの父親も母親も、どちらもポールを愛してはおらず、お互いを不快な思いにさせるためだけに子供を取り合っていることに気づきます。その証拠にポールはろくなものも食べさせてもらっておらず、日がな一日テレビを見ることしかせず、無気力・無感動な生活を余儀なくされていました。
お節介なスペンサーはひとまずポールを引き取ることを考えます。しかし、スーザンとの家庭生活のことや、探偵としての危険な生活のことを考えるとポールを養子として引き取ることなどは考えられません。そこで、スペンサーはポールに自立して生きることと、その方法を教えることにしたのでした……。
以下ネタバレ
私は20代前半のころ、ポールと同じように無気力無感動だった時期があって、同じように毎日テレビを見ては、まっすぐに座っていられるだけの筋力も無く、自分がこうなってしまったのはすべて周りの人間のせいだと青臭いことを考えていました。そんなときにこの小説に出会えていたらなぁと思わず思ってしまいました。
やりたいことが無いのなら徹底的に体力づくりをさせるというスペンサーの教育方針は大賛成です。体力が無ければやりたいことができてもできないし、そもそもやろうとする気力がわきません。習慣教育で有名な今村暁さんがやっておられる個人塾は、無気力・無関心な不登校な子が多かったらしいのですが、そこでもまずさせることは勉強ではなく腕立て伏せなどの体力づくりだったようです。
運動が苦手な人からしたら「脳みそ筋肉かよwww」と思うかもしれませんが、これって本当に大事なことだなと思います。心の弱い人は筋肉を鍛えて自分を強く見せるともいいますし、心の不安を解消するには、肉体の改造はとても良い手法なのだと思います。
日に焼けて、たくましく成長したラストシーンのポールには、かつてのひょろっこくて生気を感じないガキの面影はありませんでした。ポールの「なにも自分のものにすることができなかった」という言葉に対するスペンサーの一言は、まさしく名言であります。
大人になるということは自分の心と体を鍛えて、自分の責任で自分の人生を生きることなのだということを教えてくれたすばらしい作品でした。高校生におススメしたい本ですね。

¥864
Amazon.co.jp
みなさんこんばんは。
最近教養のためと思ってクラシックなんぞをiPodで聞いている私ですが、昔の作曲家さんのヅラってよくよく考えると非常に興味深い形をしていますよね。そもそもまずそれなんでかぶろうと思ったの??っていう疑問が頭から離れません。ハゲ隠すなら小粋な帽子でいいんじゃない??っていう。それとも何か別の理由があるのかしら。あれ、オーダーするときなんていってオーダーするのかしら。「ちょっとバッハのアレよりボリュームある感じで。うん、巻き毛は5段」とかってカスタマイズすんのかしら。いらないだろ。それ。
さて、本日の本はロバート・B・パーカー『初秋』です。
スペンサーシリーズと呼ばれる人気ハードボイルドものの一作。解説を読んでみますと、もう男の中の男!という感じのハードボイルド探偵にも関わらず、ハメットといった典型的な探偵とはまた一味違った特徴があるそうな。ハードボイルとといやぁ酒とタバコと女に目が無く、不規則な生活で、無口……というかっこいいんだけれどもネガティブというイメージを伴います。しかし、このスペンサー。体は鍛えるわ、めちゃくちゃおしゃべりだわ(彼女に演説しまくり。これ彼女嫌じゃないのかなww)、料理はするわ、お節介だわでものすごい健全な生活を送っています。それが、彼の思う男道を全うするために必要なことだからなのでしょう。
今回彼のところに舞い込んできたのは旦那に息子のポールを誘拐されたので取り戻してほしいという奥様・パティからのご依頼。しかし、スペンサーはポールの父親も母親も、どちらもポールを愛してはおらず、お互いを不快な思いにさせるためだけに子供を取り合っていることに気づきます。その証拠にポールはろくなものも食べさせてもらっておらず、日がな一日テレビを見ることしかせず、無気力・無感動な生活を余儀なくされていました。
お節介なスペンサーはひとまずポールを引き取ることを考えます。しかし、スーザンとの家庭生活のことや、探偵としての危険な生活のことを考えるとポールを養子として引き取ることなどは考えられません。そこで、スペンサーはポールに自立して生きることと、その方法を教えることにしたのでした……。
以下ネタバレ
私は20代前半のころ、ポールと同じように無気力無感動だった時期があって、同じように毎日テレビを見ては、まっすぐに座っていられるだけの筋力も無く、自分がこうなってしまったのはすべて周りの人間のせいだと青臭いことを考えていました。そんなときにこの小説に出会えていたらなぁと思わず思ってしまいました。
やりたいことが無いのなら徹底的に体力づくりをさせるというスペンサーの教育方針は大賛成です。体力が無ければやりたいことができてもできないし、そもそもやろうとする気力がわきません。習慣教育で有名な今村暁さんがやっておられる個人塾は、無気力・無関心な不登校な子が多かったらしいのですが、そこでもまずさせることは勉強ではなく腕立て伏せなどの体力づくりだったようです。
運動が苦手な人からしたら「脳みそ筋肉かよwww」と思うかもしれませんが、これって本当に大事なことだなと思います。心の弱い人は筋肉を鍛えて自分を強く見せるともいいますし、心の不安を解消するには、肉体の改造はとても良い手法なのだと思います。
日に焼けて、たくましく成長したラストシーンのポールには、かつてのひょろっこくて生気を感じないガキの面影はありませんでした。ポールの「なにも自分のものにすることができなかった」という言葉に対するスペンサーの一言は、まさしく名言であります。
大人になるということは自分の心と体を鍛えて、自分の責任で自分の人生を生きることなのだということを教えてくれたすばらしい作品でした。高校生におススメしたい本ですね。