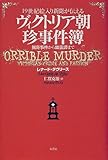虐殺器官 (ハヤカワ文庫JA)/早川書房

¥778
Amazon.co.jp
インフルエンザにかかりました。管理人です。
最初、ただの風邪かな~と思ってひたすらベッドで寝ていたのですが、熱が39.6度をマークしたときにこれはまずい。死ぬ。ちょっと三途の川見えてきた。と思ってあわてて救急病院へ。検査をしてもらったらインフルエンザでした。
ERのお医者さんって本当にすごいですよね。夜中の1時とか2時だとかにバリバリ働いて……。私を診察してくださったお医者さんは若い女の先生だったのですが、めっちゃ咳してました……先生……あなたこそ大丈夫ですか……?すいませんこんなときに診察してもらっちゃって……。
さて、本日の本は伊藤計劃さん『虐殺器官』です。
ゼロ年代ベストSFに選ぶ人も多いこの作品、今度アニメ映画化するようで。ミーハーな私は早速読んでみました。
舞台は2020年頃のアメリカ。主人公のクラヴィス・シェパード大尉は米軍の特殊検索群i分遣隊というところで暗殺の任務を請け負っていた。今回彼のところに来た仕事はジョン・ポールという男を生け捕りにすること。ジョン・ポールは発展途上国のPRを行う会社に勤めていた男だが、彼が行く場所行く場所で激しい虐殺・内乱が起こっているというのだ。いったいどうやって内乱を起こすのか、そしていったいなぜそんなことをするのか。SFとしてだけではなくミステリーとしても評価の高い作品です。
以下ネタバレ感想
これは偶然なんですけど、この本を読む数日前、私は「言語が思考を規定する」のだな~となんとなく考えていたんですよ。思考は必ず言語がないと行えないから、言語の範囲が思考の範囲なんだと思っていたんです。でもこの本は真逆のことを言っていて面白いなと思いました。つまり、思考というものは言語なんてものを使う前からすでにそこにあって、言語は後から発達したただの「器官」に過ぎないというんですね。キリンの首が長いほうが生存に有利だったように、言語を持ったほうが生存に有利だったからそれを獲得したまでだと。なるほど、と思いました。
ジョン・ポールはこの器官としての言語を「虐殺器官」として用いることで行く先々で内乱を起こしていくわけですが、その理由が「ええええ!そんなのありかよ!……でも確かにそうだ……」と納得せざるを得ない理由なんですよね。一流のホワイダニットという評価も頷けます。愛しいものの平和を守るための虐殺。持てる者がそれを持ち続けるために、持たない者のすべての死を背負う覚悟をしたジョン・ポール。決して許されてはいけないのだけど、日々の生活に追われてそんな場所には目も向けないというのは本当にそのとおりだと思ってしまいました。
このお話はシェパード大尉の一人称で進むわけですけども、痛覚や良心の呵責が外部からコントロールされている大尉の思考はなんとなく鈍磨していて、グロテスクな描写が多いにもかかわらず「見えているのに見えていない」感覚なんですね。私達のような普通の人間は自分というものの範囲がきっちりと自分で保有している肉体として想像できるけれども、彼らにとっては自分の範囲がなんだか曖昧なんじゃないでしょうか。この曖昧さの心地悪さはシェパード大尉のお母様の状態のときにも感じました。曖昧な死。生と死は完全に分かれているわけではなくて連続的につながっているというところ。月並みな言葉で言うと科学の発展に心の理解が追いついていない感じ。
ラストにシェパード大尉はアメリカで「虐殺器官」を発動させますが、私はなんだか「博士の異常な愛情」のラストシーンを思い浮かべてしまいました。アメリカ大変なことになってるのに、大尉の鈍磨した感覚では何も感じないんでしょうね。
どうでもいいのですが、私の好きなモンティ・パイソンネタがところどころ出てきてうれしかったですw特に『モンティ・パイソンとホーリーグレイル』は傑作だと思うので、興味をもたれたかたは是非ご覧になってくださいね!

¥778
Amazon.co.jp
インフルエンザにかかりました。管理人です。
最初、ただの風邪かな~と思ってひたすらベッドで寝ていたのですが、熱が39.6度をマークしたときにこれはまずい。死ぬ。ちょっと三途の川見えてきた。と思ってあわてて救急病院へ。検査をしてもらったらインフルエンザでした。
ERのお医者さんって本当にすごいですよね。夜中の1時とか2時だとかにバリバリ働いて……。私を診察してくださったお医者さんは若い女の先生だったのですが、めっちゃ咳してました……先生……あなたこそ大丈夫ですか……?すいませんこんなときに診察してもらっちゃって……。
さて、本日の本は伊藤計劃さん『虐殺器官』です。
ゼロ年代ベストSFに選ぶ人も多いこの作品、今度アニメ映画化するようで。ミーハーな私は早速読んでみました。
舞台は2020年頃のアメリカ。主人公のクラヴィス・シェパード大尉は米軍の特殊検索群i分遣隊というところで暗殺の任務を請け負っていた。今回彼のところに来た仕事はジョン・ポールという男を生け捕りにすること。ジョン・ポールは発展途上国のPRを行う会社に勤めていた男だが、彼が行く場所行く場所で激しい虐殺・内乱が起こっているというのだ。いったいどうやって内乱を起こすのか、そしていったいなぜそんなことをするのか。SFとしてだけではなくミステリーとしても評価の高い作品です。
以下ネタバレ感想
これは偶然なんですけど、この本を読む数日前、私は「言語が思考を規定する」のだな~となんとなく考えていたんですよ。思考は必ず言語がないと行えないから、言語の範囲が思考の範囲なんだと思っていたんです。でもこの本は真逆のことを言っていて面白いなと思いました。つまり、思考というものは言語なんてものを使う前からすでにそこにあって、言語は後から発達したただの「器官」に過ぎないというんですね。キリンの首が長いほうが生存に有利だったように、言語を持ったほうが生存に有利だったからそれを獲得したまでだと。なるほど、と思いました。
ジョン・ポールはこの器官としての言語を「虐殺器官」として用いることで行く先々で内乱を起こしていくわけですが、その理由が「ええええ!そんなのありかよ!……でも確かにそうだ……」と納得せざるを得ない理由なんですよね。一流のホワイダニットという評価も頷けます。愛しいものの平和を守るための虐殺。持てる者がそれを持ち続けるために、持たない者のすべての死を背負う覚悟をしたジョン・ポール。決して許されてはいけないのだけど、日々の生活に追われてそんな場所には目も向けないというのは本当にそのとおりだと思ってしまいました。
このお話はシェパード大尉の一人称で進むわけですけども、痛覚や良心の呵責が外部からコントロールされている大尉の思考はなんとなく鈍磨していて、グロテスクな描写が多いにもかかわらず「見えているのに見えていない」感覚なんですね。私達のような普通の人間は自分というものの範囲がきっちりと自分で保有している肉体として想像できるけれども、彼らにとっては自分の範囲がなんだか曖昧なんじゃないでしょうか。この曖昧さの心地悪さはシェパード大尉のお母様の状態のときにも感じました。曖昧な死。生と死は完全に分かれているわけではなくて連続的につながっているというところ。月並みな言葉で言うと科学の発展に心の理解が追いついていない感じ。
ラストにシェパード大尉はアメリカで「虐殺器官」を発動させますが、私はなんだか「博士の異常な愛情」のラストシーンを思い浮かべてしまいました。アメリカ大変なことになってるのに、大尉の鈍磨した感覚では何も感じないんでしょうね。
どうでもいいのですが、私の好きなモンティ・パイソンネタがところどころ出てきてうれしかったですw特に『モンティ・パイソンとホーリーグレイル』は傑作だと思うので、興味をもたれたかたは是非ご覧になってくださいね!