進々堂世界一周 追憶のカシュガル/新潮社
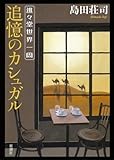
¥1,620
Amazon.co.jp
御手洗潔と進々堂珈琲 (新潮文庫nex)/新潮社

¥637
Amazon.co.jp
皆さんこんにちは。
最近、外見って大事だな。と思い始めた管理人です。小さい頃から今までブスの名をほしいままにしてきた管理人です。思春期以降はこじらせにこじらせ、「ブスは何着ててもブス」という悟りを開き、自前の糞掃衣(洗いすぎて擦り切れたユニクロ)を着ていました。でもね、この歳になってやっとね、気づいた。それが「ブスと身なりは分けて考えろ!」ということなんですね。「ブスは何着てもブス」はこれは世界の真実です。が、汚いブスと小綺麗なブスはやっぱり違うんだなと。思うわけです。すぐに自分の生活を変えることは無理ですが、少しずつアイロンの必要な服なんかを増やしていこうと思います。
そんなブスがお送りする本日の本は島田荘司御大『進々堂世界一周 追憶のカシュガル』です。最近文庫で出た『御手洗潔と進々堂珈琲』はこの作品の改題なので、間違えて重複購入しないように注意注意ですぞ!!
舞台は1974年の京都。我らが御手洗さんは世界一周の放浪のたびを終えて、京都大学で脳科学の研究をしている学生さん。御手洗さんいきつけなのが京大北門前の珈琲店『進々堂』。このお店、実在するようですね。食べログに記事が載っていました。瀟洒な洋館のような外観をしている老舗の喫茶店、という感じでしょうか。その進々堂で京大を目指す浪人生「ぼく」は御手洗さんから世界の様々なお話を聞く、というストーリーです。
もう御手洗さん大スキーの管理人は活字に御手洗という文字が出てくるだけで嬉しいのですが、その御手洗さんが……しゃべってる……物食ってる……動いてる……(五体投地
正直お話のメインは外国で御手洗さんが出会った人々なので彼の影は薄いのですが、もうね、いいですいいです。御手洗さんがいてくれるだけでいいです。
以下ネタバレ感想
①進々堂ブレンド 1974
雨の降る日風邪気味の「ぼく」が御手洗さんから借りたヴィックス喉スプレーから、中学生のときの古い記憶がよみがえる短編。日本海の漁村で育った「ぼく」はフィッシャーマンズという海の向こうの酒場を模したお店の女主人に恋をしてしまった。しかし、中学生だった彼にはその恋を実らせることが出来るはずも無く……。
「差別と誇りと道徳心は実は同じもの」という御手洗さんの言葉に驚きました。綺麗好きな人は確かに汚い習慣を持っている人を軽蔑しますよね。強い差別をする人は、実は強い道徳心があるそうな、うーむ確かに。そして「日本人では若輩者が差別の対象」という言葉は1970年代にも言えたのですね。今でこそ本当にそのとおりだと思いますが、当時もやれ新幹線授業やら受験戦争の過熱やらで若者は疲弊していたのかもしれませんね。
チンザノ・コークハイはヴィックス喉スプレーの味がするんでしょうか……どっちもやったことないんだよな……。
②シェフィールドの奇跡
シェフィールドはイングランドの工業都市。
御手洗さんたちが昼食に入った定食屋で、少し発達に障害のある青年を見たことから話は始まります。シェフィールドで御手洗さんが会ったギャリーという青年は学習障害を持っていましたが、体格が大きく、重量挙げの才能を持っていました。少し競技のスタートが年齢的に遅れはしたけれど、このまま練習を積めばイングランド代表だって夢ではないかもしれません。しかし、障害を持ったギャリーのコーチは嫌がられました。重量挙げは一歩間違えれば大怪我をするスポーツだし、万一のことがあったら……と考えるコーチの気持ちもなんとなく分かります。
最後の最後にお願いしに行ったレオンというコーチにも首を横に振られ、憤懣やるかたない気持ちでギャリーとその父親が彼の元を去ろうとしたそのとき、大きな地震が起こります。そして防災用のシャッターが、倒れたレオンの上に落ちてきてしまいます。シャッターの重さは350ポンド、ギャリーの目指す重量挙げの重さと同じです。彼は持ち上げることが出来るのか……?
ちょっとシャッターの空気の読めすぎな感じに笑ってしまいましたw
健常者がそうではない人の可能性を勝手に決めてしまうのは傲慢ですよね。怪我やトラブルなんてものは健常者でもありうることなのだし。○○だから出来ない、じゃなくてこうやったらできるって考えられるようになりたいものです。
③戻り橋と悲願花
京都は一条にある戻り橋は、陰陽師である安部清明がその下に式神を隠していたというのが有名ですよね。この戻り橋は行っても必ず帰ってこられると、出兵のときに好んでお見送りの場所に選ばれたのだとか。今回はこの戻り橋にも咲いている悲願花のお話。
1970年代といえばまだまだ戦争の傷跡がリアルに残っていた時代だったのでしょう。御手洗さんが話すのは朝鮮から日本につれてこられ「風船爆弾」を作らされた幼い姉弟のお話。風船爆弾って初めて太平洋を横断したかなりすごい武器だったようです。原理は至極簡単で、日本からアメリカに向いて吹く強い偏西風にのせて、爆弾つきの気球を流すというもの。材料は和紙と爆弾だったので大量に作れたことから、それなりの脅威として恐れられたようです。
しかし作らされる少女達にとってはたまったものではないですよね。食べるものも食べさせられず、体が動かなくなってきたらヒロポン(覚せい剤)を飲まされて作業をやらされたようです。姉へのひどい仕打ちに耐えられなくなったビョンホンは、日本兵に悲願花の球根を食べさせて復讐しようと考えますが……。
彼岸花は天国に咲いている蓮以外の唯一の花だそうですが、遠きアメリカの地に一面にさいた景色はそれはそれはすばらしいのでしょうね。
④追憶のカシュガル
カシュガルは中国の西南に位置する町。その町に咲く昔ながらの桜と、日本に狂い咲くソメイヨシノのお話。
日本で「桜」というとソメイヨシノをイメージしてしまいますよね。でもアレは江戸時代にたった一本偶然出来た異端な品種だそうな。その一本をクローンにしてそこら中に植えたのが、今皆さんが春に目にする桜たち。そろそろ寿命が来るそうで、日本の街から一気に桜が消えてしまう日が来るのかもしれません。
カシュガルで御手洗さんが出会った一人の老人。かれは美しい英国英語を話し、教養もあるのになぜか街の皆に避けられて軽蔑されていた。その影には彼が昔イギリスのスパイであった事実が隠されていました。イギリス人に利用され、民族の誇りを奪われた老人は、古くからモンゴルや清、西欧諸国に蹂躙されたカシュガルの土地そのものをあらわしているのでしょう。
私は1980年代生まれなので1970年の記憶は残念ながらないのですが、今おじいちゃんおばあちゃんの人たちはこういう時代を生きてきたのかなぁと思いました。御手洗成分が薄かったのが少し残念ですが、島田さんの作品はやっぱり面白いです。
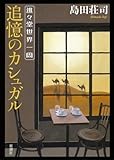
¥1,620
Amazon.co.jp
御手洗潔と進々堂珈琲 (新潮文庫nex)/新潮社

¥637
Amazon.co.jp
皆さんこんにちは。
最近、外見って大事だな。と思い始めた管理人です。小さい頃から今までブスの名をほしいままにしてきた管理人です。思春期以降はこじらせにこじらせ、「ブスは何着ててもブス」という悟りを開き、自前の糞掃衣(洗いすぎて擦り切れたユニクロ)を着ていました。でもね、この歳になってやっとね、気づいた。それが「ブスと身なりは分けて考えろ!」ということなんですね。「ブスは何着てもブス」はこれは世界の真実です。が、汚いブスと小綺麗なブスはやっぱり違うんだなと。思うわけです。すぐに自分の生活を変えることは無理ですが、少しずつアイロンの必要な服なんかを増やしていこうと思います。
そんなブスがお送りする本日の本は島田荘司御大『進々堂世界一周 追憶のカシュガル』です。最近文庫で出た『御手洗潔と進々堂珈琲』はこの作品の改題なので、間違えて重複購入しないように注意注意ですぞ!!
舞台は1974年の京都。我らが御手洗さんは世界一周の放浪のたびを終えて、京都大学で脳科学の研究をしている学生さん。御手洗さんいきつけなのが京大北門前の珈琲店『進々堂』。このお店、実在するようですね。食べログに記事が載っていました。瀟洒な洋館のような外観をしている老舗の喫茶店、という感じでしょうか。その進々堂で京大を目指す浪人生「ぼく」は御手洗さんから世界の様々なお話を聞く、というストーリーです。
もう御手洗さん大スキーの管理人は活字に御手洗という文字が出てくるだけで嬉しいのですが、その御手洗さんが……しゃべってる……物食ってる……動いてる……(五体投地
正直お話のメインは外国で御手洗さんが出会った人々なので彼の影は薄いのですが、もうね、いいですいいです。御手洗さんがいてくれるだけでいいです。
以下ネタバレ感想
①進々堂ブレンド 1974
雨の降る日風邪気味の「ぼく」が御手洗さんから借りたヴィックス喉スプレーから、中学生のときの古い記憶がよみがえる短編。日本海の漁村で育った「ぼく」はフィッシャーマンズという海の向こうの酒場を模したお店の女主人に恋をしてしまった。しかし、中学生だった彼にはその恋を実らせることが出来るはずも無く……。
「差別と誇りと道徳心は実は同じもの」という御手洗さんの言葉に驚きました。綺麗好きな人は確かに汚い習慣を持っている人を軽蔑しますよね。強い差別をする人は、実は強い道徳心があるそうな、うーむ確かに。そして「日本人では若輩者が差別の対象」という言葉は1970年代にも言えたのですね。今でこそ本当にそのとおりだと思いますが、当時もやれ新幹線授業やら受験戦争の過熱やらで若者は疲弊していたのかもしれませんね。
チンザノ・コークハイはヴィックス喉スプレーの味がするんでしょうか……どっちもやったことないんだよな……。
②シェフィールドの奇跡
シェフィールドはイングランドの工業都市。
御手洗さんたちが昼食に入った定食屋で、少し発達に障害のある青年を見たことから話は始まります。シェフィールドで御手洗さんが会ったギャリーという青年は学習障害を持っていましたが、体格が大きく、重量挙げの才能を持っていました。少し競技のスタートが年齢的に遅れはしたけれど、このまま練習を積めばイングランド代表だって夢ではないかもしれません。しかし、障害を持ったギャリーのコーチは嫌がられました。重量挙げは一歩間違えれば大怪我をするスポーツだし、万一のことがあったら……と考えるコーチの気持ちもなんとなく分かります。
最後の最後にお願いしに行ったレオンというコーチにも首を横に振られ、憤懣やるかたない気持ちでギャリーとその父親が彼の元を去ろうとしたそのとき、大きな地震が起こります。そして防災用のシャッターが、倒れたレオンの上に落ちてきてしまいます。シャッターの重さは350ポンド、ギャリーの目指す重量挙げの重さと同じです。彼は持ち上げることが出来るのか……?
ちょっとシャッターの空気の読めすぎな感じに笑ってしまいましたw
健常者がそうではない人の可能性を勝手に決めてしまうのは傲慢ですよね。怪我やトラブルなんてものは健常者でもありうることなのだし。○○だから出来ない、じゃなくてこうやったらできるって考えられるようになりたいものです。
③戻り橋と悲願花
京都は一条にある戻り橋は、陰陽師である安部清明がその下に式神を隠していたというのが有名ですよね。この戻り橋は行っても必ず帰ってこられると、出兵のときに好んでお見送りの場所に選ばれたのだとか。今回はこの戻り橋にも咲いている悲願花のお話。
1970年代といえばまだまだ戦争の傷跡がリアルに残っていた時代だったのでしょう。御手洗さんが話すのは朝鮮から日本につれてこられ「風船爆弾」を作らされた幼い姉弟のお話。風船爆弾って初めて太平洋を横断したかなりすごい武器だったようです。原理は至極簡単で、日本からアメリカに向いて吹く強い偏西風にのせて、爆弾つきの気球を流すというもの。材料は和紙と爆弾だったので大量に作れたことから、それなりの脅威として恐れられたようです。
しかし作らされる少女達にとってはたまったものではないですよね。食べるものも食べさせられず、体が動かなくなってきたらヒロポン(覚せい剤)を飲まされて作業をやらされたようです。姉へのひどい仕打ちに耐えられなくなったビョンホンは、日本兵に悲願花の球根を食べさせて復讐しようと考えますが……。
彼岸花は天国に咲いている蓮以外の唯一の花だそうですが、遠きアメリカの地に一面にさいた景色はそれはそれはすばらしいのでしょうね。
④追憶のカシュガル
カシュガルは中国の西南に位置する町。その町に咲く昔ながらの桜と、日本に狂い咲くソメイヨシノのお話。
日本で「桜」というとソメイヨシノをイメージしてしまいますよね。でもアレは江戸時代にたった一本偶然出来た異端な品種だそうな。その一本をクローンにしてそこら中に植えたのが、今皆さんが春に目にする桜たち。そろそろ寿命が来るそうで、日本の街から一気に桜が消えてしまう日が来るのかもしれません。
カシュガルで御手洗さんが出会った一人の老人。かれは美しい英国英語を話し、教養もあるのになぜか街の皆に避けられて軽蔑されていた。その影には彼が昔イギリスのスパイであった事実が隠されていました。イギリス人に利用され、民族の誇りを奪われた老人は、古くからモンゴルや清、西欧諸国に蹂躙されたカシュガルの土地そのものをあらわしているのでしょう。
私は1980年代生まれなので1970年の記憶は残念ながらないのですが、今おじいちゃんおばあちゃんの人たちはこういう時代を生きてきたのかなぁと思いました。御手洗成分が薄かったのが少し残念ですが、島田さんの作品はやっぱり面白いです。

