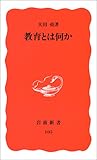音楽 (新潮文庫 (み-3-17))/新潮社

¥529
Amazon.co.jp
最近暖かくなってきたのでワンランク薄いコートで出かけたら夜に冬将軍の逆襲を受けた管理人です。まだまだ寒いとは言いますが、田んぼのあぜ道に緑の草がちらほら生えているのを見かけました。梅の蕾もだいぶ膨らんできたようです。頑張れ春将軍!!!冬将軍の首を取れ!!!
本日の本は三島由紀夫『音楽』です。
管理人は三島由紀夫のちょっと硬い文体が苦手で、敬遠していたのですが、この『音楽』は大衆向けの婦人雑誌に掲載されていたというだけあってやわらかい文体でとても読みやすかったです。
■あらすじ
日比谷で精神分析医をやっている汐見の元に、弓川麗子というその名のとおり麗しい女性がやってくる。彼女は故郷の許婚者から逃れるように東京に進学しそのまま就職、職場で隆一という想いの人ができた。しかし、彼女は汐見にこういうのである。「先生、どうしてなんでしょう。私、音楽がきこえないんです」と。
もちろんこの音楽は比喩表現で、音楽を聴く=オルガスムに達する。ということ。麗子は不感症を直してもらうために汐見の元にやってきたのでした。この小説は麗子という女性の不感症の原因を探る、一種のミステリー小説のような様相を呈しています。汐見先生はときに彼女に医師として以上の魅力を感じながら、彼女の過去から彼女自身も知りえなかった本当の気持ちを、鋭い精神分析で紐解いていきます。
■ネタバレ感想
精神分析というものがどれくらいの精度で患者さんの複雑な気持ちを言い当てられるのかは存じ上げないのですが、ここまで原因と結果がはっきりして、予想がぴったりあったら気持ちいいだろうなと思いました。恋人の隆一さん、病に命を落とした許婚者、不能者ゆえに自殺を試みる花井青年。様々な人との出会いと反応から彼女の不感症の真の原因に導かれる過程は、まるでミステリーを読むようなカタルシスがあります。
麗子は兄との近親相姦によって、兄以外の人の音楽を聴くことができなくなり、その苦しみを癒すために「兄の子どもを生めばよいのだ」という思考に至ります。小説を読むうちに麗子に心を合わせた読者は、自分の兄の子どもを生むことの望み叶わないと知った麗子の絶望と解放をリアルに味わうことが出来るように思います。
それにしても「音楽をきく」って素敵な表現ですよね。この比喩を味わうだけでもこの小説を読む価値があると思います。文学苦手、三島由紀夫苦手な人でも大丈夫!三島由紀夫入門にどうぞ!

¥529
Amazon.co.jp
最近暖かくなってきたのでワンランク薄いコートで出かけたら夜に冬将軍の逆襲を受けた管理人です。まだまだ寒いとは言いますが、田んぼのあぜ道に緑の草がちらほら生えているのを見かけました。梅の蕾もだいぶ膨らんできたようです。頑張れ春将軍!!!冬将軍の首を取れ!!!
本日の本は三島由紀夫『音楽』です。
管理人は三島由紀夫のちょっと硬い文体が苦手で、敬遠していたのですが、この『音楽』は大衆向けの婦人雑誌に掲載されていたというだけあってやわらかい文体でとても読みやすかったです。
■あらすじ
日比谷で精神分析医をやっている汐見の元に、弓川麗子というその名のとおり麗しい女性がやってくる。彼女は故郷の許婚者から逃れるように東京に進学しそのまま就職、職場で隆一という想いの人ができた。しかし、彼女は汐見にこういうのである。「先生、どうしてなんでしょう。私、音楽がきこえないんです」と。
もちろんこの音楽は比喩表現で、音楽を聴く=オルガスムに達する。ということ。麗子は不感症を直してもらうために汐見の元にやってきたのでした。この小説は麗子という女性の不感症の原因を探る、一種のミステリー小説のような様相を呈しています。汐見先生はときに彼女に医師として以上の魅力を感じながら、彼女の過去から彼女自身も知りえなかった本当の気持ちを、鋭い精神分析で紐解いていきます。
■ネタバレ感想
精神分析というものがどれくらいの精度で患者さんの複雑な気持ちを言い当てられるのかは存じ上げないのですが、ここまで原因と結果がはっきりして、予想がぴったりあったら気持ちいいだろうなと思いました。恋人の隆一さん、病に命を落とした許婚者、不能者ゆえに自殺を試みる花井青年。様々な人との出会いと反応から彼女の不感症の真の原因に導かれる過程は、まるでミステリーを読むようなカタルシスがあります。
麗子は兄との近親相姦によって、兄以外の人の音楽を聴くことができなくなり、その苦しみを癒すために「兄の子どもを生めばよいのだ」という思考に至ります。小説を読むうちに麗子に心を合わせた読者は、自分の兄の子どもを生むことの望み叶わないと知った麗子の絶望と解放をリアルに味わうことが出来るように思います。
それにしても「音楽をきく」って素敵な表現ですよね。この比喩を味わうだけでもこの小説を読む価値があると思います。文学苦手、三島由紀夫苦手な人でも大丈夫!三島由紀夫入門にどうぞ!