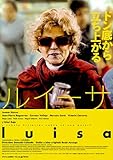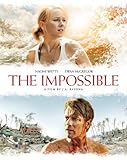というタイトルのネット営業メールが届きました。
サイトに挙げているメールアドレス宛です。こちらの社名と氏名を記載したものですが、本文はフォーマットで書かれたものです。
以下、本文を引用すると、
この度、弊社パートナーである「Yahoo!知恵袋」というQ&Aサイトで、
生活者や企業の相談に乗ってくださる「プロ回答者」を新たに募集する
こととなりまして、貴サイトを拝見しご連絡させていただきました。
ぜひ、建築家様のポジションとして
ご参加をいただきたいと考えております。
突然のご連絡となりまして大変恐縮ではございますが、
ご興味・ご関心を持っていただけるようでございましたら、
ぜひ以下の企画詳細をご覧くださいませ。
というものです。
その下には企画概要資料のリンク先が貼っていて、チラシみたいなPDFが2枚、おそらくA4裏表イメージのものがありました。
その表面は下のものです。

メールを読み進めて行くと、応募要項が出てきます。
――――――――――――――――――――――――――――――
応募要項・お申込方法
――――――――――――――――――――――――――――――
■システム利用料金
・初期費用:37,800円
・月額基本料金:4,320円
・成果に基づく追加課金:0円
・決済機能を利用した場合の従量課金:15%
■ご登録条件
・直近3年以内に2年以上、該当専門領域の業務に従事していること。
・お名前(ビジネスネーム可)と顔写真を公開して活動ができること。
・Yahoo!知恵袋へ定期的に回答の投稿ができること。
■お申込方法
・下記の資料請求フォームより資料をご確認いただけます。
続いて資料請求のリンク先が載っています。
びっくりです。
2年以上の専門分野に従事している専門家に知恵袋で回答してもらうために、その専門家からお金を徴収するってどういうこと?
これってたとえば建築家が図面書いたものをクライアントにお金を添えて渡すってことじゃないか。
設計料をマイナス請求させるんか。
医者に診てもらって医者からお金もらうんか?
Yahoo!どうなってるねん。