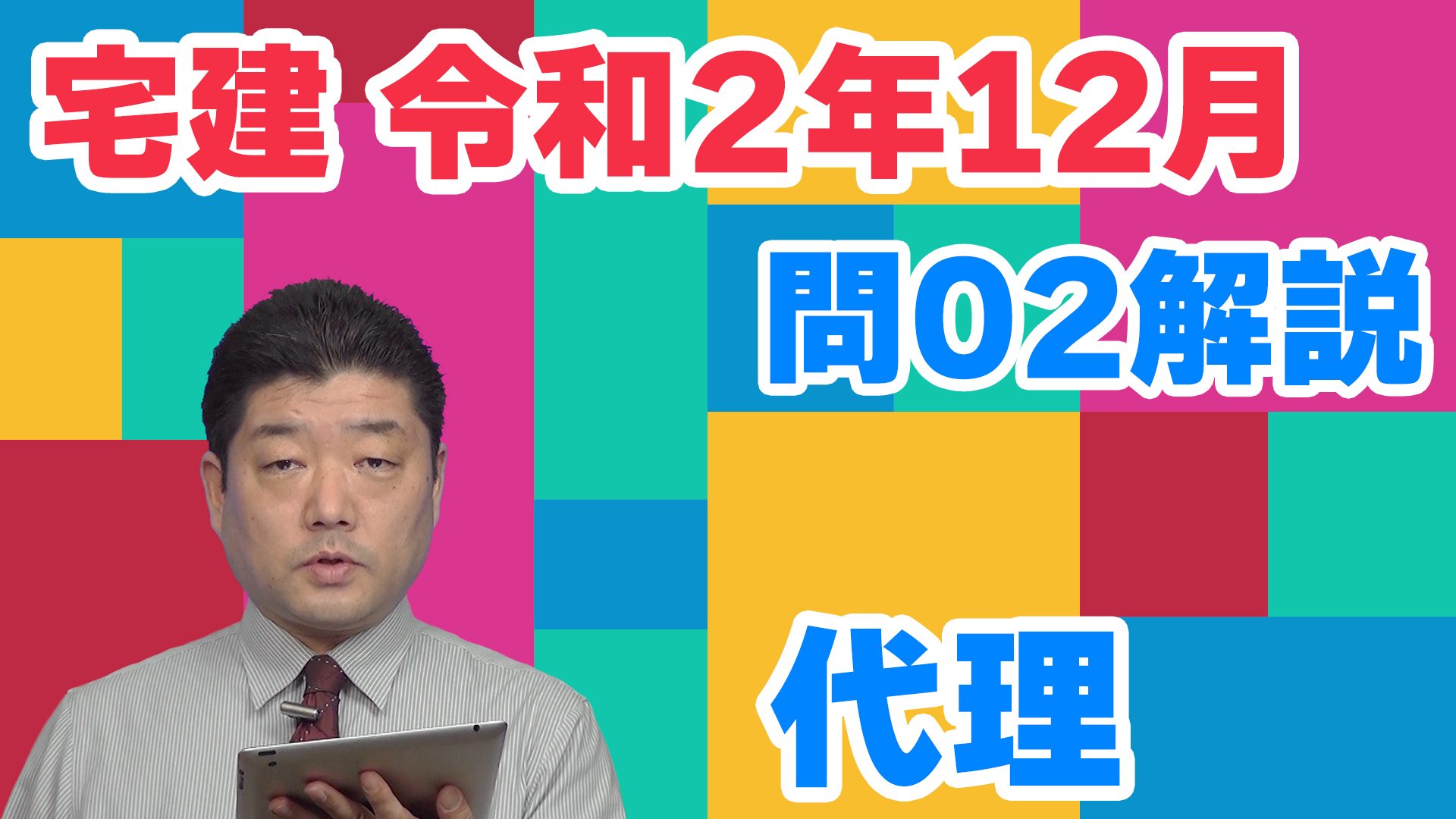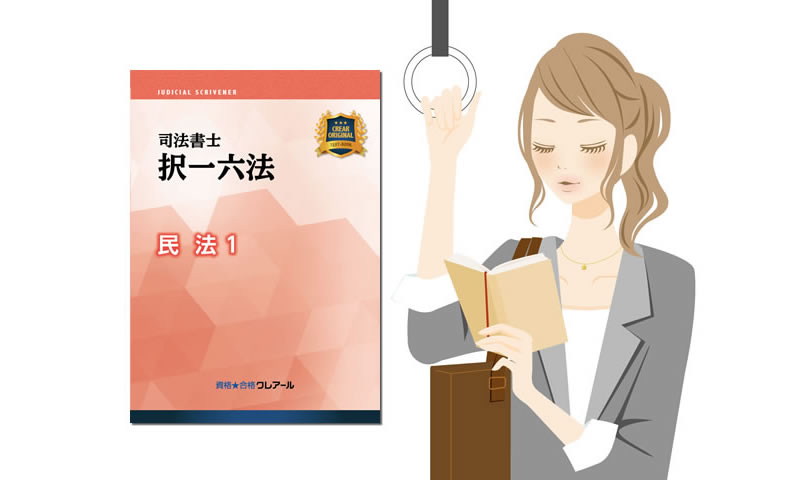※宅建Tシリーズと「基本テキスト」については「序章」をご覧ください。
A) そもそも「代理」とは?
S:本人以外が、役所の窓口で手続きするには、委任状が必要です。
の関係になります。
生成AI(Google gemini)に、「民法の代理とは」で聞いたところ
『代理とは、代理人が本人に代わって意思表示をして、その法律効果は本人に帰属させることを言います。
代理には、「法定代理」と「任意代理」の2種類があります。
法定代理は民法のいたるところに規定されており、親権者が未成年者を代理する場面が典型例です。親権者は、未成年者に代わって財産を管理したり、法律行為を行ったりすることができます。また、親権者がいない場合や親権を喪失した場合には、未成年後見人が未成年者に代わって財産管理や法律行為を行うことができます。
一方、任意代理は、本人と代理人との代理権授与行為によって生じます。たとえば、Aが所有する土地をBに売りたい場合に、AがBに対して土地の売却についての代理権を与えたとすると、Aが本人、Bが代理人となります。』(24年5月20日)
でした。
P: 今回の筆者と母の関係は、「任意代理」での
本人Pが、委任状を通して、P母に代理権を授与。その結果、P母が筆者Pの代理人になった
ということですね?
S:はい。
数百円の証明書でも、数億の不動産でも「任意代理」の構図は変わりません(例 ↓)
B)未成年者の法定代理人/制限行為能力
S:このため、「代理」は宅建試験でもよく出題されるわけですが、出題パターンが広いので、今回は、生成AIも例に挙げた「法定代理人」の中で、さらに「未成年者・未成年後見人」について取り上げます。
P:ちなみに、今後は、
宅建14 代理② 成年後見人 ※あわせて、認知症高齢者問題と家族信託
宅建15 代理③ 任意代理と過去問
を予定しているそうで、その間「代理」については、基本テキストの40~53ページで、基本知識は得られるとのことです。
S:ちょうど、昨年(23年の問8)で、「未成年者の法定代理人」が出題されたばかりなんですよ。
B-1)制限行為能力と未成年者
P:そもそも、 問題8 肢1、2の「制限行為能力」が、?なんですが…。
S:「制限行為能力者」も、民法で重要な基本ワードのひとつで、基本テキストでは20ページ~と、「代理」より前に説明があります。
ただ、「法定代理人」というのは、そもそも判断能力が不十分な「制限行為能力者」を保護するために法律が定めた「保護者」、いわば「制限行為能力者」と「法定代理人」とは表裏一体なので、都度、説明しますね。
P:未成年者=子ども の保護者といえば、親ごさんですよね。 ※補足1
S: 民法の規定でいえば、「親権者」です。
民法第818条
① 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
<中略>
③ 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。
③に、「父母の婚姻中」とあるように、父母が離婚すると、これまではどちらか片方が「親権者」になりました。
P: これまでは…ということは、これからは?
S: 24年5月17日に「離婚後も父母双方が子どもの親権を持つ”共同親権”」の改正案が国会で可決されましたので、2年以内に民法改正が行われます。
今年の宅建試験と直接関係はありませんが、昨年(23年)「未成年者」が出題されたのも、22年4月施行の改正民法で、18歳未満が「未成年者」とされたことと関りがありそうなので、民法改正に関わる事項は注目です。
B-2) 取り消しできる? できない? それが問題だ
P: 現状は、親権者が子(未成年者)の法定代理人になるということで。
さて、23年問8は、4つの肢がどれも、未成年者の行為の「取り消し」ですが、上のリンク先の解説を読むと、「法定代理人の同意なく未成年者が契約などの法律行為をしたときは、取り消すことができる」わけですよね?
ただし、法定代理人や本人が成年になった後「追認」すれば、「取り消し」自体が、取り消しになる? と。
S: ごく簡単にまとめると、そうなりますが、上の解説記事のとおり、
a:そもそも未成年者が取り消しできるケースか?
a-1:単独でできる行為(法定代理人の同意不要)
a-2: 未成年者が相手を騙したとき
a-3:時効
b:追認ができるのか? できないのか?
b-1:未成年者本人の追認
b-2:法定代理人の追認
b-3:追認の催告
など、場合分けがややこしいため、昨年(23年)の問8のような出題がされたわけです。
なので、いったん、a,bの場合分けを確認してから、問8に当てはめてみます。
B-2-a-1)単独でできる行為(法定代理人の同意不要)は、取り消しできない
P: まずは、a-1:法定代理人の同意が不要、つまり未成年者が単独でできる行為ですね。
S:ここは、民法第5条に規定があります。
民法 第5条
『① 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
② 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
③ 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。』
①の「単に権利を得、又は義務を免れる法律行為」は、たとえば、親戚からお年玉をもらうなど、未成年者の不利益にならない行為です。
P: 5条の②で、『法定代理人の同意なしの法律行為は、取り消しができる』と、規定されているわけですね。ここは、主語がないのですが、未成年者本人と、法定代理人のどちらも取り消しができわけですか?
S: 法定代理人については、別に民法120条に規定があります。
『① 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。』
未成年者だけでなく、次回説明予定の成年被後見人など、制限行為能力者全般について、本人またはその代理人は、取り消しができます。
この120条の「制限行為能力者」については、次回も触れます。
P:そして、民法5条③で、
・法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内
・目的を定めないで処分を許した財産
も、未成年者が単独で処分できると。
S:「目的を定めないで処分を許した財産」は、子どものお小遣いをイメージしてもらうと、分かりやすいと思います。
あと、民法6条1項の
『一種または数種の営業を許された未成年者が、その営業に関してする行為』
も、単独でできる行為になりますが、こちらは宅建業法と関わるので(かなり後になると思いますが)その際にふれます。
B-2-a-2)未成年者が相手を騙したとき
S: 民法21条に
『制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。』
とあって、この条文も制限行為能力者全般に当てはまりますが、たとえば高校生が20歳以上だと偽って、コンビニでお酒を買ったら、取り消しできないということですね。
P: それはまた、別の問題がありそうですが…。
B-2-a-3)時効
S: 消滅時効については、宅建T:11で、おもに債権を例に説明しましたね。
取消権については、民法126条に規定がありまして、
第126条
『取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。』
追認については、次のB-2-bで説明します。
取消権全般について、行為の時から20年で時効により消滅するわけです。
P:15歳で契約して35歳ですか? その間は取消ができるとなると、相手方が困ると思いますが…。
S:「未成年者本人の追認」と「追認の催告」は、次のB-2-bで順に、説明します。
B-2-b)そもそも追認とは?
P: 「追認」は、文字通り「追加でOKする」ということですよね。
S: そうですね。
民法の122条に
『取り消すことができる行為は、第120条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。』
とあります。
本来は取り消しができますが、この「追認」の意思表示をした後は、取り消せなくなります。
120条は、先にB-2-a-1)で挙げました。
P: 今回の、未成年者のケースでは未成年者本人と法定代理人が追認できるわけですね?
S: 未成年者は、18歳に達すると、追認ができるようになります。これが、下記第126条の太字
『取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。』
ですね。
P: つまり、18歳から未成年者も追認ができる。
その後5年間、つまり23歳の時点で、126条の規定により、取消権が消滅するわけですね。
B-2-b-1:未成年者本人の追認
S:「追認」については、民法124条に、
『① 取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。
② 次に掲げる場合には、前項の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しない。
一 法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をするとき。
二 制限行為能力者(成年被後見人を除く。)が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認をするとき。』
とありまして、未成年者の場合は、18歳(成年)になって「取消しの原因となっていた状況が消滅」し、かつ取消権があることを知った後でないと、追認できません。
が、②-2 によって、法定代理人の同意をえれば未成年者でも追認できます。
P:次回は、冒頭で書いたように
宅建14 代理② 成年後見人 ※あわせて、認知症高齢者問題と家族信託
の予定です。
※補足1 基本テキスト20ページ。赤ん坊や幼稚園児などの行為(契約)は、そもそも「意思能力」がないため「無効」(取り消しと違って、初めからなかったものとされる)です。
【BGM】
S選曲:ニック・カーショウ「The Riddle」
P選曲:スパンダー・バレエ 「True」
【写真提供】Pixabay