「それで、もし八丁堀が来たら、……お嫁さんのほうの話はどう云っておくの」
直吉はどきっとして振返った。しかし、その云い方は、まきがここにいる気持ちになったことを示すものだ、ということに気づき、ぱっと顔を明るくしながら、
「そいつはあっしから返辞をしますよ」
こう答え、そこにいる文吉を抱いて、二度も三度も乱暴なくらい高くさしあげた。
「おとなしく待ってるんだぜ、坊、今日は直がいいお土産を買って来るからな、早く帰って来るからな、いいか、おとなしく待ってるんだぜ」
まきは泣き笑いのような表情で、直吉のよろこびにあふれる声を聞いていた。
(p325より)
---------------------------------
好きとか慕っていると、言葉にしなくても十分に2人の気持ちが伝わってくる文章です。
今回は、先日紹介した『柳橋物語・むかしも今も』の2編目、むかしも今もを紹介します。
こちらも、柳橋物語と通じる、切ない恋愛と江戸の人の温かさや風景が、人情小噺を聞いているような読みやすさで伝わります。
あらすじはというと、結構『柳橋物語』のように複雑ではあるのですが、
主人公は愚直だけが取り柄の直吉という男。
この直吉は早いうちに両親に死なれ、9歳の時から紀六という指物師の家の世話になります。
もちろん、職人たちの中にあっては直吉は「のろま」と呼ばれたり、ひどい扱いを受けるのですが、そんな彼を紀六の親方と奥さんは優しく見守ります。
親方との子である「まき」の子守りとなった直吉は熱心に真剣に、しかし心優しくまきの世話をするのです。
そんな折、清次という容姿端麗で頭のいい若者が紀六に弟子入り、まきも、他の弟子衆も次第に直吉よりもこの清次に関心・興味が湧いていってしまいます。
そんな清次を直吉は苦手にしていました。というのも、他の連中が自分ではなく清次愛情が移ってしまったことへの嫉妬なんていう浅いものではなく、自分の愚鈍さが見抜かれているという恐れ、そして自分に持っていないものをもっていることに対しての敗北感といったほうがいいでしょう。
その後、奥さんと親方が相次いで死んでしまいます。直吉は、清次とまきの後見を頼まれ、しかも稼業を守ってほしいと懇願されます。2人は結婚、直吉はまきへの想いを隠しながらも、親方の言いつけ、そしてこれまで良くしてもらった紀六を守るために献身的に働きます。
しかし、直吉には清次に対する一つの疑念が。親方が死に際し、打ち明けたことなのですが、それは、
それは、清次は紀六の金を持ち出して博打にうつつを抜かしているということ。
実際、注文された品の質は雑になって、弟子たちもどんどん離れていっている有様。
そこで直吉はある行動に出ます。
では、詳しい内容は以下に掲載することにします。
ネタバレを含む個人的な感想です。
~1回目 2009.12.31~
ではあらすじを続けます。
直吉は家を、まきを守るためにも清次に忠告します。
とはいえ清次のばくち打ちは止まることなく、お得意さんだった店やかつての弟子まで金をせがみに行く有様。
ついに弟子の力を借り、清次はしばらくの間、江戸を離れて清い体にすることにします。
まきと、まきのお腹にいた子どもを残して。
そうして文吉という子どもを産んだまきと直吉は、それぞれ日々を過ごしていくのですが、地震が起き、被災をしたまきの目が見えなくなってしまうというさらなる災難が。
これまで別々に暮らしていた直吉とまき、文吉は一緒に暮らすことにし、清次の帰りを待つことにします。
直吉は自分の想いをひた隠しにし、自分を抑えながら。
3人の生活が、貧乏ながらも幸せになって行くのですが、風の噂で、清次はやはり博打をやめることができず、逃げた先の上方でも続けているとのこと。もはやどうしようもない男です、清次。
そんなそんな折、ついに帰ってきました。清次が。しかも若干の誤解をしながら。
当然、一つ屋根の下で自分の妻子と、妻の幼少時を含め自分よりも一緒にいた時間が長い男が暮らしていたのですから、何があってもおかしくないと思った清次の疑心も分かるのですが、直吉は言われもないことで罵られたこと、そして賭博をやめられなかったことを一気に責めます。
初めてといってもいい、直吉が苦手だった清次と向き合っての非難です。
清次はその場を離れますが、直後、直吉はすぐ自分の言ったことでまきと清次の関係が壊れてしまったと後悔するのです。なんて愚直なんだ、直吉。。

しかし、まきの発言は彼を救うことに。まきはすでに清次に愛想を尽かしており、むしろ直吉がきちんと言ってくれたことに感謝さえするとのこと。しかも、まきは幼い頃から盲目となってしまった今に至るまで献身的に世話をしてくれている直吉の愛に気づいたとも告白。
ようやく、直吉の愛が実り通じたのです。
感想です。
途中、ヒロインが盲目になってしまい、それを献身的な愛情で支える、というのは、先日に読んだ『春琴抄』における佐助と春琴と似たような構造なのですが、佐助のマゾヒスティックな偏愛とは違い、直吉の場合は仮にまきがどのようになろうとも直吉のあふれんばかりの愛情は変わりません。
結末は書いてありませんが、直吉はまきの告白をしっかり受け止め、今後3人は仲良く暮らしていくことでしょう。もしかすると、結婚するのではないかと思えるような書き方でさえあります。
「あたしの望みはもう一つしきゃないの、それだけでいいの――聞いて呉れて直さん」
「あっしにできることでしょうね」
「今でなくってもいいの、いつか、あんたの気持ちがそうなったら、――もしもそんな気持になるときが来たら、……」
空地の向うの端で、船から砂を揚げる賑やかなざわめきが聞えだした。直吉は赧くなった顔で、とまどいをしたように、曇り日のどんよりした空をふり仰いだ。
(p360)
ここでは、直吉の気持ちは言葉には表れていません。
しかし、「あんたら、今までこの物語を読んできたんでしょ?そしたら直吉の気持ちはもう言わなくても分かるでしょ?それを直吉に最後まで言わせちゃうっちゃあ野暮ってもんよ」という作者の声が聞えてきそうな感じがします。
また、物語としては戻りますが、3人の同居生活によるよからぬ噂を心配したかつての紀六の弟子たちが、直吉に縁談話を持ってきて、まきと文吉は弟子家族が面倒を見るということが提案された場面でも、直吉とまきの表情や直接的には触れない言葉で、愛情を表現しています。
それが冒頭に紹介した部分なのですが、縁談を断ることを知った時のまきの明るい表情、そしてそれを察した時の直吉の明るい声。
何も言わなくても愛情が伝わるんですねぇ。
この小説はその表現が巧くなされていると思いました。
『柳橋物語』とも当然に通じる部分はありますが、『柳橋物語』はおせんが幸太の愛情を知ったのが遅かったということが悔やまれるのに対し、この『むかしも今も』は2人の明るい結末が、心温まる感じがします。
総合評価:★★★☆
読みやすさ:★★★☆
キャラ:★★★☆
読み返したい度:★★★★






 )を書いておくことにします。
)を書いておくことにします。
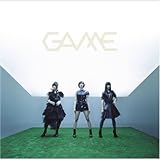

 と思えて仕方ありません。
と思えて仕方ありません。

