いったん何かを心に決めると、そのための冷静な算段以外は、事の是非や損得の判断や感情などの一切が消えてしまう。自分がそういう男だということに気づいたのは、十六歳で同級生だった女生徒を追い回し、二階の窓から相手の自宅に侵入して警察沙汰になったときだったが、そのときも実は、その女生徒に心底恋焦がれていたというのではなかった。以来、自分がやろうとしたことにはいつも、自分でも説明のつかない空白が伴っているのを自覚してきたが、まさにそのときも似たような感じだった。一彰は、朝に目覚めたときと同じ、重力しかない何者かであり、まるで興奮していなかったし、冷静だったのだ。
(p22-23より)
---------------------------------
一彰という主人公が、その心の空白を次第に埋めていく、そんな長大な話です。
高村薫さんの長編李歐を紹介します。
今回は、読むのに苦労しました。
その理由としては、まず、長いということ。文庫にして約500ページ。そして登場人物に中国人・朝鮮人が出てくるので、特徴が掴みにくかったこととあわせて、余計に長く感じました。
そして、時代背景や舞台設定が自分に馴染みの薄いものだったことです。
時代は1970年代から90年前くらい、舞台は主に大阪なのです。さらには登場人物の一人、守山耕三からは1930年代の満州事変から日中戦争にかけての話も語られることで馴染み薄さはパワーアップしたりと、なかなかキツかったです。
そして、本来は恋愛物だったり冒険物だったりという本をこれまで愛読していた自分にとって、この本のようないわゆる「ハードボイルドもの」に慣れていなかったということが一番の理由のような気がしました。
しかし、裏を返せば、初体験ということでかなり新鮮で、読み応えがありました。
割に冷静な文体ながらも、そのスリリングなストーリー展開によって、思わずうなってしまう所も多々ありました。
物語は、どこか感情が欠落した吉田一彰という主人公を軸に、闇社会に足を踏み入れたり(もしくは成り行き上で踏み入れることとなってしまった)、守山耕三や娘の咲子、刑事の田丸、裏社会の原口や数々の女性らと触れ合ったり、李歐と呼ばれる同い年の中国人とかかわり合いながら、自分の生きる道を模索していく、といったような内容です。
では以下はネタバレ含むので、いやな方は見ないで下さい。
- 李欧 (講談社文庫)/高村 薫

- ¥780
~1回目 2010.1.14~
自身の頭の整理をつけるためにもあらすじをざっと書いておきますと、
大阪大学に通う大学生の吉田一彰。
彼は一時期、祖父母のもとで東京で育ったのですが、実は以前、大阪に母と2人で暮らしていました。守山耕三が経営する守山工場のそばで。
しかし、母は守山工場の従業員と2人で駆け落ちたために、一彰は東京で暮らすことになったのです。
そんな思いから、大阪にやってきて、当時工場にいた中国人・朝鮮人の従業員を探すことになります。
とはいえ、別に母を探したいとかいう明確な目的はなく、感情の欠落している一彰のこと、なんとなくといった方がいいかもしれません。
そんな中、一彰はふとしたことから殺人の幇助をすることになります。
しかもそのターゲットとなっていたのは、かつて母とかけ落ちた男も含まれており、ここからいよいよ一彰の人生が大きく動き始めます。
犯行を行った銃撃犯が、不思議な魅力を持つ李歐で、事件後、その李歐を匿っていたのはかつて子ども時代に縁のあった守山工場の工場主、守山耕三。さらには笹倉という闇社会に生きる老獪な男も射殺事件の実行犯の一人であり、守山とも銃を作らせていたということで関係があり、幼少期の一彰も知っていたといい、一彰と以後様々な場面で関係してきます。
李歐は、笹倉が取り引きに使う銃を横取りし、金儲けをしようと、一彰に呼びかけます。
一彰はその提案に同意し、ここから何やら普通とはいえない、一彰と李歐の友情を超えた仲が濃密になっていきます。
2人は銃略奪をうまく成功させ、その足で李歐は中国大陸で一旗挙げることを一彰に言いのこし、日本を去っていきます。一彰はそんな李歐に、「待っているから、いつか自分を中国大陸へ連れて行ってくれ」と嘆願し、この壮大な願いが以後一彰の生きる道となっていくのです。
李歐が日本を去った一方、一彰は横取りした銃を笹倉と取り引きし、守山が笹倉から借りていた金を帳消しにするという約束で返却、殺人幇助での数年間の懲役刑を経て、守山工場で働くことになり、守山死後は、守山工場の2代目として工場を守っていきます。
さらには守山の娘、咲子とも結婚をし、子どもを授かり、それなりに安定した生活を送りますが一彰はなんだかスッキリしません。
それは、李歐との約束があったから。
しかし、そんな折、李歐は途中、死に瀕する場面もありながら、約束どおり、大陸にムラを作っており、一彰をいつでも迎えられるとの事。
一彰は日本での今の生活と、約束とに悩みます。
咲子にも相談するのですが、咲子は当然反対します。あわや離婚という状況がありながらも咲子と邂逅、咲子も一緒に中国へ渡ることを考えるということに。
しかし、その矢先、咲子は何者かが送ってきた爆弾によって帰らぬ人に。
一彰は、もはや自分が生きる道は中国しかないことを実感し、息子と共に李歐のつくった中国のムラへ行くのです。
・・・なんだか核心をきちんと話せていない様なあらすじになってしまいましたが(笑)、次に感想を書いておきます。
まず、一番に触れておかなければならないのはタイトルにもなっている、中国人の李歐。一彰ほどの登場シーンはないものの(実際李歐が一彰と絡むのは前半のクライマックスと最後の少ししかないのですが)、その存在感は圧倒的なもので、一彰でなくともそのキャラクターに惚れてしまいそうです

その李歐と一彰との関係は、友情以上の同性愛的な雰囲気を感じさせます。
一彰は男として李歐に魅力を感じているというより、李歐といると骨抜きにされている、熱にうなされているとも言えるかもしれません。
それは例えば、李歐が一彰に銃の横取りをしようと持ちかけられた、その李歐の声を頭の隅に置きながら、房子という中年の女性と性行為を行うのです、それはそれは激しい興奮を伴って。
または、李歐の生死を他人から聞くにつけ異常なほどに一喜一憂するところからもそれが伺えます。
そして、その李歐と、最終的に手を結んだのが笹倉。かつて李歐と一彰に銃を略奪され、目の敵にしていただろう彼ですが、彼もまた李歐に惹かれた一人なのでした。
しかし、それと同時にこの事実は、月日が経つと色んな状況が、当時には到底考えられないくらいに変わってしまうことがある、という歴史的法則すらも物語っている気がします。
物語は冷戦真っ只中の60~70年代を主軸に、その冷戦の崩壊までを追ったものですが、冷戦最中にあと数十年で冷戦は終わる、ということは夢物語だったはず。
しかも、冷戦時、共産主義国である中国に渡航するということは、現在の旅行感覚では全然なくて、死を賭した命がけのものだったはずです。
しかし、世界は変わった。冷戦も終わり、中国も市場開放が進みつつある。ゆえに中国への渡航はすんなりと行けるようになった。一彰はそこで決心した間もなく中国へ向かうことが出来たのです。
そう考えると、人の気持ち、歴史、これらが年月が経てば何かしら変わっていくことを示すと同時に、変わらないもの、つまり一彰と李歐の気持ち、これがより強調されて普遍的なものに感じました。
次に、一彰と守山耕三との関係。
これは思わずうるっときてしまいます。おそらく2人はお互い親子だと思っていたでしょうが、そこに至るまでは様々な葛藤があったのです。
特に守山は、
・自分の工場の従業員が一彰の母親と駆け落ちをしたことによって、一彰の人生が変わってしまったこと。
・実は、工場では密かに銃の製造を行っており、そういった闇の部分を一彰に触れさせたくなかった。
ということから、一彰が守山工場に勤めるということに、一彰と関わっていくことに躊躇があったのでしょうが、それがすでに親心といいましょうか。
むしろ、守山は幼少の一彰に対して、すでに親のように接していたのではないかと思います。
母親の駆け落ち当日、守山は一彰を喫茶店に連れて行き、その帰りに不意に守山に抱き上げられるのです。一彰に対して色んな思いがあったのだと思うと、この場面は胸が苦しくなります。
だから、結果的に守山工場を継ぐようになり、まるで親子同然の生活を少しでも送れたということは、守山にとってすごく幸せだったのだろうなぁ

最後に、一彰と咲子の関係。
一彰は、自分を感情が欠落しているとか、冷静に物事を考えると分析しているようですが、咲子と出会い、耕太という息子を授かるにつれ、それが変わっているように思います。
もちろん、一彰は気づいていないだろうけども。
しかし、現に咲子が家を出てしまって、色々考え事をしながら機械で指を怪我してしまうこと、なにかと耕太にかまうそのパパっぷりは、少なくともいい家族じゃないか、いや、むしろ普通のよくある家庭ではないのかとも思えてしまいます。
端から見れば幸せだと言うことでも、当人は気づいていなかったり、否定したりする。
でも、これって実は普通によくあることであり、確かに若い頃は無茶をした一彰ですが(もちろん本人はそう思っていないだろうけど)、守山耕三や咲子や耕太と触れていき、また次第に年をとっていくことでいい親父になっていったんじゃないなぁと思いました。
ただ、普通の親父と決定的に違っていたのは、一彰には李歐がいたこと。
夢を追って大陸に行く、というよりは、大陸に行くことが彼の生きる道になっていたという迫真の決意は最終的に果たされますが、咲子を爆死で亡くしてしまったことで、より未練がなく中国へいけたんだろうな

この小説、前半は読みやすいとはいえませんが、後半に行くにしたがい各登場人物それぞれに愛着のようなものが湧いてきて、面白いです。
機械のことには疎いので、旋盤のしくみや銃の構造なんかを細かく説明されたのはきつかったですが、一彰が、頭でこんなことを考えているのかと思うと、それすらも愛着が湧きました。
総合評価:★★★☆
読みやすさ:★★
キャラ:★★★☆
読み返したい度:★★★★
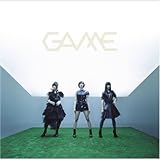
 」と驚愕、CDショップに走り、Perfumeを追いかけることに決めたのです。
」と驚愕、CDショップに走り、Perfumeを追いかけることに決めたのです。









