-
- Atomic Heart/Mr.Children

- ¥3,059
概要:1994年に発表された、Mr.Childrenの4thアルバム。300万枚以上を売り上げている、Mr.Childrenにとって最多の売上を誇る(2010年現在)。このアルバムが発売された前後、1994年-1995年は、彼らの作るシングル・アルバムが全てミリオンセールを達成したことから、俗に「ミスチル現象」なる社会現象となっていく。本作はまさにその先駆け的な作品である。
総論:
言わずもがなの、お化けアルバム。Mr.Childrenのアルバムの中でも傑作の一つとして後世に至るまで、語り継がれることだろうと思います。
曲はそれぞれがよく作られていて、それがシングルであろうとカップリングであろうとアルバム初出であろうと、まったく質の違いは感じられません(12曲中、シングルは「Innocent World」と「Cross Road」しかありませんが、全曲がシングルとして有り得るクオリティなので全くすごいバンドです)。
今のMr.Childrenはさほど興味がないのですが( )、この頃は美メロが溢れ出して嬉しい悲鳴を上げていたんではなかろうか、くらいの印象を受けます。
)、この頃は美メロが溢れ出して嬉しい悲鳴を上げていたんではなかろうか、くらいの印象を受けます。
アレンジも、ミスチル第5のメンバーとも評される、小林武史さんとMr.Childrenがうまく噛み合って、素晴らしい音作りがなされています。
アルバムの曲順は比較的曲調で
ロック→ポップ→ダーク→ポップ
といったように分かりやすい内容であります。
抄説:★は5つが満点で☆は0.5点。さらに違う色のタイトルにクリックしていただくと偏狭な思い入れの記事に飛びます。
1.printing ☆
カメラのシャッター音が重なる効果音です。
評価しようがありませんが、次の曲にも効果音としてこのシャッター音が登場するので、意味のないトラックでもありません。
2.Dance Dance Dance ★★
このような渇いた音は、初期のMr.Childrenには珍しいと思うのですが、それだけ音楽の幅の広さを窺い知ることができます。
それまでのシングルには見られない音なので、従来の音作りにはとらわれない、前進性が伺われます。
歌詞は社会風刺やエロ描写も入りつつ、それでいてサビはポップで、オルガンやギターのワウなんか入ったりしてなかなかです。
最後のドラムとギター、好きですが、素晴らしく素敵な個人的に好きなメロディではないので、星は低めです。
3.ラヴ コネクション ★★★★
このアルバムがヒットしている最中に出された、これまたお化けシングル「Tomorrow never knows」のカップリングとして、後にシングルカットされた曲です。
こちらもロックテイストではありますが、
しっかり決め打ちされている、よいこのポップロックです。
編成はバンドにブラスセクションが加わっています。冒頭のSEとの関連から、どこかのクラブで歌っている的な感じがします。
ギターはサビやソロでこれまた全曲と同様、エフェクトとしてワウが使われており、確かにこの時期のミスチル(もしくは小林武史プロデュース作品)には多かったような気がします。
歌詞もやはりちょいエロ描写。女性の声もコーラスとして入っているのでより、それが浮き彫りになります。
4.Innocent World ★★★☆
前記2つがロックテイストだったためか、3曲目で
ミスチル王道ポップの登場。
イントロだけでなんだか頬が緩みます

先に触れた、このアルバムに収録されている2つのシングルのうちの1曲なのですが、こちらは前作の勢いもあって、彼らにとってオリコン初登場1位、さらにはその年の日本レコード大賞を受賞するという、バンドとしてはある意味頂点を極めたといっても過言ではない作品です。
ストリングスやシンセサイザー、アコースティックギターの音色が透明感を演出、サビでは鉄琴のような音色でさらにパワーアップ。
ソロは珍しく、ギターではなくベース。とはいえはっちゃけるわけでもなく、きっちり弾いています。しかしこの部分、アコースティックギターとシンセサイザーと合わさりすごくいい音の空間を演出しているのです。
最後のサビに入る前だけ3拍置くなんて憎いなぁ~
 「その時は笑って」と歌う部分、ここがこの歌で一番好きな部分
「その時は笑って」と歌う部分、ここがこの歌で一番好きな部分です。むしろここを聴くために聞いているくらい素敵です。
最後はコードの違う前奏で締めるところも練られているなぁ
 5.クラスメイト ★★★★
隠れた名曲発見
5.クラスメイト ★★★★
隠れた名曲発見です

この時期、小林武史さんのプロデュース作品にはスチールドラム音とシンセフルート音が多用されているのですが、この歌の前奏もそう。
柔らかいホーンセクションやオルガンもこの歌によく合います。
歌詞は思わず再会したかつてのクラスメイト。その男女の秘密の恋を歌っています。
しかし曲調は明るく桜井さんも思い詰めたような歌い方ではないのですが、途中のホーンのソリ(3:22~)から展開部していくにつれ、なんだかその歌声が切々としてくるように感じます。
こちらも3曲目、「ラヴ コネクション」ど同様、シングル「everybody goes-秩序のない現代にドロップキック-」のカップリングとして収録されています。
しかし、よく言えばカップリングになりうるクオリティの高さが証明されてもいるんですが、
悪く言えば手抜きではないのかなぁと思ってしまいますが・・・
6.CROSS ROAD ★★★★☆
この名曲の嵐はなんなんでしょう

こちらは、Mr.Childrenを世に広めた1曲です。エンジンがかかりにくかったものの、そのメロディが次第に認知されるや否や、ぐんぐんとセールスを伸ばし、彼らにとって初のミリオンセールに達したシングル曲であります。
もちろん、メロディや歌詞は美しく、グッと来るものがあるのですが、私自身は、その
アレンジのものすごさに強烈に惹かれました。
これはここでは語りきれないので、「1曲詳説」の中で語りたいと思います。
が、前奏を例に取ってみると、
シンセフルートのハモりから始まり4分で刻むストリングス、それを支えるのびやかなベース(中川さん)で始まります。この規則正しい4分音符で刻まれるストリングスが、これから先、歩んでいくんだ、という歩調と重なる気がするのです。
途中でエレキ(田原さん)が入り、サビ直前でドラム(鈴木さん)も本格的に登場し、歌(桜井さん)が始まる。この順に楽器・メンバーが増えていく、そして盛り上がったテンションで歌が始まるこの感じが好きです。
この前奏からも凄く練られているのだなということを感じます。
認知されるべくして認知された歌なんだなぁ
 7.ジェラシー ★★★★
7.ジェラシー ★★★★
こちらはMr.Childrenの新境地とも言えるような
妖しい歌。チョーキングしたギター音や電子処理されているであろうドラムがそれを醸します。
その怪しげな音で中学生だった当時の私は、この曲を飛ばしていたのですが、じっくり聴いてみるとサビがなかなかの美メロで、桜井さんの何かを求めるような叫びにも似た歌声がマッチしています。
展開部で、それまで聴けなかったアコースティックギターのコードが鳴らされることで、「ハッ」という気にさせられます。歌詞は「なぜ人は愛なんていう愚かな幻想に溺れるのか」的な哲学じみたことを言ってるんですがね。
全編に
エキゾチックな雰囲気があり、次の曲との関連性も感じます。
8.Asia ★★★★
こちらも隠れた名曲だと思います。
最初の「アジアンソウル~」の部分をサビととした場合、その後のAメロ・Bメロはミスチルのポップ性そのもので、サビは暗いですが、それを越えたところにあるものを聞き逃せません。
珍しく、作曲は桜井さんではなく、ドラムの鈴木さん。ということで、若干ドラムの音量が大きく、そして若干ねちっこい音色です。
ただ、歌は変化に富みますが、
曲のアレンジが幾分単調なので、しばらく聴くと飽きるかも知れません 9.Rain
☆
9.Rain
☆
こちらも1曲目と同様、効果音なので、評価は出来ません。
雨の音です。
10. 雨のち晴れ ★★★★
ポップに戻ってきました。
なんだか鬱蒼とはしている状況だけれども、なんだか「なんとかなるさ」みたいな30代独身感が見事にアレンジでも出ています。
Aメロはコロコロしたギター、おどけたオルガンで、歌詞はお気楽極楽な感じ。
Bメロはなんとなく堅めのギターとオルガンで、歌詞は少し悩ましげな感じ。
サビはシンセサイザーの音と、ギターのワウで浮遊感で、歌詞はなんとなくな希望を歌い上げる。
アレンジと歌詞が見事にマッチしています。
中学生・高校生時にこれを聴いても実感湧かなかったんだけど、今聴くと、歌詞に共感します。
俺も年を取ったのだなぁ~と実感すると同時に寂しくなります
 11.Round About~孤独の肖像~ ★★★★
11.Round About~孤独の肖像~ ★★★★
この曲の
殊勲賞は、サックスとピアノでしょう

個人的にはなぜかゲームの
ロックマンのBGMに聴こえてしまいます
 都会の寂寥感とか、空虚感を感じる、この時期のMr.Childrenにあった感じ
都会の寂寥感とか、空虚感を感じる、この時期のMr.Childrenにあった感じです。前々作のアルバム「kind of love」の「All by myself」とか前作「versus」の「蜃気楼」とか。
ソロのサックスはなんとも言えぬ、どこの音楽とも言えぬ無国籍感がよく出ていると思います。
12.over ★★★★★
アルバムのみの収録なのに、Mr.Childrenファンにも絶大な人気を誇り、それ以外の人も「なんか聞いたことある」という反応が返ってくる可能性大の、
お化けアルバムの最後を飾るお化け歌。
こういう、別れの歌詞なのに、曲調が明るい歌、弱いのです。
それは、無理に明るく振る舞って、心で泣いてって感じに聞こえるからです。
「The time is over」なんて言って絶望的なのに…
ギターソロはメロディアスな旋律で、
サビがなんとなく行進曲ぽく、戻らない彼女に対して気丈に前に進んで行こうという感じが曲でも感じることができるのです。



 」
」


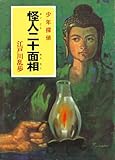










 )、この頃は美メロが溢れ出して嬉しい悲鳴を上げていたんではなかろうか、くらいの印象を受けます。
)、この頃は美メロが溢れ出して嬉しい悲鳴を上げていたんではなかろうか、くらいの印象を受けます。



 大木と小松
大木と小松