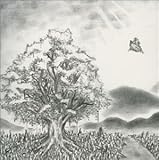「ちょうどいいわ。引っ越し祝いあげる。」
そして、くるくる紙に包まれたもうひとつの包みを差し出した。広げてみると、バナナの絵が描いてあるきれいなグラスが出てきた。
「それで、ジュースを飲んでね。」
えり子さんが言った。
「バナナジュースを飲むと、いいかもしれない。」
雄一は真顔で言った。
「わー、嬉しい。」
私は、泣きそうになりながら言った。
口には出せずに、そう思った。
大切な大切なコップ。
(p45より)
---------------------------------
さて、世界的なベストセラーのキッチンです。
続編も所収されている文庫の中の一編ですが、短いながらも瑞々しい文体ですぐ読めてしまいます

有名どころですが、一応あらすじを話しますと…
唯一の肉親である祖母を亡くしたみかげという大学生の女の子は、一人取り残され広すぎる家で、ある種の放心状態とも言える状況で日々をすごしていました。大好きな台所の中で。
そんな折、同じ大学生の田辺雄一という青年が(祖母が通っていた花屋の店員、ただそれだけの関係だったのだが・・・)、家を尋ねてきて、しばらく自分の家に暮らしたらどうかと提案します。
みかげと雄一は顔見知り程度の関係だったんですが、みかげは雄一の家に上がり込み、そのまま同居することになります。
雄一は母親(えり子さん)と二人暮し。この母親は実は父親
 ニューハーフなのです。
ニューハーフなのです。そして、彼女は夜のお仕事をしており、そんな色気もあり自分の好きな道を楽しんでいる姿を見て、みかげは憧れのような、本当の母親のような感情を抱きます。
そんな奇妙な同居生活からはじまる、みかげの新たなる出発を描いた作品とでもいえましょうか。
では以下はネタバレ含むので、いやな方は見ないで下さい。
- キッチン (角川文庫)/吉本 ばなな
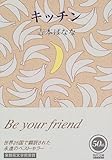
- ¥420
~1回目 2010.2.16~
続編も所収されているので、一緒に掲載しようと思ったのですが、この作品はこの作品で完結していると思うので、独立して掲載します。
さて、あらすじの続き、ラストまでですが、
次第に(というかいきなりですが)、雄一とえり子さんとの3人の生活にみかげは慣れていきますが、しかし3人の中ではどうであれ、他人からみるとこの関係は異様なものに移ってしまう。
もともとかかわりがほぼなかった、みかげと雄一・えり子。
それがいきなり一緒に暮らしているってんだから、もちろん雄一の彼女には誤解をされて別れたし
 、みかげ自身もいつまでもこの安寧のうちに暮らしてはいけないと思い、家を出ようかなと思い始めます。
、みかげ自身もいつまでもこの安寧のうちに暮らしてはいけないと思い、家を出ようかなと思い始めます。そんな中みかげが見た夢。
雄一が淡々とみかげに語りかけるのです。
「利用してくれよ。あせるな。」(p54)
と。
その夢うつつの状態、起きあがりキッチンへと水を飲みに向かうと雄一が。
しかも、なんと、雄一もみかげがついさっき見た夢と同じ夢を見ていたのでした。
奇跡というか、異常というか。しかし、この夢の中にこそ、かげの気持ちと雄一の気持ちが現れていたのかなとも思える部分です

その後も、いつかはこの家を出て行かなければならない、とも思いつつもみかげは、いつまでもここにはいられないという気持ちもしっかり持ちます。
しかし、前までとは異なり世間体を気にしてとか逃げからではなく、
「もっともっと大きくなり、いろんなことがあって、何度も底まで沈み込む。何度も苦しみ何度でもカムバックする。負けはしない。力は抜かない。」(p61-62)
という力強い気持ちで分かるように、成長の証としてではないでしょうか。
さて、感想ですが、若干淡々としすぎている感じはしました
 それは展開が早くて読みやすいという長所でもあるのですが、みかげ、雄一、えり子くらいしか登場人物は出てこないので、もうちょっと3人の関係を眺めていたかったなぁと思うのです。
それは展開が早くて読みやすいという長所でもあるのですが、みかげ、雄一、えり子くらいしか登場人物は出てこないので、もうちょっと3人の関係を眺めていたかったなぁと思うのです。そうしたら、みかげが家を出て行く、負けない。という力強い気持ちがより共感できたんじゃないかなぁ

しかし、この作品で一番印象に残った部分は、祖母とすごした家を引き払い、本格的にえり子宅にお世話になるという場面。
祖母と過ごした家は、自分が住んでいたとは思えぬほど他人の家のようでした。
その時点で、みかげはいよいよ気づくのです。
ついこの間まであったものが、ものすごい勢いで去っていたことを。
それを失うことは、心から悲しいものだということを。
そして、二度とその感覚はもう味わうことができないのだということを。
ここでみかげはようやく自身のおかれた場所を見つけることが出来たのでしょう。
さらに追い討ちをかけるように、引き払った後、バスでえり子宅に向かう途中、おばあさんと、孫の会話を耳にします。
おばあさんが孫に優しくかけるその声と優しく見つめるそのまなざし。
もう二度とないのです。そう自覚したみかげは、思わず涙を落としてしまいバスから慌てて下車、文字通りわんわん泣くのです。
ようやくその状況を知ったみかげが、いわく、生まれて初めてというほどの泣き。
前述した、みかげと雄一との夢のリンクはこの出来事の直後に起こります。
雄一とえり子の住む家に居候することがなければ、みかげが祖母が(つまり肉親と呼べる人が)いなくなってしまった、ということに気づき、受け入れるまで、もっともっと時間がかかったことでしょう。
現に、雄一が居候話をもちかけにみかげの家に訪れる前は、廃人寸前だったのですから。
そう思うと、最後の場面。すごくぐっと来ます。みかげとえり子さんとの会話。
「みかげの素直な心が、とても好きよ。きっと、あなたを育てたおばあちゃんもすてきな人だったのね。」
とヒズ・マザーは言った。
「自慢の祖母でした。」
私は笑い、
「いいわねえ。」
と彼女が背中で笑った。(p61)
自慢の祖母と言えるようになったこと。
みかげが現実を受け入れ強い気持ちで生きることができるようになったことがよく分かると思います

大事件があるわけでもなく、大それた結末があるわけでもありませんが、
みかげに感情を移入し、その結末にほっとできた小品です。
総合評価:★★★
読みやすさ:★★★★★
キャラ:★★★
読み返したい度:★★★

 そのまま3人で幸せになればいいじゃないか
そのまま3人で幸せになればいいじゃないか と思える場面です。
と思える場面です。