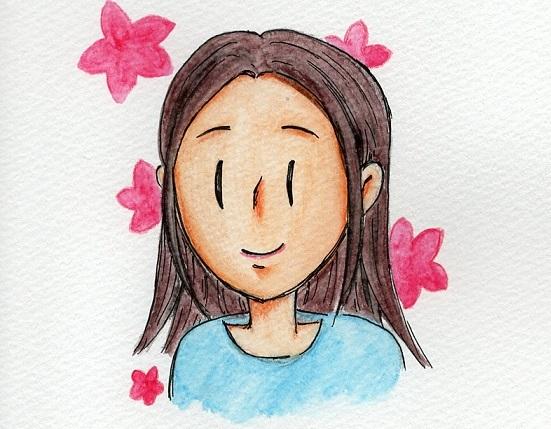2024年4月のテーマ
「私が30年手放していない漫画」
第三回は、
「ざ・ちぇんじ!」(全2巻)
氷室冴子 原作、山内直実 漫画、
白泉社文庫、1999年発行
です。
コミックスで全4巻だったものをまとめた文庫版です。
もともとコミックス版で持っていて、大人になってから文庫版を買い揃えたもので、幾度かの引っ越しを経てもずっと手放せない作品です。
原作は、1983年にコバルト文庫から発行された氷室冴子さんの同名の小説で、前後編2冊ありました。
実は、小説版の方も以前に記事で書いたことがあります。やっぱり私この作品好きなんだな…。
十代の私は漫画の方を読んで氷室冴子さんのことを知り、その後、氷室冴子さんの小説にもはまっていきました。
氷室冴子、山内直実がタッグを組んだ漫画は他にもあって、「雑居時代」、「蕨が丘物語」、「なんて素敵にジャパネスク」と全部集めていました。
氷室冴子さんの小説としても、山内直実さんの漫画としても、私的には「なんて素敵にジャパネスク」が最高だと思っておりますが、それでも「ざ・ちぇんじ!」はある意味別格。その訳をこれから書きたいと思います。
まず、あらすじをば。
平安時代、権大納言・藤原顕通卿には二人の北の方(正妻)がおりました。二人の性格は正反対。西の対屋(たいのや)の政子さまは物事をはっきり口に出して言うし几帳(きちょう※布を垂らした衝立で部屋を区切ったり女性の姿を隠すために使われる家具)は蹴倒して歩くし、火桶を投げつけて盗賊を捕まえたこともあるという豪胆なお方。一方、東の対屋の夢乃さまは一見おとなしい性格ながらたいそう迷信深くて、占いはすべて信じるし新興宗教にすぐ入信してしまい自らも祈祷を行う行動力はあって、スイッチが入ると一転してヒステリックにもなるお方。そんな二人には一人ずつお子がいて、西の政子さまのところの女君は学問にも武芸にも優れた男勝り。男装で、男の子たちに交って遊ぶ元気もの。東の夢乃さまのところの男君は体が弱くて幼少期から女の子の着物を着せられて育った(そうすれば丈夫に育つと夢乃さまにお告げがあった)上、本人も長いこと自分は姫だと思い込んでいたというわけで、"権大納言家には一男一女"としか知らない屋敷の外の方々は、若君と姫君を取り違えてしまっています。二人の子供はとても見目麗しく、綺羅(きら)君(姉)、綺羅姫(弟)と呼ばれるように…。
それぞれの母親たちがわが子の現状を良しとしているうえ、世間体もあって、父親の権大納言は多くを語らず濁すばかりなので、噂は独り歩きしてやがて帝の耳にも入り、姉の綺羅君は男の子の成人の儀式である元服(げんぷく)をして内裏に出仕することになってしまいます。時を置かずして弟の綺羅姫も女の子の成人の儀式である裳着(もぎ)をすることに…。
性別を偽って社会生活を送ることになってしまった姉弟の物語です。
所謂"とりかえばや物語"なんですが、現代のとりかえばや物語みたいに不可抗力で男女の中身が入れ替わったわけではなく、本人たちの自認する性別と肉体がアンマッチだというわけでもなく(弟の場合は真実を知るまではアンマッチだったわけですが…)、平安時代の"女らしさ"に当てはまることを良しとしなかった姉と環境要因で自分の意志とは関係なく"男である"という事実から遠ざけられていた弟が結果的に社会を欺いて生きることになってしまったというお話なのです。
ただ自分たちの子供の頃からの"当たり前"のまま社会に出てしまっただけで、これからどうやって生きていくのかだとか、ばれたらどうなるのかとか、何も考えていないし、自分の性別とは別の性別でずっと生きていきたいのかということも深く考えていません。
それが、大人の仲間入りをして世間というものに触れると、性別逆転していることで特に恋愛や結婚において問題が出てきます。とりわけ平安時代は結婚するのも早いし、恋愛や結婚が政治と深く結びついているので、貴族社会では大きな関心事であり、避けて通ることはできません。
そのあたりの苦悩や葛藤を思春期の女の子たちが読んで分かりやすく共感しやすいように描いてあります。
今年の大河ドラマの「光る君へ」を観ていらっしゃる方はわかると思いますが、現代人の感覚からすると平安時代の恋愛や結婚の在り方って、女性の側からは特に抵抗感があると思います。
通い婚・一夫多妻制…女性の人権って一体…と言いたくなります。
でもそこで引っかかってムカついていたって、仕方ありません。
物語を楽しむためには、この時代はそういうものだったと一旦飲み込んでおかないと、その制度の中で登場人物が悩んだり行動を選択したりしているのだということが理解できないと思います。
昔の作品や古い時代を舞台にした作品を読むときに、その時代の常識・倫理観を現代の価値観でぶった切ることに終始していては、読んだ意味がないと私は思います。
自分の視点は一旦置いておいて、登場人物の視点に立って物語を読まなければ、作品の意図も分からなくなってしまう。
作品で何が描かれているのかちゃんと理解してから、「その時代はこうだったけど、今はこうだ。その違いについてこう思う。」という風に自分の気持ちをまとめられればいいなと思います。私自身、登場人物に感情移入しすぎたりして実践が難しい時もありますが。
話が逸れました。
平安時代の恋愛を描くとなると、主人公は十代で結婚やら妊娠やら夫が他の女性にアプローチしているというような人生の大問題にぶつかることになり、冷静に考えると重いです。
コバルト文庫は少女向けの小説でしたから、原作者の氷室冴子さんはその辺りを考慮してシリアスになりがちなシーンもあえてコミカルに描かれたのではないかと思います。漫画の方もお話全体がコミカルにテンポよく進んでいきます。ある意味ドタバタ喜劇だと思います。
この作品を読んだことで、平安時代の基礎知識が得られて、「なんて素敵にジャパネスク」や「あさきゆめみし」(大和和紀さんの漫画、源氏物語)へと進んでいくことができましたし、平安時代の歴史小説、平安時代関連の新書本などにも興味を持てたと思います。
なにより、山内直実さんの絵柄がきれいで可愛く、平安貴族の世界を視覚化されていたことが私を惹きつけました。
「あさきゆめみし」は書き込みが細かく美しい絵柄で、華麗な王朝絵巻の世界を余すことなく描いてあり、私は大好きなんですが、平安時代もの初心者の頃は「ざ・ちぇんじ!」のちょっと現代風なキャラクターと絵柄、書き込みすぎない適度な抜け感がちょうど良くてすごく好きでした。
漫画に描かれている平安時代の衣装をまとったキャラクターの絵がきれいで好みだったのが多分最初のきっかけ。漫画の「ざ・ちぇんじ!」があったから、平安時代や原作者の他の作品にも興味が持てて、更に言うと古代を舞台とした小説にまで広がり、永井路子さんの小説を読むようになっていきました。
基本的に長いお話が好きな私ですが、「ざ・ちぇんじ!」は全2巻の中で起承転結ぴったり収まっていて、とても心地よいです。今のティーンエイジャーが読むと、平安時代のしきたりや婚姻制度に引っかかって素直に物語が入ってこないんじゃないかという気もしますが、この時代を題材にした作品はたくさんあると思うので、それらの入り口としてもいいんじゃないかと思います。(私がそうだったから希望的観測かもしれませんが。)
「ざ・ちぇんじ!」、小説の方も含めておすすめいたします。(*^▽^*)