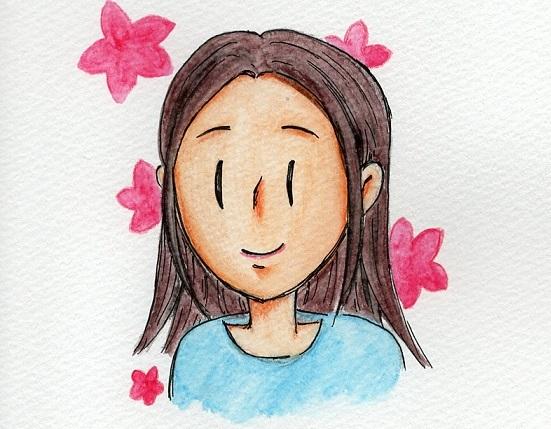2022年1月のテーマ
古典が楽しくなるかもな本
第三回は、
「ざ・ちぇんじ!」新釈とりかえばや物語<前後編>
氷室冴子 著、
集英社コバルト文庫、1983年発行
です。
現在では中古でしか手に入らないので、2012年に再版されたものも下に貼っておきます。
再版版は私は読んでいません。
この本は、私が中学生くらいの頃にまず漫画版を読んではまり、のちのち古典に興味を持つきっかけになった本です。
ティーンズ向けの文庫、集英社コバルト文庫の作品で、古典の「とりかへばや物語」を下敷きにしてはいますが、言葉遣いなど現代風にアレンジされていて、ティーンズに親しみやすく平安時代の文化や風習を伝えてくれています。
平安時代、権大納言(ごんだいなごん)家の二人の子供たちが主人公のストーリーです。
活発ではっきりした性格の女の子が若君として、内気で引っ込み思案の男の子が姫君として育ち、なんと若君はそのまま元服(成人の儀式)をして宮中に参内する貴族になってしまいます。姫君の方も裳着(女の子の成人の儀式)をして内大臣家の姫として求婚者が現れる始末。
若君の方はもしも女だということがばれてしまえば帝をたばかった罪で死罪になってしまうので、決してばれてはいけない秘密を抱えて生活します。もちろん不都合なこともいろいろ出てきてしまうので、若君も姫君も本来の性別の姿に戻りたい、、、となっていくというお話です。
原作の「とりかへばや物語」は読んだことがないのですが、ざっくり調べてみると大筋は大体同じなものの、ところどころ変えてあるようです。
ちなみに、このお話はジェンダーギャップについて書かれているものとはちょっと言い難いです。
それぞれの性の社会的役割が固定化されていることに主人公たちは疑問を持ってはいるのですが、生まれながらの性と自身の体の間にギャップがあると感じているわけではないようです。
作者の氷室冴子さんの作品は現代小説もファンタジー小説も含めてたくさん読みましたが、10代でも読みやすくて面白かったのに、大人になってから読んでもやっぱり面白くて、すごい作家さんだなと思っていました。氷室さんが2008年に亡くなられたときはニュースを見てショックを受けたことを覚えています。
さて、この作品は「平安時代の文化や風習をわかりやすく感じられるから」おすすめしたいと思ったわけですが、それの何が良いかについて、もう少しお話させていただきたいと思います。
「あさきゆめみし」のところでも少し書きましたが、古典文学がわかりにくい原因の一つが専門用語です。
用語の知識なしに古典文学を読むのは疲れると思います。
あくまでも経験談でしかありませんが、読みやすい漫画や小説で用語に慣れ親しんでいれば、古典文学を読もうと思ったときにぐんと楽なんです。
帝のことを言い表す言葉だけでも、"主上(おかみ)"、"今上(きんじょう)"、"当今(とうぎん)"などたくさん出てきます。
殿上人(てんじょうびと)は、帝のいる清涼殿に入ることの許された高位の貴族。
東宮(とうぐう)は、天皇の後継者。次期天皇。
北の方は、貴族の正室。第一夫人。
物忌み(ものいみ)は、陰陽師の占いによって良くない物の怪につかれているなどと判断されたときに建物にこもって謹慎すること。この時は宮中に参内しなくてもよい。というかしてはならない。
入内(じゅだい)は、帝の妃として嫁ぎ宮中に入ること。
などなど・・・。
ストーリーを追って読んでいく中でたくさんの言葉がインプットされていきます。
また、上記の"物忌み"のような、当時の習慣を知ることも大事です。
現代小説を読むときに、登場人物に心情的に共感できるのは、些細な日常の描写が影響していることも少なくありません。
作品世界の中での前提条件を知っていることは、内容を理解するときにすごく役に立つのです。
「あさきゆめみし」は絵で作品の世界を理解するのに最適だと私は書きました。
絵の雰囲気で平安時代の世界に飛び込んでいける人ももちろんいますが、もうちょっと現代との溝を埋めてからでないとしんどいなという方には、「ざ・ちぇんじ!」をおすすめします。なんたって文章がかしこまってないですから。
氷室冴子さんの平安時代が舞台の小説には、「なんて素敵にジャパネスク」というのもあって、こちらはオリジナルストーリーの長編です。
こっちも好きだけど長いので、まずは「ざ・ちぇんじ!」で自分に合うかなーというのを確かめてみられてはいかがでしょうか。
山内直美さんによって漫画化された方もおすすめいたします。(*^▽^*)