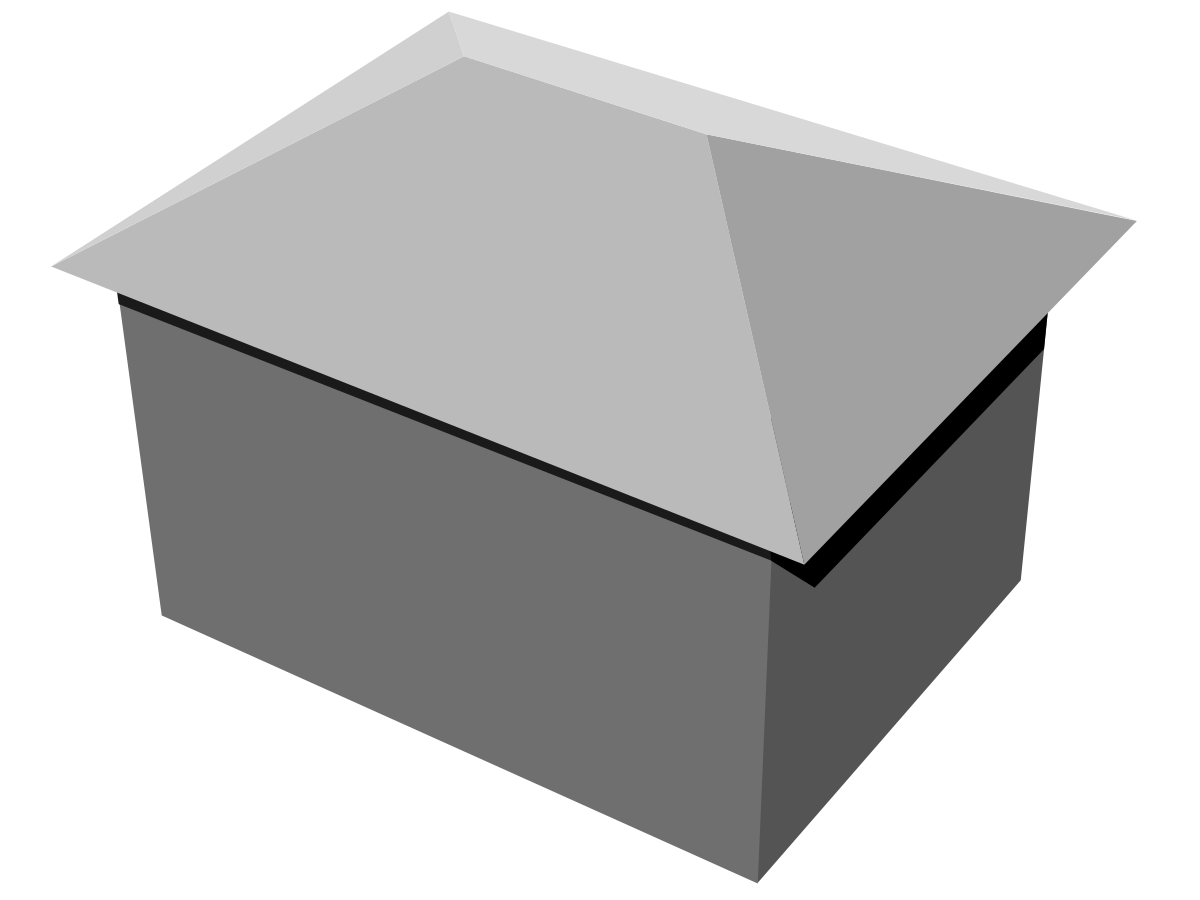奈良県は奈良市にあります、十輪院
に行ってきました(^_^)/
十輪院は、元は元興寺の子院だったと考えられており、元興寺の近くにあるので、併せて訪問することを、お勧めします。(訪問するまで、気づかなかった……💦)
また、国宝の本堂の内部拝観については、ハッキリ定まっている……という訳でも無いようなので、事前に拝観可能時間をご確認のうえ、訪問するようにしてください。
では、レポートします。
・国宝 十輪院本堂

鎌倉時代の作。
航空写真で見ると、良くわかりますよ。

↑この部分に、"石仏龕"があり、緑でマークした部分が本堂です。
桁行き(けたゆき/正面)5間、梁間(はりま/奥行き)4間の、長方形の建物です。詳しく見ていきましょう。
①の1間は、壁がありませんね。吹き放ちの広縁になっています。
④の1間は、少し奥まっています。石仏龕を拝観するための入口が、本来ここなのです。詳しく見ますね。

↑縁側が途中で切れて、少し奥まっているでしょ。今は結界があって、入れませんが、昔はここから入って石仏龕を拝んだようです。

↑こちらは、①の吹き放ち部分。広縁が作られて、すっきり開放されてます。
では、広縁に上がってみましょう。

↑正面3間は、跳ね上げ式の蔀戸(しとみど)、左右には連子窓が設えられています。

↑低い天井は、竿縁天井。下から押し上げれば、板がズレるので、エロ本が隠せます(^_^;)
さぁ、内部に入りましょう。
ですが、残念ながら内部は撮影禁止🚫です。
内部は、中央3間が主室で、両サイド1間は脇室となっています。
主室には、内陣が組まれ、その背後に石仏龕を拝観するための"相の間(あいのま)"があります。
石仏龕は、石の内側をくり抜いて石像を彫り出したもの。石像彫刻の1種で、重要文化財指定を受けています。
また、脇室には宝物類を展示していました。
主室の柱は円柱で、脇室の柱は角柱と、使い分けられ、仏の世界と人の世界を明示しています。
レポートは、以上です。