心理学といっても、いろんな方向性があるように思う。
例えば、
成功哲学のマーフィの本と、
癒しの本では、全く違う方向性を持っている。
『自分を人に分かってもらおう』とする『働きかける』心理学と、
逆に『自分自身を見つめ、心の声を聞こう』とする心理学というかな…。
観察していると、ビジネスに成功したが、身体症状に悩まされたり、何か足りないものを感じたりすると、癒しの心理学で癒され、また、ビジネスに戻っていったりする。
ですから、こういう人には、両方、必要な心理学なんだと思う。
ヨガなんかにも、『集中と拡散』二つのことを同時にやるとか、難しいことが書かれている。
昔から、こんなもんなんでしょ。
例えば、
成功哲学のマーフィの本と、
癒しの本では、全く違う方向性を持っている。
『自分を人に分かってもらおう』とする『働きかける』心理学と、
逆に『自分自身を見つめ、心の声を聞こう』とする心理学というかな…。
観察していると、ビジネスに成功したが、身体症状に悩まされたり、何か足りないものを感じたりすると、癒しの心理学で癒され、また、ビジネスに戻っていったりする。
ですから、こういう人には、両方、必要な心理学なんだと思う。
ヨガなんかにも、『集中と拡散』二つのことを同時にやるとか、難しいことが書かれている。
昔から、こんなもんなんでしょ。

 )
) 。
。
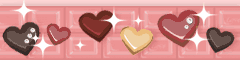



 同じアホなら踊らな損、損
同じアホなら踊らな損、損 』と覚え書き φ(.. )
』と覚え書き φ(.. )