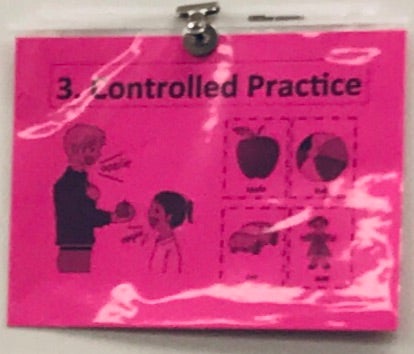みなさん、こんにちは❗️
少しずつですが、春の訪れが感じられるようになってきた今日この頃、いかがお過ごしでしょうか❓
本テーマの初回は、「1単位時間の授業の組み立て方① ー4つの柱編ー」ということで、上の写真にて示された、1単位時間の授業の組み立て方の概要について説明させていただきました!
そして前々回の記事では、「1単位時間の授業の組み立て方② ーControlled Practiceー」ということで、上の写真の3番目の過程、3. Controlled Practiceについて
そして前回の記事は、「1単位時間の授業の組み立て方③ ーMeaningful Practice編ー」ということで、4番目の過程、4. Meaningful Practice について解説させていただきました👍🏻
👇🏻今までの記事は下記よりご覧ください👇🏻
今回は、「1単位時間の授業の組み立て方④ ーまとめ編ー」ということで、 “1. Review” “2. New Language” “3. Controlled Practice” “4. Meaningful Practice”との関連を図りながら、1単位時間の授業の流れをより詳しく確認していきましょう🤘🏻
いきなりですが、 “1. Review” “2. New Language” “3. Controlled Practice” “4. Meaningful Practice”を組み入れた、1単位時間のより詳しい授業の流れのモデル例を示します👇🏻
〈1単位時間の授業の流れのモデル例〉
ちなみに、これからお話しさせていただくのは、あくまでも「例」ということを、ご承知おきください🙇🏻♂️
1.導入
「はじめの挨拶」
まずは挨拶ですね❗️
専科教員の場合は、この段階で、指導する学級の児童のコンディションを把握し、
「今日はどのようなテンションで授業をしようか。」「どのようなアプローチで児童に接していこうか。」
などと、児童への関わり方を考えておくとよいです。
なお、「児童対教師でスモールトーク」と例示しましたが、これは、学級の実態によって、いきなり「児童対児童」でスモールトークをさせてしまうと、英語に対して苦手意識がある児童が「スモールトーク」に対して抵抗を感じてしまう可能性があるからです。
私の場合、「児童対教師」で既習表現をおさらいしてから、「児童対児童」のスモールトークに移行するパターンが多いです。詳しくは今後別記事で解説できればと思います!
「ウォームアップ」
体育でいえば「準備運動」に当たりますね❗️
児童の学習に対するスイッチをオンにするため、活動を工夫しましょう👍🏻
例えば、挨拶の段階で、「児童に元気が欠けているなぁ」と感じたら、サイモンセズゲームなどの、身体活動を伴う学習を取り入れるなど、「ウォームアップで取り上げたい語彙、表現等」と「児童の様子」との兼ね合いを考え、柔軟に対応できるとよいと思います👍🏻
2.展開
「今までの学習の復習」
これは、 “1. Review”に当たる段階ですね。「本時に至るまでに単元の学習で学んだ語彙等の復習を行う。」と書きましたが、もちろん「過去単元や下学年で扱った語彙、表現」を扱うこともあります。
大切なのは、「本時の学習をより分かりやすくするために、本時で扱う事項と関連のある既習事項を、単元内外問わず精選して扱うこと」です。この点が意識できていれば、キーワードゲームのようなゲーム系のアクティビティやデジタル教材に収録されているチャンツなど、どのような指導法でもよいかと思います。
「語彙や表現の導入・確認」
これは“2. New Language”に該当します。表現のみを導入する場合は、私たちがよく聞く言い方に置き換えると、「場面設定」という言葉が一番当てはまるかと思います。
本段階は、「本時で扱う語彙や表現の使い方」を児童に理解させることが目的です!表現のみを導入する場合は、以下に示すように様々な方法があります👇🏻
・デジタル教材に収録されている、表現を用いたやり取りの映像を提示する。
・教師が一人二役となって、表現を用いたやり取りを示す。
・教師師がパペットを用いて、教師、パペット間で、表現を用いたやり取りを示す。
・教師がALTと表現を用いたやり取りを示す。
・プレゼンテーションソフトで作成したスライドを使い、表現を用いたやり取りを示す。
などなど。
詳しい実践例等はまたお話しできたらと思います❗️
「知識及び技能の習得に重きをおいた学習活動」
こちらは“3. Controlled Practice” に当たるとともに、学習指導要領でいうところの「言語材料について理解したり練習するための指導」に該当します。本学習活動を計画的に積み重ねていき、「知識及び技能」の定着を図りましょう。ドリルやチャンツ、ゲームなど様々な指導法があります。
「思考力、判断力、表現力等の活用に重きをおいた
学習活動」
こちらは、 “4. Meaningful Practice”に該当するとともに、学習指導要領でいうところの「言語活動」とほぼ同義です。
「知識及び技能をどのように活用して気持ちを伝え合っていくのか」という、「思考力、判断力、表現力等」の活用に重点をおいた学習活動を意図的に行いましょう。
3.まとめ
「本時の振り返り」
他教科と同様に、本時で学んだことや自身の成長・課題点等について振り返ります。できれば、ワークシートなどに、文章で振り返りを書かせることを推奨します。そのように私が考える理由やワークシートの工夫については、また別の記事でお話しできればと思います。
振り返り後に各々の意見を全体で共有する場を設けると、他の友達の振り返りからさらなる学びが得られる「学び合い」の場にもなります✨
「終わりの挨拶」
ただ挨拶をするのではなく、児童に「次回も頑張ろう」という前向きな気持ちをもってもらえるよう、本時の学習に向かった姿を褒めるなど工夫しましょう。
1ヶ月ごとに歌を決め、終わりの挨拶の際に歌うのも、児童にたくさんの語彙や表現に触れさせることができ、面白いですね👍🏻
さて、今回は、「1単位時間の授業の組み立て方④ ーまとめ編ー」ということで、1単位時間の流れについて、モデル例を挙げて話させていただきましたが、気を付けていただきたいのは、
①モデル例はあくまで例であること。
②1単位時間の授業構成というものに正解はなく、「本時の目標」や「児童の実態」等に応じて、柔軟に流れを組み立てなければならないということ
です👍🏻
ですので、モデル例から参考になる学習の段階を選んでいただき、それを自由に組み合わせて、ご自身の授業を構築していただければ幸いです💡
さて、テーマ「授業の組み立て方のポイント」の初回のトピックである、「1単位時間の授業の組み立て方」シリーズですが、①から④まで一区切りつきました💨ここまでお読みいただき、誠にありがとうございます✨
今後、テーマ「授業の組み立て方のポイント」では、授業づくりに役立つ応用的なテクニックなどをご紹介するため、不定期に更新していく予定です!
これからも本ブログでは、少しでも役立つ情報を共有できればと思いますので、引き続きチェックのほど、何卒よろしくお願いいたします🙇🏻♂️
それでは素敵な一日を✨