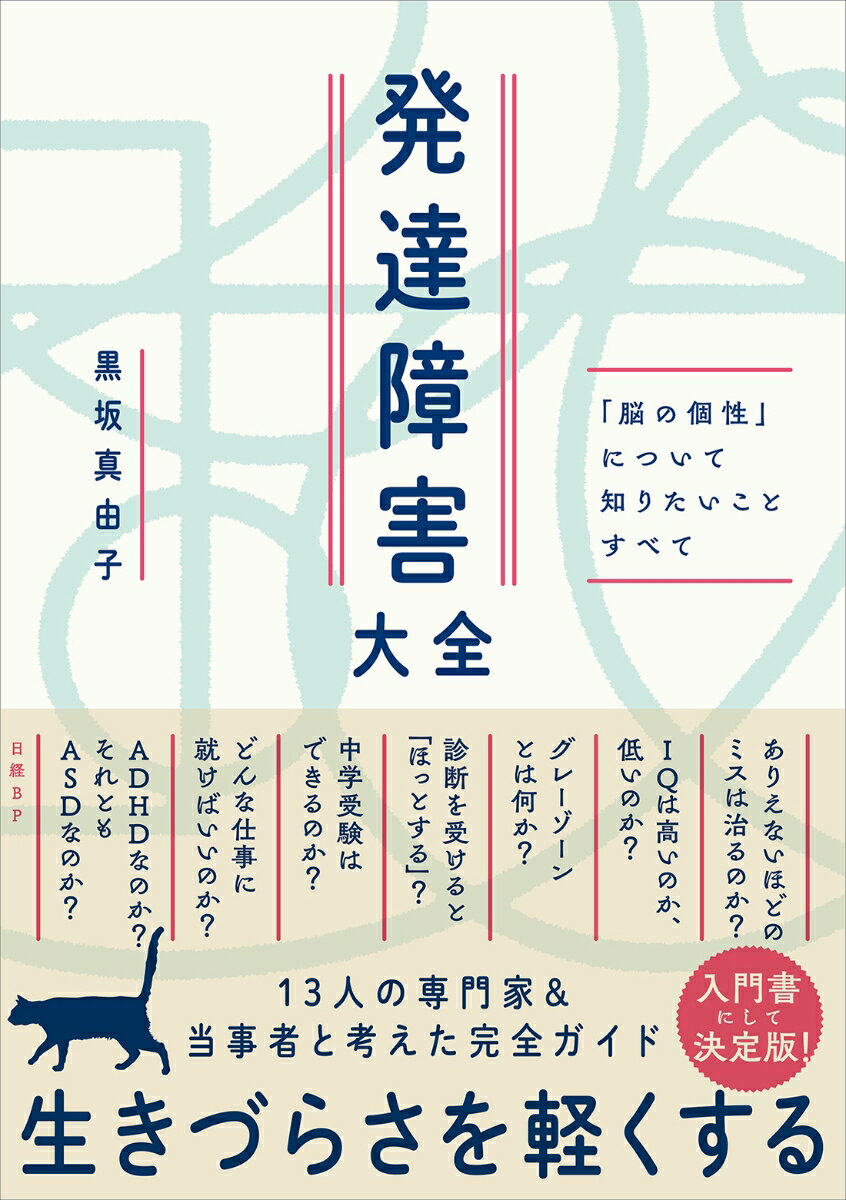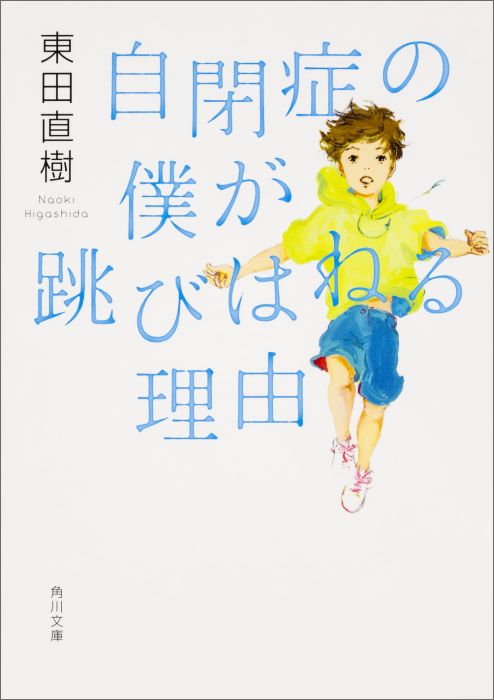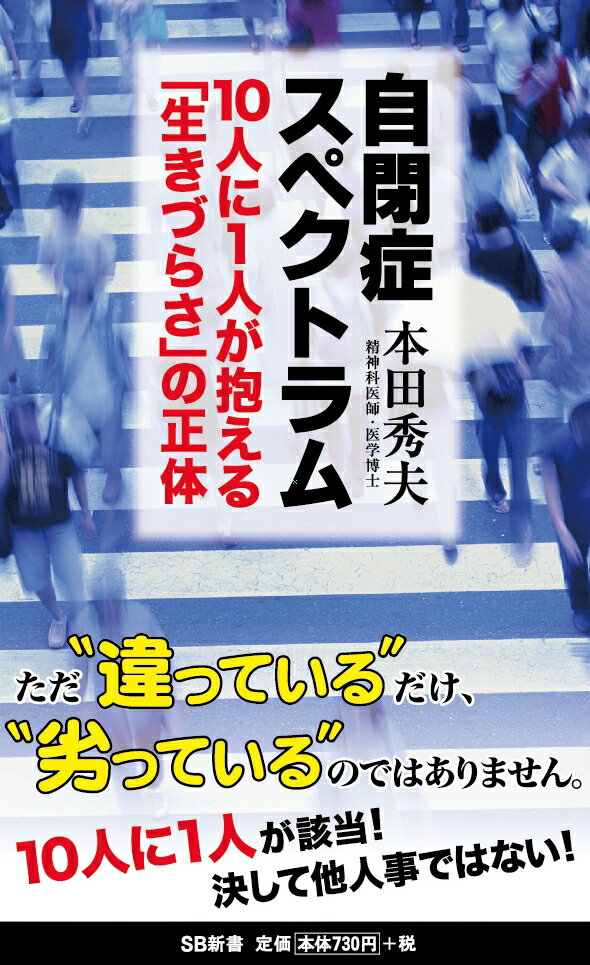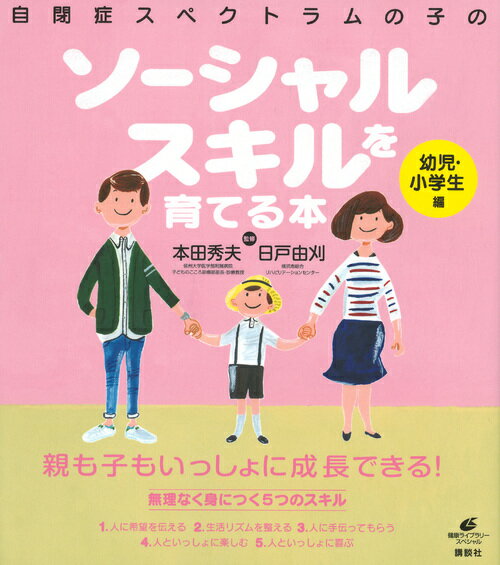こちらの続き→
特別支援教育や発達障害児の高校に関する部分です。
私は高校のこと、それ以降の進路のことがすごく気になっていたので、すごく為になりました。
専門家は高等特別支援学校、特別支援学級に携わった教員です。
学校について
・国連は2022年に「特別支援教育」の中止を日本政府に要請。支援学校だけでなく、支援学級や通級も含む。インクルーシブってやつ?!
・支援学校には発達障害だけでは入れない。ただ、知的な問題があれば、療育手帳がなくとも入れる(これ、本当?)
・支援学校か学級かを選べるようになったのは、2013年以降で、本人と親の意向を最大限尊重することになった。それ以前は強制的に支援学校に入れられることもあった。
・支援学校と学級、迷ってたら、まず学級を勧める。ダメだったら学校へ来ては?と伝える。地元の学校で、地元の友達に出会えるのがすごくいい。障がい児は生涯地元から出ないことが多い。
・支援学校は自尊心が育つ。パット見分からない障がいの子ほど、支援学校はいい環境。普通校でいじめられ、支援学校に来る子もいる。
・中学生で比べると、支援学校の子は自己肯定感が高い、普通校の子はより自立しているそう。どっちをとるかということ。
・軽度→支援学校、重度→支援学級の逆転現象が起きている。理由は重度が学級にいて、軽度な我が子は放置されるに違いないと見学で実感した親が、支援学校にいれることが増えている。支援学校の風景もだいぶ変わった。
・支援教育にはお金がかかる。高等支援学校だとひとり年間380万かけている。
・大阪の知的障がいの就職率は17%、愛知、東京は30%。理由は東京、愛知は大企業が多め、大阪は中小が多め。
・高等支援学校のカリキュラム「ものづくり」「福祉園芸」「流通サービス」、共通履修「販売」「清掃」など
・どんな職場でも清掃はある。メイン業務ではなく、後片付けや掃除のような補助員を育成するプログラムになっている。
・支援学級→普通高校は2021年で半数を超えた。支援学級→支援学校高等部は4割は程度。昔は、支援学級→普通高校は3割切っていて、ほぼ支援学校高等部への進学だった。
・理由は定員割れした高校が増えたこともあるが、大学に行かせたい親が増えたことによる。8割超えが何らかの形で進学し、20歳まで働かないのに、障がいもある我が子がどうして18歳から働かないといけないのか、と思うようになっている。
・普通高校に「自立支援コース」「エンパワメントスクール」などサポート体制がある学校がある。
・「自己決定力」が大切。障がい児はマイノリティで、マジョリティに従ってきた子が多い。
・障害者雇用の月収は12-13万。生活保護と大差ないが、人に褒められ、必要とされることに人間は幸せを感じる生き物。
・不登校は小学生で1.7%、中学生で6%
・原因はいじめなどを含む友人関係で、不登校継続理由は無気力、不安定になる。背景に学習障害、発達障害がある。自己肯定感が下がりやすい性質がある。
・普通高校には「全日制」「定時制」「通信制」がある。「定時制」でも朝昼授業のところもある。
・N高のような通信制高校も増えている。授業はなく、添削指導(レポート提出)と面接指導(スクーリング)で学ぶ。スクーリング日数はさまざまで週5のところもある。
・通信制高校の課題はモチベーションの維持。中途退学率は全日制の4倍
・公立高校にも通級指導がある場合かある。
・高専が向く子もいる。5年制で54校ある。大学編入、高専の専攻科に進学もできる。就職率99%
・専修学校高等課程も人気。全国400校。実践的な職業教育が受けられる。工業、医療、教育、福祉、衛生、商業、服飾など。資格取得に力を入れる。
・自動車整備士、建築士、介護福祉士、准看、調理師、美容師、簿記などの資格
・高校進学準備は早めに。2年くらいを目処に。
・合理的配慮は公立高校では義務化、2024年以降私立高校でも義務化される。センター試験、高校入試でも合理的配慮がある。
続き→