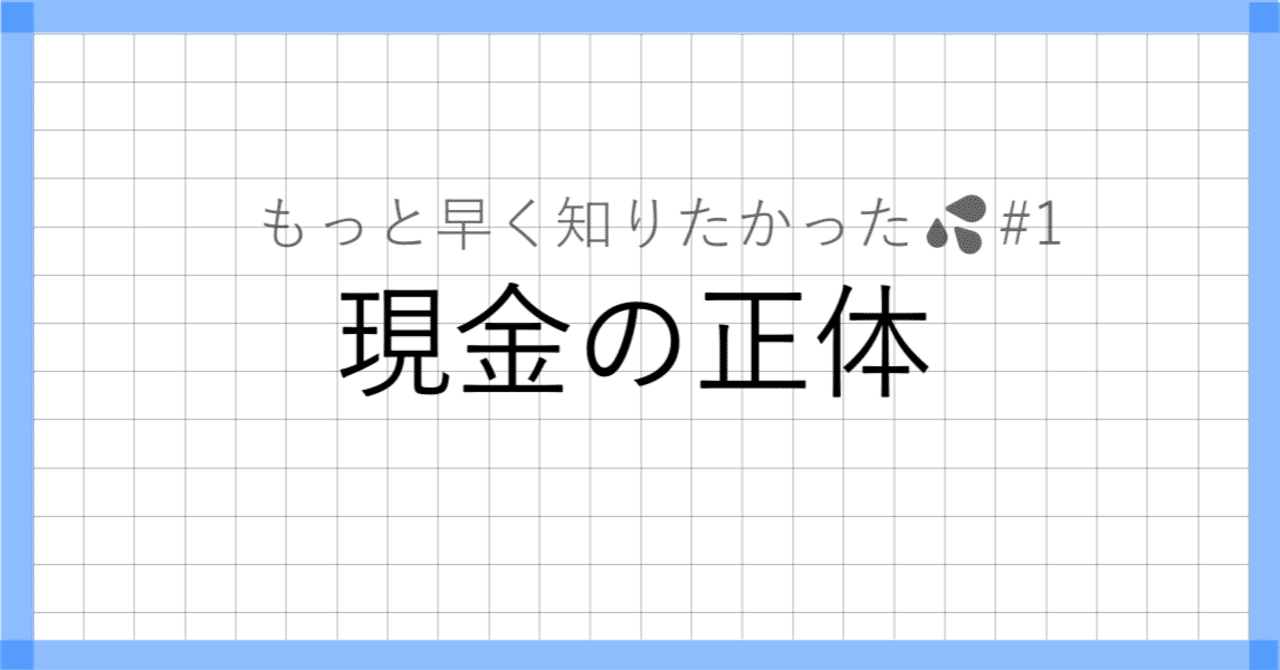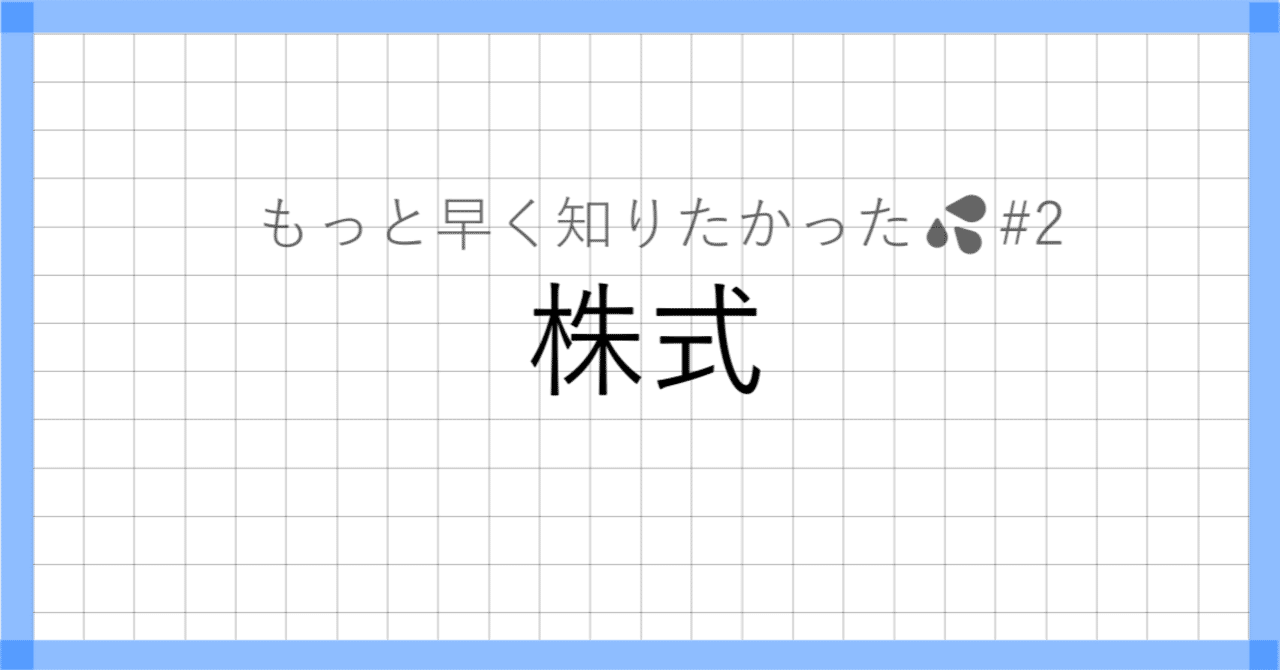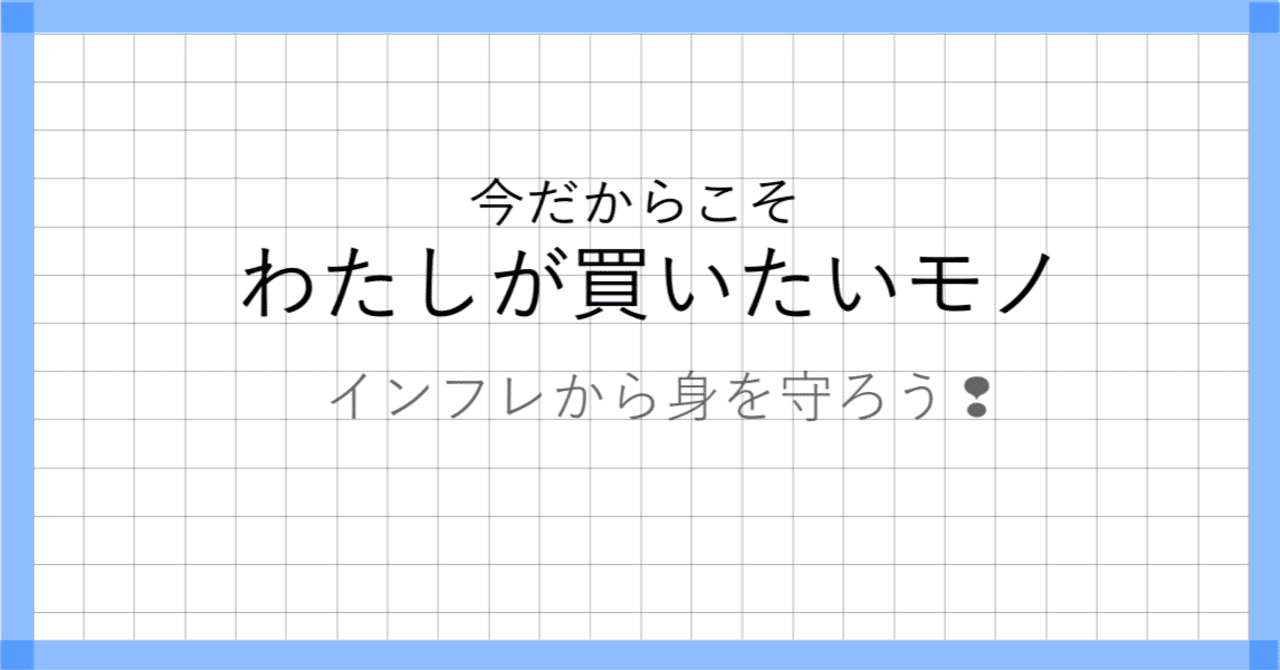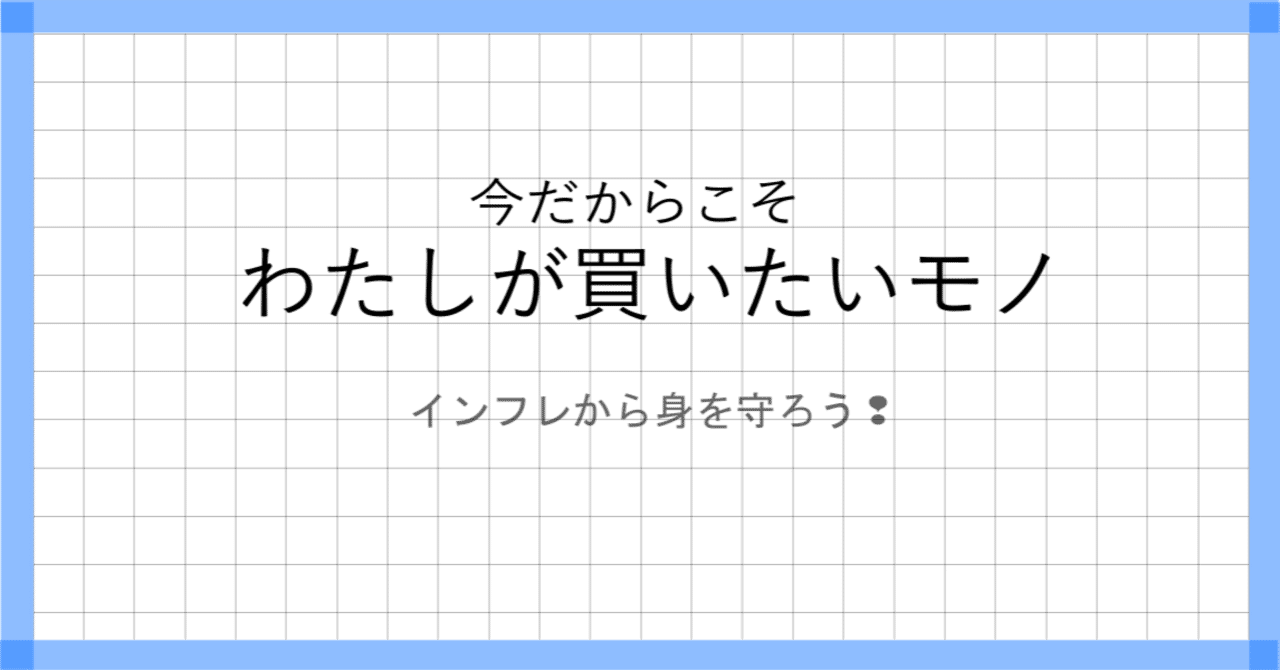「いつまで続くんだろう。」
収容されてからずいぶん経つが、まだ地上は落ち着かないのだろうか。
父親は別の区画に居るのがわかっているからいいものの、兄さんの安否もいい加減に気になって仕方がない。
「隣の訓練していた連中もどうなったかわからないしな。」
言われたとおりに毎日、この配管内の巡回をし続け、たまに異音のする箇所を見つけては報告、機械に詳しい彼が隙間に入り対処することもある。
一人で行動することは禁止されていて、これは何かあった時に助けを呼ぶなどの対応ができるようにするための安全対策だとされている。
いつどんな時代でも人間は技術に依存してきた。
空気中の窒素から肥料を製造することで食料の確保を十分に出来るようになったし、いつでも清潔な水を飲めるようにし、本来排出するだけの汚水でさえも浄化して放出することで安全な環境を確保してきたわけだ。
でなければ、いくら時代が進もうが常に我々はあらゆる病原菌におびえながらの生活をせざるを得なかったに違いない。
病原菌と言えば、医療でさえも日進月歩の技術の賜物だ。
さて、半ば強制的とはいえ、この莫大な費用と数十年をかけて作り上げたであろう大きな大きなシェルターにこうして居さえすれば、少なくとも飲み食いや寝る場所に困ることはない。
しかし、離れ離れになった家族の安否、青い空と自然の空気が日々恋しくなってきている自分を感じる。
「もし地上に出た時、地平線まで一面瓦礫だったらどうする?」
「どうするって。」
「逆に俺らが地上に出る頃にはすっかり違う国になっていたりしてな。」
「…。」
思えば、国もひとつのコミュニティに過ぎない。
何が違うかって、規模と携える手段が違う。
また、それぞれの歴史や文化を抱えていて、そこに生まれた者たちの生涯の心の財産や誇りだったりするわけだ。
同じ言語を話す民族だけで集落をつくって生活しているとしても、自分一人で体と心を休めるための空間は誰であっても必要だろう。
社交的であればあるほどいいに越したことはないが、帰る家とそんな居場所は誰しも必要なのであって、そんな大事な区別さえも取っ払ってしまうようなバカな考えを持つ人間はさっさと始末した方が良い。
今のカオスな現状は、過去の向こう見ずな権力者たちが招いた災厄なのかもしれない。
※この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在する人物や団体とは一切関係がありません。
※この作品は2025年7月18日にnote.comに掲載したものです。