「わかりました。じゃあお手伝いしましょう!」
こんな支援はもちろん
だめです。
しかし、
「好きな歌を歌いたい。」
「美味しいご飯を食べたい。」
「外に散歩に行きたい。」
「好きな服を着たい。」
というような患者さんの希望であれば、
我々作業療法士は、
「どうやったらこれができるだろうか?」
「どうしたら、もっとこの人らしい生活を送る支援ができるだろうか?」
と考えます。
当たり前と言えば当たり前の話です
何を今さら、こんなことを言っているのだ
と思われるかもしれませんが、
なぜ前者は良くなくて、後者はOKなのか。
この理由について、
自分でも納得できる説明方法が、
いまだに見つからないでいます。
もちろん法律に反するからという説明方法もありますが、
それはセラピストとして面白くない。
なんか自分でもなるほど!と思える
説明を見つけたいのです。
よく
「利用者様主体の、、、」
とか
「クライアント中心の、、」
とか
「患者さんの想いを反映した。。。」
とかそういう言葉はあります。
この言葉の真の意味を考えたり、
これを追求すると言うことは、
非常に奥深い課題が含まれていると思います。
どこまで本人の意向に沿って
支援していけばいいのか?
それは、現場で働いていると、
迷う場面があります。
「死にたい」と言う人は、殺すのか?
「家からどこにも出たくない」という人は、
引きこもり生活をただ続けてもらうのか?
独り暮らしが危険を伴う認知症高齢者が、
「施設には絶対入りたくない。」というのであれば、
その人が孤独死するまで、独り暮らしを続けてもらうのか?
いろんな思いになるのです。
患者さんはいろんなことを、
自分の希望として語ります。
「このままでいいんです。」
「ずっと眠っていたいです。」
「年金もらえて生活できたらそれでいい。」
「薬は飲みたくない。」
いろんな想いのうち
何を採用して支援につなげ、
何はなだめて、
「そういう気持ちはわかるけど、もうちょっと頑張ってみようよ!」
と励ますか。
そこには、セラピスト自身の
「この人にはこうあってもらいたい」
という
セラピスト自身の想いが含まれていると思うのです。
だから、
「私はクライアント中心主義でやっています。」
と言ったって、
それは50%。
残り50%は必ず自分の想いが含まれている。
そう思います。
「死にたい」と語るクライアントに対して
その人が
「やっぱり生きててよかった。」
そう語る瞬間を見たいから、
「まあそんなこと言わず、今日は散歩でもしましょうか?」
とかニコニコしながら、
その人に語りかけることができる。
そういうものじゃないかと思います。
だから、セラピストの思いって言うのは
絶対に必要なものです。
セラピスト自身が、
どうしたいのか?
どうなって欲しいのか?
それを望みすぎず、
だけど、まったくクライアント任せにするのでもなく、
50対50くらいの感覚で、
持っておく。
そういう感覚で日々私は働いています。
それは、人になにかを教えるときも一緒。
後輩や学生。
彼らのこうなりたいっていう想い。
それを50%。
それに加えて自分の彼らにこうなってもらいたい。
という自分の想いが50%。
そのバランスが大切かと思っています。
12月20日(日)そんな教え方のコツを
お伝えしたいと思います。
12月20日(日)
自分も相手もやる気が高まる教え方セミナー
どうぞよろしく!
☆セミナー情報
今後のコミュニケーションセミナーの予定をお伝えいたします。
平成27年12月20日(日)
自分も相手もやる気が高まる教え方セミナー
~目標設定と伝える情報の単純化で伝わりやすくなる指導教育のコツ~
□平成27年11月13日(金)
埼玉県老人保健施設協会さん主催
多職種連携のためのコミュニケーション講座
☆メルマガ情報
メルマガ配信しています!!!
メルマガ登録はこちらからでもどうぞ。
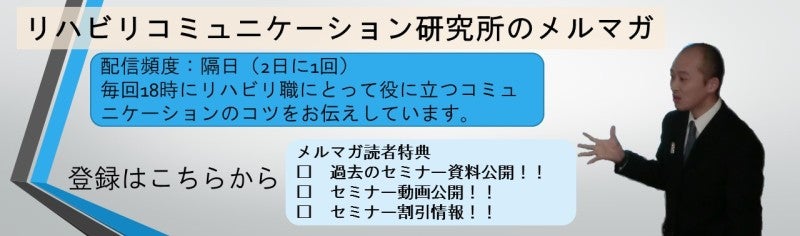
2日に1回 リハビリ職のためのちょっとしたコミュニケーションのコツについてお伝えしています!!
メルマガの内容はブログとはまた違った内容を配信してますので、おたのしみに!!
また、メルマガ登録者限定で、セミナーの音声、セミナー動画、セミナーのレジュメなど、特典いっぱいです。
無料にて配信しています!!
よかったら登録どうぞ~登録、解除、再登録、すべてフリーです。
☆podcast始めました!!
iPone,iPodtouch,iPadの方はこちら!!
それ以外のかたはこちら!!!