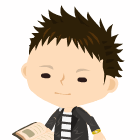先週から40度近い高熱が出てなかなか下がらず、寝たきりですることがないので、具合がマシなときに配信で映画を観たり
ブログを書いたりして過ごしています。
そんななかなかアマプラで観た『落下の解剖学』。
素晴らしかったため思わず2回観ました。
2023年のカンヌでパルムドール、アカデミー脚本賞を受賞したとのこと。
受賞は伊達じゃないと思いました。
この作品は法廷サスペンスと紹介されることも多いようですが、謎解きが主題ではないため、それだとミスリードに感じます(そもそも、ただのサスペンスやミステリならカンヌで最高賞を獲ることはまずないわけですが・・・)。
私がすごいと思ったのは主に2つで、ひとつは崩壊に瀕する夫婦の姿がものすごく真に迫っていること、もうひとつは私から見て、裁判というものの本質がかなり正確に表現されていると感じた点です。
本作の重要なシーンとして、夫の死の前日の夫婦喧嘩の録音が法廷で再生される場面があります。
その生々しさ・・・。
自分ばかり家事を負担していることに不平を言う夫、最初は冷静に受け流そうとする妻ですが、ネチネチと過去の不倫や子どもへの影響まで持ち出されてついに爆発。お互い叩いたりモノに当たりだしたり、凄まじい修羅場の音声が法廷に響きわたります。
よくこんな迫真のケンカの脚本が書けたなと感心します。
夫婦喧嘩って、他の人間関係でのケンカとは性質がちょっと違うと思うんですよね。
実はそこに至るまでの恨みや不満が蓄積しているわけで、「自分は絶対に悪くない」と感情を塗り固めた上でのことだから、簡単に和解できない。
でも大抵はどっちもどっちもの言い分があるから、それを指摘されると悔しくてお互い人格攻撃をしだすという・・・。
そして、それまで大した証拠もなく空中戦だった法廷に、いきなりこうしたナマの証拠が出されることで、雰囲気が一変してしまう。
「これはひどい。確かにこんなに憎み合っていたら殺したくなるかも・・・」というわけです。
でも冷静に考えれば、そんなのは夫婦生活のほんの一場面にすぎないし、ケンカしたから相手を殺すなんて短絡的すぎます。
そんなこといったら毎日どれだけの殺人事件が起きていることか。
でも裁判では実際のところ、裁判官は提出された証拠のみに基づいて判断するので、証拠に矛盾しないストーリーを認定した結果、確かに証拠とは矛盾しないものの、真実とはまるで違う、ということは往々にして起こります。
そのことを法廷で懸命に訴えようとする主人公の言葉は、多くの裁判当事者の気持ちを代弁していると思いました。
この映画でも裁判官は「裁判は真実を発見する手続だ」といいますが、違います。
弁護人も、「事故死という主張では誰も信じない。自殺でいくしかない」と主人公を説得します。
裁判官は当事者が提示するストーリーや事実のどれが本当らしいかを判断することができるだけで、結局は単に「どっちをとるか」の問題になります。
どっちも真実ではない場合でも、いずれか選択せざるを得ないのです。
そしてこの映画でも、この「選択せざるを得ない」という点が、残された子どもの心の問題として重く扱われています。
子役のミロ・マシャド・グラネールの演技がこれ以上ないというくらい素晴らしく、胸を打ちます(その他の俳優も皆本当に素晴らしい。検事役の憎ったらしいこと!)。
何か新奇な要素があるわけではないのに、まだこれだけすごい映画が作れるのだと思うと、クラシック音楽や現代美術がかなり行き詰まっている感じがするのに比べ、映画にはまだまだ未来があるなあと思いました。
ひとつ残念なのは、いろんなレビューサイトなどで見ると必ずしも評価されていないことです。
「長すぎる」「結論が出ずにモヤモヤする」「サスペンスとして平凡」のような。そういう映画じゃないのに・・・。
これを作品関係者が見て「日本ではこういう作品はあまり評価されないのだな」などと思われたとしたら残念でなりません。