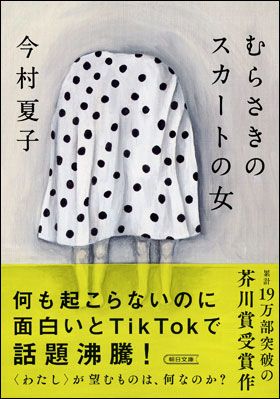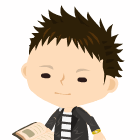書きたいのに、なかなか(うまく)書けないスピッツのこと。今回はアルバム『とげまる』12曲目の『若葉』です。
最初聴いたときは正直「地味な歌だなー」と、あまり印象に残りませんでした。
ただ私はいつもそうで、だいたい時間が経ってから「こんなにいい曲だったなんて!今までごめんなさい!」となります。
『若葉』も、なんとなく歌詞は頭に残っていて、生活の中でふと「つなぐ糸の細さに気づかぬままで」とか「今君の知らない道を歩き始める」といった歌詞を思い出し、いい歌だな、もう一度聴いてみようと・・・。
そして今は大好きになり、大変な名曲だと思っています。
卒業の歌は世の中にたくさんあって、『若葉』も若者の別れの歌のように思えます。
でもこの曲のように、2つの季節を歌うことで時間の経過を感じさせる作品は多くない気がします。
「花咲き誇る頃」と、それを振り返る「若葉の繁る頃」の歌です。
この曲は歌詞の繰り返しがほとんどなく、同じメロディが、違う歌詞で何度も歌われます。
そのたびに思い出される景色が移り変わり、古いアルバムをめくっているような気持ちになります。
ひとつの曲で草野さんの歌詞がたくさん読めるのも、単純に嬉しい。
草野さんも、たくさん歌いたい言葉があったのでしょうか。
この曲はたぶん若者の歌なのでしょうが、すっかり大人になってから若い頃を振り返った自分の気持ちにもとても近いです。
今思えば私も、将来なんて霧の中で何も見えず、でもなんとなく、いつまでも今が続くのだと思い込んでいました。
そして、「つなぐ糸の細さに気づかぬまま」、たぶんもう一生会うことはないだろう人たちのことを思い出します。
サビの後ろのギターのロングトーンがとてもいい。
『ありがとさん』もそうでしたが、スピッツの曲はこういうロングトーンがすごくいいなと思います。
ギターのアレンジはテツヤさんが考えるんでしょうか?すごいなー
メロディもゆったりとしてシンプルなので、合唱曲にして卒業式で歌ったらみんな泣いちゃうだろうなーなんて思っていたら、やっぱり同じようなこと考えるんですね。
実際歌っている学校あるのかな?
合唱にしたらすごくいいと思う。
曲では最後に、季節が「花咲き誇る頃」から「若葉の繁る頃」となり、思い出に鍵をかけて歩き始めるという歌詞で終わります。
「君を忘れない」とかではなく鍵をかけちゃうところがスピッツだなあと思います。
振り返りつつ独り歩いていく感じが、『テクテク』を思い出させます。
草野さんの詞は、深く共感できるところもあるけれど、「あるある」ではありません。
そういう感情もあるのか、そうだったかもしれないと、自分も気づかない気持ちに言葉が与えられることにいつも驚きます。
ボブ・ディランにノーベル文学賞が与えられるのなら草野さんにもあげるべきだ!
シューベルトの歌曲が教科書に載るのならスピッツの歌も載せるべきだ!
と本気で思います(教科書にはもしかしたらもう載っているかもですが)。
草野さんとスピッツは本当にすごい。
いつも同じこと書いてますが。