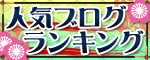日本には、「商売と屏風は大きくすると倒れる」という格言が昔からあります。非常に有名な格言です。これは、何でも当てはまります。
人間は自己を拡大していく傾向があり、物事を広げようとしていくのです。商売も大きくしたいのです。商売の場合は、フランチャイズで展開するのです。ケンタッキー・フライド・チキンも、マクドナルドも、コカ・コーラもフランチャイズです。いくらでも大きくできるのです。世界各国に広げることもできるのです。ラーメン屋でもフランチャイズ化できれば、何処まででも大きくできるのです。
何でもよいのですが、店舗をつくります。10店舗をつくるまでは難しいのですが、10店舗くらいまでは、今までの人材で何とかやれるのです。10店舗を超えて、20店舗まで伸ばそうと思うと、人材が足りません。今までの人材は店長にしたりしているので、人材が足りません。
すると、新しい人材を入れて教育しなければいけませんが、引き継ぎが上手くいきません。上手くいかない会社は、伸びることはできません。
伸びてきたラーメン屋は多々ありますが、ある程度まで大きくすると、伸びられなくなってしまうのです。途中で終わってしまうのです。何が間違っているのでしょうか? 商売の基本は、あまり大きくしてはいけません。
大阪にある金剛組は、飛鳥時代からある会社です。創業から1400年経っている、世界一古い会社です。金剛組は、会社を大きくしません。着実に仕事をこなしていくのですから、潰れません。
1400年以上、続いているのです。こんな会社は世界中を探してもありません。みんな、100年も持ちません。3代目くらいで潰れてしまうのです。それは、企業を大きくするからです。大きくしたほうがいい会社もあります。
1店舗では安定しなくても、10店舗もあれば安定しますが、そこまでです。10店舗までです。竹田恒泰先生も、4店舗くらいのラーメン屋を造ったのですが、今では2店舗です。「何が一番の悩みか?」と言うと、人が集まらないそうです。
僕も黒帯ラーメンを食べに行ったので、知っているのです。教えてあげましょうか? 竹田恒泰先生のラーメンは、塩が足りません。ところが、商売を始めて「上品なラーメンをつくろう」と思うと、どうしても薄味になってしまうのです。薄味だと「美味しい」と感じません。
スパゲッティにしても、中華料理にしても、薄味だと美味しくありません。ところが、つくるほうは、「塩分は体に害があるから、出来るだけ薄味で、名人の味にしよう」と思うのです。だから、利尻昆布を使ったりしているのです。
竹田恒泰先生に教えてあげましょう。もう少し、味を濃くしなければいけません。あと、3割塩分を濃くしなければいけません。そうすると、急に売れるようになるのです。
どうしても薄味でつくりたくなるのです。家庭の延長で「俺のラーメンは、美味いだろう」と言うのは、ダメなのです。商売でやる場合は、味を強くしなければいけません。
それは余計な話ですが、そのようなことをやりながら店舗を伸ばす場合は、10店舗くらいまでです。何百店舗、何千店舗もつくろうというのは、バカなのです。店舗が多ければ、多いほど身動きができなくなってしまうのです。そのようになってしまった人は、店舗が人の手に渡ってしまっているのです。
カレーのCOCO一番屋は、喫茶店を経営しているオジサンがカレー屋を始めたのです。それが上手くいったのです。調子に乗って、300店舗まで増やして、行き詰ってしまったのです。
COCO一番屋は、エスビー食品から原料を買っていたのです。エスビー食品に相談したら、「300億円で買いましょう」ということになったのです。店舗を買い取ってもらったのですから、その意味においては事業は成功です。
1店舗からやってきて、300店舗まで増やして、エスビー食品が買い取ってくれたのです。300億円で売れたのです。COCO一番屋の経営者は、エスビー食品です。エスビー食品は店舗を買っておいて、経営は元のフランチャイズオーナーにやらせたのです。
普通は商社マンが入ってきて、営業をやるのですが、フランチャイズの社長に経営をやらせているのです。従業員もそのまま使っているのです。ということは、300億円が丸ごと儲けです。エスビー食品は、そのまま仕事ができるのです。
人間は分をわきまえると失敗しません。飲み屋も1店舗から始めて、5店舗までは趣味が生かされるのですが、5店舗を超えると味が落ちてしまうのです。
僕は先週の土曜日、B屋というアジ天の美味しい店があるので、5時間もかけて店に行ったのです。出てきたものは、アジフライだったのです。昔は、アジ天があったのです。「アジ天が食べたい」と思って、B屋に行ったら、今はアジフライしかありません。
「ああ、そうか。B屋と言ってもここで魚をさばいていないな」とわかったのです。冷凍食品で仕入れているのです。B屋は100店舗もあるのですから、各店舗に冷凍食品が配られるのです。
すると、どんどん味が落ちてしまい、昔のアジ天は食べられないとわかったのです。これは、フランチャイズ化の欠点です。漁港で捕れた生の魚をさばいて、「アジ天は美味いでっせ!」と言えば、「あの店へ行きたいな」と思うのです。
ところが、冷凍食品を解凍して、アジフライを出しても美味しくありません。冷凍食品では、てんぷらはムリなのです。てんぷらは鮮度を要求されるのです。陸揚げされて長時間経ったアジではだめなのです。アジフライは衣をつけるから、誤魔化せるのです。そんなものは美味しくありません。B屋には、がっかりしました。
江戸時代の幕藩は、300藩あったのです。各地方で独特の自治があったのです。殿さまは藩主ですから、「お前、死ね」「財産は没収だ」という自治権を持っていたのです。それを治めている徳川幕府は、将軍家です。全ての藩に指令できたのです。
実際は藩主が政治を握っていたのです。島津藩の殿さまは、家臣や領民に恐れられたのです。部下は藩主を恐れたのです。将軍家など雲の上の存在ですから、見たこともないから恐れません。
藩主は生殺与奪権を持っているのです。「お前は切腹だ!」と言えば、藩主の命令に従わなければいけません。領民は藩主を恐れたのです。
江戸時代は300諸侯もあったのです。各地方は藩主が治めていたのです。それを統合していたのが江戸幕府です。それで江戸時代は上手くいったのです。藩主は自分の領地を治めたのです。
ところがその上には日本国があり、それは幕府が治めたのです。その上には、天皇家があるのです。それで上手くいっていたのです。
世界の経済、文明の問題は、そうでなければいけません。世界の国々が藩主のようにまとまっていけばよいのです。それを治めるのが天皇です。これからの社会は、そのようなゆるやかな連合で、世界をつなげていくことが大事です。(②に続く)
お読みいただきありがとうございます。
よろしかったらクリックしてください。
応援よろしくお願いします!
↓↓↓
■『正理会ちゃんねる』
第8回目のお話は、「創価学会について③」です。
是非、ご覧ください!
↓
■『中杉弘のブログ』2006年より、好評連載中です!
↓↓↓
http://blog.livedoor.jp/nakasugi_h/?blog_id=2098137
■『中杉弘の人間の探求』にて、「法華経入門講義」を連載しています!
こちらもご覧ください。
↓↓↓
https://ameblo.jp/nakasugi2020