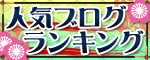モンゴル騎兵のおとり戦術 / Mongolian Cavalry's Decoy Strategies
物事の本質というものを学者は複雑にします。よくその根底を眺めてみれば、真実は単純です。何も難しいことはありません。
中国共産党の一帯一路の目的は、明解です。一帯一路とは、他国を侵略するためのものです。それに理屈をつけて、このようなことを言うのです。
「中国はチベットを資本主義からの侵略から守ったのだ。資本主義はチベットから出て行け」という目的で、チベットを共産主義社会にしたのです。だから、「これは侵略ではない」と言っているのです。中国は、凄い屁理屈をつけるのです。
中国は、このような屁理屈をつけているのですが、実際は侵略です。モンゴルもそうです。「モンゴルは、資本主義になりかけた。中国は資本主義の悪人どもを追い払って、半分は中国共産党が支配した」と言っているのです。
彼らは「正義の中国だ」と思っているのです。余計なお世話です。他所の国へ土足でズカズカと入ってきて、「お前達を資本主義から守ってあげる」などと言ったら、それは侵略です。
真理は単純です。学者は、単純な真理を複雑にしていくのです。物事は、単純化して考えたほうが、間違いはありません。
例えば、単純化した真実として、源義経の話をするとよくわかるのです。まず、源義経は武芸の達人です。鞍馬寺の修行時代にあらゆる兵法を学んだ武芸の達人です。それを兄の頼朝が嫌ったのです。
「何故、頼朝は義経を嫌ったのか?」というと、義経が強いからです。「自分はやがて義経に殺されるのではないか?」という猜疑心から、義経を疎(うと)んだのです。「義経は鎌倉に入るのではない!」と兄の頼朝は、義経が鎌倉に入ることを拒み、東北に追いやったのです。
東北の奥州平泉にいたのが、藤原家です。義経は源氏の棟梁の息子です。源氏が藤原家を世話したことがあったのです。その恩があり藤原氏は、「義経様が来られる。義経様を守らなければいけない」という律儀な人だったのです。藤原氏は、義経を徹底的に守ったのです。
藤原氏は、秋田県にある安東水軍と親戚だったのです。安東水軍の本拠地は、十三湊です。安東水軍は、ロシアのアイヌ、朝鮮半島、天竺とも交易をしていて、200艘の船を持っていたのです。
安東水軍は、海外の情報を持っていたのです。アムール川を上っていくと、モンゴル人がいます。朝鮮半島、中国の情勢もわかっていたのです。安東水軍は世界の情報を持っていたのです。
そして、義経は戦争の名人です。義経は平泉に逃げて、安東水軍の十三湊に到着したのです。その頃、平泉では杉目太郎を義経の身代わりにしたのです。年も背の高さも義経と似ていたのです。「源氏にお世話になっているのだから、義経様の身代わりになれ」と言われていたのです。
そこで、鎌倉にいる頼朝は、今までは「義経は鎌倉に入ってはいけない」と言っていたのに、「鎌倉に来い」と言いだしたのです。それは、義経を殺してしまおうということです。それがわかっていたから、義経は兄の要求に答えなかったのです。それも戦争の名人の勘です。「私が鎌倉に行ったら、兄に殺される」とわかっていたから、鎌倉に行くのを断ったのです。
ところが兄の頼朝は、何回も「鎌倉へ来い」と呼び出しをかけたのです。最後に、天皇の勅使が来たのです。頼朝は自分の命令では聞かないから、天皇に頼んで天皇から命令を出してもらったのです。
天皇の命令を出して「兄が呼んでいるから、鎌倉に戻ってきたらどうか」と勅使を送ったのです。義経は益々怪しいと思っているから、鎌倉には行きません。義経は鎌倉には行かないのですから、「こちらから行くしかない」と思って攻めて行ったのです。そのようになることも義経は知っていたのです。
そこで仕掛けをしたのです。義経は館で暮らしていたのですが、そこで暮らしていたのは、杉目太郎です。その間に義経は逃走したのです。何処に逃げたのかというと、それが秋田にある安東水軍の本拠地です。
義経は安東水軍から世界の情勢を聞いていたのです。日本にいたら兄の頼朝が攻めてくるのですから、外国に逃げると決めていたのです。アムール川を下っていくと、蒙古草原があるから、そこまで逃げてしまえば、追手は追ってこられないでしょう。
義経はそこへ行こうと決めたのです。そこで戦争の名人は考えたのです。「俺が逃げたということがわかったら、何処まででも追ってくるな」と考えて、ニセのルートをつくり、義経は太平洋沿いに北海道へ逃げたと思わせたのです。義経は逃げていく先々で、品を置いていったのです。
「これが弁慶の廿楽(つづら)です」「これは義経からもらった短刀です」などという証拠をたどると、奥州の平泉から、太平洋に沿って、青森から船で北海道に渡ったというルートが出てくるのです。北海道に行ったのは、義経ではありません。
義経は、安東水軍の船に乗り、大陸に渡り、アムール川を下り、蒙古草原に辿り着いていたのです。安東水軍は金をたっぷりともっていたのです。それで大陸へ行ったのです。ここまでは、議論する余地はありません。これが歴史常識論です。
兄の頼朝が自分を殺しにくるとわかっているのです。兄が殺しに来るのを4年間も待っているバカはいません。義経は、間違いなく逃げたのです。それで、安東水軍と合流して、大陸に渡ったのです。
奥州平泉から、秋田県に抜ける中央道を通って、十三湊に着いたのです。その反対の太平洋側のルートに記念品を置いていったのです。戦争の名人ならば、そうするでしょう。義経は戦争の名人です。
それで、義経はアムール川を上り蒙古平原に到着したのです。総勢200名くらいだったのでしょう。その中には、平家の落人もいたのです。アイヌ人は、100名くらいいたのでしょう。
義経の家来と、安東水軍と、アイヌ人の総勢200名くらいはいたのです。蒙古に住んでいるモンゴル人は20人くらいの部族社会です。そこへ行けば、赤子の手をひねるように征服できてしまうのです。
モンゴル人に「貴方は何処から来たのですか?」と聞かれると、「俺はテムジンだ。天から来たのだ」と言ったのです。
すると、モンゴル人は、未開の民族ですから、「はっはー、テムジン様」と言ったのです。少数の部族を統一して、中枢を造ったのです。これは、当然のことです。
成吉思汗の戦闘の仕方は、残酷です。これは、義経がとった戦法と同じです。昔の水軍の戦争は、船を漕いでいる人を殺してはいけなかったのです。それが常識だったのです。侍だけが戦ったのです。
ところが義経は、船を漕いでいる人を攻撃したのです。船の漕ぎ手が殺されてしまったら、船は動きません。それを初めてやったのが義経です。それまでは、船頭さんは殺さなかったのです。それを見ても義経は、残酷な性格だったのです。
まさに、その残酷な性格が成吉思汗に乗り移っていたのです。「お前、降参するか? 降参するならば、命は助けるぞ。降参しないならば、釜茹での刑だ!」というこことをやったのです。
大陸で暴れるのですから、思い切ったことをやったのです。義経は日本には帰れません。大帝国を造れば、他民族から殺されることはありません。そこで暮らすしかなかったのです。
成吉思汗の刀は、日本の刀だったのでしょう。成吉思汗は、姿を見せなかったと言われています。誰も成吉思汗の姿を見ることはできなかったのです。姿を見せた時には、大男だったのです。それは、弁慶が代わって出たのです。
成吉思汗は軍事の天才です。草原の民は、放牧民族ですから、兵法も軍事も何も知りません。草原の民が、世界を征服するなどできるわけがありません。いくら、モンゴル人が馬に乗ることが上手くても、軍事の天才でなければ世界を征服することはできません。それは、義経という戦争の名人がいたから、世界征服が出来たのです。これが常識です。それを歴史常識論と言います。
ジンギスカンの名前も、「ゲンギケイ」です。「ゲンギケイ」=源義経です。「ゲンギケイ」をジンギスカンにしたのです。真実は、簡単なことです。成吉思汗は、死ぬ時に「我故山に帰りたし」と言ったのです。故山とは、日本のことです。そのように考えるのが常識です。これが、歴史常識論です。
一人の人間の一生を見て、「これは真実」「これはウソ」とわかっていかなければ、真実は見えてきません。これが本当の義経像です。そのように僕は思っています。(②に続く)
※成吉思汗は軍事の天才です。草原の民は、放牧民族ですから、兵法も軍事も何も知りません。草原の民が、世界を征服するなどできるわけがありません。いくら、モンゴル人が馬に乗ることが上手くても、軍事の天才でなければ世界を征服することはできません。それは、義経という戦争の名人がいたから、世界征服が出来たのです。これが常識です。それを歴史常識論と言います。
お読みいただきありがとうございます。
よろしかったらクリックしてください。
応援よろしくお願いします!
↓↓↓
■『正理会ちゃんねる』が出来ました!
第七回目のお話は、「創価学会について②」です。
是非、ご覧ください!
↓
https://ameblo.jp/saeko7878
■『中杉弘のブログ』2006年より、好評連載中です!
(ライブドアがフリーズすることがあるので、『中杉弘の人間の探求』で「法華経入門講義」を第一回から掲載しています。そちらをご覧ください。)
↓↓↓
http://blog.livedoor.jp/nakasugi_h/?blog_id=2098137
■『中杉弘の人間の探求』にて、「法華経入門講義」を連載しています!
こちらもご覧ください。
↓↓↓
https://ameblo.jp/nakasugi2020