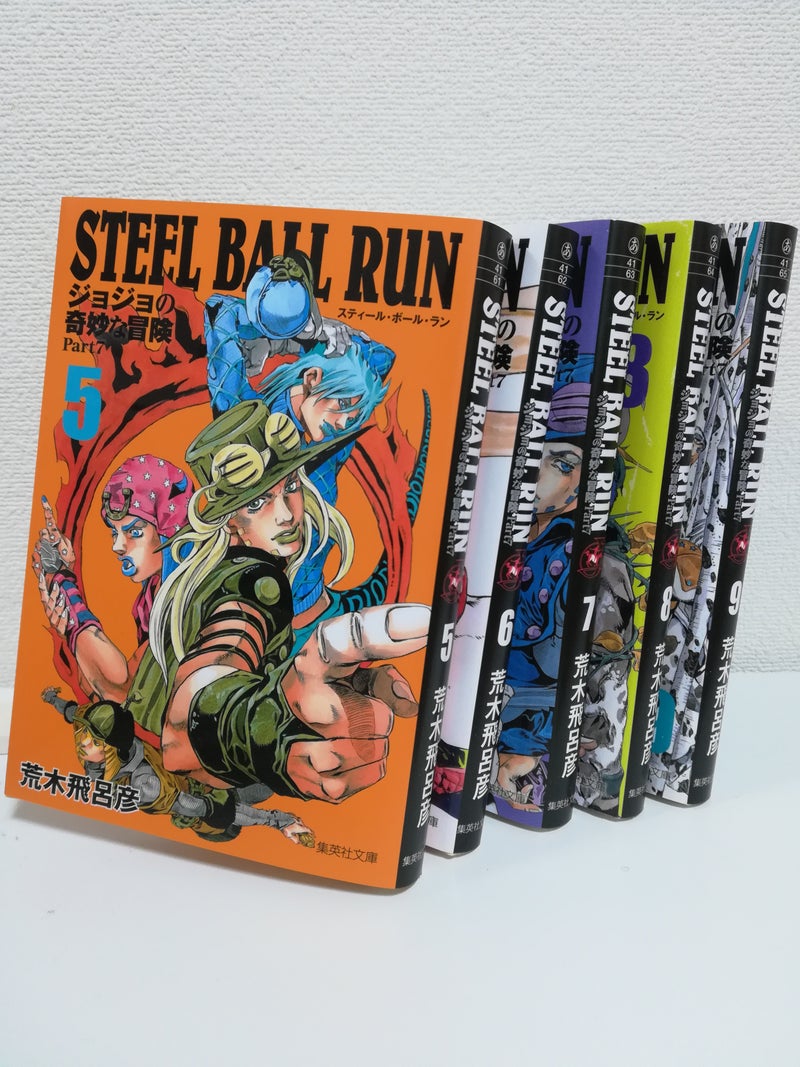【再読】 荒木飛呂彦『STEEL BALL RUN ジョジョの奇妙な冒険Part7』5~9 集英社文庫(コミック版)
前回の続きです。
本日はジョジョ7部、文庫版5~9巻までを再読しました。
以下、内容についての記載あり。未読の方はご注意ください。
ようやく私の7部最推しが登場です。
ホット・パンツ!!好き!!
3rd.STAGEゴール前でのジャイロ、ディエゴ、ジョニィの壮絶な競り合い、からのしれっとトップをかっ攫っていたホット・パンツが本当に格好良い。レースを途中でリタイアしてしまったのが残念です。本気で走ったら優勝も夢じゃなかったと思いますが、まあ彼女の目的はあくまで遺体の方ですからね。本職も馬乗りではなく修道女ですし。
彼女のスタンド能力「クリーム・スターター」は肉体を変幻自在のスプレー状にする力で、攻撃・治療・変装と応用の幅が広い、スタンドの中でもかなり使い勝手の良い能力です。特に治療に関しては肉を吹き付けるだけで済むぶん、クレイジー・Dやゴールド・エクスペリエンスよりも使いやすそうです。攻撃力はともかく、汎用性では上なのでは。実際、作中ではほとんど回復アイテムのような扱われ方で、怪我をするたびにジョニィが「ホット・パンツを探せ!!」と叫んでいます。
9巻でルーシーの窮地に駆けつけたホット・パンツはちょっと格好良すぎましたね。遺体目当ての打算的行動だと分かっていても痺れます。もうヒーローじゃん。
あ、あと似たようなシチュエーションでルーシーを助けに来てくれたマウンテン・ティムも格好良かったです。黙祷。彼のスタンドもかなり好きでした。
6巻後半辺りから危ない綱を渡り始めるルーシーには本当にドキドキさせられます。まだ十四歳だというのに夫のために命がけで大統領に挑んで、すごい度胸です。流石は旧姓ペンドルトン。勇ましい。
そしてこの辺りから大統領もラスボス感を出し始めてきます。最初は太っていたのにどんどんイケメンになっていく。
大統領が動き出してからは、レースよりも遺体集めの方がメインストーリーになっていきます。
バトルで好きなのは6巻のリンゴォ戦、8巻のサンドマン戦とシュガー・マウンテン周辺です。
リンゴォとジャイロの決闘は男同士の勝負という感じがアツい。しかも撃ち合いというアメリカンスタイルなのが最高です。
サンドマンとの戦いはかなりギリギリで、最後にホット・パンツが傷を治してくれなければ危ないところでした。サンドマンは初期よりちょっと悪人顔というか、覚悟を決めた者の顔になっています。あんな美人なお姉さん残して死んじゃうなんて。姉不幸者!!
シュガー・マウンテンのエピソードは全編通した中でも特に好きな部分です。タブーを犯すと罰を受けるタイプの能力は緊張感があってワクワクしますよね。スタンドではないですが、4部の「振り向いてはいけない小道」とかの設定も好きでした。
シュガー・マウンテンに言われた通り、ルールを守ってジョニィが遺体を自ら手放し、その後雪の中で二人がワインで乾杯する一連の流れが美しすぎます。遺体欲しさに一度はジャイロを見捨てかけたジョニィが、それでも最終的には友人を救うため遺体を敵に渡しました。よく決心したなジョニィ、偉い。
9巻は新たな追手のウェカピポとマジェント・マジェントが登場し、ジョニィ、ジャイロとの戦闘に入ったところで終了します。
ウェカピポは知的で義理堅い良キャラで、個人的にもかなり好きなので、ここからの活躍を見るのが楽しみです。大統領戦まではまだもう少しあったはず。「左半身失調」とかいうオシャレすぎるデバフは何度読んでも刺さります。
やはり単行本で一気読みするとスピード感を味わえるのが良いです。全16巻なので、これでまだ半分過ぎ。
続きはまた別日に読みたいと思います。
それでは今日はこの辺で。